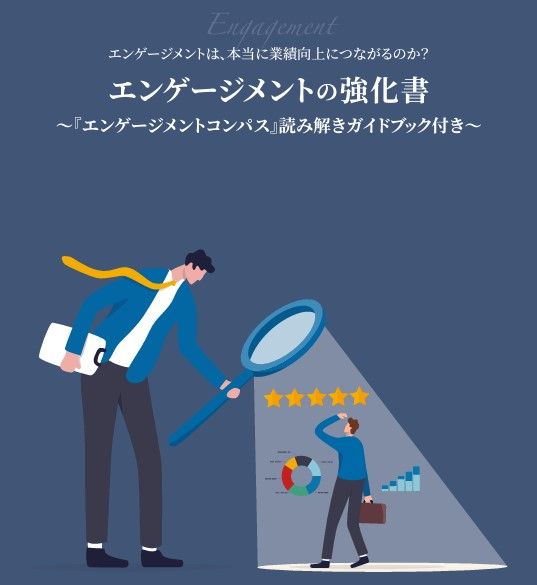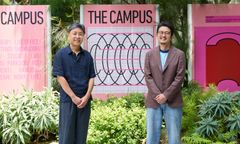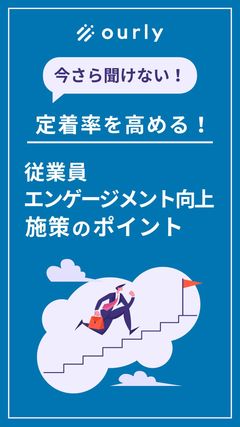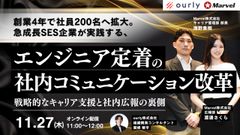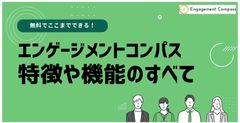「エンゲージメント」とは
ビジネスにおける「エンゲージメント」とは、企業と従業員、もしくは企業と顧客間の「関係性」、「信頼性」という意味である。特に人事領域では「愛着心(愛社精神)」や「思い入れ」、「帰属意識」として使われる。「契約」や「婚約」という強い関係性・深い絆を示す英語「engagement」から派生した。ビジネス上のエンゲージメントには、「従業員エンゲージメント」と「顧客エンゲージメント」の2種類がある。
●従業員エンゲージメントと顧客エンゲージメントの違い
従業員エンゲージメントは、「企業理念や方針への共感」や「企業が掲げるビジョンへの理解」をのこと。つまり、従業員がやりがい・働きやすさを感じて、自発的に企業への貢献意識をもつことを指す。貢献意欲はモチベーションの向上を導き、愛着のある企業からは離職を考えにくくなる。企業と従業員の相互間に信頼関係や深い絆が生じている点が大きな特徴である。一方、顧客エンゲージメントは、「企業と顧客との親密度」を指す。顧客から良好な印象を長く保てている企業は顧客エンゲージメントが高く、製品・サービスの継続利用といった行動・売上実績に直結する効果を得られるため、企業の成長を促す要因となる場合も多い。
●従業員満足度との違い
従業員エンゲージメントに類似する言葉に「従業員満足度」がある。これには「従業員としてこの企業に満足かどうか」の度合いであり、福利厚生・給与などの「待遇」や、労働環境・人間関係といった「就業環境の居心地」が含まれる。従業員側の気持ちの面が大きく、企業と従業員の信頼関係を示す「従業員エンゲージメント」とは異なる。また、従業員満足度の高さは、必ずしも業績の伸びと比例するわけではない点が明確な違いと言える。【関連記事】「従業員満足度(ES)」とは? 向上につながる5つの要素と企業へのメリットを解説
●モチベーションとの違い
「モチベーション」は、「動機」、「刺激」、「やる気」などを意味する英語で、ビジネス上でも企業や仕事に対して個人が抱くやる気や成長意欲として使われる。こちらも従業員個人のメンタルであるため、従業員・企業という関係性は存在しない点が大きく異なる。【関連記事】「モチベーション」とは? 意味や高める方法、維持する施策を詳しく解説
●ロイヤリティとの違い
「ロイヤリティ」は、企業への「忠誠心」や「帰属意識」を指す言葉だ。企業と従業員との信頼や共感を基にする「エンゲージメント」とは異なり、「ロイヤリティ」は「主従」の意味合いが強く、会社が優位な立場にあり、そこに従事するという考え方になる。【関連記事】厚労省も重視する「ワークエンゲージメント」の意味とは? 尺度や高める方法など働きがい向上のポイントを解説
【HRプロ】無料会員登録はこちらから >>
「従業員エンゲージメント」を構成する3つの要素
「従業員エンゲージメント」は、主に次の3つの要素で構成されている。(1)理解度
「従業員エンゲージメント」を測るうえで、企業の理念やビジョンへの理解は欠かせない。企業への愛着は、理念やビジョンを理解し、支持することからはじまる。自分が持つ理想と企業がかなえたい理想がマッチしていれば、「ビジョンの実現のために自分は何ができるのか」を考え、行動するようになるだろう。従業員エンゲージメントを高めたいのなら、従業員に対して企業側の思考を開示し理解してもらう必要がある。
(2)共感度
企業の理念やビジョンへの理解に加え、従業員がそれらにどれだけ共感しているのかも重要なポイントだ。企業が持つ目標に共感できれば、自分が会社にいる意義を見出して誇りを持って業務に取り組めるだろう。従業員に自社の目標に共感してもらうためには、従業員と直接的なコミュニケーションを積極的に行い、話し合いや意見交換を重ねる必要がある。
(3)行動意欲
「従業員エンゲージメント」が高い従業員は、企業が成功するために自発的に行動しようとする意欲も高い。企業の理念やビジョンを理解し、共感しているからこそ、従業員は「会社が成功するために積極的に動こう」という意思を持てるのだ。自身の行動が会社に貢献できていると感じられれば、従業員エンゲージメントはさらに高まり、企業への愛着や信頼も増すだろう。
「エンゲージメント」が注目される背景
「エンゲージメント」が注目される理由は、少子化による人手の減少、優秀人材の流出・離職率の高まりなど、人材確保が企業にとって喫緊の課題となったという点が大きい。終身雇用や、3年間程度は1社に留まる不文律の慣習は維持されなくなり、優秀な人材ほどよりよい待遇・評価を受けられる企業へ移ってしまう。人材流出の歯止め、離職率低下への取り組みが必須となった企業・人事にとって重要度が増したといえる。「エンゲージメント」への積極的な取り組みが必要になった原因を3つ挙げてみよう。
●離職率の上昇や若手のメンタル不調
2020年以降、感染症対策や働き方改革への取り組みが活発化しテレワークを取り入れる企業が増加した。そのような中で入社した新入社員や若手従業員は、同僚・上司などの職場のメンバーと業務以外の気軽な関係性構築ができず、対面コミュニケーションも不足し、組織で支えあう環境が作れいことが増えた。従業員エンゲージメントの要である企業への愛着・帰属意識の醸成が難しなった結果、離職率上昇を招いた。また、小さな不安をすぐに解決できない環境から、メンタル不調に陥る若手も増え、従業員エンゲージメントを高める必要が生じた。
●働き方の多様化
前述の通り、テレワークが普及した結果、管理職・上司たちが行う、部下の出社状況や業務の進捗・効率の把握といったマネジメント項目が増加・複雑化した。また、人材不足を補うために、子育て中・介護中の潜在的人材が就業しやすく、ワークライフバランスが考慮された就業環境も求められるようになった。多様なライフスタイルにマッチした働き方を許容する企業が、従業員エンゲージメントの高い企業とみなされる傾向がある。【関連記事】「働き方改革」とは? 目的や関連法、取り組み事例をわかりやすく解説
●人的資本開示・人的資本経営への注目
上場企業を対象に、2023年3月の決算期以降は「人的資本情報の開示」が義務化されたため、翌24年度から、開示項目の指標のひとつである「従業員エンゲージメント」に対し、企業価値を高める戦略として組む傾向が強くなった。これに伴い「人的資本経営」にも注目が集まり、「人材は消費するものではなく投資するもの」という価値観を再検討する潮流が生まれた。これも従業員エンゲージメントに注目が続いている要因である。【関連記事】HR総研:2024年度新入社員のエンゲージメント合同調査 結果レポート
「従業員エンゲージメント」を高めるメリット
「従業員エンゲージメント」を高めることは企業側にもメリットがある。代表的なメリットを4つ紹介しよう。●売上・利益、生産性の向上
従業員が仕事に達成感を持ち、それぞれの能力を十分に発揮できれば、それに比例してパフォーマンスや生産性が向上していく。個々の従業員があげるパフォーマンスの向上が組織全体の成果へと広がれば、企業としての売上アップ、業績向上につながる。【関連記事】そもそも「生産性向上」の目的とは? 課題やメリット、人事施策につながる取り組み方法も解説
●離職率の低下と人材確保
従業員エンゲージメントが高い状態とは、従業員の企業への貢献度も高い状態である。「自分はこの企業に貢献している」というポジティブな意識から、企業への愛着や帰属意識が高まるので、結果的に離職率が低下する。また、企業理念・方針への理解度も高まるので、業務に対するやりがいが生まれ、人材流出が防げる。【関連記事】「離職率」の平均や計算方法とは? 高い会社の特徴や改善策も解説
●モチベーション・定着率の向上
自分が担っている仕事が企業に貢献できていると実感することは、モチベーションに大きく影響を与える。達成感・働きがいの実感によって企業への貢献意識が高まるので、従業員の定着率上昇に効果が生まれる。【関連記事】「従業員エンゲージメント」を高めるには? 10の施策と向上のポイントを解説
●顧客満足度・ブランド価値の向上
従業員それぞれが自身の担う仕事に満足し、能力を最大限に発揮できれば、日々のパフォーマンスや生産性が自ずと向上する。その成果が、グループや部署へと波及することで、企業全体の売上・業績が上がれば、顧客満足度向上にも良い影響が生じる。顧客満足度の高さは企業のブランド価値を高めることにもつながる。【関連資料】日本企業のエンゲージメントの今とこれから~学習院大学 守島教授とHR総研が1年間のサーベイ結果を分析
「従業員エンゲージメント」の測定方法
従業員エンゲージメントを高めることが企業課題である以上、常に現状のエンゲージメントの度合いを把握するために、測定が必要である。続いては、「従業員エンゲージメント」の測定方法を紹介していく。●アンケート調査
最も主流な測定方法はアンケート調査である。定期的にヒアリングやアンケートを実施し、職場のメンバー間の全体的なバランスを見つつ、従業員一人ひとりが働きやすい環境に整備するよう工夫が必要だ。頻度は月に1回~半年に1回程度が一般的だ。これにより、従業員が重視するポイントや価値観を把握することにつながる。●エンゲージメントサーベイ
従業員のやる気や会社への愛着心を調査するエンゲージメントサーベイも有効な方法だ。仕事のやりがいや職場環境、上司や同僚との関係性、会社のビジョンへの共感など、多角的な質問を通して従業員の感情や意見を把握できる。さらに、サーベイ結果は組織の課題発見や改善策立案に役立てることができ、従業員の満足度向上や離職防止につなげていける。【関連記事】「エンゲージメントサーベイ」とは? メリットや導入の流れを解説
●代表的な指標
エンゲージメントを測る指標の代表的なものは、主に以下の3種が挙げられる。・エンゲージメント総合指標
従業員が企業に抱いている総合的な印象。「企業に満足しているか」、「継続して働きたいか」、「友人・知人に薦められる企業か」といった質問をする。
・エンゲージメントレベル指標
業務・仕事に対してどの程度の熱意ややりがいを感じているかを計る。「自身の仕事に誇りを持てているか」、「仕事中の時間経過を長い(短い)と感じるか」などの質問をする。
・エンゲージメントドライバー指標
従業員エンゲージメントを向上させる要因となるもの。さらに「組織ドライバー(職場環境や人間関係といった従業員と企業の関係)」と「職務ドライバー(従業員が感じる仕事への満足度や難易度)」、「個人ドライバー(仕事に影響を及ぼす従業員個々の資質)」の3点で構成される。
●定量的指標
従業員エンゲージメントは定義・意味が多岐にわたり、やる気・熱意などの抽象的な心の持ちようも含まれるため、定量化は難しい。定量化する際、多くの場合ポイントとなる数値は以下の10点である。・欠勤率
・離職率
・従業員満足度の伸び
・教育・訓練の効果測定
・顧客満足度の伸び
・イノベーション件数(新規事業や新プロジェクトの創出数)
・財務税務パフォーマンス
・品質向上の度合い
・生産性向上の度合い
また、パルスサーベイ(意識調査)を利用する方法もある。例えば、「表情と没頭度合い(顔認証機能を利用)」、「キーボードのタイピング数と集中度合い」、「心拍数などの生体データを利用」といった測定方法となる。
●エンゲージメント調査の質問例
従業員エンゲージメントを調査する際、面談やアンケートという手法がよく使われる。調査として効果的な質問例には以下のようなものがある。・企業・職場が自身に期待していることは何か、きちんと把握しているか
・仕事を効率的・効果的に進めるために企業から提供される資料・材料・道具などは不足なく十分であるか
・自身が最も得意なことで能力を発揮する機会を、企業・職場から与えられているか
・職場の同僚・メンバーは自分の成長促進に協力的だと感じるか
・直近7日間で、自身の仕事ぶりや成果を評価された、もしくは褒められたか
・上司や同僚、職場のメンバーは、業務以外の面でも気にかけてくれたり、ひとりの人間としてコミュニケーションをとってくれたりしているか
・職場や仕事に対して持論や意見を発言するシーンで、尊重してくれていると感じるか
・企業の掲げる目標や理念・方向性に対し、自身が担っている業務は重要だと感じるか
「エンゲージメント」測定・運用時の注意点
「エンゲージメント」を測定する際、またサーベイ実施・運用の際には気を付けたいポイントがある。主な6つについて解説していく。●調査目的の明確な共有
エンゲージメント調査を実施する際には、まず「なぜ調査を行うのか」の目的や活用方針を明確にし、従業員にも伝えることが重要だ。目的説明が曖昧だと回答の信憑性や率が下がり、不信感につながる。調査の背景や意義、個人情報保護も丁寧に説明したい。●相関関係と因果関係を区別する
調査データの結果を活用する際には、単なる数値の関連性(相関関係)を鵜呑みにし、因果関係と誤認すると間違った施策や意思決定につながるリスクがある。例えば「エンゲージメントが高い部署は業績が良い」というデータから、直接的な原因・効果関係と決めつけてしまうのは危険と言える。分析・運用時の質を高めるためにも、相関関係と因果関係を区別することに注意を要する。●運用負担の軽減
エンゲージメント可視化調査・分析は複雑で、運用負担が大きい点がデメリットである。負担軽減にはシステム導入も検討すべきだが、金額的な導入コスト、自社の状況にマッチしたシステムを選定する手間も考慮する必要がある。●従業員の負担軽減
調査の設問数が多すぎたり頻度が高かったりすると、従業員にとって大きな負担となってしまう。本業に差し障りもない時間で回答できる内容や、スマートフォンでも回答しやすい仕組みを設けるなど、業務を邪魔しない配慮が必要となる。●安心感や納得性の確保
従業員のプライバシー保護に努め、「回答内容が処遇等に影響しない」と約束することで、不安や抵抗感を軽減しやすくなる。従業員の承諾を必ず得ることや、心的負担にならないよう配慮が必要である。●調査結果の活用とフィードバック
調査後は必ず結果を従業員へフィードバックし、分析内容や今後の改善アクションを丁寧に共有する。調査が「やりっぱなし」だと信頼を失い、次回以降、協力することに抵抗感が生まれてしまう。【HRプロ】無料会員登録はこちらから >>
「従業員エンゲージメント」を高める施策
続いて、測定した「従業員エンゲージメント」を、現状よりも高めていくために実施すべき施策を見ていく。●企業理念・ビジョンの浸透
企業の目標・目指している方向性を従業員に向けて発信できているかを再確認する。発信力だけでなく従業員への浸透度合いも確認が必要である。企業側は、積極的に発信・周知・共感を促すために「ミッション・ビジョン・バリュー」を理解していることも重要だ。【関連記事】「MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)」とは? 意味や策定のメリット、企業事例、ポイントなどを解説
【関連記事】「企業理念」の意味や重要性とは? 経営理念との違いや企業事例も紹介
●マネジメント層の教育とリーダーシップ強化
マネジメント層へのコーチングや、フィードバックについての教育を実施し、部下の状況を理解し、熱意ややる気、潜在能力を引き出すためのサポート力を養わせる必要がある。特に新入社員や若手には、サポート役を配置するメンターシップ制度を導入するのも良い。マネジメント層以外でもリーダーシップのある人材は適正に評価し、リーダーシップ強化をはかることも重要である。ただし、リーダーとしての資質は定数化や評価が難しい。適正評価の実施には数値的実績だけでなく、やる気・熱意といったソフト面も加味し、多面的な評価システムを作ることが必要である。リーダーシップを発揮できる人材は、周囲を巻き込む推進力があり、組織全体の前進・エンゲージメント向上のトリガーにもなる。
【関連記事】「リーダーシップ」の定義や種類とは? マネジメントとの違いや求められる能力も解説
●社内コミュニケーションの活性化
円滑な人間関係を維持し、従業員の居心地のよい職場環境を保つことも従業員エンゲージメント向上に必要である。企業は、より多くの従業員から共感を得られる手法を選び、心的安全性が保たれた社内コミュニケーションを活発化していかなければならない。これによって、従業員としては企業への帰属意識が高まり、離職のリスクを軽減できるだろう。【関連記事】「社内コミュニケーション」の活性化に向けた取り組み事例とは? 課題やイベントなど会話不足を解消するためのポイントを解説
●キャリア形成・教育研修の充実
従業員のキャリア形成や個々の成長につながる研修などの機会を作って支援することも大切である。従業員がやりがいや意義を実感できると、さらなる成長を目指して自発的にクリアすべき目標を持ち、ポジティブに自身のキャリアと向き合える。教育機会の充実はキャリア形成のサポートにつながる。教育機会を設ける側のマネジメント層・上司も、自身の組織での立ち位置などを再確認したり、部署の業務の棚卸しになったりする。仕事に対する意欲・モチベーションを高める機会にできる。
【関連記事】「キャリア」とは? 意味や6つの理論、自律支援の重要性を解説
●人事評価制度の見直しや働き方改革
前述した「リーダーシップのある人材への適正評価」と同様、仕事に積極的で成果も出ている人材に対しては適切に評価する必要がる。そのためには、状況に応じて現行の評価制度を見直すことも重要である。見直しの際には、基準をより明確化・具体化すること、公平性を担保することも大切なポイントになる。【関連記事】そもそも「人事評価」とは? 目的や評価制度の導入手順を解説【最新手法や事例も紹介】
【関連記事】「人事評価制度」の作り方をわかりやすく解説! 評価項目や設計・運用の7ステップを紹介
●承認・称賛の文化づくり
従業員がお互いの成果を褒め、感謝の言葉を互いに口に出す習慣を作ることで、信頼関係を構築する。その際、従業員の間だけで個人的に謝意を伝えるのではなく、公に伝える手段を用いることで、個々のモチベーションを向上させることができる。感謝をコメントとともにポイント化するツールや、社内掲示板などを活用し、認め合う波紋が社内に広がる環境を生み出でれば、深い絆が結ばれる効果も期待できる。
●タレントマネジメントやDXの活用
従業員エンゲージメントの定期的な把握のために、タレントマネジメントやDXの活用も有用である。タレントマネジメントのデータ活用によって、適切な人材配置を行うことができ、従業員それぞれの能力を最大限に発揮させることが可能になる。活躍の場が与えられることが従業員エンゲージメントの向上に効果的であるのは、前述の通りだ。また、個々の特性を把握することにもつながり、長所が見つけやすくなる点も、従業員エンゲージメントにとって非常に有効だと言える。
【関連記事】採用や育成で注目の「タレントマネジメント」とは何か? 定義や目的を整理し、導入フローもチェック
「エンゲージメント」向上の課題とリスク
「エンゲージメント」を高めようとする中で、最大の課題は、「表面的な満足度」と「真のエンゲージメント」を区別できない点にある。アンケート調査や施策の導入で一時的に満足感が上がっても、日常業務のストレスや上司との信頼不足が解消されなければ、長期的な効果は得られない。それだけでなく、組織が一方的に「エンゲージメント向上」を押し付けると、従業員にプレッシャーがかかり逆効果となるリスクもある。重要なのは、心理的安全性を前提とした対話的な環境づくりだ。●「エンゲージメント」が上がらないときの改善策
「エンゲージメント」がなかなか高まらない場合、まず原因の可視化と仮説検証が欠かせない。漫然と施策を増やすのではなく、「上司のマネジメント力」、「組織への信頼」、「仕事の意義づけ」といった要因を分解して把握することが重要だ。その上で、従業員との対話や1on1を通じて、期待や課題を言語化して共有する。小さな成功体験を積むことが効果的だ。例えば、チーム単位で成果を称える文化を作ることで、自発的な貢献意欲を引き出せる。短期的な指標に一喜一憂せず、継続的な改善サイクルを回すことがポイントである。●計測や施策運用で起こりやすい失敗例
エンゲージメント施策では、「測ること」が目的化してしまう失敗が多い。サーベイ結果を集計するだけで終わり、分析やアクションに結び付かないケースだ。また、経営層やマネージャーの理解を得ずに施策だけを進めると、現場との温度差が生じやすい。単発の研修やイベントで満足してしまい、本質的な行動変化につながらないことも課題となる。さらに、成果を人事評価に直結させすぎると、正直な回答が得られずデータの信頼性が損なわれる。目的とプロセスを明確にし、現場に根付く運用を徹底することが重要と言える。●情報管理や個人データ活用のリスク
エンゲージメント調査や人材データ活用の拡大に伴い、個人情報の取り扱いリスクが高まる。匿名性を保てない設計や、目的外利用への懸念が従業員の不信感を招く恐れもある。特に、サーベイ結果を個人単位で評価や昇進に利用すると、監視される感覚を与え、エンゲージメント施策そのものが逆効果となる場合もある。安全な情報管理体制を整えるだけでなく、活用目的や範囲を明示し、透明性の高い運用を行うことが重要だ。信頼関係の上に成り立つデータ活用こそ、持続的な組織発展の鍵となる。「従業員エンゲージメント」向上の企業事例
「従業員エンゲージメント」の向上に取り組んでいる企業は、いったいどのような施策を行っているのだろうか。ここからは、従業委エンゲージメントの向上に取り組む企業の事例を紹介する。●スターバックス
アメリカ発のコーヒーチェーンスターバックスは、商品の質に加え従業員の接客の質も高いことで有名だ。店舗に訪れる顧客に対して笑顔ではきはきと接客するさまに、心地よさを覚える人も多いだろう。スターバックスの特長は、明確化されたビジョンを全社で共有している点にある。「お客様のサード・プレイスを作る」を合言葉に、すべての社員が店舗に訪れるお客様にとって心地良い場所を作れるよう取り組んでいるのだ。
このような姿勢は、社員だけでなくパートやアルバイトにもおよぶ。パートタイマーやアルバイトは、スターバックスの従業員の8割を超えており、同社に欠かせない戦力だ。社員以外の従業員をパートナーと呼び、理念やビジョンに共感してもらうよう取り組んでいる。
チェーン店には珍しく、マニュアルが用意されていないのもスターバックスならではだろう。マニュアルがない店舗では、どのように行動し接客するのかは従業員にゆだねられる。では、従業員は何を指標にして業務に取り組んでいるのだろうか。その指標こそがスターバックスの理念やビジョンなのだ。
「お互いに心から認め合い、誰もが自分の居場所と感じられるような文化をつくる」
お客様が自分の居場所だと思ってもらえるように、従業員が自分の居場所だと感じられるように、相手を心から認めようとする姿勢があの心地よい空間を作り上げているのだろう。
●小松製作所
建設機械の大手、小松製作所もイノベーションの創出を促進するために2012年から「従業員エンゲージメント」の向上に積極的に取り組んでいる。現場の従業員エンゲージメントに深く関わる、マネージャー層を対象としているのが特徴だ。マネージャー層が気を配るべきポイントを明確化し、説明会を実施するとともに教育・研修体制を整備した。それに加え、育児や介護など家庭の事情に配慮する支援策、休暇制度を整えたという。
また、全従業員に「コマツウェイ」と名付けた小冊子を配布し、経営層を含め価値観の共有を図った。小松製作所が定めた「マネージャー層が気を配るべきポイント」は信頼、モチベーション、変化、チームワーク、権限移譲の5つ。従業員は信頼感を持つことでリスクへの抵抗がなくなり、周囲との情報共有もスムーズになる。
モチベーションにおいては、従業員が新たな挑戦に取り組めているのか、やりがいを感じているのかを把握する必要がある。また、従業員エンゲージメントの向上に取り組み、イノベーションが起これば企業は大きく変化する。従業員同士が連携を取りながら事業環境の変化に柔軟に対応できるよう、マネージャー層に研修やワークショップを実施していという。
これらの施策によって、小松製作所は従業員エンゲージメントの向上に成功し、さらには売上向上も果たしている。
マーケティング領域における「エンゲージメント」
「エンゲージメント」は、マーケティング領域ごとに意味や考え方に差異があることをご存じだろうか。ここで、代表的なマーケティング領域における意味、指標などを確認していく。●SNSにおける「エンゲージメント」の意味
SNS・ブログ・公式サイトなどが含まれるウェブマーケティングの領域では、エンゲージメントは「顧客エンゲージメント」としての意味になる。SNSで顧客と積極的にコミュニケーションをとることは、いち消費者である顧客を、購買意欲の高いファン層、一見ではなくリピーターへと押し上げる効果がある。重要顧客を増やすために、SNS領域でのエンゲージメントは昨今注目度が上がっている。
●Facebook/X(旧Twitter)/Instagramでの指標
Facebookでのエンゲージメント指標は以下の3点である。・「シェア」のクリック数
・ページに添付された画像や設置リンクのチェック回数
X(旧Twitter)でのエンゲージメントの指標は多岐にわたる。代表的なものは以下の通り。
・ツイート詳細の表示数
・プロフィールの画像、ユーザー名のクリック数
・添付画像やビデオのクリック数
・設置リンクやカードのクリック数
・ハッシュタグのクリック数
Instagram での指標は2点に絞られる。
・「コメント」の数
Instagramは顧客の反応が個別フォロワーの反応として明確に現れる特性がある。そのためウェブマーケティング上でエンゲージメント計測・分析するには欠かせない領域である。
3種のSNSそれぞれ、ワンクリックという小さなアクションではあるが、不特定多数の「いいね!」という賞賛の声が波及することによって「バズる」という現象も起こりうる。こういった現象がエンゲージメント構築のきっかけとなるケースもある。
●エンゲージメント率の考え方
「エンゲージメント率」とは、SNS上でユーザーが積極的な反応を示した割合を数値化したもの。ひとつの投稿に対して、それぞれのSNSが定めたエンゲージメント発生の割合を示すものである、また、Facebook、Twitter、Instagramなど、SNSごとにエンゲージメント率の計算方法が異なる。まとめ
「従業員エンゲージメント」を高めるために新しい取り組みをしようと考えると、どのように、何から手を付けるべきか迷うこともあるかもしれない。しかし、「従業員エンゲージメント」は評価とは違い、必ず使わなければいけないツールがあるわけではなく、10問程度のアンケート調査や、組織内・メンバー間で互いを承認しあい褒める文化の醸成から始めることができる。人材の定着・離職防止は引き続き経営に関わる重要課題である。「企業の成長は人材の成長あってこそ」と考え、管理・教育するという主従関係的な視点ではなく、従業員一人ひとりの長所や得意分野をよく見ること、人として温かなコミュニケーションが取れる環境・土壌作りが肝要である。
- 1