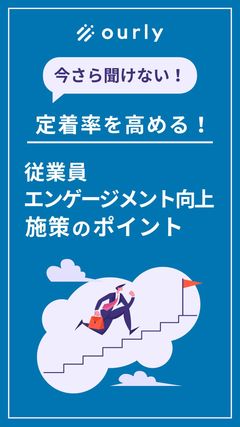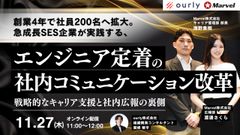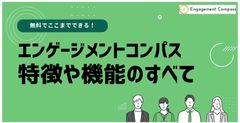厚生労働省資料にある「柔軟・多様・快適な労働環境を整備する」
まず、厚生労働省「働きがいのある職場づくりのための支援ハンドブック(以下、厚労省資料)」では、次のような『働きがい向上に必要な6つの取組』を掲げています。(1)働きがいの現状を確認する
(2)柔軟・多様・快適な労働環境を整備する
(3)仕事の意味や面白さを見出せるよう働きかける
(4)従業員と組織の方向性を一致させる
(5)納得感ある評価や処遇を導入する
(6)能力・キャリア開発を充実させる
今回は「(2)柔軟・多様・快適な労働環境を整備する」を取り上げます。そして、労働環境を整備する取り組みとして、厚労省資料で具体的な取り組みとして、次のような内容を例示しています。
●業務効率化による労働時間の削減や、休暇取得をしやすい制度
●時差出勤やテレワークなど、時間や場所にとらわれない働き方
●衛生的で整頓されたオフィス、静かで集中できる環境
●職場の円滑な人間関係や風通しの良い組織風土
●懇親会やクラブ活動を通じて、部署を超えた横のつながり
それでは、これらを踏まえて「柔軟・多様・快適な労働環境を整備する」ための3つのポイントをまとめてみました。
ポイント(1):労務に関して「軸となる取り組み」を掲げる
厚労省資料では、従業員の働きがいを引き出す労務制度として「労働時間の削減」、「休暇取得をしやすい制度」、「時差出勤やテレワーク」などを例示しています。他にも、育児・介護休業の取得推進などさまざまな取り組みが考えられます。一方で、さまざまな取り組みが滞りなく実現できれば良いですが、すべてを実現させようとすると、経営に無理が生じてしまったり、特定の管理職や従業員に過度な負担が生じたりすることにもなりかねません。
会社として労働環境を整備する上で「何が軸となる取り組みを掲げること」も一つの方法です。
例えば、従業員の裁量が高い仕事であれば「時差出勤やテレワーク」の推進に力を入れることが効果的かもしれません。また、身体への疲労が蓄積されやすい業務については「労働時間の削減」を明確に掲げることが効果的かもしれません。
軸となる取り組みから始めていくことで、会社と従業員との間で、労働環境整備に向けた方向性が共有されることになります。それにより段階を踏みながら、軸となる取り組みだけでなく、一つひとつの取り組みを充実させることへもつながっていきます。
ポイント(2):「5S活動」に基づき、整頓などの目的を明確に
厚労省資料では「衛生的で整頓されたオフィス」を例示しています。ここでの「整頓」を、5S活動『整理』、『整頓』、『清掃』、『清潔』、『躾(しつけ)』として捉えてみます。例えば、次のように「それぞれの活動が、労働環境へどのように影響するか」をまとめると、それぞれの目的がより明確なものとなります。
●「整理」をすることで、無駄なものがない労働環境へつながる
●「整頓」をすることで、効率的な仕事ができる労働環境へつながる
●「清掃」をすることで、転倒防止など安全な労働環境へつながる
●「清潔」を意識することで、衛生的な労働環境へつながる
●「躾(しつけ)」を通じて、整頓などが習慣化され、安心できる労働環境へつながる
さらに、業務内容などに応じて「5S活動の中で特に何を重要視するか」を明確にできれば、効率的かつ効果的に活動を展開することができます。
ポイント(3):業務外でのつながりは義務ではなく「多様性の象徴」
厚労省資料では「懇親会やクラブ活動を通じて、部署を超えた横のつながり」を例示しています。業務外でのつながりの場面をつくり、日常の忙しさから離れたコミュニケーションを通じて、円滑な人間関係につながっていきます。一方で、このような場面へ参加することが、誰もが良いと感じるとは限りません。参加に負担を感じたり、他にやりたいことがあったりする場合は、参加をしないことも一つの選択肢です。懇親会やクラブ活動は、当然、義務ではありません。義務のような捉え方をしてしまうと、働きがい向上とは、かけ離れた結果になってしまいます。
懇親会やクラブ活動は、あくまでも選択肢の一つとして捉えましょう。懇親会やクラブ活動が義務ではなく「多様性の象徴」となり、一人ひとりの業務外の過ごし方を尊重することが、働きがいを向上させる労働環境へとつながっていくのです。
- 1