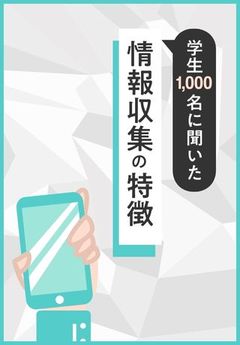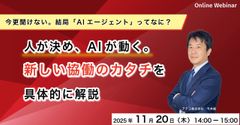「AI採用」とは
「AI採用」とは、書類選考や面接などの選考過程において、何らかの形でAIを活用した採用活動を指す。その目的としては、採用業務の高度化・効率化が挙げられる。具体的には、レジュメや求人票の自動作成、履歴書やエントリーシートの自動スクリーニング、適性検査の分析、AIによる面接評価、自動マッチングなどでAIが活かされている。「AI採用」が広がる背景
「AI採用」が広がる背景としては、特に以下の二点が着目される。●AI技術の進化
近年はAI技術、特に生成AIの進化が著しい。それに伴い、大量の応募者のレジュメ解析や面接評価などもAIに任せ、分析や判断の高度化、採用活動のスピードアップにつなげようという動きが加速している。●採用の難易度上昇
労働人口の減少により採用競争が激化していることもあって、採用の難易度がますます上昇している。そうした厳しい中で、いかに成功率を上げるかが人事の課題となっている。それだけに企業としても、蓄積した人事データをAIに学習・分析させ、より適切かつ効率的な採用活動につなげていきたいと意図している。「AI採用」の現状について
「AI採用」は国内外で大きく広がりつつある。Thinkings株式会社が、企業の人事・採用担当者を対象として実施した「2023年度の採用活動におけるAI活用」に関するアンケート調査によると、43%の企業がChatGPTなどのAIツールを採用活動に活用していると回答。最も多かった活用領域は、「求人票の制作」(60.5%)、次いで「スカウト」、「WEB面接」(いずれも31.4%)となった。また、AIツールを活用した人の81.4%が、採用目標数を達成したと回答。一方、「活用していない」と回答した人のうち「達成した」と回答した人は47.7%に留まっており、AI活用が人材の質向上につながっていることが窺える。採用におけるAI活用シーン例
採用活動の中で具体的にどんな場面でAIが活用されているのか。その例を紹介しよう。●求人要件分析
AIは、これまで蓄積してきた採用データや社内の人材情報を分析し、活躍できる人材の特徴を可視化することができる。例えば、活躍している社員のスキルセット、性格傾向、キャリア経路などを基に「成功人材モデル」を生成し、新規求人の要件定義に反映させることが可能だ。これにより、求人の精度や母集団の質を高めることができる。●求人票・スカウト文面作成
生成AIツールを活用することで、求人票やスカウトの文面を自動作成することができる。候補者一人ひとりに合わせて、クオリティの高い文章を仕上げられるので、アプローチの精度はかなり高いと言える。例えば「エンジニア志望の20代向け」や「地方在住者向けリモートワーク求人」など、応募者属性に応じてトーンや訴求ポイントを最適化できる。●母集団形成・候補者検索
採用候補となる人材の母集団形成や候補者検索にもAIが役立つ。具体的には、求人媒体のデータベースやLinkedIn、FacebookなどのSNSを分析し、レコメンド機能により自社の求人要件に合致した人材を効率的に提示してくれる。条件検索だけでなく、スキル類似度やキャリアパターンの関連性なども加味できるため、「見逃されていた潜在的な適合候補者」を発見することも可能だ。●候補者管理
候補者情報を蓄積するデータベースの管理においても、AIは効果を発揮する。例えば、情報の更新要否のチェックや求人に適した候補者の抽出などもかなり容易になる。応募後に活動が止まっている候補者を自動的に検出したり、スキルアップや転職活動再開を判断してアプローチタイミングを提案したりもできる。●面接
AIを活用した面接サービスも多くなってきている。一般的には、応募者がオンライン上で、事前に設定された質問に回答する様子を録画したデータをもとに、応募者の発言内容や話し方、表情などを多角的にAIが分析する。企業はその結果に基づいて採否を判断していく。また、AIが面接官となって質問を自動生成し、候補者ごとに柔軟に応答するシステムも登場している。●書類選考・スクリーニング
人事担当者にとって、応募者から寄せられるエントリーシートや履歴書、職務経歴書を確認するのは大変な作業だ。その点、AIを活用すれば、履歴書をデータ化して書かれている内容に基づいてスコアリングや職務経験のマッチ度査定を行ってくれる。評価基準を予め設定しておくことで、候補者のランク付けも可能となる。●適性検査・性格診断
近年では、適性検査・性格診断の機能を搭載したAIサービスも登場している。これを用いることにより、回答傾向、行動パターン、心理的特徴などを高度に解析し、迅速・高度かつ客観的な検査・診断結果を得ることが可能だ。トップ社員の検査・診断結果と照らし合わせれば、活躍見込みや部署配置の適正度も判断しやすくなる。●スケジュール管理
選考にあたっては、候補者や採用担当者・面接官、会議室などの状況を事細かく確認してスケジュール調整をしなければいけない。この作業はかなりの労力となる。AIを活用し、カレンダーやチャットツールと連携することで、スケジュールの作成や関係者への連絡が自動化されるので、採用担当者の負担の軽減を図れる。●応募受付・管理・問い合わせ対応
AIによって、応募受付や管理もスムーズに行える。また、AIチャットボットを導入すれば、24時間常時対応が可能となり、問い合わせへの業務を効率化することもできる。●採用効果分析・改善提案
AIを採用活動に関するデータ(応募数、通過率、採用単価など)の分析に活用することで、データの可視化がしやすくなる。また、結果もデータとして明確に提示されるため改善策を講じやすい。しかも、定型業務から解放されることで、本来専念すべき業務に集中しやすくなり、採用のプロセスが改善される。●AI活用に向かない採用業務
すべての採用業務でAIが活用できるわけではなく、代替が難しい業務があることも理解しておきたい。具体的には、応募者と信頼関係や人間関係を構築する、応募者の潜在的な感情やモチベーションを理解する、企業文化との相性を見極める判断するといった業務には向かない。こうした「人の感情」や「価値観」に関する業務や複雑な判断を伴うケースでは、人間の関与が必要となる。【こちらも読まれています】「人事管理システム」の編集部おすすめ比較! 機能・費用相場・選び方も解説
【こちらも読まれています】「ダイレクトリクルーティングサービス」編集部おすすめ比較! メリット・費用相場・スカウトとの違いなどを解説
「AI採用」のメリット
次に、「AI採用」のメリットを取り挙げていく。●工数削減・負担軽減・人件費削減
採用活動には多大な労力を要する。例えば、膨大な数となるESを一通ずつ読み込んで、候補書を絞り込む過程は人事担当者にとって大きな負担となる。それをAIに任せることで、工数を大幅に削減することができ、コスト面での効果も期待できる。●人的ミスの低減
採用活動でも、間違いを犯す、目が行き届かないなどと言った人的ミスはつきものだ。その点、AIを活用するとミスを低減し、精度の高い採用業務を進めることができる。●評価の公平性担保
どうしても人が面接すると、応募者に対する好みのバイアスが反映されてしまう。要は、面接官が違うと評価にバラツキが生じるということだ。AI面接であれば一貫性のある結果を得られ、面接の「質」と「公平性」を担保できる。●採用基準の統一化
人には主観や感情があり、採用活動を進める上でもそれらが移入されやすい。その点、AIは事前に定めた採用基準に準拠した判断をしてくれるのでブレもない。自ずと、会社としての採用基準の統一化を実現できる。「AI採用」のデメリットと注意点
一方、「AI採用」にはデメリットや注意点もあることを覚えておきたい。運用リスクや倫理的な観点も踏まえて導入を進める必要がある。具体的には、以下の通りだ。●AIの限界を理解する
AIは万能ではない。限界があることを理解した上で導入に臨む必要がある。元々AIは、事前に学習したデータやアルゴリズムに基づいて処理を行い、結果を出力する仕組みだ。そのため、データが不十分であったり、偏りがあったりすると、AIが導き出す予測や評価にも偏りが生じる。AIのアウトプットは“判断の補助”と位置づけ、担当者が俯瞰的に精度や妥当性を検証する姿勢が求められる。●最終的な判断は人が行う
採用可否など最終的な判断をAIに一任するのは避けるべきだ。AIが提示する情報はあくまで参考値であり、候補者の人柄やポテンシャル、将来性など、数値化しにくい要素を人が総合的に評価する必要がある。また、応募者との信頼関係を保つためにも、「AIはあくまで審査の一部を担う存在であり、最終判断は人間が行う」ことを明確に伝えることが重要だ。透明性のある運用ルールを公開することで、企業イメージの向上にもつながる。●AI活用に抵抗や不安を持つ求職者に配慮する
「AI採用」に抵抗感を抱く求職者は一定数存在する。特に面接をAIが担当する場合、「人間味のない選考」、「公平性に欠けるのでは」という不安を感じるケースもある。そのため、AIを導入している背景や意図(例:選考の公平化・効率化など)や、AIがどの段階・範囲で活用されるのか、最終判断がどのように行われるのかを事前に丁寧に説明することが望ましい。説明不足は誤解を招き、辞退率の上昇や企業への不信感につながりかねない。●データの偏りリスクに注意する
AIは過去のデータを学習することによって判断を行うため、元データの偏りがそのままAIの判定結果に影響する。例えば、特定の年齢層や学歴傾向に偏ったデータを学習させると、その傾向を再現するような「バイアス採用」を引き起こす可能性がある。また、AIがどのように評価を導いたのかが見えにくい「ブラックボックス化」もリスクである。偏りを防ぐためには、学習データの更新・監査や、AIの判断根拠の可視化が欠かせない。●データ・個人情報の管理を徹底する
「AI採用」では、多くの応募者データや動画情報を扱う。これらは「個人情報」や「機微情報」に該当する場合もあるため、情報漏えい・不正利用のリスク管理が非常に重要だ。データ暗号化、アクセス権の厳格管理、外部委託先のセキュリティ評価などを徹底する必要がある。また、応募者から適正な同意(オプトイン)を得ることも法的義務となるため、プライバシーポリシーの明示や取り扱いガイドラインの策定も欠かせない。●導入費用や運用コストを把握する
「AI採用」には、システムの導入費用だけでなく、運用コスト・ライセンス契約料・定期的なアップデート費用なども発生する。加えて、自社専用のAIシステムを開発、モデルを学習・チューニングする場合、そのための社内データ整備やメンテナンスにも人件費がかかる。導入前には、それらの費用を試算し、採用規模や業務負荷とのバランスを検証することが重要だ。既存の採用管理システムとAIを連携させるのかなども検討した上で、必要に応じて、まずは限定職種や一部工程でのトライアル導入から始めるのが現実的だ。「AI採用」の導入手順
「AI採用」の導入手順を説明しよう。(1)目的と課題の明確化
まずは、なぜ「AI採用」を導入する必要があるのかを明確にしなければいけない。面接の質向上、書類選考に要する業務時間の半減など、解決すべき課題をクリアすることで、AIをどこにどう活用したら良いかがイメージしやすくなるはずだ。(2)AI活用業務とシステム・ツールの選定
自社の採用フローの中でどの業務にどんな課題があり、その解決や改善に向けて、AIの活用が有効であるかを検討したい。どんな場面で用いるのかが想定できれば、どのようなシステム・ツールが必要かも明確になる。実際の選定にあたっては、信頼性や機能性、コスト、セキュリティなどを総合的に評価したい。(3)体制整備・ツール導入
「AI採用」を導入するには、そのメリットや必要性を社内に説明して合意を得る必要がある。もはや、採用活動そのものは人事部だけで行うものではなく、現場の協力や理解がなければ成功しない時代になっているからだ。また、自社の目的に合致したAI採用ツールを選定することも重要となる。ツールを決めた後は、IT部門と連携しセキュリティやネットワークの整備も行うようにしたい。(4)実施・改善
システム・ツールを導入した後は、運用と改善のフェーズに入っていく。運用を開始するにあたっては、自社の採用基準や人事評価基準などのデータをシステムに組み込む必要がある。また、運用後は定期的に効果検証を行い、必要であればデータの追加やアップデートを実施することも検討したい。「AI採用」の企業事例
ここでは4社の先進的な「AI採用」の企業事例を紹介しよう。●ソフトバンク
ソフトバンクでは採用オペレーションにおいてDXを積極的に推進し、AIを積極的に活用している。一つ目はエントリーシートの評価。これまで人が読んで評価していたところを2017年にIBM社のWatsonを導入し、一次評価をAIが行うようにした。二つ目が動画面接の評価。従来の集団面接から、学生から提出された動画をAIが評価する動画面接に置き換えた。こうした「AI採用」の導入によって、エントリーシートの年間工数は約75%、動画面接の年間工数は約85%削減され、その時間をより戦略的な採用活動に活用できるようになり、学生負担の軽減、評価基準の統一、企業イメージ向上にもつながったという。【もっと詳しく】なぜソフトバンクは採用DXを進めるのか ~攻めの採用戦略を支えるテクノロジー活用~
●荏原製作所
荏原製作所は、ポテンシャルのある人材の見極めや入社後の配属、組織の同質化といった課題に対し、多様な人材の採用を目的に独自の「ピープルアナリティクスAI」を開発・導入した。AIが適性検査や面接での発言・表情データを解析し、応募者の能力やバックグラウンド、経験や職歴といった「目に見えない多様性(タスクダイバーシティ)」を可視化することに成功。これにより、人材の潜在能力や特性を正確に把握しやすくした。同時に、多様な人材を惹きつけることを目的に「アンバサダー」という専門のジョブを新たに設置し、候補者にウェルビーイングを感じてもらいつつ、企業ブランディングにもつなげている。【もっと詳しく】新たなジョブ「アンバサダー」とデータを組み合わせた採用は、面接やオンボーディングに何をもたらしたか
●MANGO(現SEPTENI CORE)
宮崎のデジタルマーケティング支援会社であるMANGO(現SEPTENI CORE)は、若者の県外流出という人材課題に直面し、全国をターゲットにしたオンライン完結型の新卒採用を推進。セプテーニグループのAI人材育成システム「HaKaSe」を導入し、応募者の個性データと360度評価を分析。これにより、入社後の活躍シミュレーションや面接の相性診断を可能にした。選考はすべてオンラインで完結し、個性診断を基にした面接官用の事項提示や内定者へのキャリアフィードバックも実施。その結果、県外からのエントリー数は3年間で5倍に増加し、U・Iターン入社率は60%を達成した。【もっと詳しく】オンライン完結型の新卒採用で県外からのエントリー数が5倍に。コロナ禍で実現させる「U・Iターン採用」と「地域活性化」
●トランスコスモス
トランスコスモスは応募者選考に直接AIを活用するのではなく、面接官育成にAIを活用している。面接動画をAIに読み込ませることで、面接官の表情や話し方、質問内容をAIで可視化・スコア化し、客観的な強みと課題を把握できる仕組みを構築。さらに、個別最適化されたeラーニングやフォローアップ研修と組み合わせ、AIデータと人間の感性を融合したハイブリッドな育成体系を確立した。これにより、面接官のスキルが向上し、応募者の満足度向上や内定承諾率の10%増加を実現させた。【もっと詳しく】面接官育成にAI技術とヒューマンスキルを融合――内定承諾率10%増を実現したトランスコスモスの新・採用力強化プロジェクト
まとめ
「AI採用」は人事担当者の業務負担を軽減してくれるだけでなく、公平性の担保や基準の統一化など得られるメリットも大きい。しかし、AIを活用した採用にまだまだ抵抗を感じる人も存在することはしっかりと認識しておかなければならない。他にも、応募者とのコミュニケーションを取る機会が減ってしまう、応募者の考えを深掘りしにくいなどの課題も挙げられる。そうしたリスクを想定したうえで、自社ならではの工夫も施していくことをぜひ期待したい。導入には慎重な準備と運用が欠かせない。まずは、自社の採用課題を明確化し、AIが貢献できる領域を見極め、ツール導入後も継続的に効果検証や運用改善を行い、精度向上に努めることが重要となる。
【HRプロ】無料会員登録はこちらから >>
- 1