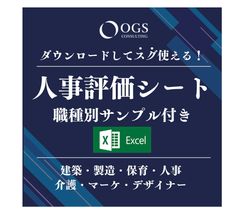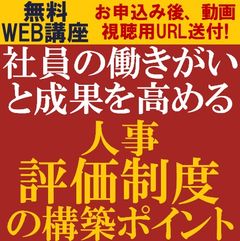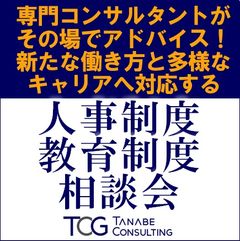「人事評価制度」の基本構成
「人事評価制度」とは、従業員の能力や業績などを客観的に評価し、昇格・昇進や給与・賞与といった待遇に反映させる仕組みだ。まずは「人事評価制度」の基本的な内容・成り立ちについておさらいしておこう。そもそも「人事評価」とは? 目的や評価制度の導入手順を解説【最新手法や事例も紹介】
●人事考課との違い
「人事評価」は、評価する項目や評価基準が従業員全員に対して開示されているのが一般的だ。また評価結果は給与・昇進などの待遇に反映されるだけでなく、従業員の育成・能力開発、異動・配置に活用されることも多い。「人事考課」もまた給与や異動・配置の参考にされるものだが、経営層、人事部、管理職によるシークレットな査定という特性を持つ。「人事評価」と「人事考課」の区別がない企業、あるいは「人事評価」+「人事考課」によって待遇や異動を決める企業もあるが、本稿ではオープンな査定の仕組み=「人事評価制度」について解説していく。●「人事評価制度」を構成する3つの制度
「人事評価制度」は「評価制度」単独で運用されるものではなく、従業員に序列をつける「等級制度」および給与や賞与を決める「報酬制度」とセットで機能することが一般的である。・評価制度
従業員の「何を」、「どのように」評価するかを定めた制度。評価する項目は、能力、ノルマ達成率や契約獲得数といった業績、事業への貢献度、資格、勤務態度など多岐に渡り、企業・業種・職種によって大きく異なる。・等級制度
従業員の序列を決めるための制度で、「等級」のほか「グレード」や「レベル」といった言葉が使われることもある。従業員を評価した結果、一定の基準を満たしていれば上の等級へと昇格することになる。等級が上がれば、求められる職務内容や役割、与えられる権限、就任できる役職、報酬も上がる仕組みで、評価項目の内容や基準も等級ごとに決められているのが一般的だ。「等級制度」の種類や企業事例とは? 人事労務管理への活用法も解説
・報酬制度
評価の結果と等級に応じて給与・賞与などの報酬額を決定する制度。客観的な評価+社内での序列に応じた報酬となることから、公平・公正な仕組みと言える。【人事評価制度の導入を検討中の方へ】「評価制度」に関するお役立ち資料やセミナー、サービスはこちら >>
【資料ダウンロード】2025年度版 人事労務関連法改正ガイド >>
「人事評価制度」を作るための7つのステップ
「人事評価制度」は、以下のような7段階の流れを意識して設計・導入することが望ましい。(1)制度の導入目的を明確にする
自社の企業理念、経営計画、事業の現状と課題、従業員が目指すべき姿などをもとに、何のために「人事評価制度」を策定・導入するのか、目的を明確に定めたい。導入目的を明確化することで評価項目・評価基準を設定しやすくなり、「人事評価制度」がなぜ必要かを社内に説明・周知しやすくもなるだろう。主な導入目的は以下のようなものがある。●生産性向上につなげたい
「人事評価制度」によって従業員は、自分が公平・公正に評価されている満足感、会社に貢献できている実感、頑張りや成果が待遇に反映されている納得感などを抱けるようになる。従業員のモチベーションとエンゲージメント、成長意欲が向上し、結果として生産性アップにつながるはずである。●人材育成に生かしたい
「人事評価制度」によって従業員の能力・保有スキルや資格、経験値、得意・不得意といった情報を可視化することができる。会社は個々のキャリアの方向性や現在の能力・特性をもとにした適切な育成計画を立案・実行しやすくなり、従業員は「次のステップに進むためには何が必要か」を理解し、自発的な能力開発に取り組んでくれるだろう。●人員配置を最適化したい
従業員の能力、適性、経験などを可視化し、将来的なキャリア感も把握できれば、能力を活かしたり伸ばしたりするために必要なポジションを与え、最適な部署に配置することが可能となる。●待遇の基準明確化
前述した通り「人事評価制度」は評価と等級と報酬が一体化したものであり、公平・公正な仕組みであることから、昇進や報酬額をシステマティックに決めることができる。従業員は納得感を抱き、モチベーションやエンゲージメントの向上にもつながるはずだ。(2)評価項目を設定する
従業員の「何を」評価するかは、従業員に求める資質・行動指針をベースとして決めることになる。また営業・セールス担当か、技術職か、総務・人事・経理といったバックオフィスか、部署や職種によっても評価すべき項目は変化する。代表的な評価項目は以下の通りだ。●能力評価
業務を遂行する能力と、そのために必要な知識・技術、保有する資格・検定・免許などを評価する。当然、業種や職務内容によって求められる能力は変わる。評価対象となる技術や資格を職種ごとに細かく設定し、企業がどのようなスキルの保持を期待・推奨しているかを示すことが必要となる。●業績評価
従業員の業績・成果を評価する。契約件数や売上げなど客観的な数値で個人の成果を表せる業種・職種であれば、わかりやすく公平感もある評価項目と言える。一方、総務・人事・経理などバックオフィス系業務やアシスタントなど、成果の数値化が難しい職種については、下記のMBO(目標管理制度)に基づく評価や情意評価を応用するなど工夫が必要となるだろう。●MBOに基づく評価
「MBO」はManagement by Objectivesの略で、「目標管理制度」と訳される。部署・職種に求められている成果や従業員の意欲・希望などを総合的に勘案して従業員自ら目標を設定し、それを「達成できたかどうか」に加え、その過程での行動や取り組み方も評価することになる。「目標管理(MBO)」の意味や目的とは? 面談と評価時のメリット、目標設定の手法で有名なSMARTなどを解説
●情意評価
仕事に対する意欲、取り組み方、遅刻・欠勤の有無、職場のルールや上司からの指示を遵守する姿勢、協調性やコミュニケーションの取り方など、業績以外の側面を評価する。成果・業績を数値化しにくい部門の従業員も評価できることになるが、評価の基準作りや実際の評価には公平感・公正感がいっそう求められる。●年功評価
日本の企業では長らく、入社年次・勤続年数をもとに昇給・昇進・報酬額を決定していたが、中途採用の増加や成果主義の導入などによって「古い人ほど偉い」という価値観が通用しにくくなっている。とはいえ、永年勤続に対する報奨や退職金の算出に反映させるべく、会社への長年に渡る功績を評価する意義はあるだろう。●職務評価
従業員が社内でどれくらい重要な仕事を担っているのか、担当する職務内容とその難易度を評価する。職務内容によって必要となる知識・スキル、精神的・肉体的な負担、責任の重さなどが異なるため、それらを分析したうえで評価項目を細かく設定するべきである。●役割評価
上記の職務評価が「ジョブ」に対する評価であるのに対して、役割評価では、その人が組織内のどんなポジションにいて、どのような役割を果たしているか、「ミッション」の遂行度を評価することになる。●コンピテンシー評価
社内にいるハイパフォーマーのスキルや仕事への取り組み方、価値観などを調べると、行動パターンに共通点が見られることがある。成果を出している従業員に共通する行動特性は「コンピテンシー」と呼ばれ、優秀な人材と同じような行動を取れているかを評価するのがコンピテンシー評価だ。多くの人たちにハイパフォーマーの行動を見習ってもらい、従業員全体の能力向上を図るという意味も持つ評価項目・評価技法と言える。「コンピテンシー」とは? 意味や活用メリットを解説【項目例一覧付き】
●360度評価
1人の従業員を、上司、部下、同僚などさまざまな立場の人が多面的に評価するのが360度評価だ。直属の上司だけでは見逃してしまうこと、気づかなかったことが評価されるとともに客観性も確保される。「360度評価」とは? メリットや評価項目・運用の流れを解説
(3)評価の基準・手法・頻度を設定する
従業員の「何を」評価するかとともに、「どう」評価するか、評価基準と評価手法を決めることも重要である。たとえば「チームリーダーとしての役割を十分に果たしているか」という評価項目に対し、「とても良い」から「とても悪い」まで、あるいはAからDのように数段階のランクをつける手法が一般的だ。等級や役職が上がれば、求められる職務や能力、果たすべき役割は変わるので、当然ながら評価基準も変わる。職種・等級・役職ごとに、どんな行動や成果が「とても良い」とされるのか、何を満たしていないとDランクにとどまるのか、細かな規定が必要だ。評価の基準や手法は定量的・客観的で公平なものであることが理想で、各種の評価項目をバランスよく組み合わせて従業員を多角的・総合的に評価することも重要である。評価を実施する時期、評価対象とする期間、評価頻度(年1回や半期に1回など)なども決めておかなければならない。
(4)待遇への反映方法を整備する
項目ごとの評価結果や総合評価を、どう待遇に反映させるのかを決める。「評価に応じて昇給する」、「特定の項目で高評価を得た場合は賞与に反映させる」、「一定以上の評価を何期か連続して得られれば等級が1つ上がる」、「その等級における給与の上限と下限を設定する」、「等級ごとに就任できる役職とその手当を決める」など、評価と等級と報酬を連動させた規定を作成することになる。(5)マニュアルの整備と評価担当社員の教育
評価項目、評価の基準・手法、評価する際の注意点などをわかりやすくまとめるとともに、評価・等級・報酬がどのように連動しているかを解説した「人事評価マニュアル」の整備は必須の作業だ。このマニュアルをもとに評価担当社員(主として管理職)に対して、客観的に評価するためのポイント、評価者が陥りがちな心理的傾向、評価とその結果が従業員に与える影響などを盛り込んだ研修を実施する。重要なのは「面倒」や「適当でいい」などと考えずに偏りのない公平・公正な評価を実現する、そのための教育である。(6)従業員への周知から運用へ
「人事評価制度」の目的と必要性、具体的にどう評価されるのか、誰がどのタイミングで評価するのかといった制度の概要を全社員に対して周知しなければならない。文書だけで済まさず、質疑応答を含む説明会を開催することが望ましい。周知機会から運用開始まで1カ月~数カ月程度の期間を置くようにしたい。(7)定期的・継続的な改善
運用開始後は定期的・継続的な改善に取り組みたい。マニュアル通りの評価が実践されているか、制度に対する従業員の理解度・納得度・満足度は十分なレベルにあるか、従業員の成長は見られるか、スムーズな昇進・昇格・異動が実現しているか、業績やエンゲージメントは向上したかなど、「人事評価制度」の導入目的が達成できているかをチェック。不具合の解消に加えて、事業の成長やビジネス環境の変化などに応じたアップデートも不可欠となる。【評価制度の見直しを検討中の方へ】「評価制度」に関するお役立ち資料やセミナー、サービスはこちら >>
「人事評価制度」を設計・運用する際のポイント
次に「人事評価制度」を設計・運用する際に留意すべきポイントについて解説していく。●社会情勢や政府の要請を踏まえた設計とする
働き方関連法案の改正・施行により「同一労働・同一賃金」の原則が導入され、どのような雇用形態であれ、給与をはじめとする待遇に不合理な格差が発生しない仕組みが求められるようになった。またリモートワークの増加、オフィス出勤とのハイブリッド化、フレックスタイム制の普及など働き方の多様化も進んでいる。こうした動きに対応した「人事評価制度」を設計しなければならない。「同一労働・同一賃金」の意味、ニュース・サービス・セミナーなどの最新情報
●経営戦略・人事戦略と連動させる
近年のビジネスシーンにおける大きな動向として、人的資本経営や「経営戦略と人事戦略の連動」がある。自社の理念を実現するために経営戦略を立て、そこから逆算して人材の獲得・育成・活用に取り組む、という流れだ。単純に業績や働き方の良し悪しを評価するのではなく、部門ごとに求められる人物像を設定し、そこへ向けて従業員が成長できるよう、経営戦略、採用、評価、育成、配置が一体化した、合理性の高い「人事評価制度」とするべきである。●中長期的な視点で取り組む
ビジネス環境が激変する中で、事業の方向性、組織のあり方と規模、従業員の多様性、求められる人物像、ハイパフォーマーの行動特性なども揺れ動くだろう。「人事評価制度」に期待する効果も変化するはずであり、短期間での成果を目指すのではなく、会社組織としての中長期計画を念頭に置いた設計と運用を心がけたい。●現実的に運用できるかどうかが大切
「人事評価制度」の導入により、評価者である管理職や、運用にあたる人事部の負担は大きくなる。マニュアルが整備されていなかったり運用に手間がかかりすぎる仕組みだったりすると、評価が停滞し、評価・等級・報酬の連動が機能しなくなって、制度が形骸化してしまう恐れがある。自社の状況に合わせたシンプルな制度設計とし、Microsoft Excelなどで独自に作成した評価シート、または人事評価システムを提供している事業者を利用することでスムーズな運用を実現させたい。まとめ~「人事評価制度」は課題解決と持続的成長に寄与する仕組み
「人事評価制度」を機能させるためには、自社の課題に合わせた合理的でわかりやすい設計、必要性と目的の周知徹底、公平・公正な評価につながるマニュアル整備と評価者の教育、評価・等級・報酬の連動、スムーズな運用と定期的な改善が不可欠となる。これらが実現すれば、従業員の行動目標・行動指針が明確となり、高い意欲とともに業務を遂行する社員が増え、自身の待遇に対する納得感、エンゲージメント、定着率が向上するはずだ。会社側には、育成の効果アップ、離職率の低下、従業員の適性に応じた人材配置といったメリットがもたらされ、採用力も高まるはずだ。結果的に生産性は大きく向上するだろう。
企業としてのさまざまな課題解決、そして持続的成長を果たすための有効な施策として「人事評価制度」の設計・導入を検討したいところである。
- 1