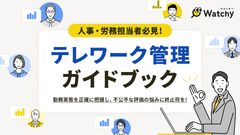「勤怠管理」とは? 意味と「就業管理」との違い
「勤怠管理」とは、企業が、従業員の日々の労働時間を正確に把握するための仕組みのことだ。主な管理項目としては、下記が挙げられる。・出勤、退勤、休憩時間
・欠勤・遅刻の状況
・休日の取得状況
●「就業管理」との違い
企業が行う従業員の管理で、「勤怠管理」に似たものとして「就業管理」がある。これは、企業の従業員が作業する開始時刻や就業時刻、休憩時間などを「統一」することを指す。従業員の労働時間や休暇、休日などに関し、「法律に則したルール」を定めなくてはならない。企業は、従業員の働き方が不均衡にならないように配慮し、生産性やパフォーマンスを向上させなければならないため、「勤怠管理」のほかに「就業管理」が必要なのである。「就業管理」として企業が管理する内容は、以下のとおり。
・従業員の出勤時間や欠勤状況
・休暇の取得状況を把握し、企業の就業規則の遵守状況について
・管理の記録に基づいた給与・残業代の計算、有給休暇の取得日数などの管理
「勤怠管理」と「就業管理」の違いとは、管理システムで例えると、「就業管理システム」は、従業員の出社時刻や退勤時刻、休憩時間の「統一」を管理することを指す。一方、「勤怠管理システム」は、従業員の勤務時間や欠勤日数などの数字的情報の管理を行うためのものだ。
【関連コンテンツ】「勤怠管理」に関するお役立ち情報やサービス情報一覧はこちら >>
【HRプロ】無料会員登録はこちらから >>
「勤怠管理」を行うべき事業所
「勤怠管理」を行うべき事業所は、労働基準法の労働時間の規定(第4章)が適用される事業所を指す。農業や水産業といった自然や天候の影響によって業務日・時間が左右される特定の職種を除いて、従業員を雇うほとんどの事業所が対象である。【参考】e-Gov法令検索:「労働基準法」第四章 条文
「勤怠管理」の対象者
「勤怠管理」の対象である従業員は、企業の規模・業種に拘わらず、管理監督者以外の「雇用している全従業員」が該当し、例外はないとされてきた。ここでいう「管理監督者」とは、従業員の労務管理において一定の責任がある者(部長や事業所長、経営層の秘書など)を指し、経営に関わる業務を請け負っている従業員が含まれる。ただし、2019年4月に改正された「労働安全衛生法」では、「事業者は、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない」という条文が追加された。これによって、「管理監督者」は「労働時間を適正に把握すること」が義務化されているので注意が必要だ。
また、厚生労働省の「ガイドライン」によると、「労働基準法第41条に定める者及びみなし労働時間制が適応される労働者(事業場外労働を行う者にあっては、みなし労働時間性が適用される時間に限る。)を除くすべての労働者」とある。この、「労働基準法第41条に定める者」が、上述の「管理監督者」といった事業所の責任者を指す。
なお、「みなし労働時間制」には、「事業場外労働のみなし労働時間制」、「専門業務型裁量労働制」、「企画業務型裁量労働制」が含まれる。例えば「高度プロフェッショナル制度」は、「みなし労働時間制」には当たらないが、健康確保措置は求められ、年間104日以上の休日取得状況の把握が必要となる。それぞれの制度によって、配慮すべき項目があるため、細かな内容を確認しておく必要があるだろう。
【参考】厚生労働省:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(PDF)
「勤怠管理」で管理する項目
前述の通り、「勤怠管理」は、労働時間が適性に守られていることを管理する仕組みだ。「労働基準法」の第32条では、法定労働時間は「1日8時間、1週間に週40時間を超えない範囲内」と定められているため、この範囲を遵守するよう管理する必要もある。ここでは、管理項目を確認していこう。●出勤日、欠勤日、休日出勤日
1ヵ月単位でこれらの勤務状況を把握しなければならない。これは、給与計算にも影響するため、適切な管理が必要だ。また、従業員の健康を管理する上で、従業員が適切に休日を取得できているか、休日出勤があった場合は、その分の代休や振替休日をきちんと取得できているかなどの情報は欠かせない。●始業・終了時刻、労働時間、休憩時間
1日の労働時間も正確に把握する必要がある。この記録をとっておくことで、遅刻や早退が多い従業員に、適正な業務指導や部署移動・配置換えといった対処をする際、根拠として示すことができる。また、給与面でも、賃金算定のために始業・終業について「1分単位」で管理する。●時間外労働時間、深夜労働時間、休日労働時間
企業は、「時間外労働」や「深夜残業」、「休日出勤」を行った従業員に対して、「割増賃金」を支払う義務がある。また、「法定労働時間」を超過した労働時間も支払い義務があるため、企業の人員コストに大きく影響する。それぞれ割増率は異なるため、「勤怠管理」で正確に時間を把握・管理することが必要だ。●有休取得日数・残日数
2019年4月に「労働基準法」が改正され、「年次有給休暇の取得」も義務化された。従業員を休ませる(有給休暇を取得させる)ことも、使用者としての企業が負っている義務であると明文化された形だ。従業員が適切に有休を取得できているかを把握するためにも、勤怠管理をしっかり行うことは重要である。「勤怠管理」の重要性
企業にとって「勤怠管理」が重要な理由には、下記のようなものがある。●使用者側の法定義務とコンプライアンス遵守
企業に課される「勤怠管理」の法的義務は、従業員の過重労働を防止することを目的としている。「労働基準法」の「法定労働時間(原則として、1日に8時間、1週間に40時間)」の遵守というコンプライアンス面と、政府が推し進める「働き方改革」を推進する面でも、企業は「勤怠管理」について義務を負っていると言える。また、「働き方改革」にともない、2019年4月1日に改正された「労働安全衛生法」によって、労働時間の把握は「客観的な方法」によって行うことも義務化された。このことから、企業は従業員の勤怠状況に関して、タイムカードやICカード、もしくは勤怠管理システムを用いた客観的な記録をとり、3年間の保存が必要となった。
●正確で明瞭な給与計算の実現
「勤怠管理」は企業の義務ではあると同時に、メリットももたらす。正しい労働時間の確認を基にした給与計算は、コストカットに役立つだけでなく、透明性のある給与支払いにもつながる。反対に、勤怠管理が正しく行われていなければ、残業代の正確な把握ができず、保険料や税金の計算に支障をきたす恐れもある。「未払い残業代」に関する問題が取りざたされている昨今、2年間さかのぼって後から支給することが認められているとはいえ、もとから正しく支払うことで、従業員とのトラブル回避にも役立つ。●労務トラブルの未然防止
従業員数や企業規模が大きいほど、従業員一人ひとりに目を配って管理することは困難になる。「勤怠管理」によって、問題のある労働について早期の対策が打てれば、過重労働や訴訟といった企業トラブルを未然に防ぐことにもなる。長時間労働を減らすことで、従業員の心身の健康維持、モチベーション・生産性の向上も図ることができるだろう。●働き方の健全化と労働環境の改善
過酷な長時間労働や残業手当の未払いを起こすような悪質な企業は、適正な労務が行われておらず、コンプライアンス遵守の精神に反している。「勤怠管理」が正しく行われ、労働時間と賃金支払いに透明性が確保されていることは、法令遵守と健全経営が徹底されているという証左となり、健全な職場環境の維持と企業価値の向上が期待できる。●企業の信頼性と組織運営の安定化
適切な「勤怠管理」により法令を遵守する姿勢を示せば、クリーンな企業イメージにつながる。これにより従業員の安心感が醸成され、離職防止や採用競争での優位性を支える要素にもなるだろう。正しい労務管理は組織の運営基盤を強化し、持続可能な企業成長を支える重要な要素として機能する。「勤怠管理」の主な手法とそれぞれのメリット・デメリット
「勤怠管理」の具体的な手法としては、アナログなものから、テレワークにも対応できるデジタルなものまであり、自社に合ったものを選ぶ必要がある。●紙の出勤簿
勤怠を紙の出勤簿で記録する方法は、「勤怠管理」の中で最もアナログな手段だ。「紙の出勤簿」は、出勤・退勤時刻、残業時間、休憩時間、休日取得、遅刻・早退といった情報をカレンダー仕様の紙のフォーマットに手書きで書き込む。すべての情報を1枚のシートに一元的に管理できる点はメリットだ。しかし、この方法では従業員の手書きによる「自己申告」が主となるため、労働環境の客観性が担保されにくく、不正申告やサービス残業といった労務リスクを引き起こしやすい。
紙媒体を使用した管理方法については、記入や修正する際は手書きであること、基本的に従業員からの申告であることから、厚生労働省の「ガイドライン」に定める「客観的な記録」にはなりにくい(ただし、この「ガイドライン」には、自己申告制の特例措置についても定義されており、クリアできていれば「客観的な記録」として認められる場合もある)。
・特別な機器が不要で導入コストはほとんどかからない
・1枚のシートにすべての情報をまとめて管理できる
【デメリット】
・「自己申告」が主となるため、「客観的な記録」としての信頼性に欠ける
・不正申告やサービス残業を引き起こしやすく、労務リスクが高い
・毎月の集計作業が手作業となり、負担とミスにつながりやすい
●タイムカード
「タイムカード」は、専用のタイムレコーダーに打刻シートを差して出退勤時刻を記録する方法だ。一般的に1ヵ月間の勤怠状況を、1人当たり1枚のシートで管理するケースが多く、打刻時刻が物理的に印字されるため、神の出勤簿よりも客観性があるとみなされる。打刻する端末(レコーダー)を1台~数台購入すれば、あとは用紙を補給するだけで済むため、導入・運用コストは比較的低く、複雑な操作もいらない。ただし、操作が単純な分、記録できる内容も始業・終業時刻に限られているものが多く、休憩時間や残業時間の管理、勤怠データ使った分析といったことには向かない。
また、レコーダーが社内に設置されるため、テレワークや遠隔地での勤務、直行直帰といった多様な働き方には対応できず、「リアルタイムに打刻して記録を残せない」ことがデメリットになる。毎月の集計作業では手計算するか、別の表計算ソフトを使用しなければならず、人事・労務担当者の労力と時間的負担があり、転記ミスといったリスクもある。
また、タイムカードによる管理も、基本的に従業員の手動による申告であり、打刻漏れや不正打刻が発生しうることから、厚生労働省の「ガイドライン」に定める「客観的な記録」にはなりにくいことにも注意を要する。
・導入コストが比較的低く、複雑な操作がいらない
・手書きよりも打刻時刻の客観性はある
【デメリット】
・従業員の手動のため「客観的な記録」を担保し切れない場合がある
・記録できる内容が単純で、データ分析や詳細な勤怠管理には不向き
・社内でしかリアルタイムに打刻して記録を残せない
・集計作業に手間と時間がかかり、転記ミスが発生しやすい
●表計算ソフトによる管理(エクセルなど)
エクセルなどの表計算ソフトを使って、従業員が出退勤時刻を入力する手法もある。セルに数式を設定することで労働時間を自動計算でき、打刻(入力)から集計までを同時に行える即時性はメリットである。また、無料のテンプレートもインターネット上で入手しやすく、コストをかけずに、すぐ使用できる。また、休憩時間や休日、遅刻・早退などを細かく分類し、自社の実情・働き方に合わせてフォーマットをカスタマイズすることも可能だ。しかし、基本操作は従業員自身が行うため、入力ミスや不正申告の可能性は否めず、これも「客観的な記録」とはい言い難い。テレワークなど勤務形態によっては対応できない可能性もある。また、可能な記録が単純計算・集計に留まるため、例えば、勤怠記録を利用して分析を行いたい場合、せっかくデータ化されていても分析の材料としては不十分だ。さらに、法改正があると、残業の割増率の変更にともない定期的に計算式やシート構成を確認・変更する手間も人事・労務担当者に発生する。
・自動的に労働時間を計算でき、打刻(入力)から集計までを同時に行える
・フォーマットが入手しやすく、自社の状況に合わせてカスタマイズができる
・導入コストは低い
【デメリット】
・入力ミスや不正申告の可能性があり、「客観的な記録」としては不十分
・高度な分析の材料としては不十分
・法改正に合わせて計算式の変更が必要
・ファイルの共有管理やセキュリティ対策が煩雑になりやすい
●勤怠管理システム
勤怠管理システムは、タイムレコーダーやスマートフォン、パソコンなどと連携して、打刻から集計、分析までを一貫してシステムで管理する。メリットとしては、どこからでもリアルタイムで打刻管理ができ、集計や分析にかかる手間も少ないことが挙げられる。給与システムや人事システムとも連携できるので、転記する手間がなく、給与計算ミスの防止にもつながる。個別の勤務状況にアラート機能を設定すれば、労働過多になっている従業員を自動で割り出したり、適切な対応をすぐに行ったりすることができる。コンプライアンス強化の面で見ると、最も有効な方法と言える。
また、打刻手段にはICカードの他にも生体認証(指紋・指静脈・顔の認証)や、GPSを使うといったさまざまな方法があり、パソコンだけでなくスマートフォンやタブレットで利用できるなど、デバイスの選択肢の幅が広いこともポイントだ。テレワークや社外での業務が多い従業員がいる場合でも、インターネットに接続できれば、クラウド型のシステムとスマートフォンやタブレットを組み合わせることで、オンタイムで簡単に管理が行える。
ただし、こういった「勤怠管理システム」の導入にはコストがかかりやすい。システム選びの際には、操作性やセキュリティ面など、注意が必要な点もあることを忘れてはいけない。
・客観性が高く、法令遵守に最も適している
・どこからでもリアルタイムで打刻管理ができる
・集計や分析にかかる手間が少ない
・給与システムとも連携できる
・アラート機能により労働過多になっている従業員を割り出せる
【デメリット】
・導入および運用にコストがかかる
・操作性やセキュリティ面、既存システムとの連携などを慎重に確認する必要がある
「人事管理システム」の編集部おすすめ比較! 機能・費用相場・選び方も解説
「勤怠管理」を“客観的な記録”にするためのポイント
「勤怠管理」は、原則的に「客観的な記録」であることが必要条件だ。従業員数を含めた企業規模、雇用形態などさまざまな要件から、自社の状況や従業員にとって一番適した管理方法を選ぶことが肝心である。管理方法を検討する際には、以下の点をチェックしておくとよいだろう。(1)打刻忘れのミスを防止でき、従業員にとって操作性は簡便か
(2)給与計算や勤怠データの集計といった他の管理業務にも流用でき、人事担当者の負担にならないか
(3)従業員数や雇用形態、導入コストなど、自社の実情や働き方に即した方法で管理できるか
「勤怠管理」で注意すべきポイント
ひとつの企業内でさまざまな働き方をしている従業員がいたり、雇用形態がまちまちであったりする現在、多様な働き方に対応した「勤怠管理」も求められている。●多様な働き方の従業員、契約社員、非正規雇用の従業員
多様な働き方が広がっている今、勤務形態ごとに適切な勤怠管理を行うことが求められている。「変形労働時間制」や「みなし労働時間制」などが適用される従業員の場合、出勤簿やタイムカードなどのアナログ手法では管理が難しい。また、契約社員は、契約通りに勤務しているかを把握するために、正規従業員と同等の勤怠管理を行わなければならないため、働き方に合わせて、始業・終業時刻を正確に記録し、給与計算に反映できる勤怠管理を導入する必要がある。ただし、非正規社員の中でも「派遣社員」の場合は、勤怠管理は派遣元企業が行うため、派遣先の企業は勤務時間の把握・管理ができていれば問題ない。
●パート・アルバイトの従業員
パートやアルバイト従業員のシフト管理にも「勤怠管理」が必要だ。パート・アルバイト従業員が多い職場では、勤務日や勤務時間が一人ひとり異なるため、休憩時間や勤務時間などをしっかりと把握することが重要だ。また、個々に時給も違うため、給与計算も手間がかかる。適正で客観的な記録と、手間をかけずに勤怠データ収集が行えるよう、正規雇用の従業員と同様に勤怠管理の方法を検討した方がよい。また、シフト管理では、1日の人件費や本人の勤務希望日なども考慮しなければない。シフト作成業務にもかなりの労力を要するため、業務希望日を反映しながら自動でシフト作成もできる勤怠管理システムなど、時間と手間を省く管理方法の検討も必要だ。
●「扶養控除内」を希望する従業員
従業員が「扶養控除内」での勤務を希望している場合は、扶養控除内に収まるように配慮した勤怠管理を行わなければならない。配偶者の扶養に入っている従業員の場合、年収や週の労働時間の規定範囲を超えると、扶養から外れてしまう可能性があるからだ。いわゆる、所得税が発生する「103万円の壁」、従業員が501人以上の企業で勤務日数・時間など諸条件によって個人で社会保険加入義務が発生する「106万円の壁」、配偶者の社会保険の扶養から外れる「130万円の壁」である。まずは、従業員がどの「扶養控除内」を希望しているのか確認して、従業員にとって損害とならないよう、配慮ある管理を行うことが重要だ。
テレワークにおける「勤怠管理」の方法と注意点
オフィスから離れた場所で働くテレワークでは、従業員の労働時間を「適正に把握」することが企業の重要な義務となる。労務リスクを避け、多様な働き方を支えるためには、従来の管理手法を見直し、デジタルツールを活用した明確なルールと仕組みの導入が不可欠となる。●テレワーク下で、自己申告制の勤怠管理を行うには
テレワーク下の勤怠管理では、人事労務の担当者や上司が、直接、従業員の勤務状況を把握することはできない。そのため、社内ルールを徹底させるよう対策が必要となった。勤怠管理の方法としては、基本的に「自己申告制」によるものとなる。自己申告制をとる場合は、従業員に対し適正に記録を行うことを周知・指導し、必要に応じて実態調査も行う必要があるだろう。また、テレワークに適した勤怠管理システムを導入することも検討が必要だ。その場合には、インターネットに接続できればどこでも使えるクラウド型で、スマートフォンなどのデバイスを組み合わせて使用できるような、できるだけ手間がなく、操作性も簡単なものを検討する必要がある。
●テレワーク下の勤怠管理における注意点
・違法な長時間労働を防止企業は、本来は全従業員の実労働時間の実態を適切に把握しなければならない。しかしこれが徹底されず、法定労働時間を超えた長時間労働を従業員に強いてしまうケースがあり、社会問題化している。特にテレワーク下では人事や上長の目も届きにくいため、こうしたリスクは高まる。
例えば、勤怠管理システムと社内の各システムを連携させ、退勤後は業務に関連するシステムへのアクセス制限を行うといった施策で、長時間労働や隠れ残業を防ぐことができる。勤怠管理を応用した施策によって、長時間労働を行ってしまうような社内風土を廃し、健康被害などで問題が顕在化する前に対策を打つことにもつなげられる。
・年次有給休暇取得の義務付け
勤怠管理システムの中には、年次有給休暇などの各種休暇の取得を管理する機能を備えたものもある。この「休暇管理機能」を活用することで、各従業員の休暇取得状況を一覧で管理することが可能になり、従業員自身も休暇の取得日数・残日数・年次有給休暇取得率をリアルタイムで確認できる。
●チェックしておきたいテレワーク下の「勤怠管理」システムに必要な機能
・「勤務時間の管理」ができること最低限、始業時刻・終業時刻・休憩が打刻でき、従業員それぞれ雇用形態に則したルールが適用できることも必要だ。
・「作業状況の管理」ができること
勤怠管理ツールには、オフィス外で働いている従業員の作業中のパソコン画面をスクリーンショットできるといった、作業状況が把握できたり、営業職にはGPS機能を使って立ち寄った先を把握できたりするツールもある。ただし、管理面での「作業が見えない」ことへの不安は軽減できるが、従業員に「監視されている」ととられないよう、限度や範囲に対する配慮が必要だ。
・給与やその他のツールと連携できること
せっかく管理ツールを導入するのであれば、その記録が給与やその他のシステムと連携できた方が、コストカットにつながり、管理業務の効率化にもなる。テレワークを契機にして勤怠管理システムを導入するならば、自社の既存の給与システムと連携可能なものを選ぶと良いだろう。
まとめ
政府推進の「働き方改革」やコロナ禍によって、多様な働き方が認められるようになったことで、「勤怠管理」は、単に遅刻・欠席を取り締まるような役割だけではなくなった。そして、法律改正などで、企業が担う義務の内容にも変化が生じている。企業は、従業員の働きやすさにつなげるために、刻一刻と進む変化に対応した勤怠管理を行うことが求められているといえる。よくある質問
●従業員の「勤怠管理」は義務か?
2019年4月に改正された「労働安全衛生法」では、「事業者は、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない」という条文が追加されている。これによって、「管理監督者」は「労働時間を適正に把握すること」が義務化された。また、労働時間の把握は「客観的な方法」によっておこなうことが必須となっている。●「勤怠管理」は誰の仕事か?
「勤怠管理」は労働基準法において、使用者(会社)の責任であり義務とされているが、実際の業務を誰が担当するかは企業によって異なる。創業したばかりの企業であれば社長がおこなうケースもあるだろうし、中小企業であれば総務担当が、大企業であれば労務担当や人事担当の部署が担当するのが一般的だ。- 1