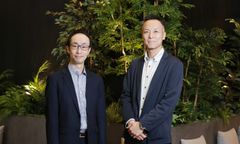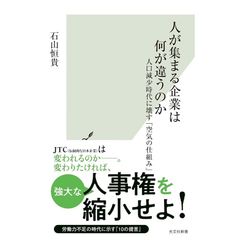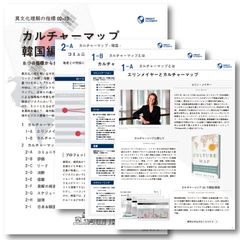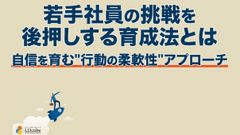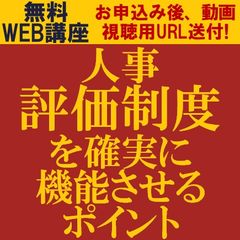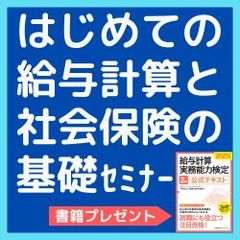「キャリア」は、職務を基軸とした経歴や経験などを意味する。近年では、従業員のエンゲージメントやモチベーションの向上、企業の生産性向上を目的として従業員の自律的なキャリア形成を支援していこうという取り組みが注目されている。本稿では、「キャリア」の意味や主なキャリア理論、自律支援の重要性、さらにキャリア自律支援の重要性と具体的な施策などを詳細に解説していく。

「キャリア」の意味と厚生労働省による定義
「キャリア」とは、日本語で「職業や職務の経歴」と訳される。厚生労働省によると、“「経歴」、「経験」、「発展」さらには、「関連した職務の連鎖」等と表現され、時間的持続性ないし継続性を持った概念”であると定義付けられている。言い換えれば、「キャリア」を積む結果として、職務上の能力が磨かれていくと説明している。【人事担当者必見】キャリア自律に関するお役立ち資料やセミナーなどはこちら >>
よく使われる「キャリア」の関連用語
「キャリア」に関連する用語が多数存在する。それぞれの意味を理解しよう。●キャリアアップ
キャリアアップとは、専門的な能力・知識をより一層身に付け、職歴や経歴を高めることを言う。目標を実現するための手段であるだけに、個人によって考え方や方法は異なる。具体的には、仕事の範囲を広げる、給与を上げる、昇格するなどが挙げられる。●キャリアビジョン
キャリアビジョンとは、自分が理想とする将来の仕事像、人生像を意味する。「昇給・昇格を目指す」、「仕事を通じて社会課題を解決したい」などという仕事上の目標はもちろん、「ワークライフバランスを確保したい」など仕事を進める上での価値観も含まれる。●キャリアプラン
キャリアプランとは、仕事上の目標や理想とする働き方、およびそれらを実現するための長期的な計画を言う。5年以上のスパンで考えることが多く、同じ企業での昇進や昇格だけでなく、将来的な転職や独立など、さまざまな選択肢が用意されていることも踏まえて、人生全体に関わる仕事のプランを設定する。●キャリアデザイン
キャリアデザインとは、将来における自分の理想像やキャリアの積み方を設計することを意味する。「どんな経歴やスキルをいつまでに身に付けるのか」「プライベートで叶えたいことは何か」などを考え、それらを実現するための道筋を主体的に立てていくことが求められる。【HRプロ関連記事】「キャリアデザイン」の意味や目的とは? 企業が実践できる具体例も紹介 >>
●キャリアパス
キャリアパスとは、勤務先におけるキャリア形成のプロセス、道筋を指す。なので、特定の組織に限定されないキャリアプランとは意味合いが違って来る。キャリアパスは、社員本人が自ら計画することもあれば、会社側がモデルプランとして社員に提示することもあり得る。●キャリア自律(キャリアオーナーシップ)
キャリア自律とは、主体的にキャリア形成に取り組むことを言う。キャリアオーナーシップとも言い、米国のキャリア・アクション・センターでは、「変化する環境において自らのキャリア構築と学習を主体的かつ継続的に取り組むこと」と定義する。ポイントは、キャリア自律は自らの意思に基づいて行う継続的な学習から形成されるということ。環境は常に変化するだけに、柔軟性を持って自分のキャリアを切り開いていく姿勢が重要となる。●キャリア開発
キャリア開発とは、業務に携わるプロセスによって培われた能力や知識、経験、スキルを中長期的、かつ継続的に磨いていくこと。自らのこれまでのキャリアを振り返ったうえで、必要な能力を獲得するために、今後どういった経験が必要となるのかを従業員が企業とともに考え、実行していくことが重要となる。【HRプロ関連記事】「キャリア開発」の意味とは? キャリアデザインとの違いや企業に必要な背景、方法を解説 >>
【資料ダウンロード】キャリア開発に関するお役立ち資料やセミナーなど >>
人材育成に役立つ6つの「キャリア理論」を紹介
キャリアカウンセリングの発達に伴い、さまざまなキャリア理論が生み出されている。それらを紹介していこう。●プランド・ハップンスタンス理論
プランド・ハップンスタンス理論とは、1999年に米国スタンフォード大学のジョン・D・クランボルツ教授が提唱したキャリア理論だ。日本語では「計画された偶発性理論」などと訳される。従来までのキャリア理論は、「自分で計画し実行する」という考え方に立っていたが、この理論では「偶然の出来事が個人のキャリア形成に役立つ」と考える。予期せぬ出来事をチャンスと捉え、積極的に行動することの重要性を示唆している。●キャリア・アンカー
キャリア・アンカーは、米国の心理学者エドガー・ヘンリー・シャイン教授が提唱する、キャリア形成に関する理論だ。具体的には、「キャリア」を選択する際に、自分の動機とコアコンピタンス、価値観という3つの要素が重なった部分を人生のアンカー(船のいかり)と捉える。適職の発見に役立つとされている。●プロティアン・キャリア
プロティアン・キャリアとは、米国の心理学者ダグラス・ホール教授が提唱した、キャリア形成に関する理論である。環境の変化に応じて、個人が自律的かつ変幻自在に働き方や能力を柔軟に変えることができるキャリアと位置付ける。プロティアン・キャリアを築くために不可欠となるのが、アイデンティティ(自己認識)とアダプタビリティ(適応能力)であると説いている。●ライフキャリアレインボー
ライフキャリアレインボーは、1950年代に米国の教育学者ドナルド・E・スーパー教授が提唱した理論だ。「キャリア」は仕事に限らず、社会や家庭でさまざまな役割(家庭人・労働者など)と時間(年齢)を積み重ねた結果、生涯にわたる「ライフキャリア」として形成されると説いている。●成人の発達理論「4S」
成人の発達理論「4S」とは、全米キャリア開発協会の会長を歴任したナンシー・K・シュロスバーグ氏が提唱する理論だ。「転機」の視点から成人の発達を捉え、「キャリア」は人生における転機を乗り越える努力と工夫によって形成されると説いている。具体的には、自身のリソースである4つの「S」、すなわち「状況(Situation)」、「自己(Self)」、「支援(Support)」、「戦略(Strategies)」を検証した上で、変化を受け入れることが重要だと説く。●特性因子理論
特性因子理論は、米国のフランク・パーソンズ(Frank Parsons)教授が唱えた、人と職業のマッチングに関するキャリア理論だ。個人の能力や特性に合致した職業を選択することで、仕事に対する満足度が高くなるという仮説を起点にしている。個人と職業を適切にマッチングさせるポイントには、自己分析と職業分析、理論的推論という3つの要素がある。また、それらを補完するために7つの段階での支援も提唱している。「キャリア形成」のための5つのポイント
「キャリア」を形成するにあたっては、幾つかのポイントがある。それらを解説したい。●自己分析
今後自分がどんなキャリアを築いていけば良いだろうかと問われても、すぐには解が出てこないものだ。まずは、自分を深く理解しないといけない。仕事において大切にしている価値観や関心がある分野、目指している給与や理想とする働き方などを、一つひとつ具体的に考えてみることが重要となってくる。自己分析の方法は、さまざまだ。例えば、「自分史」を作成する、「マインドマップ」で思考を整理するなどが挙げられる。●中長期的視点
「キャリア形成」は、目先の目標だけでなく、中長期的な視点で考えなくてはならない。最終的なゴールに向けてマイルストーンを刻んでいくことが重要だ。具体的には、5年後、10年後などの年数、あるいは20代、30代、40代などの年代で区切り、それぞれでの目標を立ててみよう。中長期的な視点を持つことで、理想とする自分像に向かって今何をしたら良いのかが明確になってくる。●Will-Can-Mustの思考
Will-Can-Mustは、キャリア形成を考えるにあたっての重要なフレームワークの1つだ。それぞれの単語は、以下のような意味を持つ。【Will】今後のキャリアで「成し遂げたいこと」
【Can】持っている知識やスキル・経験など「できること」
【Must】目標達成のために「やらなければいけないこと」
これらの項目についてリストアップしていくことで、キャリアビジョンやキャリアプランが作成しやすくなる。
●ロールモデルの発見
自分が「こうなりたい」という人が見つけると、キャリア形成がイメージしやすくなる。そういう人が、ロールモデルだ。職場の先輩や上司で良いし、家族、有名人、歴史上の偉人でも構わない。ロールモデルを発見できたら、その人の「キャリア」や人生観、価値観を調べよう。最後に、ロールモデルのキャリアと自身のキャリアを比べ、Will-Can-Mustを整理することで、今後「自分は何をすべきか」が明確化できるはずだ。●幅広い価値観に接する
自分の考えに固執するだけでは、一定以上の成長はない。より良い「キャリア」を形成していくためには、業界や年代を問わず多様な人々と関わり、幅広い意見や価値観に接することが重要だ。身近な人の声を聞くことも大切だが、ときにはプロのカウンセラーやキャリアコンサルタントに助言を乞うのも有効だ。企業が従業員の「キャリア形成」を支援する重要性
今、企業が従業員の「キャリア形成」を支援することの重要性が高まっている。その背景には、幾つかの要因が挙げられる。まず、一つ目が終身雇用型・年功序列型の人事制度の崩壊だ。もはや、特定の企業で定年まで勤め上げるという時代ではなくなっている。それだけに、「どんな仕事に魅力を覚えるのか」「いかにスキルアップを図るか」といったキャリア形成が重要になってきている。
二つ目が、働き方の多様化だ。今や、「1日8時間、週5日間のフルタイム勤務」は当たり前ではない。企業としては、従業員がさまざまな選択肢の中から、自身にフィットする「キャリア」を選択・実現できるよう支援していかなければいけない。
三つ目が、転職の普及だ。より良い待遇や仕事へのやりがいを求めて、人材の流動化が加速している。労働者が主体的に自身の強みに磨きをかけ、それを存分に発揮できるキャリアを積んでいかなければならない。
実際、企業が従業員のキャリア形成を支援することで、ポジティブな効果が得られると各種調査でも報告されている。実績が出ていることも、取り組みの後押しにつながっているようだ。
企業ができる「キャリア自律」支援施策
最後に、企業として実行できる「キャリア自律」のための支援施策を4つ紹介したい。●キャリア面談
まずは、キャリア面談を実施しよう。キャリア面談とは、社員のキャリア形成を実現するための取り組みをサポートする面談を意味する。「どのようなキャリアを思い描いているのか」を聞き取り、その上で現在の立ち位置を確認したり、キャリアパスを提示したりしてキャリアビジョンとキャリアプランを固めていくことが目的となる。●キャリア研修の実施や教材の提供
キャリアデザイン研修の実施や教材の提供もぜひ検討してもらいたい。理想とするキャリアを実現するには、まずは的確なキャリアプランの作成と目標の達成に向けて行動し続ける姿勢が不可欠となる。それらを身に付ける、絶好の機会となるはずだ。●自己啓発補助
国の「キャリアアップ助成金」などを活用して従業員のキャリア形成を支援するのも有効だ。キャリアアップ助成金には、アルバイトや契約社員を正社員に登用することで助成金が支給される正社員化コースがある。令和6年度の場合だと、有期雇用の従業員を正社員に登用すると中小企業で80万円、大企業で60万円が支給されている。「キャリアアップ助成金」とは? 正社員化コースなどの条件や金額を解説
●キャリアコンサルタントとの連携
効果的なキャリア相談を推進していくためにも、キャリア相談窓口にはキャリアコンサルタントの有資格者を置きたい。キャリアコンサルタントとは、他者のキャリア相談に応じる専門家だ。社内にこの資格を持った人がいなければ、外部との連携も検討したい。まとめ~変化の時代におけるキャリア形成と企業の責任
近年は、社会がますます多様化・複雑化しており、変化のスピードも速い。そうした時代で企業が勝ち抜いていくためには、組織を構成する従業員一人ひとりが自らの「キャリア」を自律的に形成していかなければいけない。ただし、従業員任せにするだけではいけない。会社は社員のキャリア形成を支援するために必要な制度や職場環境を整備する必要がある。人事担当者として取り組むべき施策は数多い。何から着手すれば良いのか、この機会にぜひ検討し直してもらいたい。- 1