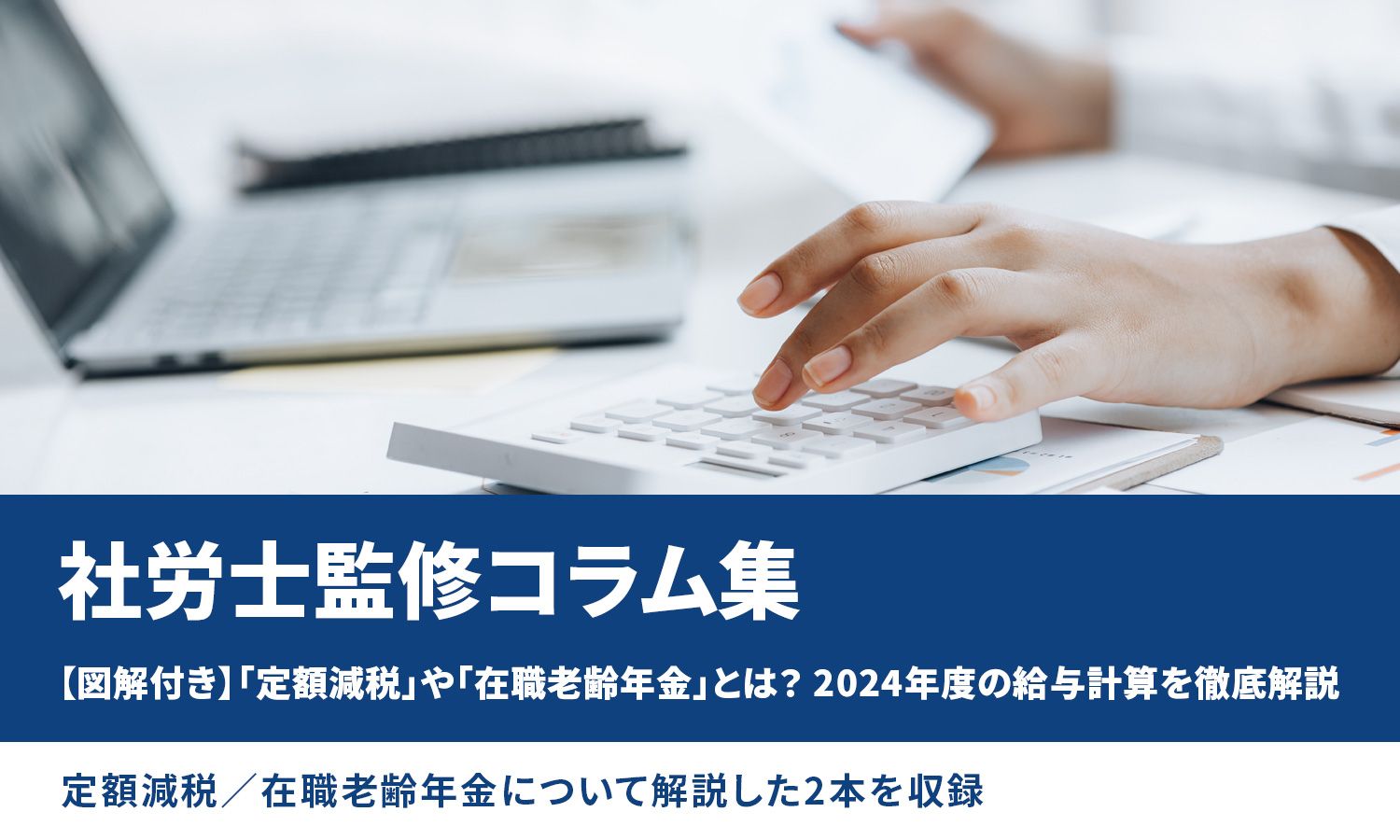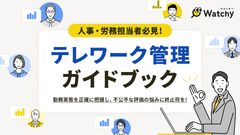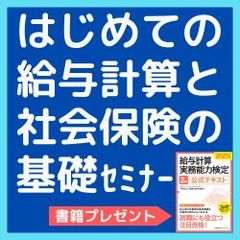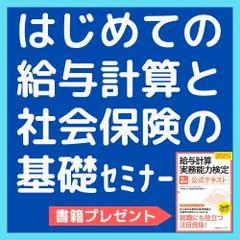「給与計算」とは
「給与計算」とは、従業員に支払う賃金を正確に算出し、処理する業務のことだ。基本給・残業代・通勤手当などの「支給額」と、所得税・社会保険料・住民税といった「控除額」を計算し、最終的な支給額(手取り)を確定する。毎月必ず行う業務であり、法改正への対応や年次調整、社会保険関連の手続きなども関連するため、正確性と専門知識が求められる。【関連記事】そもそも「給与」について正しく理解していますか? 給料・手取りとの違いや計算方法を解説
●「給与計算」の役割と目的
「給与計算」の目的は、従業員に適切な報酬を支払い、労働契約の履行と企業の法令遵守を確実に担保することにある。計算ミスや支払いの遅延・滞納は、信頼関係の毀損だけでなく、法的トラブルの要因となるため、高い精度と透明性が求められる。また、給与情報は人件費の把握や原価管理、経営計画の策定においても活用される。つまり、従業員に正確な報酬額を支払うというだけでなく、経営判断の重要なデータ資産としての役割もあると言える。
「給与計算」の計算式
従業員に支払う給与を算出する「給与計算」では、以下のような計算式に基づいて行う。この計算式は大きく3つのステップで構成されている。最初のステップは総支給額の計算だ。従業員の勤怠データを基に、基本給、残業代などの割増賃金、各種手当(通勤手当、役職手当など)を算出し、これらを合算する作業である。
ステップその2は控除額の計算。健康保険、厚生年金、介護保険、雇用保険などの社会保険料、さらには所得税、住民税などを算出する。
そして最後のステップ3が実際に支給する額の計算。総支給額から各種控除額を差し引いて、従業員に支給する実際の額=手取り額を確定させるのである。
詳しい「給与計算」の方法と手順は以下の章にて解説している。
「給与計算」に関する年間業務スケジュールと月例業務
「給与計算」を、余裕を持って行うために、ある程度の年間スケジュールと毎月の定例業務を理解しておくことをお薦めする。以下が年間スケジュールと毎月の主な業務だ。【「給与計算」に関する主な年間の業務スケジュール】
| 月 | 業務 | 業務内容 |
|---|---|---|
| 4月 | ・給与改定 ・社会保険 ・労働保険 | ・新入社員や異動社員の給与登録・改定、「給与支払報告書」「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の提出 ・3月分の健康保険料、介護保険料の改定 ・雇用保険料の改定 ※締日によって異なる |
| 5月 | ・住民税 ・賞与計算 | ・住民税の年度更新 ・賞与計算 ※6月支給の場合 |
| 6月 | ・労働保険 | ・「労働保険年度更新」の手続き |
| 7月 | ・社会保険 | ・4~6月の給与を基に社会保険料算定、「算定基礎届」の作成・提出 |
| 8月 | ・社会保険 | ・4月に昇給した社員の社会保険料改定 |
| 10月 | ・社会保険 ・年末調整 | ・7月に「算定基礎届」を提出した社員の社会保険料改定 ・年末調整の準備(書類配付) |
| 11月 | ・賞与計算 | ・賞与計算 ※12月支給の場合 |
| 12月 | ・年末調整 | ・年末調整の実施、源泉徴収票の発行 |
| 1月 | ・税務関係 | ・法定調書および「給与支払報告書」の提出 |
| 日(時期) | 業務内容 |
|---|---|
| 10日 | ・勤怠データ集計(労働時間、遅刻早退、休暇など) ・前月の給与から控除した源泉徴収税額の納付 ・前月の給与から控除した住民税特別徴収税額の納付 |
| 17日~22日 | ・給与計算(支給額と控除額の決定) ・給与明細の発行 |
| 22日 | ・金融機関にて給与振込手続き |
| 25日 | ・給与支払日 |
| 月末 | ・前月分の社会保険料の納付 |
【合わせて保存】資料ダウンロード2025年度版 人事労務関連法改正ガイド >>
「給与計算」を始める前に押さえておくべき基本ルール
「給与計算」を行う際に、必ず把握しておきたい基本ルールがある。その3点をわかりやすく解説しよう。●賃金支払いの五原則
給与の支払いについては、労働基準法で定められた通称「賃金支払いの五原則」を遵守することが求められる。(1)通貨で支払う
原則として日本円の現金で支払う必要がある。ただし従業員から許可を得て銀行口座へ振り込むことや、電子マネーのデジタル払いも可能。
(2)直接支払う
原則として労働者に直接支払う必要がある。ただし病気などで受け取れない場合に、本人の意思があれば同居の配偶者や子供が給与を受け取ることは認められている。
(3)全額支払う
未払いはもちろん、分割払い、不当な天引き・借金との相殺、支払いの一部保留も認められない。ただし過払いの調整などが可能なケースもある。
(4)毎月1回以上支払う
最低でも月1回以上、支払わなければならない。雇用契約が年俸制であったとしても、分割して月1回以上支払う必要がある。
(5)一定の期日を定めて支払う
事前に取り決めた期日に遅延なく支払わなければならない。ただし支払日が休日の場合は前日または後日の支払いが認められる。
【関連記事】「給与控除」の考え方と賃金支払いの5原則/会社が給与から天引きするお金の話(第1回)
●最低賃金制度
労働者の賃金は最低賃金法によって保護されている。最低賃金は都道府県ごとに異なるため、事業所が全国に点在する企業では、転勤・出向時などに注意が必要だ。最低賃金は毎年10月に改定されるため、定期的に確認するようにしたい。なお最低賃金には、都道府県別の地域最低賃金と、特定産業に適用される特定最低賃金の2種類が存在し、原則として高い金額が適用される。万が一最低賃金を下回る賃金で雇用契約を結んだ場合、契約は無効とされ、最低賃金が自動的に適用される。
●社会保険の加入要件
厚生年金保険など社会保険の加入要件はこれまで段階的に拡大されてきた。2024年10月以降は以下の通りであるが、今後も改正・拡大される可能性があるため、厚生労働省のホームページなどで定期的に情報を確認すべきである。・対象…………従業員51人以上の企業
・勤務時間……週の所定労働時間が20時間以上(残業は含まず)
・賃金…………月額8.8万円以上(基本給と手当の合計/残業代などは含まず)
・雇用状況……2カ月を超える雇用の見込みがある
・身分…………学生ではない(ただし休学中、定時制・通信制の学生は加入対象)
【関連記事】「社会保険」の加入条件は? 適用範囲や企業と従業員の手続きを解説【2024年適用拡大】
●勤怠情報・就業規則の確認
「給与計算」には、勤怠情報と就業規則との整合性が欠かせない。従業員の労働時間が割増賃金などの算出に用いられる。残業代や深夜勤務手当、各種手当を計算する際には、実労働時間や適用ルールに沿ったデータを把握しておく必要がある。また年齢、結婚、転居、配置・配属・転勤、昇格・昇給、新たな役職といった情報も給与の算出に影響を及ぼす。勤怠および人事関連の情報全般を正確に記録・管理することが不可欠である。「給与計算」のやり方・手順
実際に「給与計算」を行う方法と、支払いまでの手順を4ステップで解説していく。●ステップ1:総支給額を計算する
ステップ1である総支給額の計算は、さらに3つの作業に分解して考えるとわかりやすい。(1)従業員の労働日数・労働時間を集計する
まずは勤怠管理システム、出勤簿、タイムカードなどを基に、従業員の勤務状況を整理・集計する。必要なのは給与の計算対象期間における、勤務日数・欠勤日数、労働時間、残業時間、遅刻や早退の有無、有給休暇の取得状況といったデータだ。とりわけ重要なのは、実際の労働時間が法定労働時間(1日8時間・週40時間まで)を超過していないかの確認だ。法定労働時間を超える「法定外残業」があれば、規定の割増賃金を支払わなくてはならない。法律で週1回以上と定められている法定休日に出勤した場合にも割増賃金が適用される。また夜22時から翌朝5時までの労働は「深夜労働時間」に該当し、これも割増賃金の適用対象となる。
【法定労働時間についてより詳しく知りたい方へ】「労働基準法」とは? 労働時間・賃金・休憩・休暇などの規定や違反例と罰則についてわかりやすく解説
(2)基本給、各種手当、割増賃金の計算
続いて、「基本給」、「各種手当」、「割増賃金」について計算していく。・基本給
多くの企業では各種手当を含まない給与のベース(基本給)を従業員ごとに定めている。昇格・降格などによる昇給・減給がないか、新入社員の初任給や中途入社などで日割り計算の必要がないかを確認したい。
【関連記事】「基本給」の意味と月給や手取りとの違いとは? 平均額や決め方なども解説
・各種手当
企業によっては通勤手当、役職手当、住宅手当など、さまざまな内容・金額の手当を独自に設定し、従業員に支給している。毎月固定のもの、家族の状況や勤務地によって支給額が変動するものなどがあり、就業規則・雇用契約と従業員の最新の情報を基に正しく算出する必要がある。また「役職手当は課税対象」、「通勤手当は月15万円まで非課税」など課税と非課税の区分があるため、国税庁ホームページに掲載される情報などを基に正確に計算し、リストアップしておきたい。
・割増賃金
勤怠の確認・労働時間の集計によって、時間外労働(残業)、休日労働、深夜労働の有無が明らかとなる。「1日8時間・週40時間を超える『法定時間外労働』は割増賃金の対象」、「会社が定めた所定労働時間は超えているが、法定労働時間は超えていないので割増賃金の対象外」といった分類があることに注意したい。
割増賃金の対象となる労働については、それぞれ定められた割増率を基に支払い額を計算し、基本給に加算しなければならない。この時、基本給をベースとして1時間あたりの賃金を算出し、そこに各種割増率をかけて割増賃金を求めることになる。計算手順は以下の通りだ。
②1カ月の平均所定労働時間=[(365日-年間所定休日数)×1日の所定労働時間数]÷12
③月給÷1カ月の平均所定労働時間=1時間あたりの賃金
④1時間あたりの賃金×対象となる労働時間数×各種割増率=割増賃金
割増率は下記の通り労働の種類によって異なる。また「深夜の時間外労働」では、深夜労働の割増率25%以上+時間外労働の割増率25%以上=合計50%以上となるなど、複数の割増率が適用されるケースもあるので注意が必要だ。
【各種割増率】
| 種類 | 対象 | 割増率 |
|---|---|---|
| 法定時間外労働 | 法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた労働 | 25%以上 |
| 1か月60時間を超えた時間外労働 | 50%以上 | |
| 深夜労働 | 22時から翌5時までの時間帯における労働 | 25%以上 |
| 休日労働 | 法定休日(週1日または4週を通じて4日)における労働 | 35%以上 |
(3)総支給額を計算する
ここまでに算出した基本給、各種手当、割増賃金の合算が総支給額となる。●ステップ2:控除額を計算する
総支給額から差し引くものとしては、社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料、雇用保険料)と税金(住民税、源泉所得税)などがあげられる。【関連記事】「社会保険」とは? 国民健康保険との違いや加入条件を詳しく解説
・厚生年金保険料
厚生年金保険料の計算式は以下の通りだ。会社と従業員で折半することが一般的であるため、最後が「÷2」となっている。
標準報酬月額は、まず4~6月の給与(基本給、各種手当、年4回以上支給される賞与など)の合計額を求め、これを3で割り(3カ月の平均を算出)、その額を日本年金機構が公表している「厚生年金保険料額表」に当てはめることで決まる。また2004年から段階的に引き上げられてきた厚生年金保険料率は、2017年以降は18.3%で固定されているが、今後さらに変動する可能性もあるため要注意だ。
【関連記事】「厚生年金」とは? 国民年金との違いや受給額早見表・保険料の計算方法を紹介
・健康保険料、介護保険料
健康保険料、介護保険料の計算式は以下の通り。標準報酬月額にそれぞれの保険料率をかけて算出する。
介護保険料=標準報酬月額×介護保険料率÷2
厚生年金保険とは異なり、健康保険・介護保険の標準報酬月額と保険料率は、加入している健康保険組合ごと、地域ごとに決められているため、自社の保険について確認したうえで計算しなければならない。また介護保険料は40歳から64歳に課税され、「第1号被保険者(65歳以上)」と「第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険加入者)」に分けられる。つまり40歳未満の従業員については対象外である。
【関連記事】「介護保険」とは? 制度の仕組みや手続きについて解説
・雇用保険料
雇用保険料は以下の通り、給与(基本給、賞与、残業手当、通勤手当など)を基に算出される。労使折半ではなく、従業員より事業主の負担割合が大きい点が特徴だ。
雇用保険料率と、事業主・従業員の負担割合は「一般の事業」、「農林水産・清酒製造の事業」、「建設の事業」の3つに分けて定められている。また保険料率の引き上げ・引き下げが行われることもあるため、厚生労働省の「雇用保険料率表」を随時確認するようにしたい。
【関連記事】「雇用保険」とは? 給付の種類や保険料の計算方法をわかりやすく解説
・源泉所得税
毎年1月1日~12月31日の所得にかかる所得税は、自営業などは確定申告によって額が決まり、自身で納めなければならないが、会社員の場合は会社が月給から毎月源泉徴収し、従業員に代わって納税することとなっている。手順としては、総支給額(月給)から社会保険料や雇用保険料などを差し引いた課税所得を算出し、これを国税庁による「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」と照合することで金額が決定する。
税額は扶養親族の数によって変動する。また“天引き”されるのは概算の額で、年間の課税所得と所得税額が確定するのは12月となる。そこで「年末調整」が行われ、源泉徴収された額と実際の所得税額との差を精算するのである。
・住民税
住民税の額は前年の所得を基に各自治体が決定する。会社は毎年5月に送られてくる「住民税決定通知書」で年間納税額を確認し、これを12分割して毎月の給与から差し引いて従業員に代わって納税することになる。
・社内規定や労使協定に即した控除
会社によっては就業規則・賃金規定で、欠勤・遅刻・早退をした場合の賃金減額規定などを定めていることがある。従業員ごとに異なる基準や計算方法を適用するのではなく、あらかじめ「どんなケースで減額するか」、「月給を基に控除額を算出するとして、その『月給』は基本給のみとするか手当も含めるのか」など、あらかじめ社内統一の基準を決めて運用されなければならない。また福利厚生の一環として、共済費、社宅費、財形貯蓄などを控除する労使協定を結んでいることもある。これらは「その他の控除額」として計上することになる。
●ステップ3:差引支給額を計算する
ステップ1で算出した総支給額(基本給、各種手当、割増賃金の合算)から、ステップ2で整理・算出した控除額を差し引いた額が「差引支給額」、すなわち従業員に対して実際に支払う給与、いわゆる“手取り”となる。●ステップ4:振込処理と給与明細の発行
「給与計算」が完了したら、確定した差引支給額を各従業員の銀行口座へ振込手続きを行う。多くの企業では給与支払日に合わせて銀行振込データを作成し、金融機関の対応スケジュールに従って処理する。また、同時に給与明細を発行する。主な記載項目は、以下の4カテゴリとなる。
②支給額(基本給・残業手当・各種手当)
③控除額(社会保険料・所得税・住民税・その他控除)
④差引支給額(手取り)
なお、近年は従業員がスマートフォンやPCで内容を随時確認できる電子明細が主流となっている。処理後は賃金台帳への記録や法定書類の保管も忘れないようにしたい。
「給与計算」で発生しがちな問題とリスク
「給与計算」には、企業の信頼や従業員の生活につながるさまざまなリスクが潜んでいる。主な注意点を解説していく。●情報漏洩リスク
「給与計算」の作業では、氏名、住所、誕生日、家族構成、マイナンバーや銀行口座など、従業員の個人情報を取り扱うことになる。給与額そのものも含め、これら重要な個人情報が外部や社内に漏れてしまうと、個人情報保護法違反(刑事罰の対象)となるだけでなく、会社としての信用失墜や訴訟のリスクも生じる。「給与計算」システムや各種情報へのアクセス権を制限するなど、慎重かつ徹底した管理が求められる。●労務上のミス
勤怠データの入力と転記時のミス、人事情報の更新遅れ、従業員によるタイムカード打刻漏れ、給与の支払い遅れや振り込み漏れなど、「給与計算」と支払いにおいてヒューマンエラーが発生することも多い。人事データを管理するクラウドシステムの導入など、できる限りミスやエラーを防ぐための取り組みを進めたい。●税務上のリスク
「給与計算」では、所得税や住民税、社会保険料の控除額を正確に算出し、期日までに納付する義務がある。源泉徴収税額の計算誤りや納付遅延が生じると、追徴課税や延滞税の発生、さらには税務署からの指摘・調査につながるリスクがある。また、年末調整や法定調書の提出ミスも重大な税務リスクとなるため、最新の税制改正情報を常に把握し、正確な運用体制を整えることが重要だ。●計算ミス
「給与計算」では、さまざまな法律を参照しながら勤怠データや保険料率など細かな数字を扱うことになるため、計算ミスが起こりがちだ。従業員に迷惑がかかるだけでなく、誤った額の社会保険料や税金の納付、その修正や追徴課税といった手間とリスクを抱えてしまうことになるため、クラウドシステムの利用や二段階以上のチェック体制など、ミスを防ぐ工夫が重要である。●給与に関する記録の不備
「給与計算」の記録は、賃金台帳に記載して保存することが労働基準法によって義務づけられている。保存期間は5年間(源泉徴収簿を兼ねる場合は7年間)で、年末調整や各種手続き、税務調査などの際にも使用するため、適切に管理・保管したい。「給与計算」を効率化する方法
「給与計算」は、正確性や専門知識が求められ、担当者の負担が大きい業務だ。効率化のために、システム導入やアウトソーシング、DX推進といった手段を活用していきたい。それぞれの機能やメリットを解説する。●給与計算ソフトやシステムの活用
給与計算ソフトやクラウド型システムを導入することで、勤怠情報や各種手当・控除の計算を一元管理できる。計算ミスや手作業の転記ミスが大幅に削減でき、給与明細の自動発行や年末調整への対応も効率的に行える。法改正に自動で対応してくれるため、常に最新のルールに沿った運用が可能な点も大きなメリットだ。導入コストはかかるものの、人的ミスの防止や工数削減、セキュリティ強化の面で大きな効果が期待できる選択肢と言える。
●アウトソーシングの活用
「給与計算」の業務を、専門業者や社会保険労務士事務所に委託するアウトソーシングも効率化に有効だ。複雑な法対応や煩雑な計算を専門家に一任できるため、担当者の負担を減らしつつ、ミスや法違反リスクの低減も図れる。ただし、社内にノウハウが蓄積されないデメリットもある。そのため、業者との情報連携や内製化とのバランスを見て導入していきたい。
【合わせてチェック】「人事管理システム」の編集部おすすめ比較! 機能・費用相場・選び方も解説
まとめ~ミスやトラブルを防ぐため、「給与計算」には余裕と効率が大切
従業員にとって給与は、命の次に大切なものとも言っても過言ではない。計算ミスや支払いの遅れ、「賃金支払い五原則」に抵触する行為などがあれば、従業員の生活に大きな影響を及ぼし、モチベーションやエンゲージメントの低下を招く恐れもある。「給与計算」は煩雑で、労働基準法違反、情報漏洩、信頼失墜のリスクもあってストレスのかかる業務だが、だからこそ正確な知識を習得し、最新の注意とともに適切な運用を心がけたい。従業員情報や法改正を定期的に確認することも不可欠だ。
少人数による作業、業務の属人化、時間に追われながらの計算では、さまざまなミスやトラブルの可能性が高まる。十分な人員を割いてチェック体制を構築し、「給与計算」のためのソフトやクラウドシステムの導入なども考慮することで、スケジュール的にもリソース的にも余裕のある、効率的な「給与計算」業務を実現したいものである。
【HRプロ】無料会員登録はこちらから >>
- 1