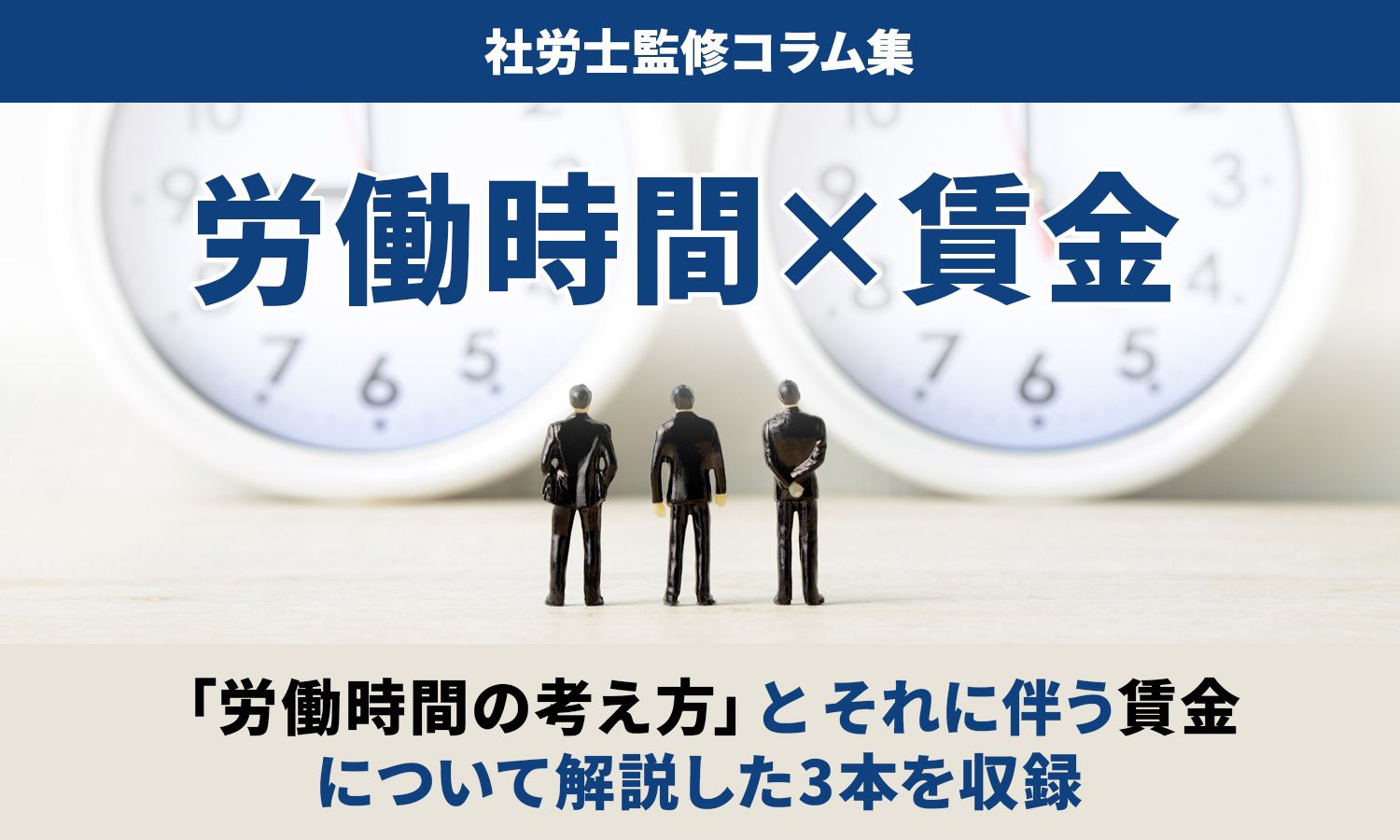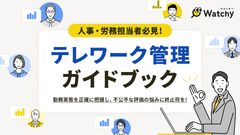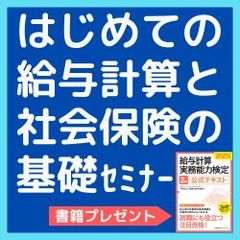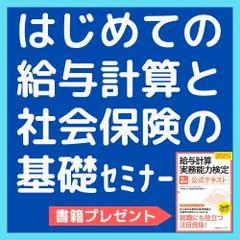休憩・着替え・喫煙・持ち帰り残業に賃金支払は必要?「労働時間と賃金」について解説/社労士監修コラム集

「定額残業代」の基本的な解説(定義・要件・法的性質)
「定額残業代」は広く普及しています。「固定残業代」などと呼ばれるほか、会社独自の名称を用いられることもありますが、名称は問いません。「定額残業代」とは、一定額・一定時間数分の残業代を毎月あらかじめ支給する制度をいいます。基本給に組み込むパターンと別手当として支給するパターンがあります。定額残業代が有効と認められるためには、厳格な要件があります。曖昧な形で支給していると違法とされ未払い残業代が発生するリスクがあります。
この定額残業代についてですが、近年、非常にご相談が増えました。定額残業代を導入したいというご相談ではなく、廃止・減額(縮小)したいというご相談です。「残業が減ったので定額残業代を支給する理由がなくなった」ということですが、残業が減った理由は会社の事情や社会情勢などさまざまです。
ところが、定額残業代の性質から考えると、実は、廃止・減額は容易ではありません。定額残業代制度は非常に誤解のされやすい制度ですので、この記事では、40時間分を別手当で支給するケースを例に解説します。
まず、定額残業代の廃止・減額の難しさを考える際には、定額残業代が合法とされる理由から考える必要があります。
「そもそも定額残業代は違法ではないか」という疑問をお持ちになる方も多いと思います。定額残業代が有効と認められるためには、厳しい要件を満たす必要がありますが、要件を満たした定額残業代自体は合法です。その理由は「労働基準法」を上回る残業代の支払い方をする制度だからです。
定額残業代を支給される社員の立場からすれば、1時間しか残業をしない月も40時間分の残業代が支給され、超過分は実労働時間に応じて追加で残業代が支給される制度です。つまり、40時間分の残業代が必ず保証される最低保証給としての性質があります。
会社が残業代を減らしたいのなら、実労働時間に応じて残業代を支払うのが最も効果が高いです。しかし、採用などを考えると、少しでも社員に保証する賃金月額を多くしたいという思いもあり、一定時間・一定額の残業代を支給することで、最低保証給を増やしているという実情があります。
定額残業代は、「労働基準法」通りの計算方法で支給される残業代を超える額が保証されています。定額残業代が認められている出発点は、ここにあるのです。
では、定額残業代を会社が一方的に廃止・減額できるのでしょうか?
休憩・着替え・喫煙・持ち帰り残業に賃金支払は必要?「労働時間と賃金」について解説/社労士監修コラム集
社員の労働条件を就業規則で不利益に変更できるのか?
定額残業代が残業代の最低保証給としての性質がある以上、廃止・減額することは労働条件の不利益変更の話になります。今まで保証されていた時間数・金額が減らされるのですから、ご理解いただける話だと思います。労働条件の不利益変更は「労働契約法」に規定があります。「労働契約法」第9条・10条では就業規則で社員の労働条件を不利益に変更することができる要件が規定されています。
原則として、変更には社員の同意が必要となっています(「労働契約法」9条)。ですが、例外として社員の同意がなくても就業規則で社員の労働条件を不利益に変更できる場合が規定されています(「労働契約法」10条)。定額残業代の廃止・減額の目的によって変わってきますが、いずれにせよ、社員の同意のない定額残業代の廃止・減額が認められる要件は厳しいと言えるでしょう。
環境変化に対応できる制度設計とは?
定額残業代の廃止・減額の相談が増えている背景には、導入時には予想しなかった環境の変化があります。残業削減の取組みにより残業時間が大幅に減少したのなら、「残業代の最低保証給」という性質を持つ定額残業代の見直しを検討する企業が増えるのは自然な流れだと思います。ところが、実際に変更しようとすると、想像以上にハードルが高いことに気づかれる企業が多いようです。これは定額残業代に限らず、人事制度全般に共通する問題です。一度導入した制度を社員の不利益に変更することは大変です。
新しい制度を導入する際には、導入時点で「将来、状況が変わったらどうするか」を想定し、あらかじめ柔軟性を持たせておくことが必要です。会社の事情も社会情勢も刻々と変化する中で、硬直的な制度となっていては社会情勢に対応できません。
現在、新しい制度を導入したり変更したりすることを検討している企業は多いでしょう。しかし、導入・変更時点で、その制度が持つ法的性質を正確に理解し、5年後、10年後の環境変化にも対応できる制度設計が求められるのではないでしょうか。
- 1