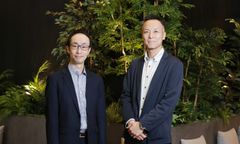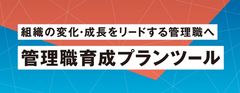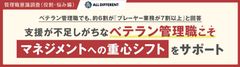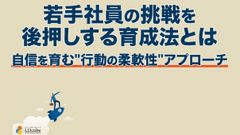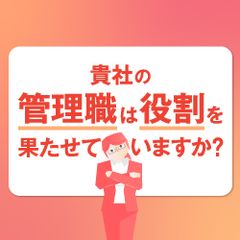【関連記事】「管理職」の定義や役割とは? 求められる能力や向き不向きを解説

「管理職研修」とは
「管理職研修」とは、企業の管理職を対象として必要なスキルや知識を身に付ける研修を指す。管理職は経営と現場とのつなぎ目となる重要なポジションだ。その能力を上げていくのは、組織にとっても重要な取り組みとなるだけに、どの企業も力を注いでいる。【合わせてチェック】「管理職研修」に関するお役立ち資料やセミナーはこちら >>
●「管理職研修」の目的
「管理職研修」の目的は、いくつか挙げられる。まずは新任管理職の場合には、プレイヤーからの意識転換・役割転換だ。管理職としての視座や行動様式を身に付ける必要がある。二つ目が、マネジメントの定石を体系的に身に付け、自社・自組織の課題を解決していくこと。三つ目が、次期経営人材の選抜・能力開発だ。後継者の育成につなげていける。●「管理職研修」が注目される社会的背景と変化
管理職層の強化は組織の持続的な成長に欠かせないキーポイントだ。しかし、近年の少子高齢化による人材不足や、多様な働き方の浸透、ダイバーシティ推進など社会背景の変化に伴い、従来型のマネジメントでは対応が難しくなっている。例えば、部下のキャリア育成、心理的安全性の確保、女性や外国人など多様な人材への対応に加え、DX推進やチームの戦略的なマネジメント能力も今や必須と言える。「現場が多忙で育成に手が回らない」、「管理職自身も課題認識が不十分」といった声も多く、経験だけに頼る育成では組織の成長に限界が生じてしまう。
こうした背景から、課題抽出・目標設定・体系的な能力開発を組み込める「管理職研修」は、現場力・組織力を底上げするための重要な施策となっている。そのため、「自社に合った研修設計」、「効果測定・改善の仕組み化」が、持続的な人材育成の肝となると言える。
「管理職研修」の種類
「管理職研修」は、対象となる役職や業務レベルに応じてさまざまな種類に分類される。以下に主な分類とその概要を取り挙げてみたい。●新任管理職研修
新任管理職研修は、初めて管理職に就任する人を対象とした研修だ。基本的には、プレイングマネージャーなので、業績向上に貢献するプレイヤー視点とチームを指揮するマネージャー視点の両方を持ち合わせるための意識転換が目的となる。具体的には、組織運営に必要な知識や管理職の役割を果たすためのスキル、マインドなどを習得する。●中間管理職研修
中間管理職研修は、課長を中心としたミドルマネジメント層が対象となる。研修の主なテーマは、リーダーシップや部門運営に関わるマネジメントスキルの強化だ。特に管理職としての行動基準や部下育成、目標設定、チームビルディングなどのノウハウ習得を図る。【もっと詳しく】「中間管理職」の役割とは? ストレス対策やスキルアップに効果的な研修などを解説
●上級管理職研修
上級管理職研修の対象は、次期経営人材として期待される部長クラスだ。そのため、経営者的な思考や行動の習得が研修の目的となる。具体的には、企業全体を見据えた大局的な意思決定や部門を連携した課題解決に取り組むための視点やスキルを醸成していく。●特化型研修(コーチング/コンプライアンスなど)
階層別で分けるのではなく、コーチングやコンプライアンスなど特定のテーマにフォーカスした「管理職研修」も実施されている。この場合、設定されたテーマに関して、より深い知識を習得することが目的となる。【自社に合った管理職研修をお探しの方へ】HRプロでは実践的な「管理職研修」サービスを掲載中 >>
「管理職研修」で扱う主なテーマ
「管理職研修」扱うテーマについて、主だったものを紹介していきたい。●経営戦略・方針の理解と浸透
管理職にはチームの部下に経営戦略・方針を理解・浸透させていく役割が求められる。どれほど部下が優れた能力を持っていたとしても、会社が目指す方向と合致しなければ、成果につながらないからだ。そのためにも、管理者自身に経営戦略・方針が腹落ちできていなければ、何も始まらない。●業務マネジメント・改善手法
管理職研修では、業務マネジメントや改善提案を行うための具体的なノウハウを身に付ける必要がある。業務マネジメントとは、部下に対して業務に関する説明や分担、締切期日などを明確に指し示し、その進捗や結果を管理するスキルだ。また、業務を進める上で生じた問題や課題を迅速かつ的確に解決するとともに、改善につなげていく対応力を養うようにしたい。●部下の育成・OJT指導スキル
管理職には、部下を教育・指導する方法やスキルの習得が欠かせない。チーム全体での成果で管理職としての力量が評価されるだけに、部下一人ひとりの能力を高めていく必要があるからだ。そのためにも、部下とのコミュニケーションを丁寧に行い、適切かつ明確にアドバイスできるようにならないといけない。コーチングの手法も用いられている。【もっと詳しく】「OJT」とは? 意味や目的と併せて効果的な進め方を解説
●チームビルディングと組織マネジメント
チームビルディングや組織マネジメントは、すべての管理職に必要とされる重要な能力となる。なぜなら、全員が考える組織を作り上げることで、チームとしての目標が達成しやすくなるからだ。そのためにも、「目標設定」「意思決定」「業務遂行」などの能力を養うカリキュラムを「管理職研修」に組み込むようにしたい。【もっと詳しく】「チームビルディング」とは? 意味や目的、施策の具体例を紹介
●コミュニケーション・傾聴力・対話力
管理職にとって、コミュニケーションスキルも不可欠だ。チームのメンバーと円滑に情報伝達・共有や意思疎通を図れなければ、業務が遂行できないからだ。同様に、傾聴力や対話力も求められる。部下だけでなく、管理職は経営陣とやりとりする機会もある。相手の真意を把握するためにも、研修でしっかりと磨き上げていきたい。【もっと詳しく】「コミュニケーション能力(スキル)」とは? 種類や高める方法を解説
●コンプライアンス・リスクマネジメント
企業や組織においては、社員が就業規則や社内規程などのルールを順守し、企業倫理や社会的規範、社会道徳に沿った行動を取る必要がある。そのためにも、管理職は研修でコンプライアンスの知識を学んでおくようにしたい。また、経営層に近づくに連れ、リスクマネジメントの知識も抑えたい。管理職は、リスクを組織的にコントロールしていかなければいけない立場であるからだ。【もっと詳しく】「コンプライアンス」の意味や違反の事例、必要な取り組みとは?
【もっと詳しく】「リスクマネジメント(リスク管理)」とは? 意味や目的、プロセスを簡単に説明
●戦略立案と実行力の強化
管理職が組織やチームを指揮していくためには、目指すべき達成目標とその実現に向けた戦略を立案し、実行していかなければいけない。戦略の策定にあたっては、現場の状況だけでなく、組織全体の状況や社会情勢の変化なども加味して検討する必要がある。そうした大局的な戦略策定能力と実行力を、研修を通じて身に付けるようにしよう。●多様性対応・女性管理職の育成
労働人口が減少している昨今。必要な戦力を確保していくためには多様な人材を迎え入れる必要がある。また、女性の活躍を推進するためにも女性のビジネスリーダー、管理職候補を育成していく姿勢も重要だ。まずは、管理職自身が多様性を理解し、包括的な職場環境づくりを進めるための戦略・施策を習得したい。【もっと詳しく】「ダイバーシティ(多様性)」とは? 意味やメリットを解説
「管理職研修」の内容・カリキュラム
次に、「管理職研修」の内容やカリキュラム、手法を紐解いていこう。●集合研修(対面)
集合研修とは、受講者が同じ場所・同じ時間に集まり、講義やグループワークにより学ぶ対面型の研修形式だ。知識の習得だけでなく、ディスカッションやロールプレイを通じて実践的に学んでいけるとともに、参加者同士のつながりを深めることができる。ただ、実施にあたっては、会場の手配や日程調整などの運営負担が伴ってくる。●オンライン研修(eラーニング)
オンライン研修は、インターネットを活用して受講する研修形式だ。時間や場所に縛られず、個々のペースで学べるだけに多忙な管理職層に適している。また、何度も反復して視聴することも可能なので、知識の習得には最適と言える。その一方、学習する・しないは本人任せになりがちであり、実践的なスキルの習得も難しいと言える。●ブレンディッドラーニング(混合型)
ブレンディッドラーニングは、集合研修とeラーニングの利点をミックスした研修手法だ。事前にオンラインで必要な知識を習得した上で、集合研修で実践的なワークやディスカッションを行い、学習効果を高めていく。時間を効率的に活用できると共に実践力も身に付けられるのが特徴となる。ただし、設計や運用に手間がかかるので、それなりのノウハウが運営サイドに求められる。●ケーススタディ・ロールプレイ・グループワーク
管理職の意識・行動を変えるには、ケーススタディやロールプレイ、グループワークなどを用いた実践型のプログラムが有効だ。自分が当事者になったつもりで問題を見つけたり、解決に導いたりしていけるため、より現場に即したノウハウを習得することができる。【合わせてチェック】「次世代リーダー研修」編集部おすすめ比較! 内容や目的から選び方や成功のポイントまで解説
「管理職研修」の企画・設計から実施までの流れ
ここでは、「管理職研修」を企画・設計、実施する際の流れや留意すべき点を説明したい。(1)理想の管理職像の明確化
まずは、自社が思い描く理想の管理職像を明らかにする。具体的には、管理職として習得すべきスキルや能力、思考、行動規範などをリストアップしよう。さらには、具体的な要件や能力を定め、関係者間で共有するようにしたい。(2)現状分析と課題の抽出
次に、自社の現状を把握しよう。具体的には、自社の管理職が有するスキルや思考、行動規範などの項目をリサーチしたい。その上で理想の管理職像と現状の管理職の在り方とのギャップを明確にし、課題がどこにあるかを考察する。(3)ゴール設定と研修内容の設計
課題を抽出したら、研修での「学習目標」と「行動目標」の2つを設定する。「学習目標」は、何をどの程度まで習得するのかを意味する。また「行動目標」として、研修後に実務でどんな行動を取れるようになってもらいたいかを提示する。次に、それらをもとに、実施する研修内容を設計する。(4)スケジュール・運営体制の整備
「管理職研修」の内容が決定したら、研修スケジュールの作成や運営体制の整備を進めよう。具体的には、「管理職研修」に必要な日数や1日当たりに費やす時間、受講者の人数を確定したり、日程や場所などの調整を行ったりすることになる。また、運営チームの構築も進めたい。(5)実施後の効果測定と改善
研修はやり放しではいけない。必ず、「管理職研修」の実施後には効果測定と改善を行うことが重要だ。研修効果の測定方法としては、カークパトリック4段階評価法が一般的だ。これを用いることで、受講生の習熟度を反応・学習・行動・業績のレベルに分類して評価することができる。その結果をもとに、次回の研修の在り方を検討するようにしたい。「管理職研修」を実施する上での5つのポイント
次に、「管理職研修」を実施する上でのポイントを解説してみたい。●現場業務に即したタイミングと内容で実施する
「管理職研修」は、できれば対象者が管理職となって数カ月ほど経過し、業務内容や現場の状況をある程度把握した時期に実施するのが良い。どこに課題があり、どんな施策を講じて行けば良いかをイメージしやすいからだ。もちろん、研修のカリキュラムを組むにあたっては、そうした管理職の課題意識に応える内容を工夫したい。●行動変容につながる実践的なプログラムにする
「管理職研修」で学んだ内容が実践につながらないと何の意味もない。言い換えれば、行動変容を促すプログラムでなければいけないということだ。例えば、ケーススタディを扱うのも効果的だ。それによって、実戦に近い経験を積むことができる。●効果測定とフィードバックを仕組みに組み込む
「管理職研修」の効果を測定し可視化した上で、今後の改善につなげていく仕組みを構築するようにしたい。例えば、360度評価を活用して受講者がどう行動変容したかを調べるのも効果的だ。また、研修後に得られたフィードバックを収集・分析し、次回以降のプログラム設計に反映させることで、現場のニーズにより即した内容にブラッシュアップできる。●社内外のリソースを効果的に活用する
「管理職研修」では社内のリソースだけに固執することはない。有益な外部研修があるなら積極的に活用したい。必ず、投資コスト以上の成果を得られるはずだ。特に専門性が高い内容に関しては、思い切って外部に委ねた方が良いだろう。「管理職研修」の実施事例
大手企業は管理職育成において、どんな取り組みをしているのか。特徴的な「管理職研修」の事例を紹介していく。●キヤノン
キヤノンは、全管理職1,900名を対象に「キヤノンアクティブマネジメントプログラム(CAMP)」を実施。この研修は、部長・課長が部署単位で車座となり対話を重ねる半日対面型であるのが特徴で、外部アセスメントを受けてもらって自己理解を深めたり、従業員意識調査をもとに「働きがい」と「働きやすさ」を議論し、具体的な行動計画を作成したりする。加えて、好事例の共有やeラーニング、社内イベントも展開し、多角的な支援を行っている。背景には、管理職の多くが理系出身で数字やデータに基づく説明を求めること、既にマネジメント経験が豊富なため表面的な研修では納得しにくい点、そして「人事主導の研修」としての距離感ややらされ感の払拭が課題としてあったという。これらに対応するため、データに裏付けられた客観的な分析と、管理職同士が主体的に議論できる場づくりに重点が置かれた。取り組みの結果、現場の管理職が、職場の実態を客観的かつ定量的に把握でき、自律的なエンゲージメント向上が促進。管理職のリーダーシップ強化と持続的な人的資本経営の基盤づくりに成功したという。
【関連記事】全管理職1,900名を巻き込んだキヤノンの職場改革――エンゲージメント向上と職場風土改善を促進する「キヤノンアクティブマネジメントプログラム」
【参考】キヤノン:雇用と処遇
●三菱UFJフィナンシャル・グループ
三菱UFJフィナンシャルグループ(MUFG)は、多様な階層・役職に応じて管理職研修を実施している。特にライン管理職以上を対象にした「MUFG University」では、「次世代リーダーコース」と「マネジメントコース」の2つに分かれ、部店長クラスや副部店長・次長クラスが経営人材として必要な大局観や人間力、組織マネジメント力を養成している。研修は双方向型の講義やディスカッション、グループ横断的かつグローバルな視点から人材育成を行うのが特徴だ。近年ではDX推進に伴い、実践的なデジタル活用スキルを強化する「DEEP研修」や「BASE研修」なども導入され、全行員がDXを「自分ごと」として捉え業務改善に取り組む風土づくりに貢献。組織の持続的成長と現代の複雑な経営課題対応を支える重要な施策となっている。
【参考】MUFG:全行員が変革を主導する時代へ 2,000名規模のDX推進人材育成研修が始動
●LINEヤフー
LINEヤフーの管理職研修は、社員の自律的な学びと実務への活用を促進するため、多様なプログラムを展開。新任リーダーや新任部長向けのスタートアッププログラムをはじめ、部門横断・オンラインを活用したコミュニケーション支援、そしてAI活用やサステナビリティ、女性リーダー育成などテーマ別の専門研修も充実している。データアワードなどの表彰制度を導入し、学びの成果を実践に結びつける機会を積極的に提供している。また、社内公募制度「LINEヤフー Job Challenge」によって、学習成果を活かした異動や新たな挑戦が自発的に行われているのも特徴と言える。オンラインとリアルを併用し、勤務形態に柔軟に対応しながら、管理職のリーダーシップ強化と部下育成の質向上に寄与。そうした取り組みにより、社員の成長意欲と組織力の向上を図っている。
【参考】LINEヤフー:人材成長支援~パフォーマンス最大化のための成長促進
まとめ
管理職には、マネジメント力や指導力はもちろん、コンプライアンス、リスクマネジメント力、戦略策定力など多様なスキルや知識が求められる。しかし、日常業務が多忙すぎて、「自分にはどんな能力が足りていないか」、「何を伸ばしていけば良いか」と検証する機会がない場合も多い。その点、「管理職研修」は本人に自省を促す絶好の場となる。また、変化がダイナミックな現代では、学んだことがあっという間に古くなっていく。アップデートが大切であることを管理職に意識づけるためにも、「管理職研修」を有効に活用したいものだ。- 1