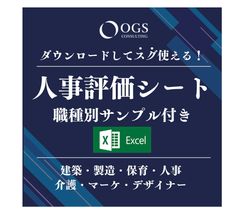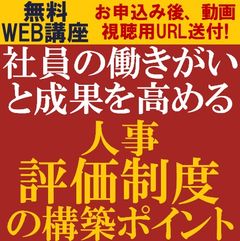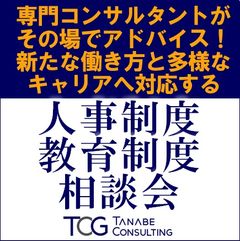(1)全社目標の明確化
中小企業の場合、「ヒト、モノ、カネ」の経営全般について何をなすべきかという「経営計画」が明示されている会社が少ないと言うのが現実です。この状態で、会社が個々の社員に目標設定を求めることは順序が逆。やはり、各社員の目標設定の前提として、先に会社に「経営計画」が策定されなければなりません。人事考課制度導入を契機に、「経営計画」が策定されるようになれば、経営全体に良い影響を及ぼすことにもなります。
(2)個人目標の設定方法
売上、利益の目標額を設定するため、全社目標→部署目標→個人目標と落とし込んでいく際に、落とし込み切れないギャップが生じる場合があります。これは、全社の目標自体が実態とかけ離れている場合に生じます。では、このギャップをどう埋めるか。この場合、2つの対応方法があります。まず、1つ目は目標数値を、「背伸すれば何とか届く」ところまで落とすことです。落としたとしても、黒字確保、及び借入金の返済原資、投資資金等が確保可能であれば、目標数値として十分と言えます。しかし、「背伸すれば何とか届く」目標では、それらが満たされないとすれば、経営の継続性に黄色信号が灯っている証拠です。
この場合は、「ビジネスモデル」の再構築を含めた収益体質の強化策を策定し「経営計画」の中に組み入れ、それを部署、社員に分担させ、各々の目標とします。これが、2つ目の対応です。
「経営計画」の必要性は数値目標だけでなく、非数値目標策定時でも同様です。「経営計画」の中に、全社的な観点から製造職、事務職、配送職等に求める施策を組み入れ、それを各部署、各社員に落とし込み、当期の目標とすることで、各社員の目標が妥当なものになります。
以上のような、全社目標の部署、個人への落とし込みに当たっては「目標マトリックス表」の活用が有効です。「目標マトリックス表」は、左欄に全社目標、右欄に各部署を並べ、各々が分担する目標を入れます。各部署の目標の総体が全社目標と合致することを確認することができる作業表です。
(3)期中の考課の進め方
期初の目標設定が終わると、人事考課表が社員の机の中に仕舞われ、期末の考課まで陽の目を見ることがないと、いうような状態が起きないようにするには、会社が「中間トレース表」を配布し、それに、まず部下に目標、着眼点に関係して、頑張った事実、十分でなかった事実を中心に記述させるます。更に、これを考課者に回付し、考課者が把握した事実を加筆します。この記録は、部下の業務及び成長の記録として人材育成に活用できると共に、事実に基づく考課の実現の力強い味方になります。
(4)考課者研修の実施
日本の多くの会社では管理職登用に際して、指導力や部下育成力の有無より、高い業務実績を上げることを重視する傾向があります。しかし、スポーツ世界でも「名選手、即ち名監督とはならず」というがよくあります。そうならないためには、管理者が自力で学び取ることを期待するだけでは不十分で、管理職としての系統だった教育研修を施すことが求められます。その一つが考課者研修です。この考課者研修は、制度導入時及び、その後少なくとも2~3年に1度の頻度で行うべきです。そして、「一般的な社員モデル」をもとにしたケースや、「自社の社員」をもとにしたケース等、ケースの内容に変化を持たせた研修としマンネリ化を防ぎます。
ある程度考課の経験を積み重ねた後では、各考課者が実際の部下考課を持ち寄って、考課の根拠や妥当性を考課者間で話し合うという進め方等を取り入れた「人事考課者研修」も実施可能になります。加えて、過去数年間の考課者別の考課の実績をグラフ化して、考課者に還元して、「寛大化傾向」、「中心化傾向」、「厳格化傾向」等々のエラーに陥っていないか自己確認させることも有効です。これらによって高い研修効果が期待できます。
(5)被考課者研修の実施
前述の考課者研修は運用の重要性を認識する会社ではある程度実施されていますが、被考課者に対する研修まで行っている会社はあまりありません。社員数が増え、被考課者が多くなると、一堂に会すること自体が困難になります。そのため、被考課者が人事考課の本質をよく理解しないまま自己評価し、実態より甘過ぎる評価、逆に謙虚過ぎる自己流での評価となるケースがよく見られます。
それを防ぐためには、被考課者研修も必要なのです。最近活用が可能になったEラーニングによる研修であれば、比較的容易に導入することができます。
(6)一次考課、二次考課、最終考課の役割の明確化
一次考課者は、日常的に部下の仕事振りを見ています。従って、一次考課者の考課は尊重されなければなりません。二次考課は一次考課の考課に甘辛や自部署優先等による不適切なものがあれば、着眼点毎に補正します。同じ業務ながら部署間での均衡がとれていないような場合は、根拠を示して考課ランクを修正します。
最終考課は各人の二次考課を修正する場合、合計点数を修正することになりますが、一次や二次考課を否定するような修正はできないよう、修正の限度を例えば二次考課合計点の5~10%以内とするなどにすべきです。同時に、修正の理由を文章で表し、それを二次、一次考課者に伝え、フィードバックの際に戸惑わないようにしなければなりません。
(7)フィードバック内容の明確化
フィードバックが適正に行われるよう、その項目を共通化するのが有効です。その項目とは、「(1)優れていた点」、「(2)改善すべき点」、「(3)部下と上司の考課ランクが異なる点についての根拠説明」、「(4)来期以降、重点的に取り組むべき事柄」、「(5)一次考課と最終考課に違いが生じた場合、その根拠」で、これをA4で1枚程度にまとめ、必ず事前に準備してフィードバックに臨むように考課者に求めます。「人事考課制度」運用のポイント
以上、運用進め方のポイントをまとめますと、「(1)適切な目標の設定」、「(2)期中の指導の見える化」、「(3)フィードバックの適切な実施」ということになります。運用中、色々工夫して人材育 成と人事考課とをうまく結び付けることが大切です。- 1