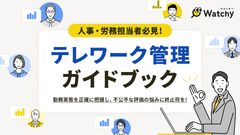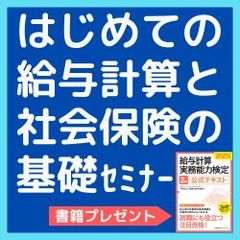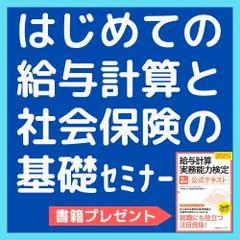「年末調整」とは~従業員の所得税額を確定させ過不足を清算する作業
「年末調整」とは、従業員がその年に納めるべき所得税額を確定させ、過不足を精算する業務である。会社は従業員に支払う毎月の給与および賞与から、社会保険料や住民税とともに所得税を“天引き”(源泉徴収)している。この所得税額はあくまで暫定的なものであるため、年間の所得額が確定した段階で、本来徴収するべき正しい所得税額を算出し、納め過ぎていれば還付、足りなければ追加徴収しなければならない。この作業が「年末調整」である。●「確定申告」と、どう違う?
個人事業主やフリーランスで働く人は、自分自身で納めるべき所得税を計算・確定しなければならない。これが「確定申告」で、毎年2月から3月にかけて納税者本人が作業を行い、税務署に申告し、確定した税額を一括または分割で支払うことになる。一方、会社に所属して給与をもらっている人は、会社がこの作業を肩代わりしていると言える。よって「年末調整」も会社側の作業となり、原則として従業員(納税者)個人が「確定申告」をする必要はない。ただし、複数の事業者から給与支払いを受けている人や、寄付金控除・医療費控除などがある場合は確定申告が必要となる。
【年末調整の効率化を検討中の方へ】「年末調整」に関するお役立ち資料やセミナー情報はこちら >>
【HRプロ】でできること、詳しい活用方法はこちら >>
「年末調整」の対象となる人・ならない人
「年末調整」の対象となる人とならない人を解説していく。●「年末調整」の対象者
(1)原則として対象となる人・「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人
・年の中途で入社し年末(12月31日)まで働いた人
・海外への転勤などにより年の途中で非居住者となった人(非居住者となる日までに支払われた給与について年末調整を行う)
以上のような人に会社が給与を支払っている場合、正社員だけでなく契約社員、アルバイト、パートも含めて「年末調整」の対象だ。「年末調整」の前に転職した人は、転職先の会社で「年末調整」を行うことになる。
(2)年の途中で退職しても「年末調整」の対象となるケース
・著しい心身障害のため12月31日までの再就職が見込まれない人
・12月に支払われる給与・賞与をもらった後に退職した人
・その年の給与総額が103万円以下のパート、アルバイト(退職後に別の勤務先から給与を受け取る見込みがある場合は除く)
●「年末調整」の対象にならない人
・給与収入額が年2000万円を超える人
・災害減免法により所得税の徴収猶予や還付を受けた人
・2か所以上の勤務先から給与を受け取っていて、自社以外に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人
・年の途中で退職し、上記の「対象となるケース」に該当しない人
・非居住者
・日雇労働者など継続して雇用していない場合
「年末調整」によって従業員が受けられる控除
「年末調整」によって以下のようなものが所得から差し引かれる(控除)。これらを計算すると所得額は少なくなり、「所得税を払い過ぎていた」ということになりやすい。そうした事態を解消するために「年末調整」を行うと考えていいだろう。・配偶者控除……配偶者の所得が48万円以下の場合/本人の所得額に応じて控除額も変動
・配偶者特別控除……配偶者の所得によって控除額が変動する
・扶養控除……16歳以上の子ども・親族を扶養に入れている場合
・障害者控除……本人または生計を同一とする配偶者や扶養親族が障害者である場合
・寡婦控除……本人が寡婦(夫と死別・離婚して再婚していない)である場合
・ひとり親控除……本人がひとり親である場合
・勤労学生控除……本人が勤労学生である場合
・生命保険料控除……生命保険に加入し保険料を支払った場合
・地震保険料控除……地震保険に加入し保険料を支払った場合
・社会保険料控除……支払った社会保険料がある場合
・小規模企業共済等掛金控除……小規模企業共済や個人型年金(iDeCo)などの掛け金がある場合
・住宅ローン控除……自宅購入のための住宅ローンを支払っている場合(2年目以降)
・所得金額調整控除……本人が特別障害者である場合など
なお以下ついては「確定申告」でのみ控除可能なので注意が必要である。
・寄付金控除……ふるさと納税、国・地方公共団体・特定公益増進法人などへ寄付した場合
・雑損控除……災害・盗難・横領によって資産に損害を受けた場合
・住宅ローン控除……初回のみ確定申告が必要。2回目以降は「年末調整」で控除可能
【合わせてチェック】「給与計算」の手順を3ステップでわかりやすく解説! ポイントやリスクも紹介 >>
「年末調整」における提出書類
「年末調整」で上述のような控除を受ける場合には、以下のような申告書・証明書が必要となる。従業員には該当箇所・必要事項を記入したうえで提出してもらわなければならない。【年末調整における提出書類】
(2)基礎控除申告書
(3)配偶者控除等申告書
(4)所得金額調整控除申告書
(5)保険料控除申告書
(6)住宅借入金等特別控除申告書
(7)その他の書類(以前の勤務先での源泉徴収票や各種保険料の控除証明書など)
●扶養控除等(異動)申告書
扶養控除のほか、障害者控除、寡婦控除、勤労学生控除、ひとり親控除を受けるために必要。扶養親族がいないなど、その控除対象に該当しない場合は空欄となる。住民税にも関わるため、必ず提出してもらわなければならない。●基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
上述の(2)基礎控除申告書、(3)配偶者控除等申告書、(4)所得金額調整控除申告書は1枚にまとめられている。このうち基礎控除は合計所得金額が2,500万円以下であるすべての納税者が対象となるため、配偶者控除・配偶者特別控除や所得金額調整控除がない場合でも提出が必要である。●保険料控除申告書および控除証明書
従業員(納税者)本人が個人的に生命保険、地震保険、個人年金保険などに加入している場合、その保険料の控除を受けるために必要となる申告書。生命保険や地震保険では保険会社から「保険料控除証明書」が郵送または電子データとして本人に発行される。これら証明書も申告書に添付・提出してもらわなければならない。また従業員が生計を同一にする配偶者や子どもの社会保険料を支払った場合、その保険料についても社会保険料控除を受けられるので、これについての証明書類も必要となる。
●住宅借入金等特別控除申告書
自宅購入のためのローンを支払っている人が控除を申告するための書類。控除を初めて受ける際は自分自身で「確定申告」を行わなければならず、「年末調整」で控除できるのは2年目以降となる。税務署から送付される「住宅借入金等特別控除申告書 兼 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書」のほか、住宅金融支援機構発行の「融資額残高証明書」、ローンを組んだ銀行などが発行する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」も提出してもらうことになる。●その他の書類
年の途中で入社した従業員からは前の勤務先で発行された源泉徴収票を提出してもらわなければならない。配偶者特別控除を受ける場合、配偶者の源泉徴収票など収入を証明するものが必要となる。この他、非居住者であることの証明書、親族に関する証明書、個人型確定拠出年金や国民年金・国民年金基金などの掛け金を支払ったことを証明する書類などが必要となるケースもある。「年末調整」のおおまかなスケジュールと手続きの流れ
「年末調整」に関する作業は、おおむね10月下旬から11月初旬頃にスタートし、翌年1月下旬まで以下のような流れで進むことになる。(1)必要な書類の回収
保険会社から加入者に対して、おおよそ10月頃に「保険料控除証明書」が送付される。この時期に「年末調整」の作業をスタートさせることが一般的だ。必要な書類を従業員に対して周知徹底し、各書類に必要事項を記入してもらい、添付すべき書類(証明書など)とともに提出してもらうことになる。その後の作業をスムーズに進めるためにも、全書類を期日までに、漏れなく回収することが肝要となる。(2)回収した書類の整理・確認
従業員から提出された書類に抜け・漏れはないか、必要事項は誤りなく記入されているか、各種の控除証明書も揃っているか……を担当部署・担当者がチェックする。作業のやり直しや停滞を招かないよう、記載内容の確認と書類の整理には細心の注意を払い、不備があれば従業員には早急な対応(書類の再提出など)を求めなければならない。(3)所得税額の計算~還付・追加徴収
書類をもとに各種の控除、給与所得・所得税額の確定、過不足の解消を以下の流れで実施する。(1)給与収入を計算する
(2)給与所得控除を差し引いて給与所得を算出する
(3)給与所得から各種の所得控除を差し引いて課税所得を算出する
(4)課税所得をもとに所得税額を確定させる
(5)定額減税額を算出して所得税額から差し引く
(6)源泉徴収税額との過不足を算出する
(7)12月または翌年1月の給与に反映させる形で過不足税額を還付または徴収する
(4)申告書類の提出
「年末調整」に関わる計算を終えたら、その内容を「法定調書」として取りまとめ、源泉徴収票、支払調書(必要な場合のみ)、給与支払報告書と合わせて、翌年1月末までに税務署または従業員の居住地である市区町村に提出する。もしも「年末調整」をしなかったら?
「年末調整」をしなかった場合、どうなるのか。会社側と従業員それぞれのデメリットを解説していく。●「年末調整」をしなかった場合の会社側のデメリット
「年末調整」は雇用主である会社の“義務”であることが所得税法で定められていて、違反した際の罰則も規定されている。・「年末調整」を実施せず、正しい税額を従業員から徴収しなかった場合
……1年以下の懲役または50万円以下の罰金
・「年末調整」を実施したものの、追加徴収額を納付しなかった場合
……10年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその両方
ただし従業員が書類を紛失したなど、会社側に過失がなく「年末調整」できなかった場合は、従業員本人の「確定申告」によって対応することになる。
●「年末調整」をしなかった従業員側のデメリット
「年末調整」によって正しい所得税額が算出されないと、所得税の過払いがあっても還付されないことになる。各種控除も受けられないため課税所得額が本来の額より高くなり、翌年の住民税額も高くなる。また従業員自身で「確定申告」をするという手間も生じる。こうした事態を防ぐためにも「年末調整」の必要性を従業員に周知し、スムーズな作業・手続きの実現を図りたい。「年末調整」2025年の変更点
税制改正によって所得税に関する規定が改正された。これは原則として2025年12月1日に施行され、2025年以後の所得税に適用されるため「年末調整」においても留意することが必要である。●基礎控除額の改正
これまで一律48万円だった基礎控除額が、合計所得金額に応じて増減するように改正された。たとえば合計所得金額が132万円以下(給与収入200万3,999円以下)なら基礎控除額は95万円、合計所得金額が132万円超336万円以下(給与収入200万3999円超475万1,999円以下)なら88万円などとなる。2025年以後の「年末調整」では、改正後の基礎控除額を参照・適用しなければならない。●給与所得控除の見直し
給与収入が190万円以下の場合の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられた(給与収入が190万円超の場合の改正はなし)。国税庁による改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に基づいて税額を計算することになる。●特定親族特別控除の創設
「特定親族」1人につき、その合計所得金額に応じて総所得金額などから一定の金額を控除する「特定親族特別控除」が創設された。「特定親族」は、本人と生計を同一とする19歳以上23歳未満の親族(里子を含む/配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人および白色事業専従者を除く)で、合計所得金額が58万円超123万円以下の人と定義され、「特定親族」の合計所得金額に応じて3万円から63万円の控除額が設定されている。●扶養親族などの所得要件の改正
扶養親族、同一生計配偶者、ひとり親の生計を同一とする子どもについては、所得要件が58万円以下(給与収入123万円以下)に、配偶者特別控除の対象となる配偶者については所得要件が58万円超133万円以下(給与収入123万円超201万5,999円以下)に、勤労学生については所得要件が85万円以下(給与収入150万円以下)に、それぞれ引き上げられた。改正によって新たにこれらの控除の対象となる親族などがいる場合には、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が必要となる。【2025年 年末調整のポイント(前編)】「年収の壁」の見直しで「年末調整」はどう変更点される? >>
まとめ~「年末調整」では正確な知識・資料と正確な業務が必須
「年末調整」に関する規定や注意事項は、今回紹介・解説したもの以外にも多数存在する。たとえば一般的には「年間給与が103万円以下なら『年末調整』は不要」とされるが、給与が88,000円を超えた月がある場合はその限りではない。また「1年以上に渡って海外へ赴任する」、「従業員が死亡した後に支払われる予定の給与がある」といった特殊なケースにも注意が必要だ。ほかにも「中途入社の人の以前の勤務先から源泉徴収票が発行されない」といったトラブル、「医療費控除や寄付金控除、住宅ローン控除(初回)があるので自分で『確定申告』を行わなければならないが、どうするのか」といった問い合わせに直面することも考えられる。従業員の中にはどんな控除を受けられるか把握していない人もいるだろう。
これらに対処するため、担当部署・担当者は税制や「年末調整」に関する理解を深め、国税庁などが発行する各種資料も準備し、「年末調整」関連の作業をスムーズに進められるような態勢を整えておかなければならない。
「自社の『年末調整』には間違いがない。必要書類の不足や記載ミスを親切に指摘してくれて、説明も丁寧で、作業全体が円滑に進み、還付が正しく迅速に行われる」と従業員からの信頼を得られれば、それ以外の業務にも好影響が出てくるはずである。
【HRプロ】でできること、詳しい活用方法はこちら >>
- 1