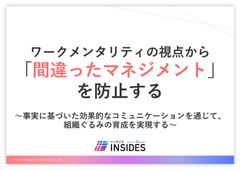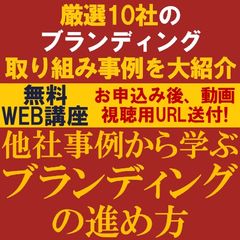「敵に塩を送る」の意外な誤解
まず、頻繁に使うことも多い「敵に塩を送る」という故事成語から見ていこう。本来の意味は、争って敵対関係にある相手であっても、困っているときには援助の手を差し伸べるという、寛大で人道的な行為を指す。これは、戦国時代の武将上杉謙信が、宿敵である武田信玄が塩不足で苦しんでいると知り、あえて自分の領地から塩を送ったという逸話に由来する。しかし、現代ではこの言葉が、「敵を窮地に陥れるために、見せかけの親切をする」とか「相手の弱点につけこんで痛めつける」といった、異なる意味で理解されていることを耳にする。なぜこのような誤用が生まれたのだろうか。
一説には、物語やフィクション作品などで、敵を油断させるために親切なふりをする、といった描写が強調されて広まったためとも言われている。また、「塩を送る」という行為が、現代の感覚では直接的な攻撃手段には結びつきにくく、皮肉めいたニュアンスで捉えられてしまったのかもしれない。
本来の美しい逸話が、誤解によって全く異なる意味合いを持って使われているのは、非常に残念なことでもある。
「情けは人の為ならず」の深すぎる意味
次に、「情けは人の為ならず」という故事成語も、誤用されやすい言葉の一つである。「情けをかけることは、結局は相手のためにならない」という意味で理解している人が少なくない。例えば、「甘やかしてばかりいると、子どものためにならないよ。情けは人の為ならず、だから厳しくするんだ。」といった具合に使われることがある。しかし、本来の意味は全く異なる。「情けをかけることは、巡り巡って自分のためになる」という意味なのである。人に親切にすれば、いつか自分も助けられることがある、という因果応報の考え方を示しているのである。
この誤用の原因としては、「為ならず」という否定的な表現が、表面的な意味だけを捉えると「人のためにならない」と解釈されやすいことが挙げられるだろう。しかし、この「為」は「~のため」という意味ではなく、「~によって」という意味合いが強く、「人のためによって(良い結果が)生じない」ではなく、「人のためによって(良い結果が)生じる」と解釈するのが正しいのである。
「間髪入れず」のスピード感の誤解
「間髪入れず」という言葉も、そのスピード感ゆえに誤用が生じやすい故事成語である。「髪の毛一本ほどのわずかな間も置かずに、すぐに」という意味で、非常に迅速な行動を表す。「質問が終わるか否かのうちに、彼は間髪入れず答えた」のように使われる。しかし、一部には「少しの間をおいて」とか「じっくり考えてから」といった、全く逆の意味で捉えている人もいるようなのである。これは、「間」という漢字から「時間的な間隔」を連想し、「髪の毛一本ほどのわずかな間」を「少しの間」と誤解してしまうことが原因なのかもしれない。
また、「入れず」という否定的な表現が、「間を入れない」という本来の意味を捉えにくくしている可能性もある。瞬時の判断や行動を表現する、非常にシャープな言葉が、緩やかな意味合いで使われているのを聞くと、その言葉が持つ本来のアサインメントが失われているように感じる。
もちろん、これらの故事成語は一つの時代を背景に生まれた言葉に過ぎないから、時代の進展とともに誤解され誤用されることもよくあることかもしれない。しかし、柔らかく美しい大和言葉ではないが、現代では生まれようもない「深い意味」が内包されていることが多い。特に、ビジネスシーンでは適切に活用したい。
番外編
折角の機会なので、ビジネスシーンにおける言葉の使い方で、気になることがあるので、お伝えしておこう。多くの方が日常的に使うであろう「配布」と「配付」についてである。遭遇する多くのケースでは、両者を使い分けることなく「配布」だけが使用されているように感じる。筆者のように、若い頃から【「配布」は「チラシ等を不特定多数の人たちに配るとき」に使用する。「配付」は「資料等を特定の人たちに配るとき」に使用する。】などと教育されてきた身からすると、違和感を感じてしまう。蘊蓄(うんちく)を垂れることなく厳密に使い分けるのも良いかもしれない。
- 1