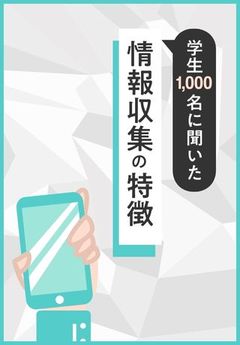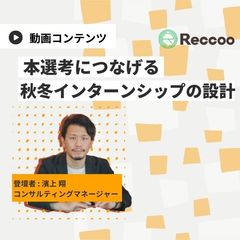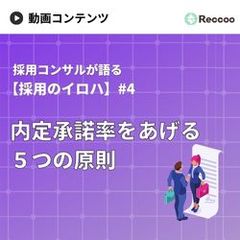第10回 HRテクノロジー大賞『採用部門優秀賞』
トランスコスモス株式会社
AI導入と採用ブランディング戦略による面接官育成と採用力強化プロジェクト
AIを活用して面接官の表情や話し方、質問内容などの要素を分析し、属人的だった面接プロセスを可視化することで、面接官は自身の強みと改善点を客観的に把握できる取り組み。AI採点機能を備えたeラーニングシステムや個別フィードバックレポートを繰り返し、面接官ごとに個別最適化された学習により、面接官のスキル向上を支援。これにより、内定承諾・入社率の10%向上を実現。デジタルとヒューマンスキルを融合させた新たな採用アプローチにより、採用活動の質向上と人材獲得力強化に寄与する優れた取り組みであると高く評価されました。プロフィール

大谷 順子 氏
トランスコスモス株式会社
BPOサービス統括 サービス推進本部
HCマネジメント部 部長トランスコスモス入社後、BPOサービス部門にて企業向けインストラクション業務を担当後、サポートデスクサービス導入や運用体制構築等マネジメント職として従事。現在は部門HR担当として制度設計/人財育成/組織開発などの人財戦略を企画・立案し、サービス提供基盤の強化・推進を行っている。

田代 彩 氏
トランスコスモス株式会社
BPOサービス統括 サービス推進本部
HCマネジメント部トランスコスモス入社後、新卒採用を経て、2010年からBPOサービス部門にて中途採用担当、その後はBPOサービス部門全体の採用戦略企画・立案を担当。事業戦略実現に向けた採用ブランディングなどの採用戦略や採用品質向上などの課題解決の企画・立案をし、実行に向けた推進を行っている。

背景にあった「母集団形成」と「選考プロセス改善」の課題
――まずは今回受賞されました、「AI導入と採用ブランディング戦略による面接官育成と採用力強化プロジェクト」の概要を教えてください。田代氏:BPOサービス部門の採用活動の品質向上のために、AIテクノロジーを活用した継続的な取り組みを導入しました。始まりは、株式会社ZENKIGENが提供する採用DXサービス「harutaka(ハルタカ)」というツールを導入したことからです。
まず、面接を録画し、AIで面接官の表情や話し方、質問内容などを日次・月次・年3回の頻度で分析。要素を可視化することで、面接官一人ひとりの強みや改善点を客観的に把握できるようになりました。
また、この可視化データを基に、個別のフィードバックレポートを繰り返し提示し、面接官の特徴や弱点に焦点を当てた個別最適化された学習を進め、効率的なスキル向上を実現することができました。加えて、月次ではAI採点機能を備えたeラーニングプログラムも実施しました。
さらには、年3回のフォローアップ研修では、BPOサービス部門の採用コンセプト『DIVE IN DYNAMISM(飛び込もう、社会の流れが変わる場所に)』に沿った専門講習を行い、データ分析から導き出された全体傾向と採用ポリシーの実践方法を継続的に学ぶ仕組みを確立しました。
こうした取り組みを通じて、面接官は自社の魅力を効果的に伝えるスキルを身に付けることができ、応募者との相互理解が深まっています。
――この取り組みを始めたのはいつ頃ですか。また、きっかけは何だったのでしょうか。
田代氏:初めに「harutaka」を導入したのは、2022年です。まだコロナ禍の頃でした。なので、会社の方針としても、面接はオンラインで行うことにしていましたので、それが追い風となって面接の録画が進みました。
急速に変化する採用市場において、多様な部門・職種に対応する人材確保が求められる中、私たちには二つの課題がありました。
一つは、母集団形成です。当社はアウトソーサーの大手でありながらも、常々人材の確保には苦労しています。特に私たちBPOサービス部門は、お客様のバックオフィス部門を担うことが多く、応募者に事業内容を理解してもらいにくいという業界特性があり、採用難易度の高さが課題でした。
もう一つが、選考プロセスの改善です。BPOサービス部門は採用人数が多く、面接官も多数擁していることもあって品質が統一されていませんでした。せっかく良い人材がいても、選考を辞退されてしまうこともあり、業務の効率化を図ると共に採用スキルを向上することで、組織全体の採用力を強化したいと考えました。
大谷氏:現場で応募者一人ひとりと面接をしている採用担当のモチベーションを上げたいという想いが強かったです。そのモチベーションが、採用の実績につながってくるからです。そこが、私にとっては一番でした。
――ちなみに面接官を務めているのは、どのような役職の方ですか。
大谷氏:基本的には、採用担当と部門の責任者や管理職者です。誰が最終面接官として、合否をジャッジするかは募集職種のレイヤーによって違います。

本記事は会員限定(無料)の特別コンテンツになります。
続きは、下部よりログイン、または無料会員登録の上、ご覧ください!
この後、下記のトピックで、インタビューが続きます。
●AI導入とフィードバックの質向上を組み合わせたハイブリッドな育成システムを設計
●魔法の杖はない――現場の心理的な抵抗感をどう払拭したのか
●継続的な取り組みの結果、内定承諾率が10%向上