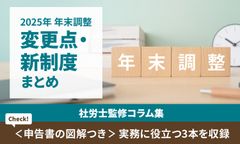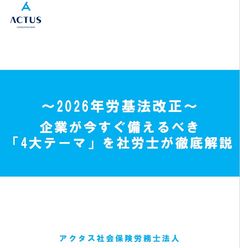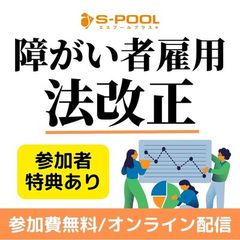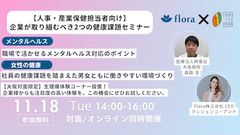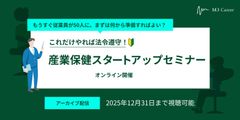今年の「重症化予防」対策の評価と改善を行いましょう
熱中症対策を大きく二つに分けると、「熱中症予防」と、熱中症発症またはそれを疑った時の「重症化予防」に分けられます。今回義務化されたのは「重症化予防」です。そして具体的に法令で定められたのは次の4つでした。
(1)熱中症をおこしやすい職場とそこで働く人の把握
(2)現場で熱中症を疑った時の連絡体制づくり
(3)熱中症を疑ったときの措置(フローチャート)の作成
(4)現場で働く人への措置の周知
この夏の「重症化予防」対策がうまくいったかどうかを、次の手順でチェックします。
まず、この夏に職場で熱中症を発症した人のデータを集めます。この人たちが(1)にあたる人たち、具体的に言うと気温31度またはWBGT値28℃以上の場所で、連続1時間または断続的に一日4時間働く人であったと判断されているかどうかを検討します。
(1)に当たる人と判断されていればよいです。しかし、(1)に該当しないのにも関わらず熱中症になった人がいた場合は危険が見落とされていた可能性があります。4月には、それらの人の働き方を検討する体制づくりを行うとともに、来る夏にその職場のWBGT値を測定するための準備をしましょう。
続いて熱中症を発症したときにフローチャート通りに動くことができていたかどうかを検討します。動けていなかった場合、(2)の連絡体制づくり、(4)の現場への周知のどちらかがうまくいっていなかった可能性があります。ほとんどの場合は周知不足ですので、周知・現場対応訓練を実施することを考えましょう。避難訓練と同じで、熱中症疑いの従業員への対応も訓練無しにはいざという時に動けません。
また、(3)のフローチャートが現場に即したものではなかったためにフローチャート通りに動けなかったことも考えられるので、この点を検討して修正案を考え、4月にフローチャートをバージョンアップさせます。
「熱中症予防」に関する計画を立てましょう
「熱中症予防」対策も重要です。4月に以下のことが決められるよう、今から準備します。熱中症の最大の原因は暑い環境そのものにあります。なのでまずは暑い職場をなるべく涼しくする方法を考えます。具体的にはクーラーやスポットクーラーの設置、送風機や気化式冷風機の設置、輻射熱を出すものから労働者を遮蔽するなどです。
次に考えるべき熱中症予防対策は、適切な連続労働時間と休憩時間の確保です。熱中症を引き起こすのは主に体の深いところの温度「深部体温」です。作業が終わっても深部体温は10分程度は上がり続けますので、休憩時間は少なくとも15分は必要です。詳細な目安については産業医や労働衛生コンサルタントに相談するのもいいと思います。
休憩場所の環境も大切です。まずは温度設定です。休憩所の室温を20℃にすると、気温が低すぎて血管が収縮してしまい体の表面に流れる血液量が減るため、結果として体の深いところの熱を外に逃がすことができなくなります。休憩所は25℃程度に設定することが勧められます。
また、特に建築現場などの屋外作業の場合、定まった休憩場所がなく、その場で休憩場所を考えなければいけないことも多いです。今年の反省を生かし、来年どのようにして休憩場所を確保するかをあらかじめ考えておく必要があります。農業も炎天下で行う作業で、あらゆる職種の中で最も熱中症の危険が高い職業の一つです。来年に向けて休憩用の建物を建てることを考えてもいいかもしれません。
最近は熱中症対策グッズも流行しています。今年最も注目されていたのは、手首にまくなどして熱中症のリスクを早めに感知するウェアラブルグッズと、アイススラリーというシャーベット状の飲み物を作って、これを作業の合間の休憩時に飲むことにより体内から体を冷やす冷蔵庫でした。これからも新しい熱中症対策グッズが出てくるでしょう。今から情報収集に努めましょう。
本人の健康管理も熱中症予防に欠かせません。睡眠不足や朝食を食べていないこと、前日深酒をすることは熱中症のリスク要因です。これらは夏になってから対応すればいいのですが、一方、肥満や糖尿病は熱中症発症のリスク要因である上に、改善に時間がかかりますので、産業医や産業保健職と共同して、早くから計画的に受診や減量などに取り組みましょう。
労働安全衛生一般にそうですが、1回システムなりルールなりを作ってしまえば終わり、ではありません。今年の結果を見て、少しでも来年の改善につなげる。これを繰り返すことで少しずつ安全で衛生的な職場になっていきます。
来年4月の準備期間に様々なことが決められるよう、秋口から計画的に取り組みましょう。
●厚生労働省:職場における熱中症予防情報
- 1