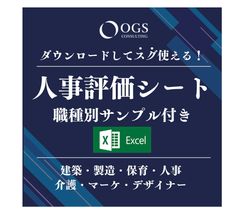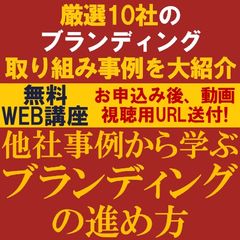「上司・部下共に納得がいく運用が出来る制度」を作るためには
この人事考課制度構築においては、継続的に運用できる仕組み作りと、社員の会社への貢献を測る評価の基準作りとがメインとなります。ただし、単に作り上げるだけでは不十分です。会社だけでなく上司・部下共に納得がいく運用が出来る制度でなければ、目的を達成したとはいえません。ところが、この「上司・部下共に納得がいく運用が出来る制度」を作ることは決して容易ではありません。それは、人事考課制度が日本企業に導入されるようになって半世紀以上が立った現在も、多くの企業で100%目的を達している例が少数派であることが示しています。
これらを念頭において、まず、継続的に運用できる仕組み作りについて解説を進めて参ります。
「人事制度」を構築する際のポイントを整理
(1)目的の明確化
最も排除すべきは、人事考課の目的を、社員間の比較により優劣をつけることとする考えです。かつて、人事考課といえば、「査定」と同義語と考えることが一般的でした。「閻魔(エンマ)帳」に部下の失敗や欠点を記録し、「減点考課」をするというものです。従って、考課の基準や考課の結果は、「一切、部下には厳秘」というスタイルでした。この考えが、長く広く常識であったため、いまだに根強く残っているのです。「他人との競争に勝ちたい」という人間の本性に合致しているためとも言えます。
ですから、ともすれば陥りがちな旧来の考えを払拭し、それらとは正反対に、すべてを公開し、以下の点を目的とすることを共通認識として繰り返し強く働きかける>ことが必要です。
a.組織目標の実現
組織目標の達成を重視し、その実現のためのプロセスを通して、長期的な観点で会社本来の「ビジネスモデル上の強み」を発揮続けられるような社員への成長を促すこと
b.公平な処遇の実現
社員の貢献を的確に考課し、昇格(降格)、昇給(降給)、賞与、退職金などの処遇に公平公正に反映させること
c.人材育成と上司の管理能力向上
上司が、期初の部下との目標設定時のコミュニケーション、期中の部下の業務遂行への支援、期末の考課結果のフィードバックを通して、部下の能力開発を図ると共に、上司自身の部下育成力を高めていくこと
(2)等級制度との連動
会社が、等級毎に社員に求める業務内容、責任度合い、レベルなどを「資格等級基準書」に定めます。その「資格等級基準書」に定めた等級別の違いを反映した考課ができるにすることが必要です。(3)職種別の違いの反映
会社内には、一般的に営業職、製造職、研究開発職、事務職、配送職、物流職等、複数の職種が存在します。同一等級でも、職種毎に会社が求める内容は異なります。それらを踏まえた内容にしなければなりません。(4)精緻さとシンプルさの併用
人事考課制度の納得性を高めようと努めるあまり、ともすれば最初の想定以上に精緻な制度になりがちです。しかし、その精緻さのため運用が行き詰まってしまうことがよく見られます。精緻さとシンプルさの二律背反の関係を、両睨みした落としどころを見出すことが求められます。(5)上司と部下のコミュニケーションの機会の確保
上司が、人事考課をすることに負担感を抱く場合があります。そうならないために、人事考課と業務遂行とが、同じことの表裏一体の関係にあることを共通認識まで高めるための考課者研修が重要です。これにより、上司が部下とのコミュニケーションの機会を増加させることができます。「人事制度」の構築で検討すべき内容
人事考課制度構築上、検討すべき項目を示します。(1)考課の種類(昇給昇格考課、賞与考課)
a.賞与考課夏季と冬季賞与支給に合わせ、賞与考課を年2回実施することが一般的です。賞与支給時期と、会社の決算月とを勘案して、各々賞与考課の期間を決定します。
賞与考課は、主として6ヵ月間の成績考課に重きを置いて考課します。そして、この結果を賞与の支給額に反映させることで、短期的な貢献に対する社員のモチベーションを刺激します。
b.昇給昇格考課
昇給昇格考課は年1回行います。考課期間は、原則決算期と同一とします。昇給昇格考課を賞与考課とは別にすると、年3回も考課することになり負担感が増加します。そのため、2回の賞与考課の平均点を、昇給昇格考課とすることが一般的です。
昇給昇格考課の結果によって、昇給額を決めます(賃金表として段階号俸表を採用している場合は昇給号数に、ポイント昇給表を採用している場合はポイントに反映します)。
また、2~3年間続けて優れた考課ランクを取り続けた社員を昇格の対象者とし、その中から昇格者を決定します。昇格昇給考課では、中長期的な能力や行動考課に重きを置いて考課します。
(2)考課制度の流れ(スケジュール)
a.目標設定半期ごとに賞与考課の目標を設定します(成績考課)。そのためには、会社全体の目標を明確にし、「目標面談」で各社員と協議して振り分けます。社員が自ら設定する目標もあります。
b.期中
部下は目標遂行のため努力し、上司はその達成のための指導、支援をします。
c.期末
目標の達成度と、行動能力考課の考課を合わせて、自己評価、一次評価、二次評価の順で考課し、考課点を算出しそれにより考課ランクを決定します。そして、その考課の内容と結果を、上司が部下に「フィードバック」します。
フィードバックでは、部下の意見を十分聴いたうえで、考課ランク、良かった点、課題として残った点、上司と部下の評価の違う項目の考課の根拠、来期の課題などを話し合います。
(3)自己評価の有無
考課者の考課の前に、自己評価を入れる場合と入れない場合があります。考課の基準や考課の結果は、「一切、部下には厳秘」というスタイルの場合は、自己評価を入れません。しかし、部下の成長を促す仕組みとする現在の人事考課制度では、期初に、人事考課表を配布することで、会社が何を求めているかを知らしめ、期中に社員がそれに沿った行動能力を発揮することを奨励します。
そして、一次考課以降の考課には全く反映させませんが、本人の評価をさせ自覚を促します。そして、上司が部下の自己評価と一次考課以降との考課ランクの差を知ることで、フィードバックすべき点を整理して話すことができるようになります。
(4)考課者と被考課者
原則として、直属の上司を一次考課者とします。部下が2桁となるように多い場合には、適宜部下の毎日の業務遂行を見ている社員(係長、主任等)を「意見具申者」として、その評価を一次考課者が参考に用いる場合もあります。また、部下が異なる部署を兼務する場合は、主たる業務の上司が、兼務する業務の管理職の意見を参考にして考課をします。
一次考課は、考課基準に基づいた「絶対考課」をしなければなりません。逆に、部下同士を並べてその順に考課するという「相対考課」をしてはいけません。次いで、二次考課は一次考課者の甘辛傾向の修正や部署間業種間の不均衡を調整して行う必要があります。
- 1