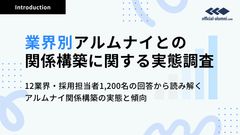「不当な会社批判を繰り返す幹部候補社員」に関する相談事例
「幹部候補の社員(近い将来の管理職)として採用した社員が不当な会社批判を繰り返しています。あまりに偏った内容で、会社はもちろんのこと、社員も迷惑を受けています。不安や動揺を訴えている社員も多くいます。試用期間中に、何度も面談を行い指導・教育を行いましたが、改めるどころか過激さを増しています。経営者への誹謗中傷とも取れる発言を行いましたが、その点は改めてくれました。このような場合、本採用を拒否しても問題ありませんよね?」この事例を考えるにあたって、まずは、本採用拒否の“法的な論点”を整理してみましょう。
本採用拒否における“法的な論点”を整理
「労働基準法」には本採用拒否の条文はありませんが、有名な最高裁判例(三菱樹脂事件判決・最大昭48.12.12)があります。「試用期間中の本採用拒否は、解約権留保付きの労働契約と呼ばれ、通常の解雇よりは認められやすい」と一般的にはされています。そこで、就業規則に、解雇の事由とは別に本採用拒否の事由を詳細に設けておく会社も多く存在します。今回のケースで本採用拒否が認められるか否かは、以下のような事情を考慮する必要があるでしょう。
●会社批判の具体的な内容/誹謗中傷の該当性/表現方法/態様/回数/程度
●どのような場面で誰に対して行っているか?
●業務命令には従っているか?
いずれにせよ、個別の事情を考慮することが必要です。この事例では、何度も面談を行い指導・教育しています。また、社員の不安や動揺など職場秩序を乱しています。
その一方で、経営者への誹謗中傷とも取れる言動については改めています。本人に誹謗中傷の意図はないように見受けられます。このような事情を踏まえると本採用拒否の法的リスクは残るでしょう。
しかし、ここで、私が取り上げたいのは、「今回の社員の言動が判例を踏まえて本採用拒否の要件を満たしているか」という話ではありません。このようなケースの場合、本採用拒否で労使トラブルに発展しないために、他にも大切なことがあると考えています。それは、何でしょうか?
労使トラブルに発展しないために大切なのは“適切な言葉”で説明すること
結論から申しあげると、会社批判を繰り返す幹部候補の社員に、 “適切な言葉”で言動の真の問題点を説明し伝えることです。真の問題点の言語化と言い換えても良いかもしれません。今回のケースでは、「不当な会社批判を繰り返しているので本採用を拒否します」という伝え方は適切ではないと考えています。もし、会社がこのように伝えた場合、どのような反応が返ってくるでしょうか?
「自分は意見を述べているだけです。会社への誹謗中傷とも取れる発言に関しては非を認め、改めています」と言われると、主観的な問題ですので平行線になりますよね。更には、「この会社は批判を許さない会社なのですね」と言われると、返す言葉に詰まってしまわないでしょうか? そのような状況で本採用を拒否するとトラブルに発展しかねません。
また、本採用を拒否すると、第三者に相談することもあるでしょう。会社批判を理由として本採用を拒否されたと聞いた第三者は、どう思うでしょうか? 「批判を許さない独善的な会社」と受け取られかねません。仮に、法的なトラブルには発展しなかったとしても、会社の評判に悪影響を与えることになりかねません。
そこで、会社批判という誤解を生みやすい言葉を使わずに、社員に問題点を違う角度から説明することが適切だと思います。
「管理職に求められる役割は何か?」を起点に、言動の問題点を説明する
今回のケースは、近い将来、管理職として活躍してもらう予定の社員の言動です。このようなケースの場合、「管理職の役割は何か?」から、社員に言動の問題点を説明することが有効だと思われます。管理職の役割は会社ごとに異なるでしょうが、その役割の一つに、会社の方針を現場にまで行き渡らせ、その実現を図ることがあるでしょう。会社が大きくなると、経営会議で決まった方針を社員一人一人に直接伝え、実行に移していくことは困難になるからです。そのような役割が管理職には与えられているため、現場の社員と会社の間に入って苦しんでいる方が多いのではないでしょうか?
今回のケースのように、不当な会社批判を繰り返し、それを一般社員に向けて広めることで職場に不安や動揺を招いている場合、管理職の役割を果たそうとしていると言えないのではないでしょうか? しかも、社員の不安や動揺を知りつつ改める意思がないのです。
「不当な会社批判を繰り返すので本採用を拒否します」と伝えたらトラブルに発展しかねません。しかし、管理職に求める役割を明確にし、その内容を説明したうえで、「管理職としての役割を果たすつもりがないなら本採用できない」と言われたら話は変わってくるはずです。仮に、本採用拒否が難しいケースだったとしても、「将来の管理職としての採用はできない」とすることは多くの方に受け入れられる話ではないでしょうか?
更に、会社と将来の管理職の向いている方向が全く違うのであれば、社員にとっても入社はストレスですので、トラブルになることは少ないでしょう。
*
今回は、本採用拒否の話をしましたが、労使トラブル回避全般に共通する話だと思われます。
法律をふまえた対応は当然のことです。社員との話し合いも大切なことです。しかし、ただ話し合いをすれば良いわけではありません。会社には多様な価値観を持った人間が集まるのですから、誤解を生まないように「適切な言葉で言語化」し伝えることが大切と考えています。
しかし、その前提として、相手の話を丁寧に聴くことが必要です。相手の話を丁寧に聴かなければ、会社が求める管理職としての役割を果たそうとしてくれているかどうか判断できないからです。
- 1