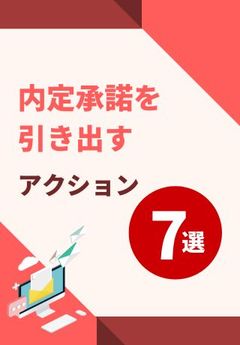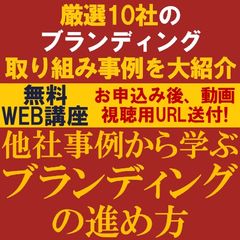部下へのそのアドバイスは適切?
アドバイスの仕方の良否は、部下に“前向きな気持ち”を醸成する上で非常に重要である。具体例で考えてみよう。例えば、リーダーが部下に対し、新規顧客向け提案書の作成を命じたとする。しばらくして、部下は完成した資料をリーダーに提出した。ところが、事前に十分な説明をしたのにもかかわらず、作成された資料は自社の優位性を的確に読み取れるものではなかった。このまま使用しても新規顧客の獲得はおぼつかない。果たして、その部下にどのようなアドバイスをするのが適切だろうか。
このような状況に遭遇したときにリーダーの皆さんの中には、「もっと差別化要因を明確に訴求しなければダメじゃないか」などと言い放つ人がいるかもしれない。もちろん、そのような発言に及ぶ心情は理解できる。しかしながら、そのような助言の仕方で、提案書作成に対する部下の思考や行動は前向きに改善されるだろうか。
意識したい『否定表現』と『肯定表現』
部下にアドバイスを与えて思考や行動の改善を促すには、『肯定表現』を活用することが有益である。一般的に、ヒトは相手の問題点が目に付くと、「○○するのはよくない」、「○○はダメだ」などの表現で指摘をしがちだ。この「よくない」、「ダメだ」は、いずれも文末が『否定表現』で終わっている。しかしながら、自身のアドバイスで相手の問題点を改善させたいと考えるのであれば、「よくない」、「ダメだ」という文末の表現を「○○するとよい」などと『肯定表現』で終わるように変えてから使用するとよい。
前述の事例であれば、リーダーが口にした「もっと差別化要因を明確に訴求しなければダメじゃないか」という発言は、文末が『否定表現』で終わっている。このようなときに「もっと差別化要因を明確に訴求したほうがいいぞ」などと言うのが、文末を『肯定表現』に置き換えるという意味である。
この2つの言い回しは、文字にするとごくわずかな相違でしかない。ところが、実際に使用した場合の心理的効果には、極めて大きな違いが存在する。『否定表現』で言われた相手は指摘を受け入れがたい気持ちになりやすく、『肯定表現』で言われた相手は指摘を受け入れやすい気持ちになるものだ。
人間は“理屈”ではなく“感情”で動く
『否定表現』でアドバイスを受けると、どんなに指摘されたことが正しいと理屈では理解できても「感情的に納得できない」という心情に陥りがちだ。指摘をした相手に反感や嫌悪感、怒りを覚えることさえ少なくない。このように『否定表現』は後ろ向きな気持ちを醸成しやすく、相手の心を閉ざすマイナスの作用を持つ。人間は “理屈” ではなく “感情” で動くものだからだ。
一方、『肯定表現』で行われたアドバイスに対しては、感情的に指摘を受け入れやすい傾向にある。「次は気をつけよう!」、「よし、がんばろう!」などと、自らの意思で前向きに考えることが大いに期待できるものだ。
『肯定表現』が受け入れられやすい理由は、プラス評価を得られたとの認識を与えやすく責めるニュアンスが表れにくいことにある。
「もっと差別化要因を明確に訴求しなければダメじゃないか」は、作成した提案書に評価の余地はなく、単に責めているようにも聞こえる助言である。そのため、アドバイスを受けた部下の心理的安全性を阻害しかねない。
一方、「もっと差別化要因を明確に訴求したほうがいいぞ」は、必ずしも責めているようには聞こえない。作成した提案書が一定の評価を受けた上で、さらに有益な情報を得られたと感じさせる助言である。その結果、部下の心に好感情と心理的安全性が芽生え、“前向きな気持ち”が醸成されやすくなるようだ。
組織風土の活性化には時間が必要
ビジネスパーソンの“前向きな気持ち”は、自身の利害よりも職場にとっての“好ましい行動”を優先する特徴を持つ。そのため、“前向きな気持ち”を抱いた人材は職場のパフォーマンス向上など、組織にプラスの影響を与えやすい。また、ひとりのメンバーの“好ましい行動”は、時間の経過とともに他のメンバーに伝染する傾向にある。結果として多くのメンバーの行動が変わると、職場の雰囲気も変わり始める。職場環境や組織風土はこのように変化することが少なくない。風土はメンバーの思考・行動特性の集合体だからである。
そのため、『否定表現』を『肯定表現』に変えて使用するアドバイスは、メンバーの“前向きな気持ち”で組織を活性化できる手法として一定の効果が期待できよう。決して難易度が高い方法ではなく、その気さえあれば今日からでも取り入れることが可能だ。
ただし、注意点がある。職場環境がすぐに変わらなくても、「この方法では組織は活性化できない」などと早合点しないことである。
組織における「風土」は、人間でいえば「体質」に相当する。人間が「体質」を改善するのに時間が掛かるように、組織が「風土」を変革するのにも時間が必要だ。従って、組織活性化手法に即効性を期待するのは適切ではない。根気強く継続することが、何よりも肝要である。
- 1