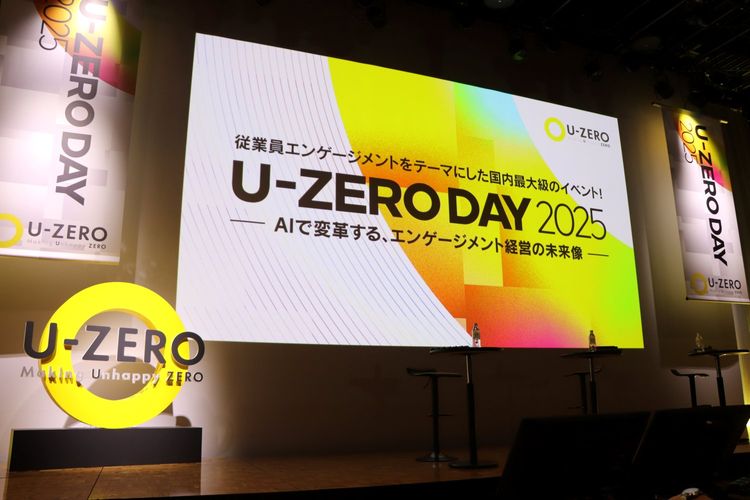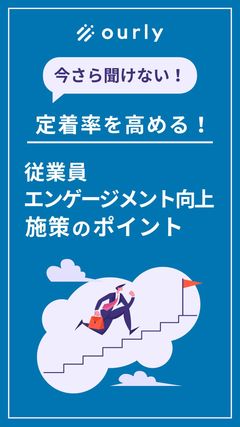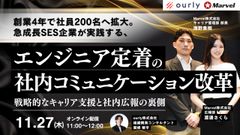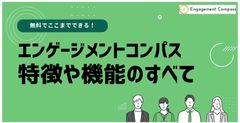HRプロ編集部 特別取材記事
“現状分析”から“全社アクション”へ――組織全体で実現する従業員エンゲージメント変革のヒント【U-ZERO DAY 2025】
株式会社U-ZEROは5月22日、東京・中央区にて従業員エンゲージメントをテーマにしたイベント「U-ZERO DAY 2025」を開催した。同イベントは、先進企業の取り組み事例の紹介や、経営者や人事責任者による基調講演の内容から、従業員エンゲージメントの変革を実現するためのヒントを提供するイベントだ。現状分析で終わらず、実行にスムーズにシフトするためのヒントが各公演に散りばめられていた。本稿では、その模様と、特に注目すべき4つの講演内容をお伝えする。
先進事例や知見によってエンゲージメント経営のヒントを探るプラットフォーム「U-ZERO DAY 2025」
どうすれば、社員がもっと主体的に、そして熱意を持って働けるようになるのか?――多くの企業の経営層や人事担当者が抱える共通の課題だろう。米ギャラップ社が2024年6月に発表した調査によれば、日本における、仕事への熱意のある(エンゲージメントの強い)従業員の割合はわずか6%と、調査対象139カ国中最低水準だった。世界平均23%を大きく下回り、31%のアメリカだけでなく、同じアジア圏の中国(19%)や韓国(13%)よりも低い数値である。
この状況を憂うのは、株式会社U-ZEROの代表取締役CEO兼CPOを務める三村 真宗 氏だ。同氏は、「働きがいのある会社」ランキング(Great Place To Work® Institute Japan)で株式会社コンカーを史上初の7年連続1位に導くと、24年6月に株式会社U-ZEROを設立し、日本の従業員エンゲージメントの変革に向けたサービス提供やサポートを行っている。
そんな三村氏のU-ZEROが主催した「U-ZERO DAY 2025」は、まさに日本のエンゲージメントの課題に光を当て、改革すべく開催された。先進企業の実践事例やトップランナーの知見を共有することで、エンゲージメント経営実現への具体的なヒントを探るプラットフォームである。
株式会社U-ZERO 代表取締役CEO兼CPO 三村 真宗 氏
5月22日に、東京・中央区で開かれた本イベントには616名以上が来場。メイン会場とサテライト会場はほぼ満席で、ホワイエに仮説席を設けるほどの盛況ぶりだった。今回はそんなイベントから、注目すべき以下4講演の内容をまとめてお伝えしたい。・[ゲスト基調講演]人的資本経営による企業価値創造…決め手となる従業員エンゲージメントの向上
この先は会員のみがご覧になれます。
著者:
HRプロ編集部
採用、教育・研修、労務、人事戦略などにおける人事トレンドを発信中。押さえておきたい基本知識から、最新ニュース、対談・インタビューやお役立ち情報・セミナーレポートまで、HRプロならではの視点と情報量でお届けします。
キーワードフォローをご利用いただくには、会員登録(無料)が必要です。
経営プロ会員の方へ
経営プロアカウントとHRプロアカウントは統合いたしました。経営プロのアカウントをお持ちの方は、HRプロアカウントへの移行・統合手続きをお願いいたします。下の「経営プロ」タブを選び、「経営プロ会員の方はこちらから」が表示されている状態でログインしてください。
[ゲスト基調講演]
人的資本経営による企業価値創造…決め手となる従業員エンゲージメントの向上
・プレゼンター
早稲田ビジネススクール 教授
(マッキンゼー・アンド・カンパニー 元日本代表)
平野 正雄 氏
最初のゲスト基調講演で登壇したのが、早稲田ビジネススクールの平野 正雄 教授(マッキンゼー・アンド・カンパニー 元日本代表)だ。平野教授は、「人的資本経営における企業価値創造」というテーマで、企業が持続的に成長し、価値を向上させる上で従業員エンゲージメントがいかに重要であるか、そしてその具体的な道筋について、独自の調査結果を基に解説した。20~50代の社会人(314名)のアンケート調査と、日本CHRO協会による人事部門調査の結果を、重回帰分析やクロス集計によって紐解いたことで、業績や企業価値を高めるために従業員エンゲージメントに有効な要素が明らかになったのだという。
とりわけ重要なのが、働きがいと心理的安全性だ。アンケート結果からは「自分たち(従業員)の声が経営に反映されているか」、「職場の心理的安全性が担保されているか」が働きがいに影響を与えており、オープンに議論し、全体で前に進めていける職場かどうかが重要だということがわかったという。
さらに心理的安全性は、働きがいだけでなく、定着意思にも連動するという相関が裏付けられた。また、「声を上げられる職場」というのは、「気兼ねなく意見できる」ということとつながり、「不正に声を上げられる」、「同僚との連帯感がある」、「組織の壁が低い」という要素と強く紐づいているということも実証できたそうだ。
一方で、経営陣のコミットメントも重要だという。制度の整備よりも、「現場の声がきっちり経営に反映されているか」、「経営と人事部門、経営と現場の信頼関係が築けているか」が重要であることがCHROへの調査で明らかになった。さらに、経営者が従業員の声に耳を傾けていることが、建設的に伝え合う組織風土を作り上げていくうえで肝要で、そうした組織風土のある職場では、経営者に対する信頼度も当然高いことも相関として判明した。一方、CHROへの調査結果では、経営陣が従業員エンゲージメントの重要性を認識しているという回答は94%にも上ったものの、実際に従業員エンゲージメントを強化するための取り組みにリソース配分を行っているという回答は49%と約半数に。さらに従業員エンゲージメントを経営のKPIとして設定しているという回答は22%に留まることが判明した。
平野教授は「経営陣は従業員エンゲージメントの重要性はわかっているが、実際には経営に反映されず、指標としてもモニターされず、継続的に改善していく取り組みに至っていない」と指摘し、「いかに経営の重要項目としていくのかを、人事のみなさまは苦心されているのだろう」と課題を挙げた。
そのうえで、平野教授は3つの具体的なアクションを提案する。
(1)日常体験の改善
・トップの関与により”安心できる”職場を作ること
・心理的安全性を担保していくこと
・サーベイの結果がしっかり経営に反映すること
(2)対話文化の醸成
・日常のフィードバックを制度化すること
・上司だけでなく同僚間でのチームを越えた連携促進
・風通しと声の届き方の見直し
(3)信頼に基づくマネジメント
・制度より信頼関係
・人事部門と経営の連携
・個別対話と共感に基づくリーダーシップ(多く対話すること)
「いろんな制度や仕組みを導入すること、サーベイを実施することに苦心されていると思うが、日常体験の改善、対話文化の醸成、リーダーが多く発信して従業員や人事部門と対話していくことのほうがむしろ重要」だと平野教授は説く。
さらに最後に「日本の経営者の特徴として、社員との対話やコミュニケーションに使っている時間が欧米の経営者と比べて非常に少ないことが調査で明らかになっている。経営陣が対話の時間を多くとることによって、組織の文化が変わっていき、メンバーが活性化されていく。経営陣が振り分けるリソースとして最も重要なのは、従業員でも予算でもなくて、実は経営陣のアテンションである」と、経営陣の関心を従業員エンゲージメントに向けていくことの重要性を強調した。
[U-ZERO 基調講演]
エンゲージメント共創経営の実現に向けて
・プレゼンター
株式会社U-ZERO
代表取締役CEO兼CPO
三村 真宗 氏
・ゲストスピーカー
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
執行役員 Human Capital Offering Leader
全 大忠 氏
・ゲストスピーカー
SAPジャパン株式会社
バイスプレジデント
人事・人財ソリューション事業本部 本部長
広田 敏章 氏
元・株式会社コンカー 代表取締役社長、現・株式会社U-ZERO 代表取締役CEO兼CPOである三村 真宗 氏が基調講演で語ったのは、7年連続で「働きがいのある会社」ランキングで7年連続1位に輝いたコンカー時代の事例、そしてそのコンカー時代に培った知見と経験を型化することをファーストステップとして、いかにU-ZEROのソリューションを通じて「エンゲージメント共創経営」を実現していくかだ。また、U-ZEROのソリューションパートナーであるデロイト トーマツ コンサルティング合同会社と、SAPジャパン株式会社の両社からも担当者が登壇し、U-ZEROと提携した理由と同社への期待を口にした。
まず、三村氏が語ったのが、コンカーでの事例を基にした「対話と信頼の文化」を創造することの大切さだ。三村氏がコンカーの代表取締役社長に就任した当初は、「数字至上主義」の方針を掲げていたせいで、社内では不信感が募り、沈黙、あるいは怒号が飛び交うような「エンゲージメントは多分0%だった」というほどの状況だった。しかし、ふと読み直したジム・コリンズの名著『ビジョナリーカンパニー2』の「適切な人をバスに乗せ、どこに向かうかを決める」という考え方に改めて感銘を受け、体制や目標を見直し、働きがいのある企業にすべく組織文化の創造に注力していった。
三村氏は「風土は自然に醸成されるもの。それに対し、文化は意図して作っていくものであり、人の価値観や行動規範に無意識の落とし込まれていく」と捉え、「文化創造」に挑んだのである。そこで、本音が埋もれて静かに分断している「沈黙と分断の文化」から、本音で語り合い信頼が育まれる「対話と信頼の文化」への転換を目指した。
「対話と信頼の文化」を創造するための取り組みとして推進したのが、社員の声を拾い上げる「タテの改革」と、社内のフィードバックを促進させる「ヨコの改革」である。
「タテの改革は、社員の声にちゃんと耳を傾けること。経営者は組織の中ではトップの立場だが、全知全能ではない。働いているのは、一人ひとりの社員。どんな課題があって、どんな改善のアイデアがあって、どんなヒントがあるのか。経営者が知らない様々な声を社員は知っている。その声にしっかりと耳を傾けること。
そして、ヨコの改革は、社員同士でもっとフィードバックをしようと促すこと。何か課題があったらそれを抱え込んだり、陰口を言ったりするのではなくて、たとえ相手にとって耳の痛い話であっても相手の成長を願ってしっかり伝えようと。自分にとって耳の痛い話であっても前向きに受け止めようと。こういうフィードバック文化を築くこと」こうした三村氏の理念の基で改革を進めた結果、コンカーは5年後に米国に次ぐまでに業績を伸ばしただけでなく、前述のとおり「働きがいのある会社」ランキングの中規模部門で7年連続1位を達成した。
三村氏は「働きがいの取り組みをしたからこそ、業績の伸びがついてきた。働きがいを作ることは、数字至上主義だった自分を戒めるための“ブレーキ”だと思っていたが、実は会社にとっては“アクセル”だった」と振り返り、エンゲージメント施策が企業の成長への投資であることを示した。
こうしたコンカーでの成功体験を一つの「型」にして他社に展開しようというのが、U-ZEROでの取り組みである。従業員エンゲージメントをハーズバーグの二要因理論によって分けたときに、労働条件などの「働きやすさ(衛生要因)」の整備は重要だが、それだけでは持続的な「やりがい(動機づけ要因)」にはつながりにくい。
三村氏は、「働きやすさ(衛生要因)」を「答えが分かりやすい科学」に例え、その対比として「動機付け要因(やりがい)」の領域を「右脳的な世界、つまりアート。答えが分かりにくい」と説き、だからこそ「”型”が有効だ」と述べた。
一方で「社内に推進体制がない」という悩みの声も三村氏の元には集まっていたという。具体的には「経営層から人事への丸投げ、人事の工数逼迫、現場管理職の困惑、そして従業員の“どうせ変わらない”という諦めといった負の連鎖」である。
そこで三村氏が掲げるのが『エンゲージメント共創経営』だ。これは、エンゲージメント向上を特定部署の責任に依らず、経営陣・人事・管理職・一般従業員が一体で取り組む考え方である。具体的には、VoE(Voice of Employee=従業員の声を経営に活かす仕組み)の構築、フィードバック文化の制度的な支援、AIを活用したエンプロイーサクセスの追求などだ。三村氏は「従業員エンゲージメントを改善することによって、離職率も休職率も改善するし、生産性も上がるし、顧客満足度も上がる。その結果、売上や利益率も20%前後改善する」と、ギャラップ社の調査を用いながらエンゲージメント向上がもたらす経営効果を示した。だからこそ、「エンゲージメントは誰かがオーナーシップを担うものではない。丸投げし合うものではない。みんなで共創するものである」と強調する。
従業員エンゲージメントの変革には、「対話と信頼」の文化醸成と仕組みづくりを、立場を問わず組織一体で推進していくことが求められる。特に人事担当者には、この“共創”のハブとして、役割が期待されるのである。
では、U-ZEROがどのように「エンゲージメント共創経営」を具現化させていくのか。その基本思想が以下である。
①洞察支援(膨大なデータからAIを活用しながら課題を抽出。リスクの高い領域から着手し、改善インパクトの最大化を狙う)
②アクション思考(モニタリングの結果から改善アクションまでやり切るクローズドループアプローチ)
③一貫性
各課題やテーマに応じたコンポーネントを一通りパートナーと提携しながら提供する
④固有課題への対応(様々な課題に対応する)という基本思想を基にしたアプローチ
そして具体的には、「デジタル」、「コンサルティング」、「エンパワーメント」の3つの領域におけるソリューションを、パートナー企業と手を組みながら提供して組み合わせることで解決していくのだという。
デジタルパートナーの一つであるSAPジャパン株式会社の広田 敏章 氏(バイスプレジデント 人事・人財ソリューション事業本部 本部長)は、「我々が提供している『SAP SuccessFactors』は採用から退職までのタレントマネジメントの一貫したプロセスをカバーしているが、U-ZEROが提供されているエンゲージメントを起点としたサービスは組み込まれていない。よって『SAP SuccessFactors』のタレントマネジメントの仕組みと、U-ZEROが提供されているエンゲージメントサービスは相当な補完関係があると位置づけている」とその補完性に自信を示した。
一方で、コンサルティングパートナーの一つであるデロイト トーマツ コンサルティングの全 大忠 氏(執行役員 Human Capital Offering Leader)も、「今までタレントマネジメントでは取得できなかったデータが、U-ZEROのソリューションを使うことによって得られる。変動性の高いデータを取ってAIで分析をすることで、エンゲージメントの根幹を把握する分析の解像度を上げていきたい。よりユーザーライクなシンプルなデータシステム構成が、AI起点であるU-ZEROだからこそできると思っている。これを使い、日本の人事部がより元気になることを進めていきたいと思っている」とU-ZEROへの期待を語った。
[事例講演]
富士通におけるVoE経営の取り組み
・ゲストスピーカー
富士通株式会社
取締役執行役員専務 CHRO
平松 浩樹 氏
・ゲストスピーカー
富士通株式会社
カスタマーグロース戦略室 Digital Sales Division長
友廣 啓爾 氏
90年の歴史と国内7万人の従業員を抱える富士通株式会社。そんな伝統的大企業の取締役執行役員専務 CHROを務める平松 浩樹 氏は、「日本企業は世界の先進国の中でも特に従業員エンゲージメントが低く、ホワイトカラーの生産性が低く、女性活躍推進も進んでいない。人への投資も少なく、生産性が低いので賃金も低く、自己啓発もなかなかしない。富士通も数年前まで、まさにそれそのままの会社であった」と語る。多くの日本企業が直面するこの根深い課題に対し、富士通は従業員一人ひとりの声を拾い上げ、自律的な組織文化醸成のために活用することで、従業員エンゲージメントを向上させる取り組みを拡大している。
平松氏は「会社と社員が選び・選ばれる関係を築き、社員の自立的挑戦を促すことが重要」とし、人的資本経営を考えるための構想フレームとして『人的資本価値向上モデル』を構築。その中で、エンゲージメント向上とキャリアオーナーシップの強化を全社的な重要テーマと位置付けた。
「会社のパーパスやビジョン、経営戦略を実現するために理想の人材ポートフォリオを描き、必要な人材や強化すべき・縮小すべき領域など要件を具体化していく。そして、現実と理想のギャップを埋める時に一番大事なのが、従業員一人ひとりのエンゲージメント向上だ。富士通では、“キャリアオーナーシップを高める“と呼ぶ。キャリアオーナーシップを高めることで会社の進む方向性、強化すべき・投資すべき領域が見えてくる」と平松氏は言う。
キャリアオーナーシップを高める取り組みの根幹にあったのが、データ活用である。エンゲージメントサーベイなどの調査を基に、従業員エンゲージメントとその他の要素の因果関係を分析することで、その分析結果を活用しながら各現場のマネージャーに一人ひとりに適したコミュニケーションを促したり、ハイブリッドワークの推進やポスティング制度の拡大、eラーニング環境の整備などの制度面の充実を図ったりと環境を整備した。
さらに「制度や仕組みでスコアは上がったが、最前線のマネージャーや社員一人ひとりの主体的な動きが不可欠」という課題に対しても、解決施策を打ち出している。
その中で、カスタマーグロース戦略室 Digital Sales Division長の友廣 啓爾 氏は「良い意味で富士通らしくない組織」を目指し、多様性と働きやすさを追求することで、社内で最もエンゲージメントが高いと言われる組織を作り上げている。
実際に、社内のポスティング制度を積極的に推奨し、キャリア採用との割合を同程度にするのと同時に、男女比率も極力同様にするように採用を進めてきた。これは「同質性が高すぎる組織は、なかなかイノベーションが進まない」という理論の下、対立した概念を内包する「二項動態」の組織とするためだ。さらに友廣氏は「インサイドセールスという仕事柄、どうしても孤独感を抱く瞬間はある。だからこそウェルビーイングな職場にするために、さまざまな施策をしている」と話す。それが月1回の対面交流であり、1on1の実施であり、ヨガなどのレクリエーションといったコミュニケーション促進の取り組みなどだ。
また、「自分の考えやチームとしての考えを言語化して、メンバーに伝えている。それも一度ではなく、あの手この手で繰り返し伝えていくことを非常に大切にした」と積極的に発信を行ったという。「施策をしたからと言って、エンゲージメントが上がるわけではない。根底にはリーダーがどういう組織にしたいか、どういう組織を作っていくかという大きなダイレクションが重要だと思っている」からだ。
そうした取り組みや考えを他部署に横展開していった結果、「富士通として従業員エンゲージメントが高い組織を作っていくというのが当たり前になった」と一定の手応えも友廣氏は口にした。
そして、今後はU-ZEROが提供するチームシナジーモニタリングをさらに活用し、表面化しにくい組織課題の可視化にも注力することで、さらなる組織力向上も見据える。
友廣氏は「エンゲージメントが高い組織でも、実は見えない課題が潜んでいることがある。AIによる分析と対話を通じて、その課題を炙り出す」と説明。組織独自の取り組みとして、さらに13個のコンピテンシー設定とその360度評価、肯定的に評価しながら解決に導くコンストラクティブフィードバックの浸透を進め、社員のさらに細かな声を拾い上げながら、その声を活用する文化の醸成を目指している。
これに加え、最後に平松氏が「AIを活用して本音を引き出したり、解決策を考えたりして、さらにその先の具体的なアクションやコミュニケーションにつなげる。こうした取り組みを別の事業部門にも広げていく」と、より大きな規模へと広げていくビジョンを示した。
[パネルディスカッション]
フィードバック文化について
・パネリスト
東京海上日動火災保険株式会社
人事企画部 人材開発室
能力開発チーム 課長
森山 大志 氏
・パネリスト
株式会社メルカリ
執行役員 CHRO
宮川 愛 氏
・ファシリテーター
株式会社U-ZERO
代表取締役CEO兼CPO
三村 真宗 氏
従業員エンゲージメント向上のカギとなるのがフィードバックだ。東京海上日動火災保険、メルカリの2社から、フィードバック文化の醸成の取り組みについて、文化を定着させるための具体的な施策について掘り下げたのが、今回のパネルディスカッションの主旨となった。
東京海上日動火災保険株式会社では、保険という形のない商品を扱う上で、「人が作り上げる信頼が全ての競争力の源泉」であるとし、以前から自由闊達なコミュニケーションを重視する文化があった。しかし、人事企画部 人材開発室 能力開発チーム 課長の森山 大志 氏は「相手にとって耳の痛いことも伝えていく、いわゆるギャップフィードバックであったり、自らの成長につなげるコーチャビリティ(受け止める力)を通じた一歩踏み込んだコミュニケーションが積極的に行われていたりしたかと言うと、そこまでには至っていなかった」と振り返る。さらに、中途採用の増加やダイバーシティの推進といった社内環境の変化を受け、「阿吽の呼吸ではなく、はっきりと言葉にして伝える文化を醸成していく必要が高まっている」という背景もあり、フィードバック文化の醸成を、2024年度から2026年度までの中期経営計画の柱の一つとして位置づけたという。
具体的な施策としては、三村氏へのインタビュー記事を全社員1万7000人に展開することによるフィードバックの必要性に関する意識喚起に加え、フィードバック研修の組成・実施を行った。フィードバック研修には、2024年度には約1000人が参加、2025年度には1500人の参加を見込んでいるという。
しかし、手挙げ制の研修であったため、研修を受講した人とそうでない人が混在し、組織の中でプロトコル(共通認識)を合わせられていなかったという課題もあったそうだ。そこで、2025年度からは手挙げの参加枠を減らし、エリア単位で参加者を選定する方式に変更した。例えば、九州・沖縄エリアではリーダークラスの参加を強く推奨することで、リーダー発で組織にフィードバック文化を根付かせるよう促すなど、エリアごとに戦略を立てて研修を運用している。
その後の実際の変化として、森山氏は「研修を受講したメンバーが内容に共感をしてくださり、自らの組織で勉強会を企画したりだとか、自分の言葉でフィードバックに必要なエッセンスを周囲に伝播するという動きが出てきている。まさにフィードバックを通じて、組織の活性化につながってきている」と、確かな手応えを口にした。
一方、株式会社メルカリの執行役員 CHROである宮川 愛 氏は、前職のシスコシステムズ CHROの経験を踏まえ、フィードバック文化の重要性から語った。シスコシステムズは「働きがいのある会社」ランキングの大規模部門で1位常連(2018年、2021年、2023年で1位獲得)として高い評価を得ていた。それでも「働きがいのある会社は、終わりがないもの」だとし、事業の3カ年計画の中に人材戦略を組み込み、「理想とのギャップの追求」、「強みをさらに活かすこと」の二つの視点に注力していた。特に大きな課題が「組織のサイロ化」と「個々の社員の優秀さを、いかにチームとしての力に昇華させるか」という点だった。宮川氏は「外資系特有の完全な縦割り構造であるため、日本企業以上に、後ろ指のさし合いになりやすい。また、社員が優秀でエンゲージメントも高いが、単体で力を発揮するだけで横のつながりが生まれなかった」と背景を語る。
だからこそ、「もっとお互いにフィードバックをする。上司から部下だけではなくて、横同士、そして組織を越えてお客様への価値という共通課題に向かって、全員が一丸となってやっていくために」フィードバック文化の醸成の必要があったという。
シスコシステムズでは、経営陣全員がフィードバック文化の醸成にコミットし、「Learning Day」という全社員の研修日を設けて集中的に研修を実施。参加できない社員には録画を提供するなど、100%の受講率を目指した。この徹底した取り組みの結果、「会社の中でフィードバックに対するプロトコル(共通認識)ができた」のだと宮川氏は言う。
フィードバックに対する誤った認識(上司から部下への一方的なもの、ネガティブなものというイメージ)を払拭し、建設的な対話を生むためのマインドセットとスキルを全社で共有できたことが、組織のサイロ化の改善につながったそうだ。
さらにメルカリでも、2024年6月からCHROとして「まずは共通認識を作る上で、経営陣の言動が一致していないと社員はついてこない」とし、経営陣全員によるフィードバック文化醸成へのコミットから着手。具体的には、まずVP層(本部長・部長・次長クラス)、次に管理職、そして最後に全社員へと、順を追ってフィードバックの考え方やスキルを浸透させていく方針で、取り組みを推進しているという。「U-ZERO DAY 2025」での講演は、従業員エンゲージメントの向上が企業の持続的成長や企業価値向上における不可欠なテーマであることが改めて示されたと言える。特に、エンゲージメントサーベイなどでスコアを測定・分析しただけでなく、そこからいかに課題解決のアクションにつなげていくかが重要であること、そしてその難しさは、どの講演においても強調された点であった。
スムーズにアクションに起こすためには、経営陣が従業員エンゲージメント向上やフィードバック文化の醸成にコミットできているか、従業員の声を拾い上げる仕組みがあり、その声が施策に反映されているか、部門・部署・役職などの単体でなく、経営・人事担当者・管理職・現場などが一丸となって取り組めているかが問われている。ぜひ自社の従業員エンゲージメント向上の施策と体制を見直してみてほしい。
ブックマークをご利用いただくには、会員登録(無料)が必要です。
経営プロ会員の方へ
経営プロアカウントとHRプロアカウントは統合いたしました。経営プロのアカウントをお持ちの方は、HRプロアカウントへの移行・統合手続きをお願いいたします。下の「経営プロ」タブを選び、「経営プロ会員の方はこちらから」が表示されている状態でログインしてください。
検討フォルダをご利用いただくには、会員登録(無料)が必要です。
経営プロ会員の方へ
経営プロアカウントとHRプロアカウントは統合いたしました。経営プロのアカウントをお持ちの方は、HRプロアカウントへの移行・統合手続きをお願いいたします。下の「経営プロ」タブを選び、「経営プロ会員の方はこちらから」が表示されている状態でログインしてください。