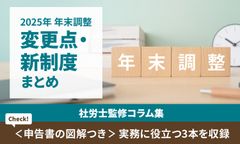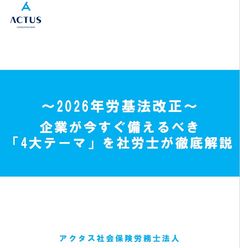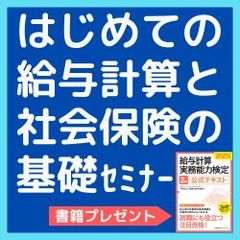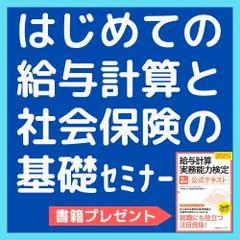■「雇用保険」に関する資料ダウンロード、セミナー、サービス、ニュースなどの最新コンテンツはこちら

「雇用保険」とは
まずは、「雇用保険」とは何かから説明しよう。「雇用保険」とは、労働者が何らかの理由で失業や休業で働けなくなった際に、安定した生活を維持できるよう一定の給付をする公的保険制度をいう。収入を得ることによって、再就職に向けて新たな資格を取得したり、能力のアップを図ったりするなどの準備を進めることができる。「雇用保険」制度への加入は事業者の義務とされており、保険料は労働者と事業主の双方が負担する仕組みになっている。
「雇用保険」とは? 給付の種類や保険料の計算方法をわかりやすく解説
「雇用保険」の加入条件
「雇用保険」はすべての事業者、労働者が対象になるわけではない。加入条件が設けられている。●適用事業所の条件(企業側)
企業は従業員を一人でも雇用する際、「雇用保険」適用事業所として「雇用保険」に加入することを義務付けられている。特に注意しなければいけないのは、初めて「雇用保険」の適用対象となる従業員を雇用した場合だ。必要な手続き書類を所轄のハローワークなどに提出しなければいけない。ただし、暫定任意適用事業に該当する場合には、事業主およびその従業員の意思によって「雇用保険」に加入する、しないを決められる。●加入対象者の条件(従業員側)
加入対象者になるには、以下の3点に該当していなければいけない。・所定労働時間が週20時間以上
最初の条件は、「所定労働時間が週20時間以上」だ。所定労働時間とは、就業規則や雇用契約上の労働時間を指す。ここで注意しなければいけないのは、実働時間を対象としていないことだ。なので、欠勤や遅刻、早退が多く、実働時間が週20時間を満たしていない、あるいは休日出勤や残業を含めると実働時間が20時間を超えていたとしても、あくまでも所定労働時間が週20時間以上であるかどうかが判断のポイントとなる。・31日以上の雇用見込み
「雇用保険」に入るには、31日以上の雇用見込みがあることも条件となる。ただし、雇用期間が定められていない、または初回契約が31日未満であっても更新の可能性がある人は加入対象となり得る。また、過去において同様の雇用契約で勤務していた人が、31日以上雇用された実績があれば更新の可能性があると判断される。・学生ではない
3つ目の条件は、「学生ではない」ことだ。ここで言う、学生とは全日制に通う昼間学生を指す。よって、夜間部や通信制の学生は「雇用保険」の加入対象とならない。ただし、昼間学生であっても例外がある。例えば、休学中の場合や、卒業見込みがあり卒業後も同じ事業所で継続勤務する予定があるといった場合には加入できる。●2028年から加入適用が拡大予定
2028年10月から雇用保険の加入条件が変更となり、適用範囲が現状の所定労働時間「週20時間以上」から「週10時間以上」へと拡大される。これによって、対象者が短時間勤務のパートやアルバイトにまで大きく広がることになる。まだ時間があるとはいえ、「雇用保険」の加入適用が変わることを織り込んだ上で、社内環境の整備を図るようにしたい。「雇用保険」の給付の種類
「雇用保険」には4種類の給付がある。それぞれの概要を取り上げていこう。●求職者給付
求職者給付とは、一般的には「基本手当(失業手当)」を意味する。「雇用保険」に加入していた失業者の生活を支援するために、再就職するまでの期間、一定の給付金を支給することになっている。基本手当の受給期間は、90日~360日。雇用保険料の支払い期間や離職理由によって異なってくる。また、給付金額も離職時の年齢や離職前の賃金によって違う。なお、給付金を受給するには、ハローワークに来所して求職活動を行わないといけない。●教育訓練給付
教育訓練給付は、労働者のキャリア形成と職業能力の向上を目的とする給付制度だ。厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講・修了した際に学費を一部支給してくれる。さまざまな適用条件を満たす必要があるが、資格を取得して再就職したい労働者にとっては有難いと言える。教育訓練給付金には、専門性や講座内容に応じて「一般教育訓練給付金」「特定一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」などの種類がある。●就職促進給付
就職促進給付は、早期の再就職促進を目的とする給付制度だ。「再就職手当」「就業促進定着手当」「常用就職支度手当」などの種類がある。いずれも再就職が決まった後に、雇用保険の所定給付日数の支給残日数などに応じて給付される。●雇用継続給付
雇用継続給付は、労働者の就労継続を支援する給付制度である。具体的には、「高年齢雇用継続基本給付金」や「高年齢再就職給付金」「育児休業給付金」「介護休業給付金」などの種類がある。「雇用保険」の被保険者の種類
「雇用保険」の被保険者は、雇用形態や対象となる従業員の年齢に基づいて以下の4種類に分類される。●一般被保険者
雇用保険の加入条件を満たしていて、以下3つの被保険者に該当しなければ一般被保険者となる。●短期雇用特例被保険者
4カ月以上の期間を定めて雇用され、週の所定労働時間が30時間以上である季節的な雇用契約の場合は、短期雇用特例被保険者として扱われる。具体的には、海の家やスキー場で働く人などが該当する。●日雇労働被保険者
日々雇用され、30日以内の期間を定めて雇用される人を指す。ただし、連続する2カ月で、どちらも18日以上同じ会社で継続して雇用された場合は、その翌月の最初の日から、一般被保険者となる。●高年齢被保険者
2017年の法改正によって、「雇用保険」の年齢制限が撤廃された。そのため、65歳以上の労働者であっても、加入条件を満たしている場合には「雇用保険」の加入対象となる。65歳以上の労働者のなかで、短期雇用特例労働者や日雇労働被保険者に該当しない人は高年齢被保険者として分類される。さらに、2022年1月からは複数の事業所での勤務時間を合算して条件を満たす場合に加入できる「雇用保険マルチジョブホルダー制度」も施行され、高齢者の雇用保険適用範囲が拡大している。雇用保険マルチジョブホルダー制度とは
2022年1月から雇用保険マルチジョブホルダー制度が施行となり、雇用保険への加入条件が拡大した。これは、マルチ高年齢被保険者として特例で「雇用保険」に加入できる制度となる。以下の条件がある。
・65歳以上の労働者で複数の事業所に勤務している
・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計すると1週間の所定労働時間が20時間以上となる
・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上ある
「雇用保険」の加入対象とならないケース
下記いずれかの条件に当てはまる労働者は、「雇用保険」には加入できない。・週の所定労働時間が20時間未満
・雇用期間が31日未満。しかも雇い止めが明示されている
・昼間学生
・取締役や監査役等の役員の職に就き、しかも部長や支店長などの役職を兼任していない
・雇用期間が4カ月未満かつ所定労働時間が20時間以上30時間未満の季節労働者
・日雇労働被保険者の認可を受けていない日雇労働者
・船員保険の被保険者
・ダブルワークや副業で複数の会社で働いているが、どちらの職場でも加入条件を満たしていない
「雇用保険」の加入手続き
「雇用保険」は、所轄のハローワークに雇用保険被保険者資格取得届を提出することで加入できる。書類を窓口に持参するか、郵送で提出することも可能だ。また、総務省が運営する行政情報ポータルサイト「e-Gov」による電子申請を活用すれば、ペーパーレス化を実現できるだけでなく、時間やコストの削減にもつなげられる。留意したいのは、「雇用保険」の加入申請期日だ。対象となる従業員が入社した月の翌月10日までに実施しなければいけない。なので、迅速な手続きを心がける必要がある。
「雇用保険」の手続きに必要な書類
初めて従業員を雇用する事業所は、「雇用保険」に加入するための手続きを所轄のハローワーク、あるいは各都道府県の労働局、所轄の労働基準監督署で行う必要がある。その際に、必要となる書類は以下の通りだ。・保険関係成立届
会社の概要や会社名、住所、雇用保険への加入日、雇用者数などを記入し、所轄の労働基準監督署に提出する。
・概算保険料申告書
労働保険料に係る賃金の総額や保険料率などを記入し、所轄の労働基準監督署、所轄の労働局、日本銀行のいずれかに提出する。
・雇用保険適用事業所設置届
会社名や住所、被保険者の雇用日、会社の概要、保険関係成立届に記載される労働保険番号などを記入し、所轄のハローワークに提出する。
・雇用保険被保険者資格取得届
被保険者番号や個人番号、事業所番号などを記入し、所轄のハローワークに提出する。
「社会保険・労働保険の電子申請」で日々の手続きをより楽に! 導入に必要なものを解説
「雇用保険」加入に関する注意点
「雇用保険」の加入手続きを行う際には、幾つかの注意点がある。それらを挙げておきたい。●加入漏れは罰則の対象となる
労働局から加入漏れを指摘され、是正勧告を繰り返し受け、悪質と判断された場合には罰則の対象となってしまう。具体的には、事業主に懲役6カ月以下あるいは罰金30万円の罰則が課せられる。●二重加入がないか確認する
複数の事業所での二重加入は、許されていない。従業員の収入が多い事業所で「雇用保険」に加入する必要がある。また、転職者についても確認をしておこう。転職前の会社で「雇用保険」に加入したままのケースがあるからだ。●加入対象から外れた場合は資格喪失手続きを行う
フルタイムのパート従業員が、週20時間未満の就業条件で働くようになった場合、「雇用保険」の加入対象から外れることになる。このように、「雇用保険」の加入要件を満たさない労働者が出た際には、就業条件変更日の前日に離職したものとして資格喪失手続きを行う必要がある。まとめ
「雇用保険」は、労働者が失業した場合などに一定期間に渡り必要な給付を行い、労働者の生活や雇用の安定を図ると同時に再就職に向けた支援・援助を目的とする制度だ。ただ、それも事業主が適用基準を満たす労働者が、「雇用保険」の被保険者となったことをハローワークに適正に届け出ていることが前提となる。万が一、それが成されていないと労働者失業した場合に、不利益を被ってしまう。そうした事態を避けるためにも、「雇用保険」の加入手続きを確実に行いたいものだ。転職や副業、ダブルワークなどが珍しくなくなってきた時代であるだけに、より慎重かつ丁寧に取り組んでもらいたい。「雇用保険」に関する資料ダウンロード、セミナー、サービス、ニュースなどの最新コンテンツはこちら
よくある質問
●1週間20時間以内で働いても「雇用保険」は適用される?
週20時間未満の労働では雇用保険は適用されない。雇用保険の加入要件の一つに「週の所定労働時間が20時間以上」があり、これを満たさない場合は加入できない。たとえ繁忙期に一時的に週20時間を超えて働いても、契約上の所定労働時間が20時間未満であれば適用対象外となる。●「雇用保険」に入らない条件は?
雇用保険に入らない条件は、①週の所定労働時間が20時間未満、②雇用期間が31日未満。しかも雇い止めが明示されている、③昼間学生、④取締役や監査役等の役員の職に就き、しかも部長や支店長などの役職を兼任していない、⑤雇用期間が4カ月未満かつ所定労働時間が20時間以上30時間未満の季節労働者、⑥日雇労働被保険者の認可を受けていない日雇労働者、⑦船員保険の被保険者、⑧ダブルワークや副業で複数の会社で働いているが、どちらの職場でも加入条件を満たしていない- 1