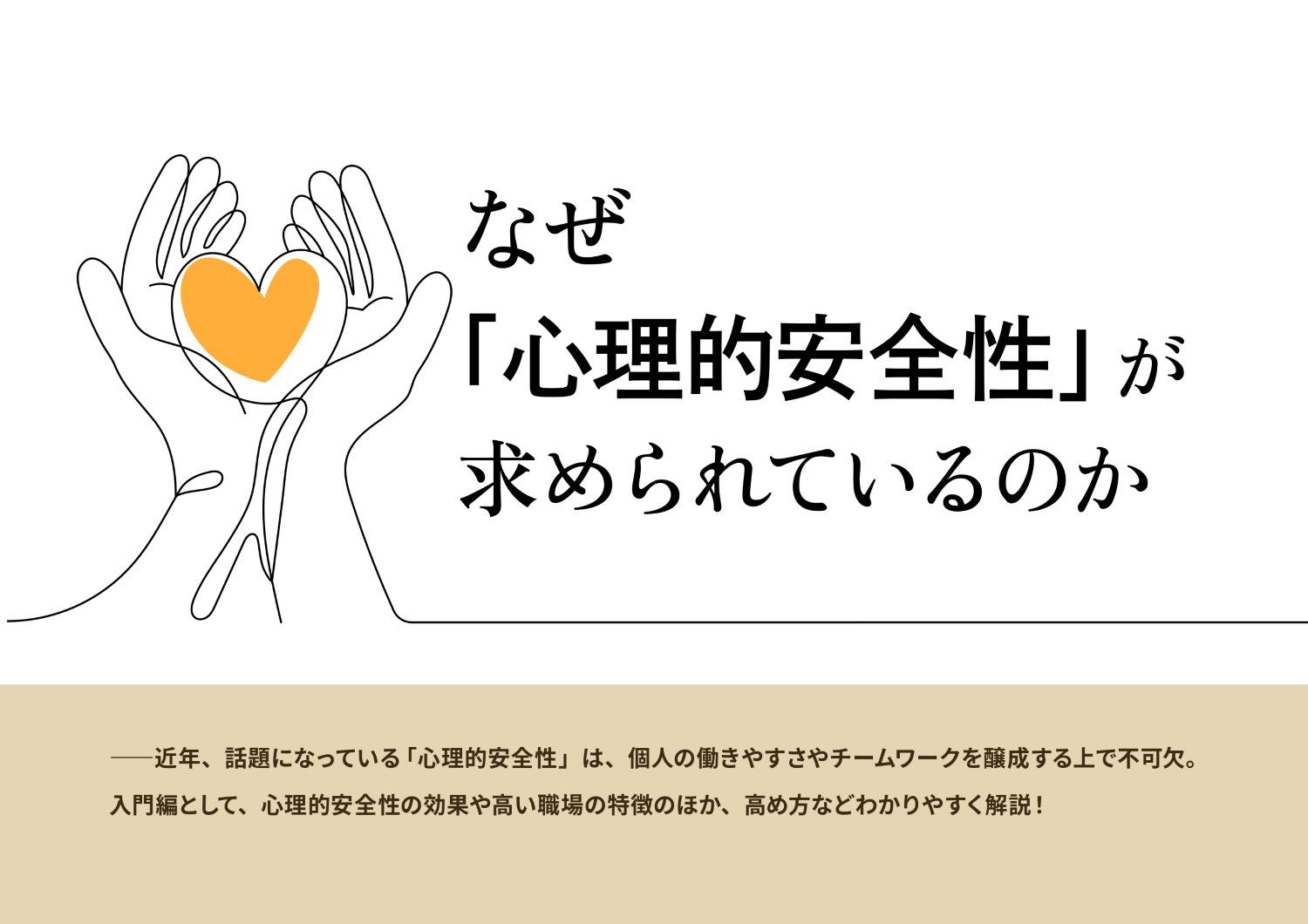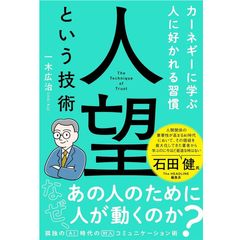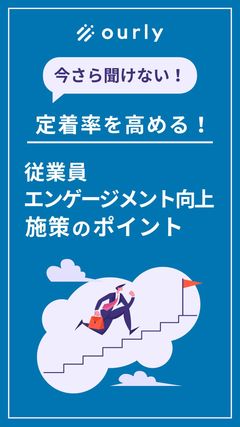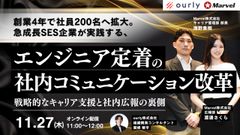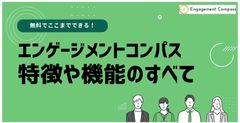■「心理的安全性」に関する資料ダウンロード、セミナー、サービス、ニュースなどの最新コンテンツはこちら

「心理的安全性」とは
「心理的安全性」とは、自分の発言や行動が拒絶されたり処罰されたりすることなく、また無知・無能だと思われることもなく、存在を受け入れてもらえる状態を表す言葉である。もともとは米ハーバード大学のエイミー・C・エドモンドソン教授(組織行動学)が発表・提唱した概念だが、「心理的安全性」が大きく注目され始めたのは、Google社による調査・研究がきっかけだった。「実績を上げているチームは『心理的安全性』が高いという共通点を持つ」ことが明らかとなり、ビジネスの現場における「心理的安全性」の重要性が世界的に知られるようになったのである。
「心理的安全性」とは? ぬるま湯組織との違いや高め方、事例を解説
「心理的安全性」が低い組織で起こる問題
「心理的安全性」が低い組織はさまざまな悪影響を受けてしまう。危機管理の面からも「心理的安全性」を高めることは重要と言えるのだ。主な問題を解説しよう。●従業員が“4つの不安”を抱きながら働くことで、個人もチームも成長できない
「心理的安全性」が低い組織の従業員は“4つの不安”を抱えているというのがエドモンドソン教授の考えだ。こうした不安の中では、周囲の顔色をうかがいながら保身を優先させて働くことになるだろう。(1)無知だと思われるかもしれないという不安
「こんなこともわからないのか」と思われるのではないかという不安が先立ち、上司や先輩に質問できないでいると、疑問を解決しないまま業務を進めざるを得なくなる。その結果、ミスの多発、パフォーマンスの低下につながる。
(2)無能だと思われるかもしれないという不安
仕事のできない人間だと思われたくないという意識から困りごとを相談できず、業務の停滞・遅延を招く。ミスがあった場合に報告できない人が増えると、さらに重大な問題へと発展してしまうリスクが高まる。
(3)周囲の邪魔になっているのではないかという不安
自分の発言が会議を長引かせるのではないか、自分の意見はこれまでの価値観を否定することになるのではないかといった考えが蔓延すると、新しいアイディアや業務改善策が提案されにくくなり、組織力が低下する。
(4)ネガティブな人間だと思われる不安
他者の意見を否定するとネガティブな人間だと思われるかもしれない。そう考えて発言を控える人ばかりになれば、問題点や懸念点の存在が見過ごされるほか、アイディアの多様性が失われてしまう。
こうして誰もが疑問や不安を抱えたまま、“ことなかれ主義”で仕事をすることで、成長の機会が失われる。コミュニケーションは不足し、問題点、新たなアイディア、改善策が共有されず、イノベーションも起こらない。各個人のモチベーションは低下し、離職率にも影響が出るだろう。
●トラブルが起きやすい
相談や質問をできないまま業務にあたると、効率は悪くなる。仕事の遅れやミスを報告することにも躊躇いがちになり、失敗を隠そう、自力でカバーしようという意識が生まれる。結果、問題が大きくなってからようやく発覚し、対応が遅れてしまうことになる。「心理的安全性」が低いと会社の信頼にまで関わる大きなトラブルへと発展するリスクが高まるのだ。「心理的安全性」を高めるメリット
「心理的安全性」を高めることで、以下のような効果やメリットが生まれる。●個人のパフォーマンスと組織の生産性が向上する
安心して仕事に取り組めるようになれば、集中力は増し、やりがいや責任感は高まり、チームや会社に貢献しようと積極的・能動的な発言と行動を見せるようになる。新しいアイディアが次々と生まれ、業務効率化やコストの削減なども進むだろう。●コミュニケーションが活性化する
「心理的安全性」の高い組織では、自然と従業員間のコミュニケーションが増え、業務に役立つ情報や知識、ノウハウ、スキルの共有が進む。ミスが減少し、仕事のクオリティは高くなるはずだ。●従業員エンゲージメントや人材定着率が向上する
安心して発言・行動できるようになれば、このチームに貢献したいという意欲=エンゲージメントが高まる。悩みを率直に相談できることもあって、離職率や休職リスクは低下するはずだ。●多様な人材が集まり、イノベーションが生まれやすい
各個人の多様な価値観が否定されない組織には、自然と多彩な人材が集まる。考え方や得意分野の異なる人々がアイディアを出し合い、知識やスキルを共有することで、生産性の向上がもたらされるだろう。イノベーション創出にもつながるはずだ。●問題を早期に発見しやすい
「心理的安全性」が高い組織では、そもそも業務上のミスは少なくなるが、たとえ失敗してしまった場合でも、それを隠したりひとりで抱え込んだりすることがなくなる。ミスを迅速に報告する姿勢が行き渡ることで、小さな問題が大きなトラブルへと発展する前に対処することが可能となるだろう。「心理的安全性」の作り方・高め方
エドモンドソン教授は「心理的安全性」を高めるために各個人が注意すべきポイントとして以下のような姿勢でいることを提言している。(2)自分のミスを認める
(3)好奇心を形にして積極的に質問する
これらに加え、組織として、あるいはチームリーダーとして以下のような姿勢を徹底することが「心理的安全性」を高めるためには重要といえる。
●多様な価値観を尊重する
チームメンバーそれぞれが得意分野や他人にはない個性、独自の価値観を持っている。それらを全員が認め、尊重することで「自分もまたチームに受け入れてもらえる」という空気が生まれる。反対意見を無視せず、「そういう考え方もある」と受容して検討することが大切である。●気軽に質問や相談ができる環境を作る
活発なコミュニケーションは「心理的安全性」を高める。オンとオフを明確にし、雑談も交えることで話しやすい雰囲気を作りたい。また仕事の進め方などのマニュアルを整備・共有し、それでもわからない点があればすぐに報告・連絡・相談してもらうといった環境を整えておくことも重要だ。自分から積極的に声をかけたり意見を求めたりするなど、普段からコミュニケーションの量を増やすことを心がけたい。●インフォーマルコミュニケーションの促進
仕事以外のさまざまな話題、趣味・嗜好に関する雑談、すなわち「インフォーマルコミュニケーション」を重ねることでも「心理的安全性」は高まる。無理強いは避けつつ、メンバーをランチに誘ったり食事会や飲み会を開いたりなど、会話の“場”を作ることが有効となるだろう。オフィスの一角に休憩スペースなどを作る手もある。●会議では全員に発言の機会を与える
キャリアの浅い人たちは会議で発言するのに勇気を要し、一度でも自分の意見を遮られたり否定されたりすると、以後の発言をますます躊躇するようになる。最初に各自の近況を報告させる、1人に1回は話しかける、最後に一言ずつ感想を述べてもらうなど、発言機会をなるべく均等化する工夫が会議進行役には求められる。●成功体験を積ませる
チームメンバーの意見に対し、そこに含まれる独自性を褒め、他者から寄せられたポジティブなコメントを伝えるようにしたい。複数の選択肢の中から最終的な判断を委ねてトライさせ、その結果として起こったプラスの変化や成果を振り返るのもいい。そうして小さな成功体験を積み重ることが「心理的安全性」を高めることになるだろう。●チャレンジを否定せず歓迎する
新しいアイディアに対してリスクばかり論じて否定することは避け、まずは提案そのものを歓迎しよう。業務改善などにつながるアイディア募集を仕組み化し、どんどん試してみることにも取り組みたい。たとえ新たな試みが失敗に終わったとしても「チームのために実践したこと」だと捉え、責めることなく、次の挑戦へと向かうポジティブな意識と姿勢が必要である。●チーム全体で共通認識と相互理解を深める
積極的な発言や新しいアイディアを求めるためには“目的”が不可欠となる。お客様に満足していただくため、非効率な業務を改善するためなど、チームとしての明確な目的を全員で共有しておくべきだ。メンバー各自のスキルや得意分野といった情報も共有しておけば、誰に何を聞けばいいかが明確となり、目標達成に向けての最適な役割分担も可能となるだろう。●感謝と称賛の風土を醸成する
誰かに何かをしてもらうことを“当然”と考えるのではなく、細かく感謝の気持ちを伝えることが大切だ。自分は頼られていて、同時に尊重もされていると感じることで「心理的安全性」は高まるのである。●評価基準を見直す
自分の発言が人事評価に悪影響を及ぼすのではないかという不安があると「心理的安全性」は高まらない。チーム全体をプラスに向かわせるための意見であればマイナス査定にはならないよう、従業員の評価基準を見直すべきである。どのような発言・行動がどう評価されるのか、基準の開示も必要となるだろう。「心理的安全性」を高めるための具体策
次に「心理的安全性」を高めるための代表的な施策を紹介していく。●1on1ミーティング
上司と部下が1対1で面談する「1on1 ミーティング」を、定期的かつ効果的な頻度で実施したい。上司側には、部下に緊張感やプレッシャーを与えないよう配慮し、仕事に取り組むうえでの悩みや懸念など本音を引き出すことが求められる。適切なフィードバックや言葉がけによって、モチベーションの向上、成長促進、メンタルヘルスのサポートも心がけたい。隠し事なく話せるような信頼関係の構築が最大の目標である。「1on1」の目的やメリットとは? 部下との接し方や企業事例も解説
●OJT(On the Job Training)
経験を積んだ先輩社員が実務を通じて若手や新人を指導する「OJT」では、業務に関する正しい指導や伝達だけにとどまらず、質問・相談をしやすい信頼関係の構築、新人に成功体験を積ませる工夫など「心理的安全性」を高めようとする意識が重要となる。「OJT」とは? 意味や目的と併せて効果的な進め方を解説
●メンター制度
直接の上司や先輩ではなく、年齢や在籍歴、職種の近い人材が“助言役”として新入社員・中途入社社員をサポートするのが「メンター制度」だ。メンターには、キャリアや人間関係の悩みに対してアドバイスし、不安の解消に努め、社内に頼れる味方がいると感じてもらい、「心理的安全性」を高めることが求められる。「メンター」とは? 意味と役割や制度のメリットを解説
●OKR(Objectives and Key Results)の設定
チームに貢献できているという実感が自己肯定感につながり、「心理的安全性」を向上させる。そのために有効なのが「OKR」と呼ばれる手法だ。チームとしての目標(Objective)を示し、それを達成するために各メンバーが果たすべき役割を明確にし、成果指標(Key Result)を設定する。1~3カ月程度の期間で“頑張れば達成できる”くらいの目標を立てることがポイントで、この目標をクリアすることで自分に自信を持てるようになり、チームへの貢献度も実感できるようになるだろう。「OKR」の意味や特徴とは? 企業事例やMBO、KPIとの違いなどを解説
●リーダー研修
入社数年目の若手社員、チームリーダー、リーダー候補には、後輩を指導する役目が期待されている。「1on1ミーティング」、「OJT」、「メンター制度」などに役立つコミュニケーション術、モチベーションの上げ方、メンタルヘルス関連など、指導役とリーダーに必要なスキルと知識を習得するための研修を導入したい。「リーダーシップ研修」とは? そもそもの目的や対象者、内容などを解説
●ピアボーナス制度
チームメンバーへの“感謝”や“称賛”を“報酬”に変えるのが「ピアボーナス制度」だ。手助けしてもらった際やチームへの貢献があったとき、その人にポイントを贈り、与えられたポイントは金品に交換することができるという仕組みである。互いに褒め合う文化が作られ、職場の雰囲気を良好にする効果が期待できる。●ピアラーニング
講師を呼んで教わるのではなく、特定のスキルや知識を持つ従業員がそれぞれ講師となって学び合うのが「ピアラーニング」だ。知識の習得やスキルの向上を果たせるだけでなく、部門や階層を超えて助け合いながら学習を進めることで、新たな交流やコミュニケーション、一体感が生まれて「心理的安全性」も向上することになる。●交流会やイベント
同じ趣味を持つ人たちの同好会や部活動、誰もが参加しやすいイベントの開催などがあれば、部門や階層を超えた交流が生まれる。会社全体で「心理的安全性」は高まるだろう。ただし参加の強制は避けるべきである。●エンゲージメントサーベイの実施
会社やチームの「心理的安全性」を見極める指標の1つが「従業員エンゲージメント」だ。組織への帰属意識が強ければ、「心理的安全性」を感じながら楽しんで働けているものと推察できる。逆にエンゲージメントスコアが低ければ、「心理的安全性」も低く、何らかの対策を取らなければならないと判断できるだろう。「エンゲージメントサーベイ」とは? メリットや導入の流れを解説
「心理的安全性」を作る際の注意点
「心理的安全性」を作る・高める上で、いくつかの注意点がある。主な5つを紹介していく。●馴れ合いにならない
「心理的安全性」がある組織は、単なる仲良しグループではない。リラックスしすぎて馴れ合いの関係になると、かえって建設的な意見やフィードバックが言いにくくなり、組織としての成長が停滞してしまう。あくまで目的は、率直な意見交換や本音を言い合える環境づくりだ。メンバー同士が適切な距離感を保ち、共通の目標に向かって意見し合える関係を作ることが大切だ。●仕事の手を抜かない
「心理的安全性」が高い職場では、失敗を恐れず挑戦できる反面、「多少手を抜いても許される」と誤解されることがある。そうなると、責任感が薄れ、業務の質が低下しかねない。安全な環境づくりと同時に、目標や役割を明確にし、メンバー全員が自分の責任を自覚しながら仕事に取り組む姿勢を維持することが不可欠となる。●一人ひとりに気を配る
全員が安心して意見を言える環境を作るには、個々の状況や性格に配慮したコミュニケーションが求められる。例えば、1on1ミーティングを活用し、メンバーごとの課題や考えを把握することで、適切なサポートやフィードバックが可能となる。上述したように、会議では発言の機会が偏らないよう工夫し、全員の声を尊重する姿勢が信頼関係の構築につながる。●叱れない上司を増やさない
「心理的安全性」を重視するあまり、上司が部下を叱ることを避けてしまうと、組織に必要な緊張感や成長機会が失われてしまう。重要なのは、人格を否定するのではなく、行動や成果について建設的に指摘し、改善を促すことである。そのため、適切なフィードバックで、メンバーが安心して挑戦し続けられる環境を整えることが大切だ。●完璧を求めない
過度な完璧主義は、ミスを恐れて挑戦を避ける風土を生み、むしろ「心理的安全性」を損ないかねない。失敗を学びの機会と捉え、改善や成長につなげる姿勢が重要で、小さな進歩や挑戦を称賛し、完璧よりも「より良くする」ことに価値を置くようにしたい。そうすることで、メンバーが安心して意見やアイディアを出しやすい職場になるだろう。「心理的安全性」の測定方法
エドモンドソン教授は、会社やチームの「心理的安全性」を把握する手法として以下の2つを提唱している。●7つの質問
(2)メンバーどうしで課題や問題点を指摘しあえる
(3)自分とは違う考え方や異質なものを拒絶し、受け入れないことがある
(4)チームに対してリスクとなりうる行動をしても安全である
(5)メンバーに助けを求めにくい
(6)自分を騙したり貶めたりするメンバーはいない
(7)業務を進めるにあたって、自分のスキルや才能が尊重され発揮できている
チームメンバーには、これらに対して「強くそう思う」、「そう思う」、「どちらともいえない」、「あまりそう思わない」、「そう思わない」の5択で回答してもらうことになる。ネガティブな状況と言える(1)、(3)、(5)に対して「あまりそう思わない」や「そう思わない」と答えられるようであれば「心理的安全性」は高いと考えられる。またポジティブな状況である(2)、(4)、(6)、(7)に「強くそう思う」、「そう思う」と回答できるのも「心理的安全性」が高い証拠だ。
●3つのサイン
(2)ミスについても話す機会が多い
(3)職場に笑いやユーモアがあふれている
チームリーダーには、こうした傾向が業務中に現れているかどうか日常的にチェックすることが求められる。3つとも見られないようであれば、当然、改善策が必要だ。
「心理的安全性」向上の企業事例
実際に「心理的安全性」向上に取り組み、成果を上げた企業の事例を紹介しよう。●富士通
富士通は2021年に「Employee Success本部」を設立し、「心理的安全性」の向上を経営の柱に据えた。全社横断でプロジェクトを立ち上げ、社員の声や専門家の知見をもとに独自の心理的安全性モデルを策定し、「心理的安全性Playbook」として社内外に公開。さらに、2,230名が参加した心理的安全性向上プログラムを展開すると、参加者の95%が「有意義」と回答したという。こうした取り組みにより、エンゲージメントサーベイの心理的安全性スコアが大幅に上昇し、現場では率直な意見交換や相互支援といった行動変化も見られている。●メルカリ
メルカリは2017年から従業員同士で感謝や賞賛を送り合うピアボーナス制度「mertip(メルチップ)」を導入している。この制度によって、社員同士がリアルタイムで感謝の気持ちを伝え合う文化が根付き、部署や拠点を超えた連携や信頼関係が強くなり、社員が自分の貢献が認められていると実感しやすくなり、心理的安全性の醸成が進んだ。また、ピアボーナス制度をきっかけに、エンゲージメント向上や活発なコミュニケーションにもつながっているという。まとめ~「楽しい職場」を作ることが組織を強くする
「心理的安全性」の高い職場では安心して仕事に打ち込むことが可能で、各メンバーは存分に能力を発揮してくれるだろう。ここで勘違いしてはならないのが「楽しい職場」と「楽な職場」はまったく異なるということだ。失敗してもまったく怒られず妥協や馴れ合いが当たり前になっている「楽な職場」では、多くの者が手を抜こうとしてしまう。報告や相談が適切におこなわれず、業務改善・生産性向上のためのアイディアや行動が見られることもないだろう。一方、仕事に対するやりがいに満ちた「楽しい職場」では、問題があれば叱られるもののフォローも得られ、感謝や称賛を贈られることも多い。的確な指示、豊かなコミュニケーション、助け合いと学び合いに満ち、個性やチャレンジが尊重される。そうして誰もが同じ目的・目標を共有して成果を出そうと努力し、モチベーションやエンゲージメントは高いレベルで維持され、個人と組織は成長していくことになる。
そんな職場、チーム、組織を作るために、リーダーは心を砕き、企業は有効な人事制度を整備するべきなのである。
「心理的安全性」に関する資料ダウンロード、セミナー、サービス、ニュースなどの最新コンテンツはこちら
よくある質問
●「心理的安全性」を作るためにはどうすればいい?
心理的安全性を高めるには、メンバー同士の信頼関係を築くことが重要となる。そのため、多様な価値観を受け入れ、率直に意見交換ができ、サポートし合える環境を作ることから始めたい。また、全員が平等に発言できる場を設け、ミスや異なる意見も肯定的に受け止める姿勢が大切となる。リーダーは1on1ミーティングなどを行ってサポート型のマネジメントを意識し、個々の強みや貢献を認めることで、安心して挑戦できる風土が作れる。- 1