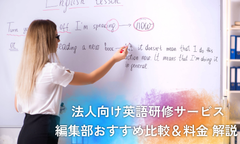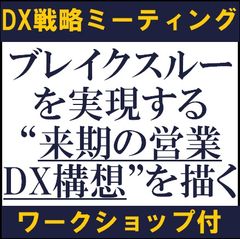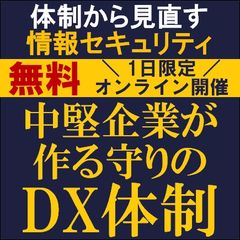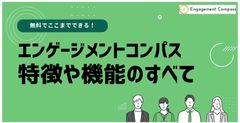そもそも「リーダー」とは
「リーダー」とは、指導者や統率者、先導者という意味を持ち、チームの目標達成や課題解決に向けてメンバーを束ねていく人を指す。具体的には、何かアクションを起こすにあたり計画を立て、メンバーの能力を見極め適切な指示をし、業務や使命を遂行していく役割を果たす。優れた「リーダー」はリーダーシップを持ち合わせており、企業経営のかじ取りをする経営陣には必要なスキルとなる。「リーダー」は限られた人しかなれないということはない。先天的な資質も一部にはあるが、後天的に身に付けることが可能だからだ。それだけに、多くの企業では若手社員や中堅社員などにリーダーシップ研修を実施し、「リーダー」へと育てていこうとしている。
●マネージャーとの違い
「リーダー」とマネージャーでは、組織内での役割が大きく異なってくる。「リーダー」は、何らかの目的・目標に向かってチームを率いて新たな価値を創出する役割を担う。一方、マネージャーは管理者として、チームや組織が社内の価値観やルールに則って業務が円滑に進むよう管理する役割を担っている。「リーダー」の役割とは
次に、「リーダー」はどのような役割を果たす必要があるのかを説明しよう。●計画する
まずは、自らが率いるチームの目的・目標を明確化することだ。KPIの設定などがこれにあたる。その上で、KPIを達成するための具体的な計画を立案していく。いつまでに、どのような方法で何を成し遂げるかや、チームとしてどうフォローするかなどといった点をまとめ上げる必要がある。●組織化する
計画が立案できたところで、チームのメンバーに仕事を割り振っていくのも「リーダー」の役割だ。目標を達成するために的確な指示や命令をメンバーに出すとともに、仕事がよりスムーズに進むようマニュアルを用意するケースもあり得る。●指揮する
メンバーに指示したとしても、本人がモチベーションを持てなかったり、実行できるスキルがなかったりすれば業務は進まない。そのため「リーダー」としては、モチベーションを引き出すような目標管理制度を導入したり、OJTなど教育制度を充実させたりといった取り組みをするだけでなく、メンバーが自らの能力を発揮できるよう、鼓舞し指揮していく必要がある。●統制する
メンバーに仕事を任せきりというわけにもいかない。一定期間が経た後、計画通りに進んでいるか、目標達成度合いを確認する必要がある。もし、上手く進んでいない業務があるなら、計画を軌道修正するなど見直しをしなければいけない。評価にあたっては、メンバーのモチベーションに影響がないよう、数値だけに着目するのではなく、質的な部分や外部要因なども含めて検討するようにしたい。●目標達成とチームの生産性向上
チームとしての目標達成と生産性向上も「リーダー」に課せられた大きな役割となる。目標達成に向け不可欠となる業務を細分化し、それらを遂行するために最適なスケジュールを構築し、効率的に仕事が進むよう気を配っていかなければいけない。また、生産性を向上させるためには、方向性やビジョンを明確に打ち出し、メンバーと共有することも重要だ。●チームの団結力向上
自らのスタイルでメンバーとの良好な人間関係を構築し、チームの団結力を高めていくことも、「リーダー」の重要な役割となる。スタイルは、これでなければならないというものはなく、「リーダー」によって変わるだろう。メンバーと頻繁にコミュニケーションを図り、自身の思考を共有するタイプもいれば、メンバーに適度な緊張感を与えながらストイックに仕事をこなすタイプもいる。●育成
メンバーの特性や強みを把握し、それぞれの成長度合いにあわせて育成できる能力も「リーダー」には必要だ。部下の長所を伸ばしていくために、適切な課題を設定していく必要がある。●モチベーション向上
チーム内において、いつも仕事に対するモチベーションが高いということは決してない。時には、下がってしまう場合もあるはずだ。そうしたケースでは、「リーダー」が自ら音頭を取ってチームのモチベーションを高め、メンバーにやる気を出してもらう必要がある。リーダーに向いている人の特徴
「リーダー」に向いている人には共通点が見られる。いくつか紹介したい。●目標達成に対して真摯
「リーダー」に最も求められるのは、目標達成に対して真摯であるかどうかだ。何が正しいのかを自分なりに考え、ブレずに行動していく姿勢を持っていれば、メンバーはついてきてくれるものだ。●意思の軸がブレない
意思の軸がブレないことも、「リーダー」に見られる共通点である。周囲の発言に影響されてばかりでは、目標を最短距離で達成することができない。そればかりか、頼りなく見えてしまい、チーム内の士気や「リーダー」に対する信頼も低下することになるだろう。●人の弱みよりも強みを見るのが上手い
人の特性や強みをいち早く見抜けるのも、「リーダー」としての適性と言える。目標を達成するためには、人の弱みにフォーカスするよりも強みを活かす方が効果的であるからだ。その方が、メンバーとしてもモチベーションが上がりやすく、自ずと生産性が向上する。●行動力がある
目標達成に向けて、先導を切って行動できる人は「リーダー」に向いている。メンバーにただ単に指示を出すだけでは誰もついてこない。自らが範を見せることが重要になってくる。●視野が広い
「リーダー」は複数のメンバーを統率する立場なので、広い視野を持っていなければいけない。メンバー一人ひとりの業務進捗や、モチベーションを把握しながら、チーム全体のパフォーマンスを上げていく必要がある。育成の参考となる「リーダー」に求められるスキル
ここでは、「リーダー」に求められるスキルとは、どのようなものなのかを具体的に見ていこう。●状況認識
まず、「リーダー」には、広い視野で物事を把握する状況認識力が欠かせない。「リーダー」が、自らの仕事や内部の些末な仕事にばかり固執していては、チームの仕事を円滑に進めることができないからだ。あくまでも、「リーダー」はチーム全体に目を向けるとともに、外部の変化にも迅速に対応できるようにしておかなければいけない。●人間関係構築
「リーダー」は、チーム全体のパフォーマンスを最大化させていかなければいけない。メンバー一人ひとりの力は限られているので、組織として業務を遂行していく必要があるからだ。そのためにも、日頃からメンバーとの良好な人間関係を構築・維持する能力が求められる。また、メンバーがお互いに協力・連携しやすいよう、チームの雰囲気づくりにも配慮しなければいけない。●コミュニケーション
「リーダー」として目的・目標を達成していくには、メンバーとの円滑な意思疎通を行えるコミュニケーションスキルも欠かせない。「リーダー」が思い描いているプランを実行するのは、あくまでもメンバーだからである。「相手の意図を考慮したやりとりができる」、「相手の気持ちを配慮しながら自分の要望を伝えられるといったスキルが必要となってくる。●心理的安全性
メンバーに不安や羞恥心を感じさせることなく、いつも通りの自分でいられるような環境や雰囲気を作りあげていくといった心理的安全性の確保も求められる。メンバーがリラックスしている状態で仕事に臨めるので、チーム全体の効率が自ずと高まるだろう。●セルフマネジメント
自らを管理しながら、自己を育てていくスキルを意味する。目標の達成を目指す過程においては、自分自身を客観的、かつ俯瞰的に見ることも求められる。●コーチング、ティーチング
コーチングは、教わる側がコーチとの双方向のコミュニケーションを通じて、自らの価値観や能力を再認識していく手法だ。何事にも意欲的な人に対して効果を発揮し、潜在能力や可能性を引き出すことができる。一方、ティーチングとは教える側が答えを提示し、教わる側がそれを受け止めて学んでいく手法のこと。ベーシックなスキルや技術を学ぶ場合には有効とされている。●課題解決
目標達成に向けた計画をいざ実行するとなったものの、当初の思惑通りに進まず、目標達成が難しくなってしまう。こうしたケースは、良くあるものだ。そこで必要となってくるのが、課題を特定し解決策を提示していくスキルである。これも、「リーダー」には必須のスキルだ。「リーダー」を理解するためにタイプや種類を整理
実は、「リーダー」と言ってもさまざまなタイプや種類がある。それらを整理しておこう。●権威主義
自分の思惑通りにメンバーを動かしていくタイプの「リーダー」を指す。「リーダー」が何もかも意思決定をしてしまい、メンバーは言われるがままに行動するだけになりがちだ。このタイプは、昭和の高度成長期には多くの企業で見られた。それで、結果も伴っていたという時代背景もある。だが、価値観が多様化した現代では、メンバーから不満や反感を持たれてしまう可能性が高く、注意する必要がある。●民主的
何を決めるにしても、メンバーと大枠の方向性についてじっくり話し合い、合意のもとで計画を立案し進めていくタイプの「リーダー」を言う。メンバーからすると、意思決定のプロセスに参加できるので納得感が得られやすい上に、裁量も委ねてもらえるので、高い満足度を持って業務にあたることができる。メンバーの自発的を引き出せるため、成長性・生産性の高いチームを作り上げていける「リーダー」であると言って良い。●自由放任
メンバーを放任する特徴を持つ。仕事の方針や意思決定などをメンバーの裁量に任ねるので、スキルの高い人材から成るチームでは、確かな成果を生み出す可能性がある。その一方、個人の裁量が大きくなるだけに組織としてのまとまりに欠け、チームの士気が低下しがちな傾向も見られる。●SL理論
SL(Situational Leadership)理論とは、メンバーのレベルに応じて「リーダー」の言動を変えていくスタイルだ。状況対応型リーダーシップとも呼ばれている。「リーダー」の行動を指示的行動と援助的行動に分類し、それぞれの高低を使い分けて対応しており、以下の4つの型が想定される。1:指示型(指示的行動:高い、援助的行動:低い)
2:コーチ型(指示的行動:高い、援助的行動:高い)
3:援助型(指示的行動:低い、援助的行動:高い)
4:委任型(指示的行動:低い、援助的行動:低い)
●クルト・レヴィンの3つのリーダーシップ類型
米国人心理学者のクルト・レヴィンは、リーダーシップを3つの類型に分類している。まず、一つ目が専制的リーダーシップだ。これは目標設定から人員の配置、工数管理までを「リーダー」が自ら取りまとめていく形のリーダーシップである。メンバーの能力が低い場合や緊急性の高い事案で大きな成果を発揮しやすいスタイルとされている。二つ目が自由放任的リーダーシップだ。これは、工数やスケジュールの管理などをメンバーに委任するタイプのリーダーシップである。メンバーは自由に動け、それぞれの能力が発揮しやすいため、メンバーの専門性や能力が高い場合に大きな成果が期待できると言って良い。
三つ目が民主的リーダーシップだ。これは、専制的リーダーシップと自由放任的リーダーシップの中間に位置づけられるスタイルといえる。最終的には「リーダー」が決定するものの、メンバーの意見に耳を傾けながら、目標設定やスケジュールなどを決めていくのが特徴だ。
●PM理論
PM理論は、日本の社会学者である三隅二不二(みすみじゅうじ)氏が提唱したリーダーシップ論である。成果につながる目標達成機能(Performance)とチームワークに関わる集団維持機能(Maintenance)をそれぞれPとMで表し、「PM」、「Pm」、「pM」、「pm」の4つのパターンでリーダーの行動理論を表していく。理想形とされるのがPMで、組織の業務遂行能力とメンバーとの人間関係を両立できている「リーダー」を指す。逆に、最も避けるべき状態は「pm」である。成果を上げる力、集団をまとめる力のどちらも備わっていないため、早急に改善する必要がある。●コンセプト理論
コンセプト理論は、「リーダー」自身と「リーダー」をとりまく環境に重点を置いたリーダーシップ論だ。リーダーシップを大きく分けて以下の5つの型に分類している。・カリスマ型リーダーシップ
「リーダー」の傑出した行動力と発想で組織を引っ張っていくリーダーシップである。目標達成に向けたリスクを「リーダー」がすべて担い、メンバーそれぞれに合った仕事を分配していくことで成果を導いていく。
・変革型リーダーシップ
組織やチームの方針を根本から見直し、改革の推進を働きかけるリーダーシップである。組織やチームの業績が厳しい局面で効果を発揮しやすいスタイルとされている。
・EQ型リーダーシップ
職場環境や人間関係、部下のモチベーションに配慮しながら、成果の創出を図っていくリーダーシップである。チームワークの良さに重きを置く場合に効果を発揮しやすいと言える。
・ファシリテーション型リーダーシップ
「リーダー」が中立的な立場から、メンバーの意見を吸い上げて行くリーダーシップである。メンバー中心でチームを動かしたい場合に有効なスタイルとされている。
・サーバント型リーダーシップ
「リーダー」がメンバーのサポーターとなり、各自の能力を最大限に引き出していくリーダーシップである。ただし、最終的な意思決定権は「リーダー」が持つ。メンバーが高い能力を持っている場合に効果を発揮しやすいスタイルと言える。
代表的な「リーダー」育成方法
「リーダー」を育成する方法はさまざまある。代表的なものを紹介していきたい。●リーダーシップ研修の実施
リーダーシップ研修では、マネジメントスキルやコミュニケーション能力のスキルアップだけでなく、「リーダー」としての考え方や発想力、話し方など、多岐に渡るテーマについて習得を目指せる。また、グループワークで他部署や他部門のリーダー候補と交流することで、視野を広げ、組織全体を見渡す力を養うこともできる。●現場での指導・実践(OJT)
実際の業務を通じた学びは最も効果的な「リーダー」育成方法と言える。段階的に責任のある業務を任せ、上司がその理解度や成熟度に対してフィードバックを行うことで、実践的なリーダーシップスキルを身につけられる。失敗も学びの機会として捉え、PDCAサイクルを進めていくことが重要だ。●1on1の実施
定期的に1on1ミーティングを実施することで、業務上の課題や悩みの共有と、具体的な解決策を見出すことができるが、それだけでなく、「リーダー」として期待していることやリーダーとしての心構えを養わせることができる。信頼関係を構築しながら、キャリアプランの設計や個人の成長目標について話し合うことで、モチベーション向上にもつながる。●eラーニング
時間や場所を選ばず、自分のペースで学習できるeラーニングは、マネジメント理論やリーダーシップの基本などを習得してもらうのに効果的だ。忙しく、まとまった時間を取れない新任リーダーでも、スキルアップを図りやすい。「リーダー」育成における課題
「リーダー」を育成するにあたって、いくつかの課題が生じる恐れがある。是非とも知っておいていただきたい。●育成難易度が高い
「リーダー」に求められる能力は多岐に渡り、短期間での育成は困難だ。また、どんなリーダー像を目指すのかも個人によって異なるうえ、業務知識だけでなく、人間関係の構築や問題解決能力など、経験を通じて培われるスキルが必要となる。そのため、画一的な教育ではなく、個性を生かした育成計画が求められる。●現場の負担が大きい
育成担当者は通常業務に加えて指導時間を確保する必要があり、どうしても負担が増大してしまう。また、リーダー候補者も新しい役割に適応しながら既存の業務をこなさなければならず、双方にストレスがかかりやすい状況になってしまう。もっとも、長期的な企業の成長を見据えれば、未来のリーダー育成は避けられない。そのため、目先の利益だけを求めず、経営層が人材育成の重要性を周知させて、バランスをもって取り組んでいきたい。●教育体制が整っていない
社内の教育体制が整っていないと、場当たり的な教育・指導になりがちだ。育成担当者によって指導内容にばらつきが生じ、統一された基準での評価が難しい状況にもなってしまう。リーダーシップ研修や1on1といった育成方法を整備する必要がある。●リーダー志向を持つ人材の減少
近年は、責任の重さやワークライフバランスへの懸念から、リーダー職を敬遠する傾向が見られる。キャリアパスの選択肢が多様化する中で、リーダー育成の対象となる人材の確保は大きな課題だ。企業として、リーダーになることのメリットを周知していきたい。●育成の効果が見えづらい
リーダーシップ能力の向上は数値化が難しく、費用対効果の測定が見えにくい。また、長期的な視点での評価が必要となるため、育成プログラムの改善点を見出しにくい。リーダー候補者と育成担当者の定期的な1on1などで、進捗度合いを確認しあう必要がある。「リーダー」育成のポイント
リーダー育成を成功させるには、組織的な取り組みと明確な方針が重要となる。ここでは、主な5つのポイントを解説する。●「リーダー」の役割を明確化する
組織が求めるリーダー像を具体的に定義し、必要なスキルや行動指針を明確にすることが先決だ。これにより、育成目標が明確になり、より細かな教育プログラムの設計がしやすくなる。●リーダー人材の選抜基準を作る
公平で透明性の高い選抜基準を設定することで、社員のモチベーション向上につながる。その際、能力や実績だけでなく、人間性や将来性も含めた総合的な評価基準を設けることをお勧めしたい。●企業全体で取り組む
経営層から現場まで、組織全体でリーダー育成の重要性を認識し、支援する体制を整えることも非常に大切だ。部門を越えた交流や、全社的な育成プログラムの実施によって、幅広い視野を持つリーダーを育成できる。●中長期的な計画を立てる
リーダー育成は短期間では成果が出にくいため、中長期的な計画が必要となってくる。育成方針に合わせて段階的な目標を設定し、定期的に進捗を確認することで、リーダー候補者に着実な成長を促すことができる。●幅広い業務や役割を任せる
リーダー育成は座学だけでは成功しない。プロジェクトリーダーや部門横断的な役割を任せて、様々な業務を経験させることで、幅広い視野を身につけたり、ビジネスセンスを磨いたり、また、より実践的な問題解決能力やマネジメントスキルを向上させたりすることができる。まとめ
先行き不透明な時代のなかで生き残っていくには、強い信念を持って組織やチームを導いていく「リーダー」の存在が不可欠となってくる。リーダーの育成は簡単ではない。そもそも「リーダー」にはさまざまな資質が問われ、育成に着手したからといって、例えば研修ですぐに成果がでるわけではない。優れた「リーダー」と呼ばれるようになるには、日頃から励行すべき行動がいくつもある。その積み重ねがあってこそなので、人事担当者としては長期的なスタンスで候補となりえる人材をサポートしていく必要があるだろう。●組織活性化につながる「サーバントリーダーシップ」とは何か? 事例やデメリットを解説
よくある質問
●「リーダー」に相応しい人の特徴は?
「リーダー」に向いている人には、以下のような共通点がある。
・目標達成に対して真摯
・意思の軸がブレない
・人の弱みよりも強みを見るのが上手い
・行動力がある
・視野が広い
- 1