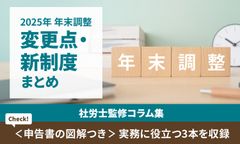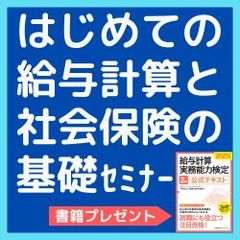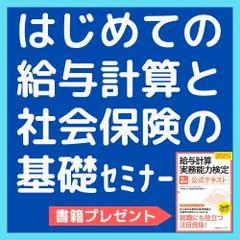■HRプロでは「雇用契約書」に関するコンテンツを多数掲載中
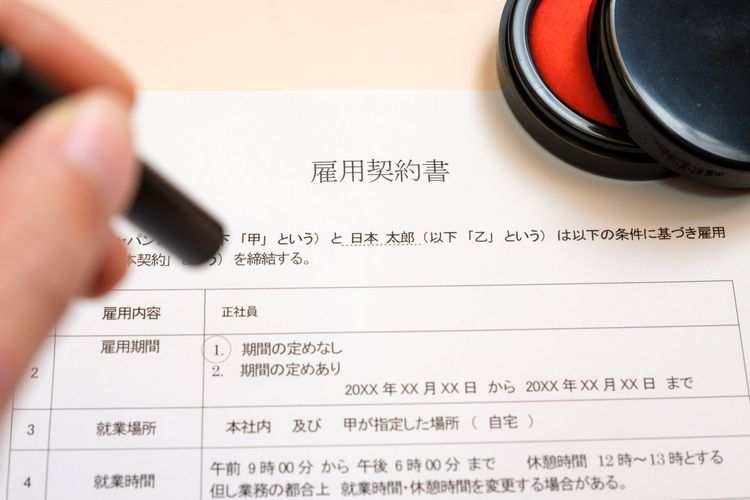
「雇用契約書」とは
「雇用契約書」とは、労働契約の内容を明確にするため、雇用主である会社・企業と雇用される側である労働者・従業員の間で取り交わす契約書である。給与・賃金・昇給、就業する場所と時間、業務内容、退職といった労働条件に関わる重要事項を取り決めて書面化したもので、企業側と労働者側の双方が署名捺印(記名押印)して締結することになる。従業員すべての労働条件を包括的に規定するものが就業規則だとすれば、「雇用契約書」は個々の従業員の労働条件について労使双方で確認・合意するものと言える。
●「雇用契約書」がないとどうなる? 法的な位置づけと役割
「雇用契約書」は法律で作成が義務づけられているものではないが、労働契約法第4条では「使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにする」、「労働者及び使用者は、労働契約の内容について、できる限り書面により確認する」と定められている。“作成が推奨されている”ものといったところである。
「雇用契約書」の記載内容が労働基準法に違反している場合、あるいは就業規則で定められた労働条件を下回っている場合、その内容は無効となる。また「雇用契約書」で取り決めた労働条件が事実と異なる場合、従業員は労働契約を即時解除することができる。
●「雇用契約書」は作成すべきか?
「雇用契約書」の作成は法律上の義務ではない。しかし、残業の可能性、変則的な休日、転勤や異動の有無、試用期間など、労働条件が複雑であればあるほど、労使双方の認識のズレを防止し、トラブルを回避するためにも作成することが望ましい。また「雇用契約書」を作成しないことで労働者・従業員が会社に対して不安・不審・不満を感じてしまうことも考えられるため、その点でも作成・締結することがベターだろう。さまざまなルールを労使双方が確認し、ともに遵守することで労働者の保護と労働関係の安定を図り、トラブルを防止する。それが「雇用契約書」の役割なのである。
「雇用契約書」と「労働条件通知書」の違いとは
「雇用契約書」と混同されがちなのが「労働条件通知書」だ。「労働条件通知書」は雇用主である会社・企業から雇用される側である労働者・従業員に対して“通知する義務のある事項”を記したもので、労働基準法によって作成と交付が義務づけられている。この点が「雇用契約書」との大きな違いだ。企業から(一方的に)交付されるのが「労働条件通知書」、企業と従業員の双方がたがいに労働条件を理解・共有・合意するための書類が「雇用契約書」と捉えればいいだろう。
●「労働条件通知書」は法律上の作成義務あり
前述の通り「労働条件通知書」は、作成および労働者に対する書面交付が労働基準法によって義務づけられている。「労働条件通知書」には賃金や労働時間といった労働条件を明示しなければならず、これら必要な事項を書面で交付しないと30万円以下の罰金が科されることが定められている。また「労働条件通知書」は交付日から3年間保管することも求められている。●署名捺印の有無
「労働条件通知書」は会社から労働者に対する“通知”であり、会社が一方的に作成して労働者に交付するものだ。一方で「雇用契約書」は、その名の通り“契約”で、会社と労働者の双方が労働条件に合意した証といえる。そのため会社側・労働者側、双方が署名捺印(または記名押印)して締結することになる。●「労働条件通知書」は記載するべき事項が決まっている
「雇用契約書」に記載する事項については法令上の規定がないのに対し、「労働条件通知書」は、労働基準法によって記載すべき事項(後述)が定められている点に注意が必要だ。●「雇用契約書」と「労働条件通知書」を同時に発行することも可能
「雇用契約書」と「労働条件通知書」の内容はかなり重複しているため、2つの文書をまとめた「労働条件通知書 兼 雇用契約書」が作成されるケースも多い。「『労働条件通知書』で通知すべき事項を盛り込んだ『雇用契約書』を作成し、会社側・労働者側の双方が合意して書面を取り交わす(契約を締結する)」ことで、通知と契約を一度に済ませてしまうわけである。「雇用契約書」と「労働条件通知書」の違いとは? 作成時に押さえておくべきポイントを整理
「雇用契約書」に記載すべき事項
「労働条件通知書」や「労働条件通知書 兼 雇用契約書」には、労働基準法で定められた事項を記載しなければならない。これらの事項は、必ず明示・記載して書面での交付が必須となる「絶対的記載事項」と、会社に該当する制度や規定があれば明示すべき(口頭での明示も可)「相対的明示事項」に分けられている。●絶対的明示事項
労働基準法施行規則第5条第1項では、以下の事項を明示することが規定されている。・就業する場所
・従事する業務の内容
・始業および終業時刻
・所定労働時間を超える労働の有無
・休憩時間、休日、休暇
・労働者を2組以上に分けて就業させる場合のルール
・賃金の決定、計算・支払いの方法、締切日と支払日、昇給
・退職、解雇
これらに加えて有期雇用の労働者に対しては、以下も明示する必要がある。
・無期転換の申込機会
・無期転換後の労働条件
またパート、アルバイトなどの短時間労働者に対しては以下も明示する必要がある。
・賞与の有無
・退職手当の有無
・雇用管理についての相談窓口の担当部署名・担当者名など
●相対的明示事項
会社が該当する制度などを設けている場合に記載しなければならない「相対的明示事項」は以下の通りである。・退職手当の決定、計算および支払いの方法、支払い時期
・臨時に支払われる賃金、賞与など
・最低賃金額
・労働者に負担させる食費や作業用品など
・安全および衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償・業務外の傷病扶助
・表彰、制裁
・休職に関する事項
●その他、記載した方がいい項目
「労働条件通知書」に記載することが定められた事項以外にも、円滑な合意やトラブル防止などの観点から、就業規則の中で特に重要と思われる項目については記載しておくことが望ましい。減給などの罰則規定、会社都合による休業に関する規定など、従業員が知りたいであろう項目を網羅することが、安心して働いてもらうための配慮と言える。●「雇用契約書」や「労働条件通知書」を締結・交付するタイミング
「雇用契約書」は締結するタイミングについても法的な定めはないが、内定日や入社手続き時などに締結することが多い。一方「労働条件通知書」は労働契約の締結に際して交付することが義務づけられている。「内定=労働契約の成立」と解された判例があるため、内定の段階で「労働条件通知書」を交付すると同時に「雇用契約書」を提示し、内容を確認してもらったうえで契約を締結するのがベストだろう。法令遵守に加えて事務作業の煩雑さ解消も考えると、「労働条件通知書 兼 雇用契約書」を作成・交付することが望ましい。「雇用契約書」作成にあたってのポイント
実際に「雇用契約書」を作成する上でのポイントを解説していこう。●雇用形態別に見た「雇用契約書」作成のポイント
「労働条件通知書」や「労働条件通知書 兼 雇用契約書」の作成においては、「記載が必要な項目を網羅する」ことが何より大切だ。その際、正社員、有期雇用の契約社員、短時間労働者であるパートやアルバイトなど、雇用形態の違いによって記載すべき内容が異なる(正社員以外の労働契約の方が記載事項は多くなる)ことに注意したい。正社員の場合
入社から定年までフルタイムで雇用継続となる正社員の場合、その旨を記した労働契約を締結することになるほか、正社員ならではの事情・事案に即した記載にも配慮しなければならない。具体的には「転勤や人事異動がありうる」、「従事する業務の内容が変更される可能性もある」といった点の記載・明示が必須だ。またリモートワークや副業など多様な働き方が浸透しつつあることを踏まえ、労働条件に関するあらゆる可能性を考慮した内容となっているかどうか、徹底精査すべきであると言える。
契約社員の場合
有期雇用契約の従業員=契約社員の場合、契約期間満了日、更新の有無、更新の判断などが「絶対的明示事項」となる。なるべく詳細に記載するようにしたい。特に更新の有無、契約更新の条件などは詳しく記載すべきである。また契約更新に際しては新たに「雇用契約書」を作成しなければならない。「自動更新」にしていると「期間の定めのない契約」とみなされることもあり、契約解除の煩雑さが増すため注意が必要である。
パートやアルバイトの場合
短時間労働者であるパートやアルバイトに対しても「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」の記載が義務づけられている。契約社員と同様、特に契約期間、契約更新の有無、更新の条件については詳細に明示するようにしたい。また労働基準法に加えてパートタイム労働法によっても、昇給、退職金、賞与の有無の明示が義務づけられているため、これらの抜けや漏れがないよう注意すべきである。
●労働時間制の検討・明示について
近年は、いわゆる「9時~5時」だけでなく、さまざまな労働時間制度の適用・導入が進んでいる。・専門業務型裁量労働制
・管理監督者制度
・事業場外のみなし労働時間制
・特例措置対象事業場制度
・変形労働時間制
・フレックスタイム制
これら特殊な労働時間制を適用して雇用する際には、その旨を明示しておく必要がある。
●試用期間の明記について
正社員として本採用する前に“試用期間”を設けている企業もある。この試用期間についても、期間、試用期間中の賃金、正式採用しない可能性などを記載すべきである。特に試用期間中と本採用時の雇用条件や待遇が異なる場合には、トラブル防止のためにも詳細に明示しておきたい。「就業規則での規定より長い試用期間は無効」、「長すぎる試用期間も無効」となるため、注意が必要である。「雇用契約書」作成時の注意点
「雇用契約書」の作成においては、留意しておきたいポイントがいくつかある。●記載に不備・漏れ・不明瞭な点があるとトラブルのもと
たとえば就業規則で「転勤・人事異動の可能性があり、その辞令には従わなければならない」とする規定があったとしても、「雇用契約書」にも明示しておいた方がトラブルに発展するリスクは低くなるだろう。また「雇用契約書」が就業場所を限定する内容になっていると、会社側は転勤を命じることができないので要注意だ。就業規則による規定と異なる条件が「雇用契約書」に記載されていた場合、就業規則が優先される、または従業員が不利となる部分が無効となることなどが労働契約法で定められている。自社の就業規則との整合性に留意し、不備・漏れ・不明瞭な点を徹底的に排除して「雇用契約書」や「労働条件通知書 兼 雇用契約書」を作成するようにしたい。
●労働条件変更時の対応
業務内容、職種、配属が変更される可能性に関しては、専門職として特定の部署・業務内容にのみ異動することになるのか、それとも広範な業務・職種への配属がありうるのか、詳細を明確にしておきたい。その他、労働条件の変更に際しては「労働者にとって有利な変更であれば、就業規則を変更することで可能となる」、「労働者にとって不利益となる変更の場合、労働者との間で合意する必要がある」ことなどが定められている。これらにも留意したい。
●「雇用契約書」は電子化も可能だが注意点あり
「雇用契約書」は、労働者が希望した場合に限り、FAX、電子メール、SNSなどでも明示できることになっている。この場合「労働者が確かにメールなどによる明示を希望した」と証明できるようにしておくこと、到達したかどうか労働者に確認すること、書面として印刷・出力できるような形式にしておくことが必要だ。また電子化された「雇用契約書」には電子帳簿保存法が適用されるため、一定期間は適切に保存されること、すぐに確認できる状態になっていることが求められる点にも注意したい。
「電子契約」とは? 関連する法律や導入のメリット、ポイントを解説
●ひな形(テンプレート)利用時の注意
厚生労働省のホームページ、または人事・労務関連のサービス事業者などを通じて「雇用契約書」や「労働条件通知書」のひな形(テンプレート)を入手することが可能だ。ただし、これらは“一般的な労働時間制で働く正社員”を前提としたものであることが多く、フレックスタイムやリモートワークといった特殊な制度のもとで働く労働者、契約社員やパートなどに、そのまま適用することは難しい。個々の労働契約や自社の就業規則に合わせて細かく修正・アレンジし、記載漏れや不具合がないよう、注意深く作成すべきである。
厚生労働省 東京労働局:様式集
まとめ
法律上、企業に「雇用契約書」を作成する義務はないが、労働条件に関するトラブルを回避するために、ぜひとも作成・締結に取り組みたい。「労働条件通知書」の交付が法的義務であることを考えれば、2つの書類をまとめた「労働条件通知書 兼 雇用契約書」を作成することがベストと言えるだろう。正社員、契約社員、パートやアルバイトなど、雇用形態によって関連する法律や、各書類に記載すべき事柄は異なる。またビジネス環境の変化に応じて、各種労働条件、「雇用契約書」、「労働条件通知書」を変更しなければならないケースも出てくるだろう。各法令を熟知・精査し、不備・漏れ・不明瞭な点を排除して書類を作成することが重要だ。
働き方の多様化が進み、労働者が求める労働環境や労働条件も複雑化する現代、労働者に安心して働いてもらうためにも、まだ作成していない企業には迅速な対応を、すでに作成済みの企業には時代に即した内容への見直しを進めたいところである。
「雇用契約書」に関するお役立ち資料、セミナー、サービスなどの最新コンテンツはこちら
- 1