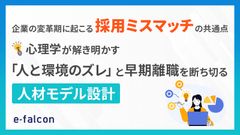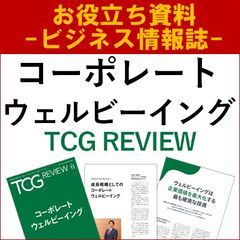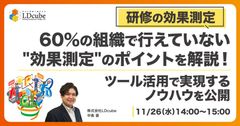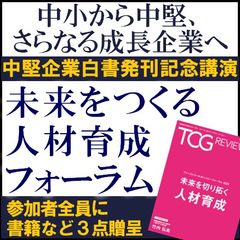■HRプロでは「人員配置」に関するお役立ち資料を多数掲載中

「人事異動」とは?
「人事異動」とは、企業が人事権を用いて従業員の配置や地位、勤務条件の変更を指示する制度を言う。企業が効果的かつ持続的に事業活動を展開していくためにも、重要な取り組みとなる。ただし、企業が勝手に行えるわけではない。就業規則に基づいて人事権を行使することが求められる。●「人事異動」の時期と頻度
「人事異動」を行う時期に決まりはなく、企業によって異なる。ただし、一般的には事業年度を終えた期初に行うことが多い。事業戦略を見直し、新たな経営年度に向けて新体制で臨んでいきたいタイミングとなるからだ。●「人事異動」は拒否できるのか?
「人事異動」を命じられた場合、従業員は拒否できるのであろうか。原則的には、拒否できない。その企業が就業規則に「人事異動」に関する規定を設けているのであれば、命令に従うことが従業員の義務となるからだ。もし、従わない場合には懲戒の対象になりうる。●「人事異動」が無効となるケース
もちろん、「人事異動」が無効になる可能性がないわけではない。例えば、「人事異動」の理由や目的が不当である、「人事異動」によって従業員に多大な不利益が生じる、労働契約で限定されている条件を逸脱するなどだ。特に、性別や国籍、出産、介護などを理由として、従業員が不利となる命令をしてしまうと不当と見做される可能性が高い。「人事異動」の目的や企業に必要な理由
「人事異動」の目的や企業に必要な理由は、さまざまだ。主なものを紹介したい。●人材の最適配置
適材適所に人材を配置することによって、人的リソースを効果的・効率的に活用していける。実際、従業員一人ひとりのスキルや適性に合致した業務やプロジェクトに配置したことで、本来の実力を発揮し活躍したというケースは多々ある。企業全体としても生産性の向上を図れる。●組織の活性化
従業員が同じ場所で同じ業務を続けていくと、仕事がマンネリ化してモチベーションが低下したり、職場自体の風通しが悪くなったりする。それを防止し、組織に活気をもたらしていくためにも「人事異動」は意味がある。「組織開発」の手法や企業事例とは? 人材や働き方の多様化の備えに向けて解説
●人材育成・キャリア形成の支援
「人事異動」を機に従来とは全く異なる業務に従事することによって、新たな経験やスキルを身につけ、キャリアアップにつなげていける。そうした従業員が増えていけば、組織全体のレベルアップも期待できる。●従業員のモチベーション維持・向上
従業員のモチベーション維持・向上も、「人事異動」の大きな目的だ。どうしても、同じ業務に長く従事していると、マンネリ化に陥ってしまい、業務への意欲が低下する可能性がある。その結果、業績にも悪い影響を及ぼしかねない。●問題の解決
長期間同じ業務を続ける弊害は、他にも挙げられる。外部からのチェックが甘くなり、結果として不正のリスクが大きくなってしまう。そうした問題を回避するためにも、特定の職務での勤務期間に上限を設けている企業もある。■HRプロでは「人材戦略」に関するお役立ち資料やセミナーを多数掲載中
「人事異動」の種類
「人事異動」は企業内と企業間という2つのタイプに大別される。違いを見ていこう。【企業内の「人事異動」】
同一の企業内で職位や部署、勤務地などが変わることを意味する。・配置転換
勤務地は同様だが、所属する部署や業務内容が変更となることを言う。・転勤
同一企業の中で勤務地が変わることを言う。・昇格・降格
企業内での役職や職位が変わることを言う。地位が上がることが昇格、下がることを降格と呼ぶ。等級変更も含まれる。・職種変更
総合職から一般職への異動や研究職から事務職への異動など、仕事内容が変わることを言う。【企業間の「人事異動」】
グループ企業内の別会社に異動することを意味する。・出向
在籍していた会社との雇用契約は維持したまま他の企業に異動し、そこで業務に従事させることを言う。労働条件は同様だが、勤務地や業務内容は変化することになる。・転籍
在籍していた会社との雇用契約を解除した上で異動先の企業と新たに雇用契約を交わし、そこの労働条件に基づいて勤務させることを言う。実態としては、転職に近い。「人事異動」を行うメリット
「人事異動」には、さまざまなメリットがある。第一に、従業員のスキルを適正に活用することができる。従業員それぞれのスキルや経験に合った業務やプロジェクトに配置することで、本人のモチベーションが上がり、生産性を高められる。二点目は、業務における属人化の防止だ。「人事異動」を行うことで複数の従業員で業務を進めていきやすくなり、何か突発的な事態が起きてもスムーズに対応できる。三点目が、従業員の成長にもつなげていけることだ。従来とは異なる業務を経験することで、より多角的なスキルを身に付けられるし、新たな挑戦の場に身を置くことでよりモチベーションも高めることができる。「人事異動」を行うデメリット
「人事異動」はメリットばかりではない、上手くいかなかった場合には、デメリットが生じてしまいかねない。具体的には、コアメンバーが異動してしまうと元々の部署が機能しにくくなる可能性がある。また、新たな業務を覚えてもらうための教育に多大なコストと時間を要する。また、「人事異動」に失敗すると離職につながりかねない点も危惧される。特に優秀な人材の離職は、企業にとっては多大な損失となってしまうし、迎え入れた部署としてもモチベーションが低下しがちだ。「人事異動」の決め方・手順
続いて、「人事異動」の決め方・手順を説明したい。(1)「人事異動」の目的・方針の確認
まずは、なぜ「人事異動」を行う必要があるのか。目的は何か。どんな方針で臨むのかなど、前提を固める必要がある。(2)異動対象者・異動先部署の選定
異動対象者を選定する際は、異動希望者の情報等を確認した上で年齢や在職年数、健康状態、階級・職位、勤務態度を含めた人事評価、賞罰などを多角的に評価していく必要がある。併せて、各部署の状況や人員の過不足、求められるスキル、異動対象者との適合性などを踏まえ、異動先を選定する。(3)異動内容の社内調整
「人事異動」のプランが固まった段階で、異動候補者と在籍部門の上長とによる面談の場を設け、異動理由や異動先での業務内容などの理解・合意形成を図る。承諾がどうしても得られず、その理由にも正当性があると判断せざる得ない場合には、経営・人事側に再考を求めるが、最終的な判断はトップの裁量となる。(4)異動者への通知・説明
「人事異動」を行うにあたっては、事前に通達を受ける従業員本人や上司らに対して内々の通知をする。これを内示と言う。タイミングとしては、辞令発表の二週間前や一カ月前程度が多い。(5)異動の実施
異動者への通知と合意取得を完了した後に、社内に「人事異動」の正式な辞令を発表する。これによって、「人事異動」に関する情報が詳細に提示され、必要な手続きを実施していける。(6)異動後のフォロー・支援
「人事異動」は辞令を下したら終わりではない。異動した従業員がスムーズに新たな部署や業務に慣れていけるようフォロー・支援することも重要となる。なぜなら、極度の不安やネガティブな感情を抱え込んでしまうケースが少なくないからだ。定期的な面談や研修を行うことを勧めたい。「人事異動」をする際の注意点
次に、「人事異動」を行うにあたっての注意点を列挙したい。●従業員の理解を得る工夫
「人事異動」を成功に導く最も重要なポイントは、対象となる従業員の理解を得ることだ。十分に納得できていれば、その後トラブルに発展するリスクはかなり低くなる。むしろ、新たな職場・業務に対して前向きな気持ちで臨んでくれるに違いない。それだけに、「人事異動が必要な理由」や「人事異動の対象者として選択した基準・期待」、「異動後の業務内容、将来的なキャリアプラン」などについて理解を得るようにしたい。●ハラスメント対策・情報漏洩対策
ハラスメントに該当しないような配慮も欠かせない。例えば、本人から何も希望が寄せられていないにもかかわらず、産休や育休を理由に部署を異動させたり、勤務時間を変更させたりしてしまうと、マタニティハラスメントに該当する。また、「人事異動」の情報が漏洩しないよう対策を取ることも大切だ。具体的には、ルールの策定や意識付け、情報管理に関する教育研修などが想定される。「ハラスメント」とは? 種類と一覧表、リスクなど徹底解説
●違法行為・人事権の濫用の防止
「人事異動」を行う際には、労働契約法に違反しないようにしなければならない。例えば、国籍や信条、社会的な身分などを理由としての「人事異動」は違法行為に該当する可能性がある。また、人事権の濫用と見做される行為も避けなければいけない。いずれも万が一、労使間でのトラブルにつながると、企業の信用問題にも影響が出てしまう。「コンプライアンス」の意味や違反の事例、必要な取り組みとは?
「人事異動」の理由の伝え方
原則的に、「人事異動」は拒否できないとは言え、できることならば異動対象者にしっかりと納得してもらうようにしたい。では、理由をどう伝えれば良いのであろうか。ポイントとしては二つある。まずは、異動の理由を具体的に説明することだ。自ら人事や上司に対して異動希望を伝えていた場合以外は、「どうして自分が異動するのか」と悩んでしまうはずだ。「上司は自分を戦力して認めてくれなかったのでは」「何か取り返しのつかないミスをしたのだろうか」とマイナスに捉えてしまうことだろう。そうした誤解が生じないよう、異動の背景や異動先からの期待も添えて説明するようにしたい。
もう一点は、異動先で新たに担当する業務内容を明確に提示することだ。「まだ決まっていない」「良くわからない」では、社員をより一層不安にさせてしまう。業務内容と自分の適性・志向がマッチしていると思うことができれば、異動を快く受け入れてくれるに違いない。
まとめ
今回は、企業が就業規則に則り人事権を行使して従業員に部署の異動、配置や地位の変更を命令する「人事異動」について解説してきた。しかし、「働きやすさ」を重視する傾向が顕著になっている現代は、より柔軟な考え方が人事やマネジメントに求められていることを承知しておきたい。具体的には、社内公募制度や社内FA制度、職群選択制度などの活用も今後はもっと考えていく必要がある。選択肢が豊富になってきた中で、改めて「人事異動」の意味や価値がどこにあるのか。今回の記事をきっかけに改めて検証してもらいたい。「人員配置」に関するお役立ち資料、セミナー、サービスなどの最新コンテンツはこちら
- 1