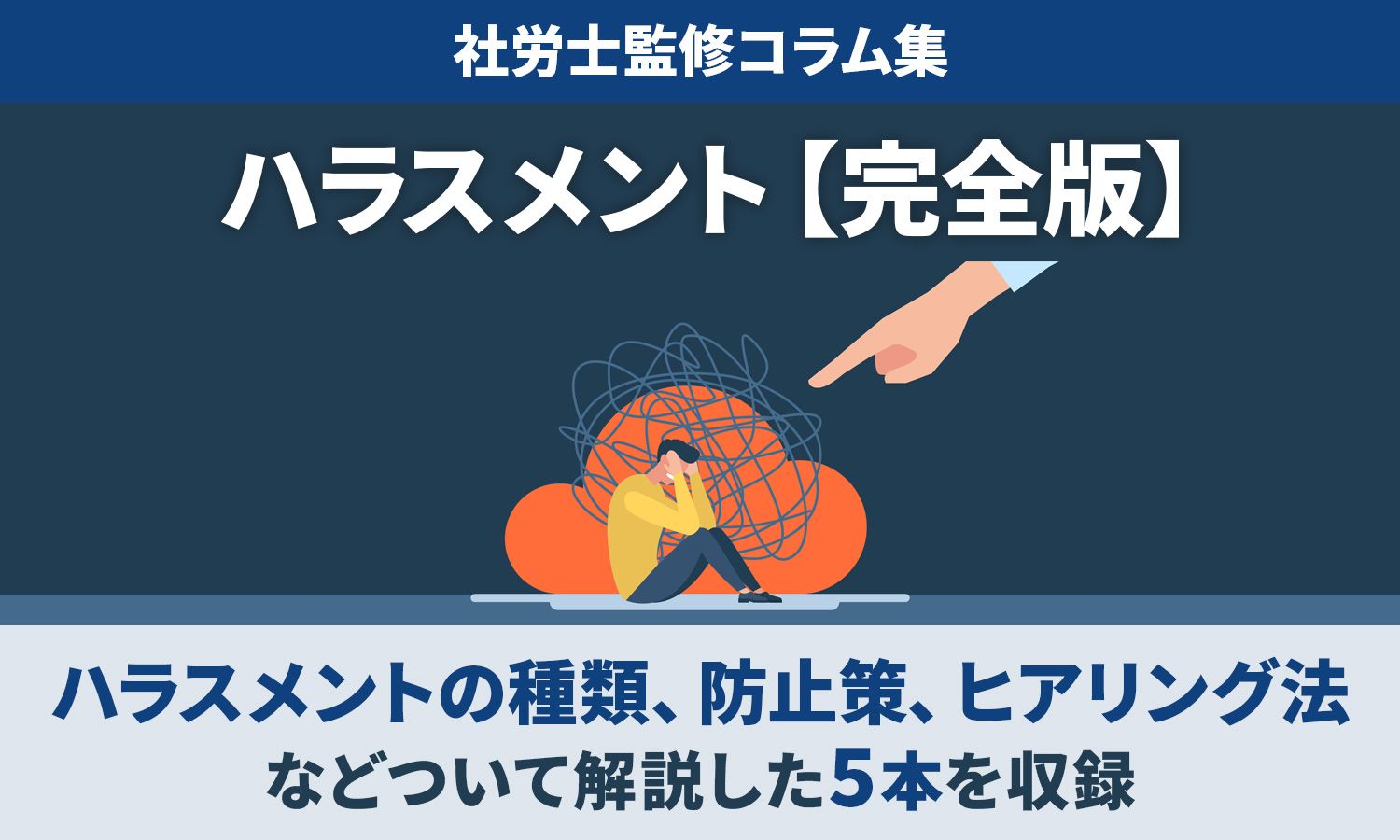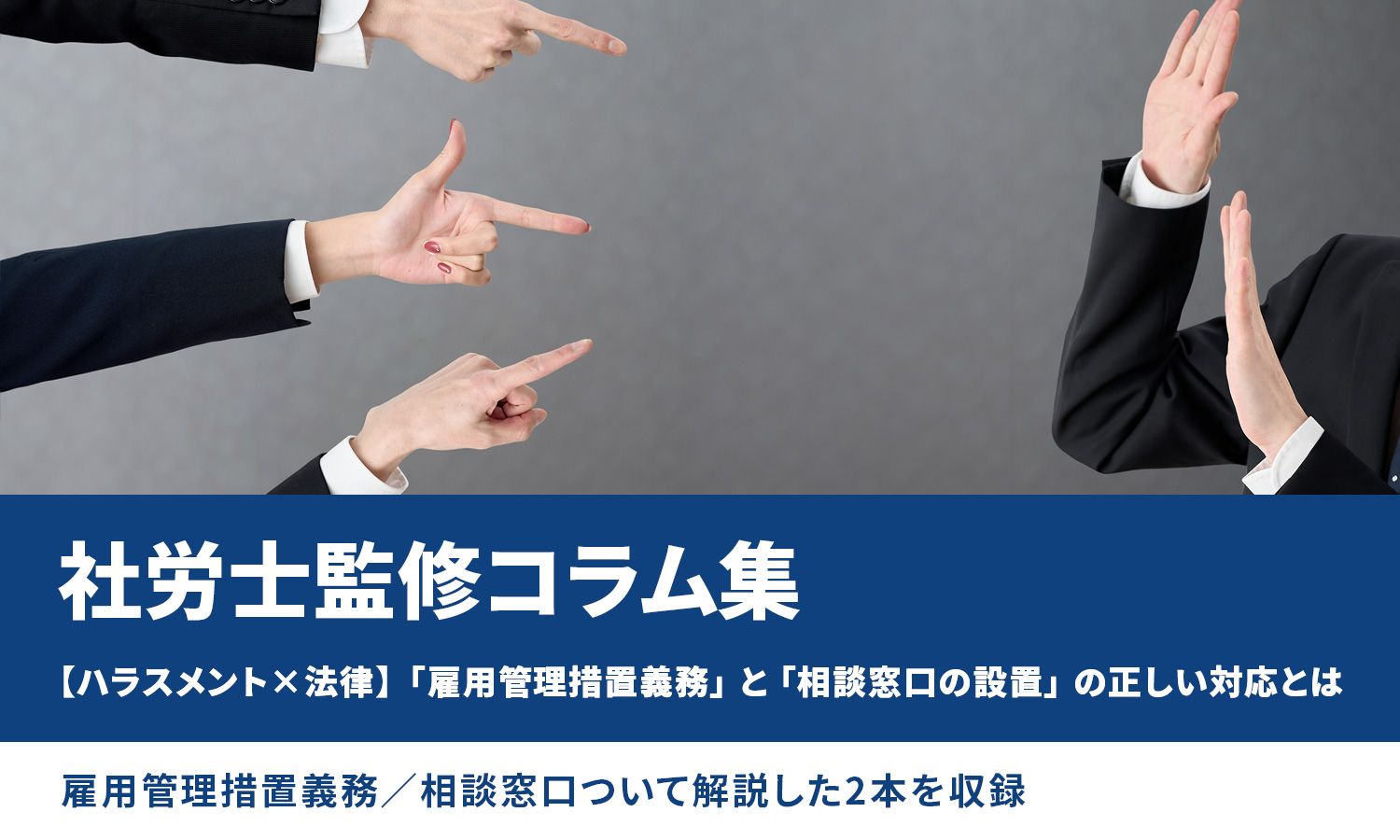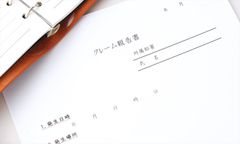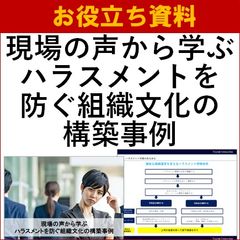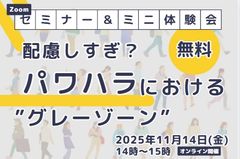■「ハラスメント」に関する資料ダウンロード、セミナー、サービス、ニュースなどの最新コンテンツはこちら

「ハラスメント」とは? 意味と定義
「ハラスメント」とは、相手の意に沿わない言葉や行動によって不快な想いをさせてしまう、嫌がらせを指す。行為者自身に意図があったか、なかったかは関係ない。相手が不快に思い傷ついたり、不利益を被ったりしてしまうと、その行為は「ハラスメント」に該当すると言える。●法律で定義された「ハラスメント」
特に注意が必要なのが、法律で定義された「ハラスメント」だ。・セクシュアルハラスメント(セクハラ):男女雇用機会均等法
・パワーハラスメント(パワハラ):労働施策総合推進法(パワハラ防止法)
・マタニティハラスメント(マタハラ):男女雇用機会均等法、育児・介護休業法
・パタニティハラスメント(パタハラ):育児・介護休業法
・ケアハラスメント(ケアハラ):育児・介護休業法
上記の種類は、とりわけ深刻なハラスメントとして、労働関連の法令で具体的な要件が明確に定義され、企業には防止や対応のための措置を講じる義務が求められている。
また、上記とは別に、社会通念上「ハラスメント」と呼ばれているものも多数ある。
・モラルハラスメント(モラハラ)
・ロジカルハラスメント(ロジハラ)
・ジェンダーハラスメント(ジェンハラ)
・テクノロジーハラスメント(テクハラ)
など
●「ハラスメント」の現状
近年、企業内における「ハラスメント」は増加している。厚生労働省が発表した「令和4年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によると、総合労働相談件数は124万8,368件(前年度比0.5%増)、15年連続で100万件を超えている。また、民事上の個別労働紛争の相談件数、助言・指導の申出件数、あっせんの申請件数の全てで、「いじめ・嫌がらせ」が引き続きトップを占めている。日本労働組合総連合会が2021年6月に発表した「仕事の世界におけるハラスメントに関する実態調査2021」でも、職場で「ハラスメント」を受けたことがある人が全体の32.4%、そのうちの56.8%が「仕事のやる気がなくなった」と回答している。「ハラスメント」の未然防止と迅速な解決を進めなくては、職場環境の健全さが維持できず、労働生産性にも大きな影響が出てしまう。
職場における「ハラスメント」の種類
「ハラスメント」には、三大ハラスメントと呼ばれる「セクシュアルハラスメント(セクハラ)」、「パワーハラスメント(パワハラ)」、「マタニティハラスメント(マタハラ)」の他にも多種多様ある。ここでは、職場で発生しやすい「ハラスメント」の種類を紹介していく。●セクシュアルハラスメント(セクハラ)
セクシュアルハラスメント(セクハラ)とは、相手に不快感を与える性的な嫌がらせである。これによって、個人としての尊厳を傷つけたり、就業環境を悪化させ能力を十分に発揮できなくなったりしてしまう。男性が女性に対して行うイメージが強いが、ここ数年の傾向としては、女性から男性や同性同士といったケースも珍しくなくなっている。セクハラは「対価型セクハラ」と「環境型セクハラ」に大別される。前者は、立場や上下関係を利用して、下位にある者に対して言動を強要すること。後者は、性的な言動を繰り返すことで職場環境を悪化させることを指す。いずれにしても、自分としてはセクハラという意識がなかったと言っても、相手はセクハラとして受け取るということもあるだけに留意する必要がある。
●パワーハラスメント(パワハラ)
パワーハラスメント(パワハラ)とは、同じ職場で働く人に対して、職務上の地位や権力などの優位性を乱用し、業務の適正な範囲を越えて精神的・身体的な苦痛を与えることだ。上司が部下に、先輩が後輩に行うことが多いが、最近では部下から上司にというケースも増えている。具体的には、目標をクリアできなかった社員を長時間立たせたままにする、特定の社員だけミーティングに呼ばないといった行動が挙げられる。●マタニティハラスメント(マタハラ)
マタニティハラスメント(マタハラ)とは、妊娠中、出産間近、子育て中といった女性に向けた嫌がらせを言う。具体的には、妊娠した旨を伝えてきた女性社員に解雇や雇止め、降格、減給を言い渡すといった不利益な取り扱いを指す。こうした行為は、労働基準法や男女雇用機会均等法、育児・介護休業法などの法律でも禁止されており、企業は防止措置を取ることが義務付けられている。出産後も女性が職場に復帰しやすい環境・制度づくりに注力していくことが重要だ。●パタニティハラスメント(パタハラ)
パタニティハラスメント(パタハラ)とは、子育てを理由として育児休暇やフレックス勤務、短時間勤務を取得しようとする男性社員の行動を非難したり、人事評価に悪影響を及ぼしたりする行為である。「男が育休だと。どういうつもりだ」、「評価がどうなっても知らないぞ」といった言葉が、これにあてはまる。もはや、子育ては女性だけという時代ではない。男性も一緒に育児を行うという価値観を持たなければいけない。●ケアハラスメント(ケアハラ)
ケアハラスメント(ケアハラ)とは、働きながら家族の介護をしている社員に対する嫌がらせを言う。具体的には、介護休業や介護時短制度などを利用しようとする際に、「そんなに休んでばかりでは重要な仕事は任せられないなあ」などと言って、上司や同僚が妨害することを指す。介護だけを理由に降格処分を下すのもこれに該当する。●モラルハラスメント(モラハラ)
モラルハラスメント(モラハラ)とは、道徳や倫理に反する行為や言動によって、相手に不快感や精神的苦痛を与えることを指す。具体的には、差別的・侮辱的な発言や不当な批判、軽蔑的な態度などである。人が見ている前で過剰に叱責したり、労働時間外で過度に連絡したりと、ビジネスシーンでも多く発生する。●ジェンダーハラスメント(ジェンハラ)
ジェンダーハラスメント(ジェンハラ)とは、一般的な意味での「男らしさ」、「女らしさ」のイメージに基づいて人をあれこれと非難したり、強要したりする嫌がらせを指す。「男性なのに、○○」、「女性なのに、◎◎が苦手なの?」といった発言も該当する。●カスタマーハラスメント(カスハラ)
カスタマーハラスメント(カスハラ)とは、顧客が従業員に対して行う理不尽な要求や言動をすることだ。例えば、過度な値引き要求、暴言、威圧的な態度、セクハラなどが該当する。カスハラは従業員にストレスがかかり、離職の原因にもなりかねない。企業は従業員を守るための対策を講じる必要がある。●アルコールハラスメント(アルハラ)
アルコールハラスメント(アルハラ)とは、飲酒を強要するなど、飲酒にまつわる嫌がらせを指す。「一気飲み」を強要したり、酒が苦手な人を執拗な勧誘したり、酔った上での迷惑行為などが該当する。最悪のケースでは健康被害につながる可能性があるため、職場の飲み会などで注意が必要だ。●リストラハラスメント(リスハラ)
リストラハラスメント(リスハラ)とは、従業員を退職に追い込むために行う不当な行為だ。突然の配置転換、仕事を与えない、過度な残業の強要、孤立させるなど、会社に居づらくなるよう仕向け、自主退職を促してしまう。従業員に大きな精神的苦痛を与えるだけでなく、法的にも問題となる可能性がある。●リモートワークハラスメント(リモハラ)
リモートワークハラスメント(リモハラ)とは、テレワークや在宅勤務などのリモート環境における、過度な監視やプライベートへの干渉、不必要な時間外連絡といった行為が該当する。リモートワーク下での配慮とルール作りが求められる。●エイジハラスメント(エイハラ)
エイジハラスメント(エイハラ)とは、年齢や世代に基づく差別的な言動のことである。若手社員を「若いから」と軽視したり、ベテラン社員を「年寄り」と呼んで能力を否定したりすれば、当然相手は傷つくことになる。年齢に関係なく、個人の能力や経験を適切に評価し、互いを尊重し合う風土を醸成したい。●その他のハラスメント
その他のさまざまな「ハラスメント」を列挙していく。・時短ハラスメント(ジタハラ)
労働時間の削減を要求しながらも、具体的な施策を何も提案せず、丸投げした状態で成果を求める行為。
・ロジカルハラスメント(ロジハラ)
正論を過剰に突き付けて相手を追い詰める行為。
・ハラスメントハラスメント(ハラハラ)
必要な範囲での指導や注意にもかかわらず、それにハラスメント行為に仕立てる行為。
・テクノロジーハラスメント(テクハラ)
ITスキルやリテラシーの差を利用し、侮辱的な言動をとったり、必要以上に難しい技術的な説明をして混乱させたりする行為。
・スメルハラスメント(スメハラ)
強烈な香水や体臭、タバコの臭いなど、強い臭いで周囲の人に不快感を与えること。
・ソーシャルハラスメント(ソーハラ)
SNS(ソーシャルメディア)を利用して行われる誹謗中傷やプライバシーの侵害、嫌がらせや攻撃的な行為。
・ラブハラスメント(ラブハラ)
相手が嫌がっているにもかかわらず、恋愛や性関係に関する話題を強要したり、自身の恋愛観を押し付けたりする行為。
・マリッジハラスメント(マリハラ)
結婚や婚姻状況に関する質問や差別的発言による嫌がらせ行為。
・パーソナルハラスメント(パーハラ)
個人の性格や特性、趣味嗜好などを理由にした嫌がらせや差別的な扱い。
・就活終われハラスメント(オワハラ)
就職活動中の学生に対し、企業側が「他社の選考を辞退するように」と強要したり、内定承諾を急かしたりする行為。
●「ハラスメント」の一覧表
上記で紹介した「ハラスメント」を一覧表にまとめた。「ハラスメント」の種類一覧表
上記で紹介した22種類の「ハラスメント」を一覧表にまとめた。| ハラスメント名 | 略称 | 概要 |
|---|---|---|
| セクシュアルハラスメント | セクハラ | 性的な言動による嫌がらせ。対価型と環境型がある。 |
| パワーハラスメント | パワハラ | 職務上の地位や権力を乱用し、精神的・身体的苦痛を与える。 |
| マタニティハラスメント | マタハラ | 妊娠・出産・育児を理由にした不利益な扱いや嫌がらせ。 |
| パタニティハラスメント | パタハラ | 男性の育児参加や育休取得に対する嫌がらせ。 |
| ケアハラスメント | ケアハラ | 介護を理由にした不利益な扱いや嫌がらせ。 |
| モラルハラスメント | モラハラ | 倫理・道徳に反する言動による精神的苦痛。 |
| ジェンダーハラスメント | ジェンハラ | 性別役割に基づく偏見や強要。 |
| カスタマーハラスメント | カスハラ | 顧客による理不尽な要求や暴言などの嫌がらせ。 |
| アルコールハラスメント | アルハラ | 飲酒の強要や飲酒に関する嫌がらせ。 |
| リストラハラスメント | リスハラ | 退職に追い込むための不当な扱い。 |
| リモートワークハラスメント | リモハラ | リモートワーク中の過度な監視や干渉。 |
| エイジハラスメント | エイハラ | 年齢や世代に基づく差別的言動。 |
| 時短ハラスメント | ジタハラ | 時短を要求しつつ、成果や業績を過度に求める。 |
| ロジカルハラスメント | ロジハラ | 正論を過剰に突き付けて相手を追い詰める。 |
| ハラスメントハラスメント | ハラハラ | 必要な指導を「ハラスメント」として過剰に主張する。 |
| テクノロジーハラスメント | テクハラ | ITスキル差を利用した侮辱や混乱を与える行為。 |
| スメルハラスメント | スメハラ | 強い臭いで周囲に不快感を与える。 |
| ソーシャルハラスメント | ソーハラ | SNS等を利用した嫌がらせやプライバシー侵害。 |
| ラブハラスメント | ラブハラ | 恋愛や性関係に関する話題の強要や押し付け。 |
| マリッジハラスメント | マリハラ | 結婚や婚姻状況に関する嫌がらせや差別的扱い。 |
| パーソナルハラスメント | パーハラ | 個人の性格や特性、趣味嗜好を理由にした嫌がらせ。 |
| 就活終われハラスメント | オワハラ | 学生に対し、就活終了を他社の選考辞退を強要する行為。 |
「ハラスメント」が企業にもたらすリスク
「ハラスメント」が横行してしまうと、企業にどんなリスクが生じるのか。5つのリスクが想定される。●法的責任を負う
企業活動において「ハラスメント」が行われた場合、その企業には不法行為責任や債務不履行責任などの法的責任が課される。そのため、「ハラスメント」があったと立証されれば、被害者が受けた精神的な損害を企業が賠償しなければならない。さらには、民事紛争に発展した場合には、風評による企業イメージの低下は免れない。●離職率の増加
「ハラスメント」が発生してしまう職場は、人間関係も気まずくなりがちだ。社員のモチベーションも低下してしまうので、有能な人材離れていく可能性が高い。転職者が続出すれば、企業としては、人材を新たに採用しなければいけない。コストや生産性の面でも悪影響がある。●職場環境の悪化
「ハラスメント」を放置すると、職場環境がさらに悪化するリスクが高まる。被害者がストレスや不安を抱えたままではなく、周囲の従業員も不安を感じてモチベーションを下げてしまう。そうなれば会社と従業員の信頼関係が崩れ、チームワークが崩壊してしまう恐れがある。●社会的信頼の喪失
前述した民事紛争に発展した場合だけでなく、「ハラスメント」が横行・発生したという情報がネットワークを通じて世に広まれば、企業の社会的な評判や信頼度に大きなマイナスをもたらしてしまう。さらに再発を繰り返したり、放置が続いたりすれば、法的措置やメディア報道によってさらなる悪影響が及ぶ恐れもある。●生産性の低下
「ハラスメント」が職場で蔓延すると、社員のモチベーションやチームワークが著しく低下する。被害者だけでなく、周囲の社員も不安や不信感を抱き、業務への集中力が低下するため、作業効率が落ち、ミスやトラブルが増加しがちだ。他方では、ハラスメント対応のために管理職や人事担当者のリソースが割かれることで、組織全体の生産性も下がってしまう。「ハラスメント」が起きる原因
「ハラスメント」が発生する背景には、職場環境や組織運営のさまざまな課題がある。主な原因を紹介していく。●ハラスメントへの意識の欠如
企業内でハラスメントの深刻さや影響について認識が希薄な場合は、当然ハラスメントは発生しやすい。従業員がハラスメントに対して無関心で看過してしまうようだと、問題が表面化せずに悪化していく恐れもある。従業員が適切な対応ができるよう、企業として重要性を周知したり、研修プログラムを実施したり対策に取り組む必要がある。●ミスコミュニケーション
従業員間や部門間での情報伝達が不十分だと、誤解が生じ、意図しない言動や行動につながってしまう。それが相手に不快感を与えてしまうのだ。逆に言えば、相手の気持ちや価値観を理解した適切なコミュニケーションや、相手の意に沿った行動を取っていれば、不快感を与えるような問題には発展しづらい。●過度な目標の設定
企業が過度に高い目標を設定し、その達成を強制することで、従業員に大きなストレスやプレッシャーを感じさせ、追い込んでしまう。また上司と部下の間でも、パワハラが発生するリスクも高まる。●ミスが許されない雰囲気がある
小さなミスも許容されず、完璧な成果が求められる社風は、ハラスメントが生じやすい環境と言える。上司が部下を過度に非難したり、従業員間で責任転嫁が行われたりする恐れがある。●一部の人に権限がある
企業内で権限が一部の人物やグループに集中している場合、権力が不当に行使される可能性が高まる。他の従業員はハラスメントを目撃しても報告を躊躇し、異議を唱えることが憚られるだろう。結果的にハラスメントが横行した状態が続いてしまう。●業務量の偏り
人員不足であったり、役割分担が曖昧だったりすると、一部の社員に業務負荷が集中してしまいがちだ。そうすると、不満やストレスが蓄積し、心身の健康を損なう恐れがある。また、上司の期待や断りづらい雰囲気から、頼まれた仕事を断れずに抱え込んでしまうケースも少なくない。そうした状況が続くと、被害者のモチベーション低下や離職につながるだけでなく、「ハラスメント」のリスクも高まる。業務の適切な分担や労働時間の管理、定期的な業務量の見直しが大切となる。企業が行うべき「ハラスメント」対策
職場での「ハラスメント」にどう対処すれば良いのか。厚生労働省では、その予防から事後対応に至るまでのサポートガイドを出している。ポイントをいくつか取り上げてみよう。●法律を周知する
1999年、男女雇用機会均等法では職場でのセクシャルハラスメントの防止措置を事業主に義務付けた。また、2017年には男女雇用機会均等法や育児・介護休業法が改正され、妊娠・出産・育児休業などに関するハラスメントの防止措置も事業主に義務付けられ、2020年には労働施策総合推進法の改正でパワーハラスメントの防止措置も義務付けられた。このように、さまざまな法律で規定されていることを企業内に周知することが重要となってくる。●対処の規定や周知を行う
就業規則の規定やパンフレット、社内報などを通じて職場での「ハラスメント」への対処の仕方を周知するのも上策である。「どんな行動がハラスメントになるのか」「ハラスメント行為をした場合、どんな処分が下されるか」などを書き記し、社員に徹底を呼びかけるというものだ。●研修で周知する
「ハラスメント」に関する専門家を外部から招き、その基本的な知識や実態、対策の必要性、具体的な対処方法などを社内の研修やセミナーなどの場で説明してもらうのも良い施策といえる。厚生労働省も積極的で、委託事業として全国各地でセミナーや講習会を開催している。それらを利用するのも一つの施策だ。●プライバシーの保護に努める
「ハラスメント」の対応を進めるにあたっては、相談者が何も心配せずに相談できるようプライバシー保護に配慮する必要がある。相談を対面で行う場合には、他の社員に気兼ねなく出入りできる場所に相談スペースを設け、同じ時間帯に相談者が重ならないように事前予約制にするのが望ましい。こうしたプライベート重視の姿勢を社内報や社内のホームページで発信し、社員に周知することも必要となってくる。●相談窓口を設置する
相談窓口を設けて、従業員が安心して相談できる体制を作りたい。相談方法も対面だけでなく、文書やメール、電話などのやりとりなど方法は色々あった方が良い。他にも、相談窓口の担当者には、「ハラスメント」に関する知見と解決に向けて誠意を持って取り組める従業員を人選することも重要となってくる。「ハラスメント」が起きた時の対処法
社内で「ハラスメント」が発生してしまった場合、迅速かつ適切な対応が求められる。ここで5つのステップに分けて対応策を解説しよう。(1)事実関係の調査
「ハラスメント」の発生した場合あるいは疑いがある場合、まず事実関係を徹底的に調査する必要がある。当事者や関係者からの相談や苦情、社内相談窓口への通報、または社外からの指摘など、さまざまな視点での情報を集め、状況を整理する。被害者と加害者の証言は一致しないケースも多いため、第三者への聞き取り調査は不可欠と言える。また被害者と加害者を隔離することも検討すべきだ。(2)調査報告書の作成
調査によって得られた当事者や関係者の証言・証拠を精査し、事実を客観的に判断したうえで、その結果を調査報告書にまとめる。報告は口頭で行う場合もあり、必ずしも報告書に記す必要はないが、社内の諮問委員会や取締役会等での重要な判断材料となる。(3)被害者への配慮と報告
被害者は精神的苦痛を受けており、なにより心のケアやサポートが必要だ。そのうえで、被害者に対して事実調査の結果やハラスメント認定の可否、補償、加害者の処分内容を適切に伝えていく。ただし、被害者が企業の対応に納得しない場合には、被害者は会社を相手に損害賠償請求することもあり得るため、事前に弁護士に相談しておくと良い。(4)加害者への処分と指導
「ハラスメント」と認定された場合、加害者に対して処分を行わなければいけない。処分内容は行為の軽重を考慮し、公平性や透明性をもって、過去の処分実績や会社の方針に基づいて決定していくのが一般的だ。そして再発防止のために、加害者への指導や教育を行うことも重要である。(5)再発防止の措置
当該事案が解決したら終わりでなく、企業として同様の問題が再発しないようにするための措置は必須だ。当事者以外の従業員への研修や教育、組織文化の改善、定期的なモニタリングや監査など、見直せるものはできる限り見直していきたい。前述したとおり、ハラスメントの報告や相談用の窓口を設置するなど、従業員が安心して問題を報告できる環境を整備することも有効だ。「ハラスメント」の悪質度と4段階の法的責任
「ハラスメント」の悪質度は、行為の内容や被害者への影響、社会的な評価によって大きく4つの段階に分けられる。| 段階 | 責任の種類 | 内容・具体例 |
|---|---|---|
| 1 | 刑事責任 | 刑法に抵触する犯罪行為(暴行、傷害、強制わいせつ、名誉毀損など)。加害者は刑事罰を受ける。 |
| 2 | 民事責任 | 不法行為として損害賠償責任が問われる。被害者は精神的苦痛や経済的損失について賠償請求が可能。 |
| 3 | 労働法上の懲戒処分 | パワハラやセクハラなど、労働法で防止措置が義務付けられている行為は企業秩序違反として懲戒処分の対象。 |
| 4 | 企業の法的責任 | 安全配慮義務違反などにより、企業自体が被害者に対して法的責任を負う場合がある。 |
最も悪質なケースは、刑法上の犯罪行為だ。例えば、暴行や傷害、強制わいせつ、名誉毀損、脅迫などがこれに該当し、加害者は刑事責任を問われる。
次に、民法上の不法行為として損害賠償請求の対象となる場合がある。これは、被害者が精神的苦痛や経済的損失を受けた場合に、加害者や企業に対して損害賠償を求めることができる。
また、刑事・民事の責任に至らなくても、労働法上で防止措置が義務付けられているパワハラやセクハラ、マタハラなどは、企業秩序違反として懲戒処分の対象となる。
さらに、こうした行為が職場環境を悪化させる場合、企業自体も法的責任を問われることがある。つまり「ハラスメント」は「刑事責任」、「民事責任」、「労働法上の懲戒処分」、「企業の法的責任」といった段階に整理できる。
知っておきたい「ハラスメント」関連の法律
職場の「ハラスメント」を防止するには、関連する法律を理解しておきたい。ここで主な法令とそのポイントを解説していく。●労働安全衛生法
労働安全衛生法は、労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境を形成するための法律だ。ハラスメント対策として、相談窓口の設置、相談体制の整備、管理者の教育、研修などを義務付けている。●労働施策総合推進法(パワハラ防止法)
労働施策総合推進法、いわゆるパワハラ防止法は、企業に対してパワーハラスメントの防止措置を義務付けている。すべての企業は、パワハラに関する方針の明確化と周知、相談体制の整備、被害発生時の迅速な対応、再発防止策の実施などの措置を講じなければならない。「パワハラ防止法」とは? 知っておくべき定義や指針、罰則についてわかりやすく解説
●男女雇用機会均等法
男女雇用機会均等法は、男女の均等な雇用機会と待遇の確保を目的とした法律だ。この法律では、セクシュアルハラスメント(セクハラ)の防止措置が企業に義務付けられており、相談窓口の設置や被害者・加害者への適切な対応、再発防止策の実施が求められている。また、妊娠や出産に関するハラスメント(マタハラ)についても、同様に防止措置が義務化されている。●育児介護休業法
育児介護休業法は、育児や介護を行う労働者の就業環境を守るための法律だ。育児休業や介護休業の取得を理由としたハラスメント(マタハラ・パタハラ、ケアハラ)を防止する措置が事業主に義務付けられている。具体的には、制度利用者への不利益な取扱いの禁止や、「ハラスメント」が発生しないような職場環境の整備、相談体制の構築などが求められる。まとめ
近年、企業内での「ハラスメント」は増加しており、次々に新たな種類が生まれている。「ハラスメント」を放置していれば、生産性の低下だけでなく、社会的信頼の喪失につながるため、危機感をもって対応していかなければいけない。人事担当者としては、従業員が安心して働ける職場環境を作り、制度を整える必要がある。また万が一起きてしまった場合には、うやむやにせず、当事者にしっかりと向き合い解決していくようにしてもらいたい。「ハラスメント」に本気で取り組む覚悟が、個人だけでなく、組織全体に問われているのだ。よくある質問
●三大ハラスメントとは?
三大ハラスメントとは、特に職場で発生しやすい「パワーハラスメント」、「セクシュアルハラスメント」、「マタニティハラスメント」を総称したもの。それぞれ労働施策総合推進法や男女雇用機会均等法、育児・介護休業法によって、企業に防止措置が義務付けられている。●「ハラスメント」を放置するリスクは?
企業内での「ハラスメント」を放置すると、人間関係や職場環境が悪化し、離職率の増加につながる。また、「ハラスメント」が行われた場合、その企業には不法行為責任や債務不履行責任などの法的責任が課され、社会的な評判や信頼度に大きなマイナスをもたらしてしまう。- 1