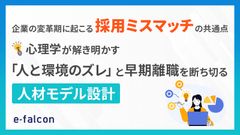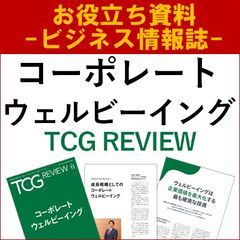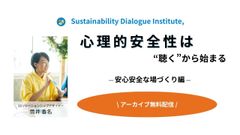具体的には、組織風土変革プログラム「BLUEPRINT」を全従業員23,000人へ展開しました。工場の操業を止め、広島のサッカースタジアムを使って11,000名の直接従業員にも一気に浸透させた点が大きな挑戦でした。その結果、社員意識調査のスコアが反転し、少しずつ変化が現れ始めているのが見られます。今後は、戦略に基づいた施策の設計・実行のフェーズに移り、厳しい環境にありながらも人への投資を継続・強化していくことを打ち出しています。
冨樫氏:厳しい経営環境の中で社員意識調査のスコアを反転させたのは素晴らしいですね。コアな部分に全社的に取り組む意思決定が効いたということですね。
では、コカ・コーラ ボトラーズジャパンの東様にもお願いします。
東氏:私が掲げたキーワードは「盤石の布石」です。基盤が固まりつつあり、新しい実行フェーズを見据えて布石を打った1年でした。昨年1月から全社横断で中期経営計画を進める中で、人事戦略を刷新し、経営陣との議論を重ねながら重点エリアを特定し、KPIを設定して実行してきました。
特に人的資本経営に関しては、毎週の役員会に加え、月1回は人事戦略専門の会議を実施し、設定したKPIを役員個人のKPIや報酬とも連動させる仕組みを導入しました。そういう意味でしっかりと仕組みを整備できました。
重点エリアでは、現場労働不足の解消や物流の2024年問題がある中で、採用プロセスや人材要件を見直し、オンボーディングを強化しました。また「パフォーマンスドリブンカルチャーの浸透」に着手し、公正な評価やフィードバック、報酬の透明性を高めました。さらにウェルビーイングについて定義し、制度とサーベイ結果を連動させて改善を推進しました。
一方で、経営のデジタル化やビジネスモデルの変革が進む中で、これに即したスキルの再定義や人材ポートフォリオの設計、リスキリング・アップスキリングの支援、自律的キャリア形成の促進などに取り組み、人事自体も未来志向で変わる必要があると考えています。
冨樫氏:まだ2年経っていない中で、ここまで広範囲に挑戦されているのは非常に印象的です。日本経済新聞の上杉様、お三方の話を聞かれていかがですか。
環境が激変するなかで、非連続な成長を想定されて、それに対して、担う人と組織の土台をきっちり作られています。
冨樫氏:未来の事業を担う人材像をどう作っていくかという点で、まさに人材戦略の核心が見えてきましたね。
冨樫氏:皆様、この1年間でさまざまな環境変化の中、組織変革に取り組まれてきたと思います。その中で得た学びや気づき、再発見について、CHROとしての役割に結び付けてお話しいただけますか。東様からお願いします。
東氏:昨年のセッションでは、CHROの役割は「ファシリテーター」であるとお話ししました。この1年はまさに、さまざまな立場の人をつなぎ、調整する場面が非常に多かったです。役員会のアジェンダ設定から始まり、各CxOの考え方や関心を踏まえ、経営陣として何をどう推進するかを導く力が求められました。
その中で感じたのは、ファシリテーターとしての調整だけでなく、人的課題について強く主張することの大切さです。経営会議や取締役会では、どうしても経済効率性や財務データという目に見える数値を基準に考えがちです。しかし、私たちのビジネスを支えている「人」に関する議題は、理論だけでは簡単に解決できません。「ビジネスモデルが変わるから、それに合わせたスキルを持つ人材を育成しよう」と経営陣が言っても、社員がすぐに順応できるわけではありません。そこには「変わろう」という本人の意識やモチベーション、未来への期待感など、数値では見えにくい要素が不可欠です。だからこそ、「このスキルが身につけば会社も自分も成長できる」という前向きな感情を醸成することが重要だと考えています。
そのため、私は「経営陣から積極的にメッセージを発信しましょう」「人材戦略を大事に考えましょう」と働きかけ、数値だけでなく定性的な側面にも目を向けてもらいました。社長の協力を得ましたが、ここにこだわり続けられるのは、CHROにしかできない役割だと感じています。
冨樫氏:昨年のセッションで、CEOの決断に対して各CxOがそれぞれの持ち場で専門性を発揮する「ツリー型」から、各CxOが連関して、線ではなく面で戦略を立てていく「ペンタゴン型」への変化が求められるという話がありました。そのペンタゴン型であっても、それぞれ各CxOの専門領域が異なりますから、どうしても議論が財務データをベースに考えがちです。そこを突破し、バランスを取るのがCHROということですね。鹿島様は、これを聞いていかがでしょうか。
鹿島氏:経営会議の中で「人」に関する話題は常に議題になり得ます。それを、その場で議論するか、後回しにするかでスピード感や議論の質は大きく異なります。そういう意味で、私自身が経営会議のメンバーとなれたことは非常に大きかったと感じています。
冨樫氏:竹内様はいかがですか。
竹内氏:とても共感できる点が多いです。CxOそれぞれが「人」に対して、多様な意見や視点を持っています。その中でCHROとして一本筋の通った方向性を貫けるかどうか、その難しさを日々感じています。
冨樫氏:昨年のセッションではCHROの役割として「オーケストラの指揮者」や「ハブ」のような、周囲の人の意見を聞きながら調整していくことが挙がりました。ただ、そうした「守り」だけでなく、時には自分の意見を貫く「攻め」の姿勢も必要だということですね。では竹内様、この1年間を振り返っての挑戦や学びはどのようなものでしたか。
竹内氏:先ほどの続きになりますが、CxOが集まる会議の中で、マツダの人事として大切にすることをぶらさずに貫けるかが一番の挑戦でした。「人」に関しては財務の観点で捉える方もいれば、教育面に関心を持つ方もいます。関心事が異なる中で、従業員一人ひとりの総力を最大化し、難局を乗り越えていくためには、「今、何に取り組むべきか」「どこに投資すべきか」を、人事の立場で貫くこと、それが大きな試練だったと思います。
また、経営環境が劇的に変化している自動車業界において、「風土」という基盤をどう守り育てるかも大切でした。マネジメントやCxOに対して、その振る舞いやリーダーシップに関するアドバイスをしたり、個別で相談を受けたり、時には“聞き役”に徹しながら、ペンタゴンの連携を築こうと奮闘した1年でした。
冨樫氏:主張の激しいであろう経営陣の中で、自分が正しいと思ったことを貫くのは、なかなか難しそうです。東様、いかがですか。
東氏:未来を見据えると、そこには曖昧さや不確実性があり、正しいことを誰も見たことはありません。ですので「自分の正しさを貫く」というよりは、全員で議論して“正しいであろうこと”を定めていくイメージです。当社の場合は、今その段階にあると思います。
冨樫氏:つまり人材戦略の柱がぶれさせないことが、CHROとしての役割だと。一方で竹内様のお話は、フィロソフィーや風土といった、自社らしさを守る、なくしてはいけないものについてですね。
竹内氏:その通りです。未来の「正解」を探すというよりは、必ず立ち返る基盤を常に持つということです。「人」の本質に照らし合わせ、傷つく・喜ぶといった人間ならではの感情を物差しとしながら取り組みを進めていくイメージです。
冨樫氏:ありがとうございます。
冨樫氏:では、続いて鹿島様。丸紅としては、この1年間を「ギアチェンジ」とテーマづけて取り組んでこられたということでしたね。ご自身としてはどのような変化があったのでしょうか。
鹿島氏:一つは先ほど申したように経営会議メンバーになったことが非常に大きかったです。もう一つは、久々に海外拠点を訪問し、そこで逞しく成長している若手社員を直接見ることができたことです。CxOは現場からどうしても距離が生まれてしまいますが、人事制度の改革が海外の現場にも根付き、社員が実際に変わっている姿を見られたのは大きな収穫でした。
また、CHROとしての役割を意識し過ぎるより、チームとして人財戦略を実現できるよう、人事部やCxO、経営企画部などと連携し、推進を支えるファシリテーションに注力しました。
さらに昨年、当社は2030年までに時価総額10兆円超を目指す、という目標を掲げました。現在は5兆円弱ですが、この目標の実現には株価の向上は不可欠です。そこに対して、人事部門の社員が「自分に何ができるか」を主体的に考えるようになりました。株主に「人が育ち、価値を生み出し、会社に貢献している」と感じてもらい、期待してもらう。もちろん、まだ道半ばですが、それを人事が担っているという意識変革ができたことは大きな変化でした。
冨樫氏:まさに人的資本経営が叫ばれて約3年、企業価値を2倍にするという目標の中で、人事がどう貢献するかを強く意識するフェーズに来たわけですね。
鹿島氏:そうです。財務の力だけでは難しく、非財務である人事がどのように価値創出に貢献するかがカギになります。もちろん、これまでもそういった自覚はあったのですが、明確な数値目標を掲げたことで、その意識がより強くなりました。
冨樫氏:ありがとうございます。では、日本経済新聞社の上杉様、ここまでの話を聞いていかがですか。
上杉氏:変化が激しく明確な正解がない中で、多くの企業が模索しながらさまざまな施策に取り組んでいます。そんな中、お三方は人事領域において、一段上の視座と変革のマインドをもって取り組んでおられる点が印象的です。人事制度の変革は、会社にとって大きな試みであり、慎重になりがちです。しかし失敗を許容し、そこから学んで修正することで正解に近づいていけるのだと思います。だからこそ、他社も小さな失敗を受け入れる寛容さを持っていただければと思います。
冨樫氏:ありがとうございます。鹿島様は上杉様の話に深くうなずいていらっしゃいましたね。
鹿島氏:そうですね。以前の中期経営戦略で人事制度改革を実施した際、「まず走らせながら修正する」という前提で1年で導入しました。経営陣も意外と受け入れてくれ、社員からも大きな反発はありませんでした。振り返れば、人事部門の我々が一番慎重になりすぎていたのかもしれません。
初めから完璧な制度を導入しようとすれば、どうしても変革が遅れてしまいます。ですので、スピードを重視して失敗を繰り返しながら修正していったということです。1年で施策を導入できたのは、経営陣の失敗を許容する姿勢があったからこそです。
冨樫氏:CEOを含む経営陣の理解は非常に重要になるということですね。マツダでは昨年から大掛かりな組織風土変革プログラムを進め、今年は工場で製造に関わる従業員11,000名を広島のサッカースタジアムに集めて、4日間のセッションをもって一気に展開したとのことでしたが、これは経営会議では全会一致で決まったのでしょうか。
竹内氏:はい。CEOとCFOの絶大なサポートがありました。特にCFOは現地にも足を運び、従業員に直接メッセージを送るなど積極的に支援してくださいました。
冨樫氏:トップが実際に動くことで、その覚悟が現場の皆様にも伝わるのですね。東様も「社長の協力を得た」とおっしゃっていましたが、CEOとの連携は、人事制度の変革のキーであるとお考えですか。
東氏:その通りです。中期経営計画の実現には、人的資本の強化が不可欠です。そのため役員会で「人材・組織・カルチャーのあり方」を定義し、そこに到達するために各部門の課題を洗い出し、重点分野を明確にしました。この方針は役員会全体での合意があり、共通認識をもって進めています。
ただし、部門ごとに優先順位や捉え方は異なりますので、そこはCEOと足並みを揃えながら調整を重ねています。また、当社にはトライアンドエラーを許容する文化もあります。
人事部門においては、相手にしているのが社員という人間なので、「間違えるのが怖い」「やり直しがきかない」と思われるのですが、当社では「うちの部門で試してみますか」と提案いただけることが多いです。スモールスタートで、上手くいったらスケールアウトするというビジネスで一般的な考え方を人事部門にも取り入れることで、多様でフレキシブルなアイディアが積極的に生まれるようになりました。
冨樫氏:人事セクションにも、スピーディーにトライアンドエラーを繰り返すカルチャーを作っていくことが、企業全体の変革につながっていくわけですね。
ここまでのお話を伺うと、環境変化が激しく正解が見えない時代にあっても、それぞれの課題に対して“ぶれない軸”を持ち、主張すべきことを示しながら、CxOを含め周囲を巻き込んでいくことが重要だと感じました。
では、最後にご覧いただいている皆様へ一言ずつメッセージをいただけますでしょうか。
鹿島氏:本日はありがとうございました。この1年間を振り返ることで自分にとっても大きな学びになりました。人事戦略が経営に直結する時代、自社内だけでの経験では人事は学びきれません。本日のセッションから得られた気づきも含め、今後も多くの事例を皆様と共有しながら学び合っていければと思います。
竹内氏:昨年は、「CHROに求められるのは人の理解」とお話ししましたが、改めてこの状況下で、その理解をもっと深める必要があると感じました。戦略を実現するのも組織を動かすのも一人ひとりの力です。一方で、今はAIの急速な進歩により、「人」が担うべき役割や使命もどんどん変化していくと想像しています。だからこそCHROとして、「人」を語り、「人」をいかに戦略に結び付けるかが、ますます求められると強く思いました。本日はありがとうございました。
東氏:CHROとして1年あまりが経ちました。昨年のセッションを振り返ると、この1年は社外からの学びをすごく求めていました。当社はスピード感をもって全社横断的なプロジェクトがいくつも進む中、定性的な側面と定量的な側面の矛盾を常に抱えています。その中で、考え方の軸をどう持つかが自分には必要でしたし、今も模索を続けています。だからこそ、社外に学びを求めましたし、これはCHRO自身が積極的に取り組むべきことだと思いました。本日はありがとうございました。
上杉氏:皆様に共通して、AIやテクノロジー、グローバル化を見据えて挑戦を続けている姿勢を強く感じました。人事領域でも、テクノロジー化が一層進みます。これは人の仕事を奪うものではなく、人力の作業を自動化したり、仮説提案を提示してもらえたり、業務を効率化できるようになると、ポジティブに捉えていただきたいです。人間にしかできないクリエイティブな仕事に集中できる環境が整ってきていますので、これまで以上に若い世代がHRの領域に進む機会も増えるでしょう。本日はその一端の話が聞けた気がします。本日はありがとうございました。
冨樫氏:本日のセッションから、HRの仕事は重たくも楽しく、同時に意義深くなってきていると感じました。未来を見据えつつ、正解のない状況で周囲を上手く巻き込み挑戦を続ける。また、さまざまなものを見極めながら、ぶれない軸を持つ。そういった「素敵」だと魅力的に思える人間性そのものが、CHROの役割なのだと感じました。本日は皆さま、貴重なお話をありがとうございました。
【昨年のセッションの模様はこちら】
先進企業3社と紐解く、変化する経営組織における「CHROの役割」とは