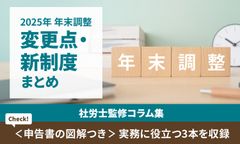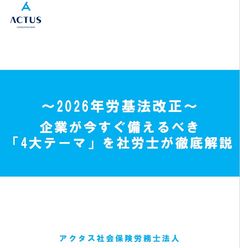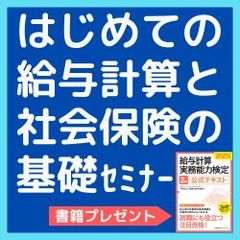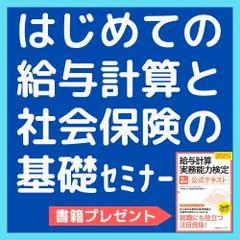月々の役員報酬が高いと「賞与の給与化」で保険料負担の軽減も可能に
「賞与の給与化」とは、賞与制度を廃止・縮小することによって生じた余剰資金を月々の給与に含めて支給する仕組みである。年間の収入は従前と変わらないため、制度を導入しても金銭的なデメリットは生じないとされている。また、企業の代表取締役などのように月々の役員報酬の水準が高い場合には、厚生年金の保険料負担が軽減されるケースもあり、手取り額が増加するメリットも享受できる。賞与と月々の給与や役員報酬とでは、保険料が賦課される仕組みが異なるからだ。
賞与の場合には、1回の支給額が150万円までに対して厚生年金保険料が賦課される。仮に、賞与が年に2回支給される企業で1回当たりの金額がいずれも120万円であれば、厚生年金保険料の本人負担分は「120万円×保険料率÷2」で計算された金額を年に2回支払うことになる。
一方、月々の給与や役員報酬の場合には65万円までに対して厚生年金保険料が賦課され、65万円を超える額には保険料が全く掛からない。例えば、月々の役員報酬が80万円でも、厚生年金保険料の本人負担分は「65万円×保険料率÷2」と計算される。65万円超80万円以下の部分に保険料負担が生じることはない。
このケースで賞与制度を廃止し、浮いた原資を月々の役員報酬に20万円ずつ割り振って支給したとしよう。この場合、月々の役員報酬は100万円(=従前の役員報酬80万円+賞与から割り振った額20万円)になる。しかしながら、月々の役員報酬は65万円を超える額には保険料が掛からないので、この場合の厚生年金保険料の本人負担額も「65万円×保険料率÷2」で決定される。その結果、年に2回の賞与に賦課されていた保険料額の分だけ、負担が軽減されることになるのである。
「保険料負担の軽減」は「年金減額」の裏返し
上記のように見てくると「賞与の給与化」は月々の役員報酬の水準が高い代表取締役などにとり、メリットの大きい人事施策のようにも思える。しかしながら、この施策には制度導入担当者の多くが見落としがちな重大なデメリットが存在する。「厚生年金保険料の負担が軽減されると、老後の年金額が少なくなる」ことである。厚生年金の老齢年金の金額は、『保険料の計算で使った給与・賞与の合計額』がいくらになるかで決定する。合計額が大きければ高額の年金が受給できるが、小さければ年金額も少なくなる。つまり、現役時代に厚生年金保険料をたくさん納めれば老後の年金受け取り額も高額になり、保険料納付が少なければ受給できる年金額も少ないわけだ。
仮に「賞与の給与化」によって賞与に掛かる保険料がなくなり、月々の役員報酬が増えたとしても役員報酬に掛かる保険料額が増加しないのであれば、その分だけ『保険料の計算で使った給与・賞与の合計額』は小さくなる。賞与制度を継続した場合に比べて納めた保険料が少なくなるのだから、将来の年金受給額も少なくなってしまう。
従って、企業の代表取締役はもちろん、給与水準の高い他の役員や社員についても、保険料負担が軽減された代償として年金額低下のデメリットを被る結果となるわけである。
保険料負担軽減の代償は小さくない
以下のような代表取締役の事例で、「賞与の給与化」の年金受け取り額への影響を具体的に考えてみよう。●引退年齢と年金受け取り:10年後の65歳で引退し、年金を受け取り始める。
●役員賞与:年に2回、1回当たり120万円
●役員報酬:月80万円
このケースで賞与制度を廃止すると、支給されなくなった役員賞与120万円は将来の年金額計算には全く反映されない。この状態が引退までの10年間継続するので、年金額計算から除外される金額は2,400万円(=120万円×年2回×10年)である。その結果、賞与制度を継続した場合と比べて減額になる年金は、年間で約13.1万円に及ぶ(2025年度現在の年金制度が継続するものとした場合の概算額。具体的な算出方法は割愛)。
一方、賞与制度を廃止したことにより軽減される厚生年金保険料の本人負担分は1年間で219,600円(=120万円×保険料率18.3%÷2×年2回)、10年間の累計額は219.6万円(=219,600円×10年)である。つまり、219.6万円の厚生年金保険料の削減ができた代償として、65歳から受け取る老後の年金が毎年13.1万円少なくなるわけだ。
この代表取締役が平均的な年齢まで生存した場合、年金減額の総額はどの程度になるだろうか。現在、65歳の平均余命は男性が19.52年、女性が24.38年なので(令和5年簡易生命表/厚生労働省)、毎年の年金額改定がないと仮定した場合には年金減額の総額は男性がおよそ255.7万円(≒13.1万円×19.52年)、女性がおよそ319.4万円(≒13.1万円×24.38年)と計算できる。
従って、代表取締役の性別にかかわらず、厚生年金保険料の削減額よりも年金減額の総額のほうが大きいことになる。とりわけ、平均余命の長い女性の場合には、年金減額によるマイナスの影響が顕著だ。

以上のように、「賞与の給与化」には報酬水準の高い代表取締役などが被りやすいデメリットが存在する。「企業の採用競争力の強化」と「個人の年金収入の確保」とを天秤にかけて企業の戦略を決定するのは、好ましい行為とはいえないかもしれない。しかしながら、本稿に示したような問題点があることは、念頭においておきたいものである。
●厚生労働省:令和5年簡易生命表の概況
- 1