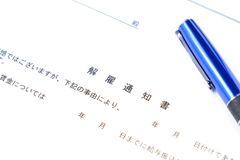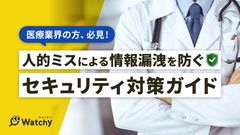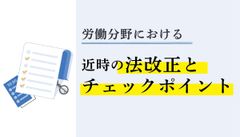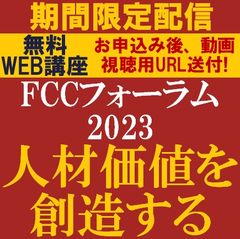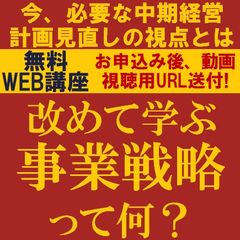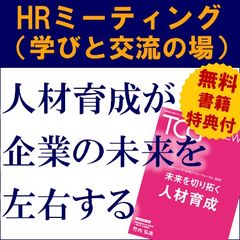社員から「就業規則をコピーしたい」と言われた場合の対応と問題点
まずは、就業規則の周知義務を定めた「労働基準法」106条1項を確認します。「労働基準法」106条1項では以下の「いずれかの」方法で周知することを義務付けています。(2)書面を交付すること
(3)その他の厚生労働省令で定める方法
したがって、「常時各作業場の見やすい場所へ掲示、又は備え付け」を行っていれば「労働基準法」106条1項の要件は満たしています。会社が社員の求めに応じて書面の交付をしなかったとしても、そのこと自体は法的に問題がありません。
しかし、書面の交付を行わない説明方法は適切でしょうか? 法律上就業規則の交付までは求められていないという説明だけでは、社員の不信感を招くことになりかねません。なぜなら、会社は就業規則の周知方法として「(2)書面の交付」も選択することもできる中、「(1)常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること」を選択しているからです。
就業規則は社員の労働条件や働く上での規則が書かれたものです。違反すれば懲戒処分を受けることもあります。「なぜ、手元に置いて確認できないのか」という疑問が生じるのは自然なことです。
そこで、社員が不信感を持たないためには、別の観点からの説明を同時に行うことが必要です。つまり、法的には就業規則の書面の交付が必要ないことを説明しつつも、同時に、「なぜ、書面の交付をしないと会社が決めたのか」を丁寧に説明することが必要なのです。
「就業規則の書面の交付をしない理由」の例
就業規則を書面で交付をしないことを決めた理由は企業ごとに異なるでしょうが、何らかの企業独自の理由があるはずです。例えば、以下のような理由が考えられます。理由例(1):最新版の就業規則を常に見て欲しい
就業規則は法改正や会社の制度変更に伴い定期的に改定されるものです。交付された古い就業規則が参照されて混乱を招くことを懸念する企業は多いです。その場合はコピーを認める形ではなく、毎年「○○年度版」という形式で一律交付を行えば、古い就業規則が参照されて混乱するというリスクは回避できます。しかし、その場合でも別の懸念を抱く企業は多いようです。就業規則は諸規程まで含めるとかなりの数になります。社員数が多くなると、毎年全てを書面で交付するのは現実的ではないという懸念です。
理由例(2):機密情報の保護
会社によっては、同業他社には知られたくない企業情報が就業規則に含まれていることがあります。例えば、独自の賃金制度が記載されている企業もあります。人事考課の手続が詳細に記載されている企業もあります。これらを機密情報として位置づけ、就業規則の書面の交付を行っていない企業もあるようです。「機密情報に該当しない部分の交付を認めればよい」とも思えますが、線引きが難しいという問題もあり、書面の交付は行わないとしている企業が多いようです。
人事労務の分野は「労働基準法」をはじめとした法律がありますので、会社の決定に法律上の問題はないと伝えることは必要です。しかし、会社が書面の交付をしないと決めた独自の理由があるはずです。その会社独自の理由を同時に丁寧に説明することが必要なのです。この2つがそろって初めて社員の不信感が払拭されることになります。
「就業規則の交付をしない」問題の根本解決を目指して
就業規則の交付をしないことにしたのなら、社員が書面の交付を求める根源的な理由に対処することも重要です。書面を求める理由を社員から詳しく伺うと、就業規則の内容が難解で理解できないケースが多いようです。そのため、就業規則を自宅で読んだり、第三者に相談したりすることで内容を理解したいとのことです。それならば、社員が就業規則の内容を完全に理解できる仕組みを会社が用意することで、就業時間外に自宅で就業規則を読む理由も薄れます。例えば、以下のような方法が有効です。
●年次有給休暇や残業など質問の多い事項に関するQ&A集を作成する
●就業規則の解説書を作成する
●定期的に就業規則の説明会や勉強会を開催する
●難解な用語を極力使用しない就業規則に変える
上記の取組は、就業規則の周知を超えた「就業規則の理解」を促す制度です。社員が労働条件を理解し、かつ、社内ルールが会社に浸透する良い機会になります。
もちろん、就業規則が実態に合っておらず、就業規則の内容自体を社員に説明できないという場合には、制度そのものの見直しが必要です。
- 1