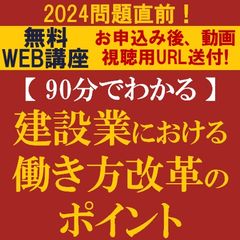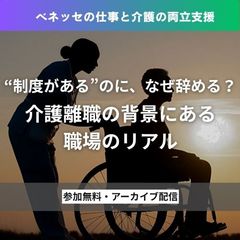「勤務間インターバル制度」とは「終業」と「次の始業」までを空けること
「勤務間インターバル制度」は、1日の仕事が終わってから次の仕事を始めるまでの間に、一定時間の休息(インターバル)を設ける制度のことです。たとえば、夜10時に仕事が終わったら、翌朝の出勤は午前9時以降にする、というような仕組みです。目的は、働く人がしっかり休めるようにして健康を守ることや、ワーク・ライフ・バランスを整えること。長時間労働や睡眠不足が当たり前になっている働き方を見直すための制度といえます。
この制度は、2019(平成31)年に「労働時間等設定改善法」が改正されて、企業に対しての努力義務になりました。
さらに国(厚生労働省/以下、厚労省)は、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の中で、2028(令和10)年までに導入企業を15%以上にするという目標を立てています。ただ、努力義務ということもあってか、実際に導入している企業はまだ5.7%(「令和6年就労条件総合調査」より)と少ないのが現状です。
「勤務間インターバル制度」導入のポイントは?
(1)現状を把握して導入の要否を決める
まずは、社員がどんな働き方をしているかの把握が必要です。勤怠システムのデータを見たり、ヒアリングしたりして、勤務時間や残業の状況をしっかり把握しましょう。例えば、ヒアリングなどの結果、長時間労働の実態もなく、実質的にインターバルが取れているような会社であれば、勤務間インターバル制度としてわざわざ設ける必要はないわけです。制度の導入の要否は、社風や組織風土といったものも関係してくるので、「なぜこの制度を導入するのか」という目的に立ち返ることも大事なポイントです。
(2)インターバル時間の決め方
「インターバルは何時間に設定すればいいですか?」とよく聞かれますが、これは企業によって異なると考えます。業種や勤務時間帯、通勤時間など、会社ごとの事情に合わせて決めるのが基本です。参考になるデータとして、労働安全衛生総合研究所の研究によると、勤務間インターバルが短くなるにつれてストレス反応は増加し、勤務間インターバルが11時間以下になると起床時疲労感と精神的不調は増加するという関連が明らかになっています。また、厚労省の「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)」では「9時間以上」を推奨しています。
これらのデータ等を関すると、企業の事情に合わせて「9時間~12時間」の範囲でインターバル時間を設定するのが妥当といえるでしょう。
さらにインターバル時間を決めるときのコツですが、「睡眠時間+生活時間+通勤時間」で考えるとよいです。例えば、「睡眠7時間、食事・入浴・家族団らんなど2時間、うちの会社の平均通勤時間は往復1時間。よって、10時間にしよう。」という設計の仕方です。
「勤務間インターバル制度」を運用するうえで気をつけたいこと
(1)安全衛生委員会の毎回の議題とする
導入したら運用状況を把握するようにします。そのために安全衛生委員会の議題にあげて審議することをおすすめします。実際にインターバルが取れているか、困っている人はいないか、課題は何か等を話し合って、必要に応じて制度を見直していきます。PDCAを回す仕組みがあると、制度が形だけで終わらず、しっかり現場に根づきます。(2)除外ルールを決めておく
どんなに制度を整えても、「緊急対応でどうしても出社しないといけない!」ということもあります。そういうときのために、“この場合は除外する”というルールを最初から決めておくと混乱を防げます。除外ルールの例としては、重大クレームの対応、突発的な設備トラブル、海外との時差に合わせたWeb会議などです。このような場合には定められた勤務間インターバルが取れなかったとしても問題なしとします。
注意点としては、除外ルールはあくまで例外的事例のため、限定列挙とすべきです。
(3)社外の理解も大事
意外と盲点なのが、顧客や取引先などの社外の理解です。「明日までに仕上げて!」という依頼が続くと勤務間インターバルがとれない状況になります。そこで、取引先や顧客に対して、勤務間インターバル制度を導入していることを説明したり、納期に余裕をもって発注してもらうよう依頼したりすることが必要な場合もあります。とはいえ、一担当者だけでは対応できないこともあるため、上司が説明をフォローすることも必要でしょう。
あるいは、「国がこういう制度を推進していて、うちの会社でも導入しています」という話を持ち出すと、理解が得られやすくなるかもしれません。
いずれにしても、社内だけではなく、社外も巻き込んだ活動になることも理解しておく必要があるでしょう。
- 1