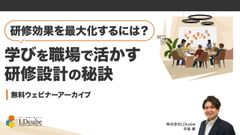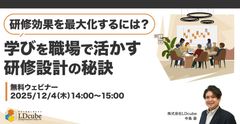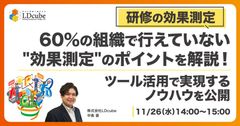――リモートワークを可能にするためにSaaSによるインフラ構築に着手したそうですが、どのようなゴールイメージを持っていたのですか。
三浦 まず、当社はベンチャーなので、できるだけ低コストで業務上の必要要件を満たす必要がありました。特にリモートワーク時に必要なコミュニケーション機能を重視したいと考えました。また、セキュリティ確保の観点から、社内にデータを置かないことも目標としました。
そこで当初はGoogleのG Suiteに、コミュニケーションツールのSlack、ビデオ会議システムのZoomなど、各種SaaSを組み合わせてインフラ構築をスタート。その後、クライアントのセキュリティ環境に合わせるためにもMicrosoft Office 365が必要であると認識しました。現在Office 365は、かつてのようにライセンスを購入するのではなく、サブスクリプション型の価格体系となっています。これはサーバー構築を自社で構築・運用する必要もなく、初期投資がほぼ不要だという点でも、当社のニーズに合致しました。
2019年1月にそれまでバラバラだったOA系ソフトウエアが統合・強化されたMicrosoft Teamsというビジネスツールがリリースされたので、当社では現在こちらを活用しています。こちらには、メール、スケジューラー、Officeアプリ、Skype for Business、OneDriveがシームレスに統合されており、文書作成だけでなく、メール、セキュアなビデオ会議システム、ファイル共有など、統一された機能環境で利用することができます。当社ではセールスフォースなど他のクラウドベースの業務システムも使うのですが、TeamsにはAzure ADというセキュリティ強化の高いIDプラットフォームを導入することで、他の業務システムとのログインID及びパスワードを共通化できる仕組みも付いています。つまり、これまでシステムエンジニアが苦労して作っていたのと同程度のシステムを、複数のSaaSを組み合わせて簡単に構築できるようになっているのです。ほかに現在は経理などバックオフィス用のマネーフォーワード、契約書管理のクラウドサインを順次導入中です。
――こうしたインフラ構築は、どのようなメンバーで企画されたのでしょうか。
三浦 元々私がITコンサルタントなので、基本構想は自分で考えました。親会社である株式会社ドリームインキュベータのITインフラ部門のスタッフの支援をいただきつつ、それぞれのSaaSサービスのベンダーからアドバイスを受けたりして進めています。導入時には一部作業の外注もしました。専任のIT担当者は置いていません。もはや、そのような時代ではないと思います。
――こうしたSaaSサービスは、例えばプライバシーマーク取得企業との取引に支障がないレベルで安全だといえるのでしょうか。
三浦 当社のクライアントは大企業も数多くあり、多くのお客様はプライバシーマーク取得企業です。当社としても、クライアントからセキュリティに関して問題ないか、という質問はよくいただいていますし、セキュリティ環境調査票も頂戴しています。そうした中で感じることは、SaaSというサービスをリリースするベンダーこそ、バックアップやウイルス対策、監査ログの取得など、セキュアな環境を担保していることであり、そうしたクライアントからの質問にも直ちに答えてくれ、その回答内容はクライアントにご満足いただくレベルのものであり、業務上支障はありません。
――実際にリモートワークを実践している社員からは、どのような声があるのでしょうか。
三浦 通勤時間をゼロにし、社員一人ひとりが働きやすい環境を構築するために会社としてのビジョンから制度、SaaSインフラ、人材マネジメントと総合的に取り組む中で、ワーママの就業率が全社員の半分を占めるようになりました。日本はもちろん、海外からリモートワークを実践する人もいます。例えば、マレーシアに1ヵ月間、子供と一緒に滞在している女性社員がいます。彼女はお客様満足度を上げるためのバックオフィス業務を担っているのですが、通常はMicrosoft Teamsで我々とコミュニケーションを取っています。つまり、自宅勤務と変わらない仕事を現地でこなしているのです。
本人からは、子供が二人いるため、出社が朝9時~夕方5時と定められていると、時短勤務をせざるを得ない。しかしながら、当社のリモートワークを利用すると、通勤に無駄な時間を取られることもないため、家事育児やお迎えなどもうまくバランスを見ながらこなすことができる、という意見をもらっています。フルタイムとして働きながら、主婦業もしっかりと両立しているようです。
――逆に、何かリモートワークをすることで困るといった意見はないのでしょうか。
三浦 バックオフィス業務の場合、直接外部の方と会わないと仕事ができないという状況はそうありません。通勤の移動がない分、生産性は上がっています。コミュニケーションが取りにくいのではないか、と思われるかもしれませんが、実際にはチャットを利用して雑談までできています。先ほどの女性社員はセールスフォース導入を担当していますが、ベンダーに対してもやりとりは全てオンラインで行っています。
こうした働き方の背景には、社員を労働時間で管理するのではなく、成果で管理をする、任せた役割を達成してくれればそれで良い、という考え方があります。実をいえば私も、まさかマレーシアに1ヵ月間滞在する社員が出てくるとは想定していませんでした。これこそ、社員が制度の趣旨を踏まえつつ、それを上手に利用してさまざまな働き方を実現しようとするアイデアが出てきている状態だと言えます。一人ひとりが自分らしい働き方を実践し、後に続く人達のお手本となっているのです。
リモートだと仕事をしないのではないか、と懸念する経営者、マネージャーは、自らのマネジメントの課題を自覚したほうが良いのではないでしょうか。社員が目の前にいたら仕事をしている、と考えるのは幻想です。
――リモートワーク導入の結果、これまでにどのような成果があがってきていますか。
三浦 通勤ラッシュがなくなった時点で、感覚的な話ですが、私はストレスが4割くらいカットできているのではないかと思っていますが、社員も自由な働き方を実現することで、元気になってくれていると同時に、「この環境を維持するために、お仕事でパフォーマンスを出していこう!」と逆に会社へのコミットメントが高まってきていることを感じています。
また、こうした働き方に好感を持って、人材も集まり始めています。最近、トップコンサルティングファームからの転職者を受け入れました。彼には、ふるさとで村おこしをやりたい、しかし家族を連れて地方に移住することは難しい、そして家族を養うためにも仕事はやりつづけなければならないという様々な思いがあったため、当社に「60%正社員」として入社してもらいました。「60%正社員」とは、労働時間も給与も60%だけれども正社員扱いで、人事評価や昇格昇進でもマイナスにならないという仕組みです。個人の事情に応じて、会社への関与率を60〜100%の間で選択でき、半年に1度、比率の変更もできるようにしています。
――ユニークな制度ですね。ただコスト面だけを考えると、60%勤務の人を正社員とすることは負担にはなりませんか。
三浦 そうなのですが、その分、通常であれば考えられないような優秀な人材の確保に繋がっていることも確かなのです。最近入社したCTO(最高技術責任者)も、「60%正社員」としてスタートしています。さらに九州在住の現役弁護士を法務担当者として採用することもできました。
私は、中小企業の場合、極めて優秀な人材を、一つの会社で抱え込むことには無理があると思っています。会社のコスト的にも、本人の能力的にも重すぎるのです。複数の会社で優秀な人材をシェアするような方向性が生まれると良いですね。そうなれば中小企業でも、より優秀な人材の確保ができます。
――最後に、働き方に対する思いなどがあればお聞かせください。
三浦 リモートワークが全て良いとはいわないにしても、救われる人が必ずいるという確信を持っています。「会社には通うもの」という既成概念を打破したい。そして当社が実践するワークスタイルが世の中に広がっていけば、子供を抱えるワーママの仕事と育児の両立、介護の親を抱える人の仕事との両立、そして東京に一極集中しているホワイトカラーの頭脳の地方活用など、社会的課題の解消にも繋がるのではと願っています。リモートワークを支えるクラウドインフラ環境が、これほどまでに身近な存在になっているという現実を、今回の取材を通じて認識させられた。また、通勤時間をゼロにし、社員一人ひとりが幸せになる働き方をする、といった目標を軸に、戦略に基づいたリモートワーク体制と、それを支える人事マネジメントがしっかりと絡み合うことで相乗効果を上げている様子を垣間見ることができた。自由な働き方を楽しみながら模索している様子は、まさに社員一丸となって「ワークスタイルラボ」という社名そのものを体現しているようであった。
株式会社ワークスタイルラボ