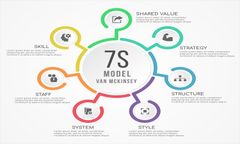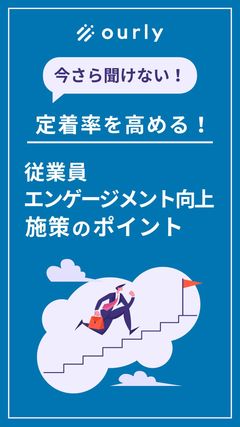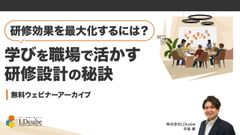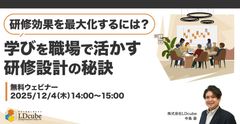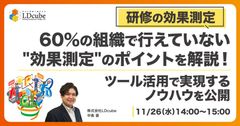――では、今回HRテクノロジー大賞を受賞された社員エンゲージメントサーベイ「BE Heard」の概要について教えてください。
井上多恵子氏(以下、井上) 「BE Heard」は、当社グループ全体の約半数を占める、エレクトロニクス事業とゲーム事業の約6万名にわたるグローバル社員を対象にしています。アメリカのGlint Inc.(グリント)社が提供するサーベイを導入し、毎年秋に3週間の期間を取って18か国語で34問による調査を実施。調査終了翌日から各社の経営層、人事、現場マネジャーの計約6,000人に分析結果をクラウド上で提供するというものです。分析結果だけでなく、今後どういった施策を講じるといいかといったサジェスチョンも表示されます。これらを踏まえ、各部門にてマネジャーは、社員と議論や対話を行い、エンゲージメントを強化するアクションを行います。こうした活動をサポートするためのマネジャー向けトレーニングも実施しています。また、対話や改善アクションのユニークで効果的な活動をサクセスストーリーとして取り上げ、社内に広く共有。さらに、社員の匿名性を担保した上で、社員の声を分析し、他の人事施策との相関を分析するなど、より有効な人事制度づくりに繋げていく取り組みを行っています。
――「BE Heard」導入に至るまで、何か課題があったのでしょうか。
井上 2011年より毎年1回、コンサルティング会社に委託して社員意識調査を行ってきました。しかし、その調査には、いくつかの改善すべき課題がありました。
一つは、結果を見られるまでに3ヵ月ほど時間を要したことです。あまりにも長すぎるので、オペレーションの簡素化など工夫を施して4週間に短縮しました。それでも、現場からは「せっかく社員の声を聞いても、結果が出る頃には考えが変わっている可能性もある」といった意見も出ていました。また、設問は全部で60問強あり、まんべんなく質問しているのでどこに課題があるのかにフォーカスしにくいという点も問題でした。
もう一つが、分析の柔軟性です。当社では頻繁に組織変更が行われますが、これまでの調査結果は人力で集計するものでした。そのため、比較対象となる過去データを新しい組織に対応させたり、いろいろな角度から切り出したりするのが難しいという問題もあったのです。ですから、多様な社員の声を的確に捉え、経営に役立つインサイトを得にくいという課題がありました。
もちろん、グローバル全体や各社ごとに大筋の社員意識は掴めたのですが、各現場としては「各現場に適した施策をと言われても、部門ごとに事情は違う」と受け止められ、ポジティブな取り組みに繋げにくい状態にありました。分析結果は各社の経営層や幹部層、および人事部門に利用が限られていました。したがって、健康診断的に組織全体の社員の意識傾向を知るだけにとどまりやすいものになっていました。一部の社員からは「現場の声は本当に届いているのか?」という疑念の声も上がっていました。
そこで、2016年に抜本的に改善させるためのプロジェクトを立ち上げました。全世界のグループ企業の人事ネットワークを通じて優れたエンゲージメントサーベイを一緒に行うパートナーを探したところ、Glint Inc.社を紹介され、「BE Heard(Glint Inc.社の商標ではなくソニー社内での名称)」を2017年に導入することに決めたという流れです。
――Glint Inc.社のどのような部分にテクノロジー上の革新性を感じたのでしょうか。「BE Heard」として調査設計した際に工夫したことは?
井上 最も重視したのは、社員のデータを扱う上でのセキュリティです。そこで、社内のセキュリティ専門チームを巻き込み、厳重な要件を出しましたが、Glint Inc.社はこれをクリアーしました。次に求めたのは、結果を集計するスピードです。この点はリアルタイム、つまり社員が回答しているそばから結果が見られることから、高く評価しました。ベンチマークすべき他の企業のデータを持っている点、組織心理学の知見を豊富に持つこともメリットを感じました。さらに、同社のミッションとして掲げている”Our mission is to help people be happier and more successful at work. (我々のミッションは人々が職場でよりハッピーに成功できるように支援すること)”が、社員を大事に扱うという当社の方針に合致したことも導入要因になりました。
橋本 ソニーの経営戦略・人事戦略に合致するように独自設問とGlint Inc.社の設問を組み合わせて調査設計を行いました。以前の社員意識調査の設問は60問強ありましたが、Glint Inc.社に移行するにあたり、人事内のデータサイエンティストのメンバーに協力してもらって独自に設問を多変量解析して類似の結果がでる設問を排除し、34問に絞り込みました。ちなみに設問は「働きやすさ・働きがい」「会社への信頼」「キャリア・成長」を含む5つのカテゴリーを設定しています。
――2019年で導入3年目となりますが、これまでにどのような成果が上がっていますか。
橋本 リアルタイムに結果が見られるという点で、「今起きている問題」をマネジャーに認識してもらう効果を感じています。ある大きな法人の社長が自らサーベイの結果と社員のコメントを読み込み、経営陣と人事部門が一体となって多くの施策を実施するなど、マネジメントの意識を高める効果がすでに出ています。
――このような取り組みを実施することで、社内から何か反響はありましたか。
井上 以前の社員意識調査では、調査結果を利用するのが一部の経営層や幹部層、人事部門に限られていました。しかし、「BE Heard」ではテクノロジーの力で約6,000人もの現場マネジャーにリアルタイムにデータを提供できるようにできたことが非常に大きいと自負しています。データサイエンティストにしかできないようなエンゲージメントを高める要因分析やコメントの自然言語処理を、広くマネジャーや人事に提供できるようになったのです。今後は、これを利用してよりよい組織に改善していく活動に取り組むマネジャーが増えることを期待しています。分析ツールを使いこなしているマネジャーからはポジティブなコメントをもらっています。
橋本 エンゲージメント向上のための人事制度や施策も改善も強化しています。Glint Inc.社のサーベイ結果から、独自に他の人事施策との関連性も解析しました。例えば、当社では直属の上司に断りなく社内のポジションに応募し異動できる、50年以上の歴史のある社内公募制度があります。その制度を利用する前と後では、エンゲージメントの度合いに明確な差異が認められました。応募する社員は異動後に大きくエンゲージメントが高くなる傾向がみられました。また、社内セミナーやイベントに積極的に参加する社員は、エンゲージメントが高い傾向が読み取れます。これまで、こうした制度の効果は簡単なアンケートや個別の聞き取り調査で確認してきたのですが、この分析でこれまでわからなかったことが可視化できました。これを他の制度にも応用し、より有効な人事制度や施策に繋げていこうと考えています。
――今後の展望についてお聞かせください。
井上 「BE Heard」によるサーベイは、一つのきっかけに過ぎません。重要なことはそれぞれの現場のマネジャーがメンバーとの継続的な対話を通じてエンゲージメントの向上に繋がる“アクション”を継続的に実施すること。我々人事部は、その動きを促進させることに努めなければならないと考えています。当社の経営においては「問題を先送りしない」ことを方針に掲げており、社員から「自分たちの声に即座に応えてほしい」という期待値に応えられるよう組織風土改革を進めていきたいと思います。
橋本 当社は、Glint Inc.社のユーザーの中で、日本にヘッドクオーターを置くグローバル企業の第1号だそうです。クラウドサービスの特徴としてユーザーベースが増えるとユーザー同士で協力して改善ができます。今後、当社のような日本企業のユーザーが増えることも期待しています。加えて、入社、退社などの社員のライフサイクルに沿った調査、各部門がベストなタイミングで行う独自調査など調査の種類も拡大し、「科学する人事」として社員の声を経営や人事施策にもっとダイレクトに反映させ、「Employee Experience(社員体験)」をより良いものにしていきたいと思います。グローバル企業のソニーには、主力のエレクトロニクス事業とゲーム事業だけで、世界のグループ企業全社員の半数を占める約6万人が在籍しており、サーベイ結果を利用するのは、マネジャー層約6,000人、人事スタッフ約600人だそうだ。この規模に対して、エンゲージメントサーベイを運営し実効に繋げていくのは容易なことではない。その点で、調査結果をリアルタイムで提供できるテクノロジーの力は大きく、Glint Inc.社をどこよりも早く導入したソニーの情報収集力や進取の精神が光る。さらに、テクノロジーを使いこなして設問設計やデータ解析を独自に行い、有効な人事施策に繋げている点でもその取り組みは高く評価できるだろう。
ソニー株式会社