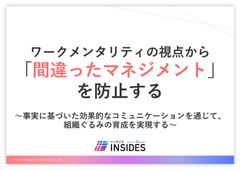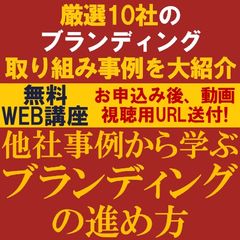会議後の「釈然としない空気」の正体
最近、多くの企業でファシリテーションの重要性が認識され、プロジェクトなどの会議にファシリテーターを配置することが一般的になってきました。社内の調整の役割も担う人事部門には必要なスキルだと思われます。ところが、ファシリテーターの役割は誤解されがちです。会議の進行役ではありません。形式的に話をまとめる役割でもありません。参加者全員が納得できる合意形成を支援することが本来の役割です。
本記事では、対照的な会議例を通して、ファシリテーターの役割、及び「真の合意形成とは何か」を考えてみたいと思います。そして、最後に、就業規則の専門家として、これまで多くのクライアント企業の労務問題の会議に参加してきた立場から、真の合意形成に至るポイントを解説します。
労務問題の会議では、激しい議論が交わされる現場を数多く経験してきました。そうした会議でこそ、本記事の内容が有益だと考えています。
プロジェクトメンバー選定を巡る対照的な会議の「事例その1」
田中さん「山田さん(若手社員)を、このプロジェクトに推薦します」佐藤さん「いや、まだ経験が浅すぎます。他の人選を考えた方が良いですよ」
話がまとまりそうもありません。そこで、ファシリテーター(F)が対話を促進するため質問をしました。
F「なぜ、田中さんは、若手の山田さんを推薦されるのですか?」
田中さん「最近、関連する業務で良いアイデアを出しているからです。今回のプロジェクトにぴったりです」
F「それならば、今回は、田中さんの言うとおりにしてはどうですか?」
佐藤さん「いや、重要案件ですよ。なぜ、経験の浅い人間を?」
F「確かに、プロジェクトが失敗につながるリスクはあります。しかし、田中さんはそのリスクを覚悟の上で今回のプロジェクトのメンバーに山田さんを推薦しているのです。責任を取るつもりでなければできない発言です」
佐藤さん・田中さん「……」
佐藤さん「確かに、その通りですね。」
田中さん「……」
佐藤さん「今回は、田中さんの覚悟を無駄にしてはいけませんね。山田さんが素晴らしい人材であることは間違いないことですし」
田中さん「……」
上記によるファシリテーターの問題点の検証と「事例その2」
上記の事例では、ファシリテーターが「推薦者の責任」という話を持ち出したことで、本来とは違った方向へ会話が進むことは容易に想像ができると思います。合意形成とは「誰か1人の優れた意見を採用する」というものではありません。田中さんと佐藤さんの対話が促進されて、互いの意見を活かした合意に至るというものです。以下の事例をご覧ください。田中さん「山田さん(若手社員)を、このプロジェクトに推薦します」
佐藤さん「いや、まだ経験が浅すぎます。他の人選を考えた方が良いですよ」
議論が平行線を辿りました。そこで、ファシリテーター(F)が会議を促進するため質問をしました。
F「なぜ、田中さんは、若手の山田さんを推薦されるのですか?」
田中さん「最近、関連する業務で良いアイデアを出しているからです。今回のプロジェクトにぴったりです」
F「佐藤さんは、山田さんが良いアイデアを出していることについてどうお考えですか?」
佐藤さん「評判は聞いています」
F「今回のプロジェクトでそのアイデアが活かされたら、プロジェクトはどうなりますか?」
佐藤さん・田中さん「成功すると思います」
F「それなら、参加すること自体には誰も反対していないのですね?」
佐藤さん「そうですね。しかし、中核のメンバーとして参加するのは反対です」
田中さん「いえ、私はアシスタントとして勉強のために参加してもらう形が良いと思っていたのです」
佐藤さん「そういう形なら、私も賛成です」
全ての会議が和やかなわけではありません。会社の重要なプロジェクトであれば、何日も前から意気込んでくる方もいらっしゃいます。では、こうした場面で真の合意形成を実現するには、どのような点に注意すべきでしょうか。
合意形成に至るには、共通認識と対立点の明確化が必要
先ほどの2つの事例はどちらも「合意形成」には至っていますが、その違いは明らかです。真の合意形成とは参加者が納得することです。そのために必要なプロセスは、共通点と対立点を明確にすることです。共通認識を明確にすることが大切です。今回のケースでは山田さんが良いアイデアを持っていて、活かした方がプロジェクトの成功に役立つという点については共通認識があります。
●対立点を明確化
しかし、佐藤さんは田中さんが「山田さんの中核メンバーとしての参加」を提案していると思い込んでいました。実際には、田中さんは「アシスタントとしての参加」を考えていたのです。このように、両者の認識にずれがありました。佐藤さんが誤解してしまった理由は山田さんが優秀であったことに起因します。
多くの会議では、このような認識のずれに気づかないまま議論が進められがちです。2つ目の会議例では、ファシリテーターの問いかけにより、この認識のずれが明確になり、参加者同士の対話が促進され、自然な形で合意形成に至っています。
今回のケースでは、元々、田中さんは中核メンバーでの推薦を考えていなかった事例です。仮に、中核メンバーとしての推薦を考えていた場合、この過程を丁寧に進めていっても合意に至らないケースも出てくるでしょう。その際、本質的な部分での対立が浮き彫りになることもありますが、それは、組織として大切なことが判明したということになります。
その本質部分をすり合わせるのか、違いを認めて共存の形を探るのか、組織としての意思決定が必要になります。
なお、参加者が納得していないまま進んだ「形式的な合意」は、プロジェクトの途中で思わぬ深刻な対立を生むことがあります。最初の段階で、どこで共通認識があり、どこに対立点があるのかを明確にしておくことが、後のトラブル防止につながります。
- 1