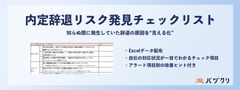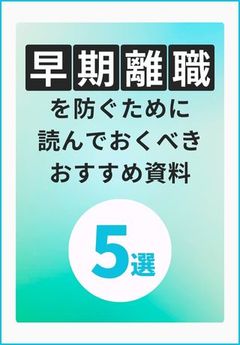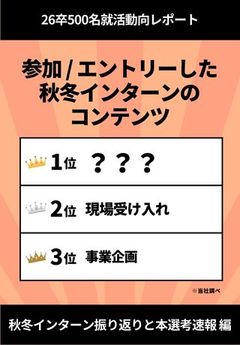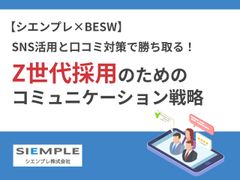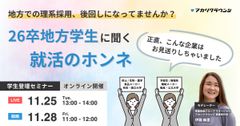HR総研では、今年も就活会議株式会社が運営する就活生向けクチコミサイト「就活会議」と共催で、2026年卒採用を実施した企業の新卒採用担当者と2026年卒の就活生を対象として、これまでの採用活動や就職活動を振り返って、それぞれの目線からの印象深いエピソードをテーマにした「2026年卒 採用川柳・短歌」と「2026年卒 就活川柳・短歌」を6~7月に募集しました。
1995年以降、長らく企業の大卒初任給の伸びは極めて低調傾向にありましたが、2023年以降、少子高齢化や優秀な新卒学生の獲得競争の激化から、初任給の引き上げに動く企業が増えています。それも数千円程度といったレベルではなく、大企業を中心に数万円~十万円レベルでの引き上げを実施したところも少なくありません。今年の応募作品では、「初任給引き上げ」に関する作品が幾つか見られましたが、面白いことに、このテーマを取り上げているのは採用担当者だけで、就活生からの投稿には見られませんでした。「初任給引き上げ」は、当事者である学生よりも既存社員のほうにインパクトがあったようです。そのほか、「生成AIの進化」や「内定辞退」などを扱った作品が数多く見られました。
今回は、その中から着眼点がユニークなもの、ユーモラスに表現されたものを入選作品として紹介します。ぜひご一読ください。

賃上げ、AI、採用難に揺れる人事の叫び
まずは、採用担当者による「2026年卒 採用川柳・短歌」の入選作品から紹介します。【最優秀賞】からです。基本給 低いと言われて ベア検討 社内の声より 学生の声(大阪府 ポテトさん)
今年の最優秀賞は、近年の初任給引き上げラッシュと売り手市場を象徴する作品が選ばれました。面接の場で学生から自社の給与水準についてストレートな指摘を受け、慌ててベースアップを検討するという、人事にとっては冷や汗ものの光景が目に浮かびます。これまで賃上げ交渉の主役は労働組合であり、その交渉は社内の論理や業績見通し、要員計画などに基づいて行われてきており、多くの場合、“ベアの検討などとてもできるようなものでない”と経営からスルーされてきたにもかかわらずです。
しかし、この作品が示すのは、そのパワーバランスが大きく変化し、“外圧”、すなわち採用市場における学生の声が、経営の重要判断項目の一つである賃金改定の直接的なトリガーになっているという驚くべき現実です。長年会社に尽くしてくれている社員の声よりも、まだ見ぬ学生の声が優先されることへのやるせなさを滲(にじ)ませつつ、それなくしては優秀な人材を確保できないという切迫感が伝わってきます。採用担当者の悲哀と企業の生存戦略が凝縮された、まさに時代を切り取った作品と言えるのではないでしょうか。
続いて【優秀賞】の2作品です。
積み上げた 俺の処遇を 一瞬で またぎ越えてく 爆上げ初任給(東京都 がんも3号さん)
最優秀賞の作品と対をなすように、賃上げのもう一つの側面、すなわち既存社員の不満を見事に詠んだ一首です。苛烈な採用競争に勝つために、多くの企業が初任給の大幅な引き上げに踏み切っています。その結果、入社以来、長年かけて積み上げてきた、あるいはそれ以上の金額を、入社間もない新人が手にすることになるとは——。初任給の引き上げに伴い、多くの場合、既存社員の処遇も見直されることになるものの、勤続年数の浅い若手社員には手厚く、長年会社に貢献してきた中堅・ベテラン社員の給与の上げ幅はごくわずか……という現象が各地で起きています。中には、既存社員の待遇改善にまで手が回らず、初任給のみを引き上げた結果、年代間での給与の逆転現象が起きている例もあるようです。
自らが採用した新人が、自分の長年の努力をいとも簡単に飛び越えた処遇を得る。その事実を目の当たりにしたときのやりきれなさ、虚しさ、そして会社への不信感までもが「またぎ越えてく」という強い言葉で表現されています。採用の成功の裏で、リテンションという新たな、そしてより深刻な課題が生まれていることを、われわれは認識しなくてはなりません。
語るほど 履歴書と違う その理由(わけ)は AIですと 君は言わずに(東京都 ねぎさん)
生成AIの進化が近時の就職・採用活動に与える影響を巧みに切り取った作品です。流暢(りゅうちょう)に志望動機や自己PRを語る学生。しかし、その言葉はどこか借り物めいていて、エントリーシートに書かれた美辞麗句との間に整合性はなく、語れば語るほど埋めがたい溝は大きくなっていく。面接官は、その違和感の正体が“生成AI作だからではないか”と確信に近い疑念を抱いています。エントリーシートとの食い違いを指摘しても、“自分の中では同じだ”の一点張りで、もはやそれをさらに問いただすすべはありません。「君は言わずに」という下の句が、核心には触れられないもどかしさと、学生・採用担当者間で行われる静かな探り合い、高度な心理戦を物語っているといえます。
生成AIが作った文章や回答そのものが否定されるのではなく、それを自分の言葉としてどう“血肉化”しているのかが重要で、その背景にある本人の思考や経験こそが面接の場で問われるべきでしょう。AIとの共存が前提となった現代における、“人間性の見極め”という採用の原点にして永遠のテーマを、われわれに突きつける一首です。