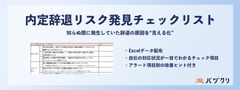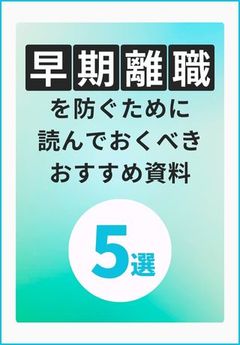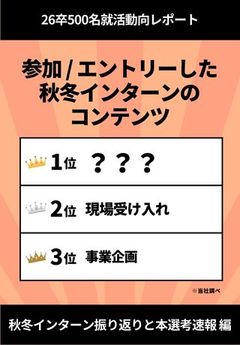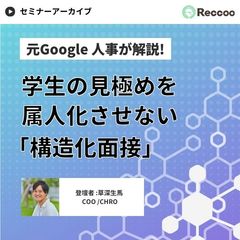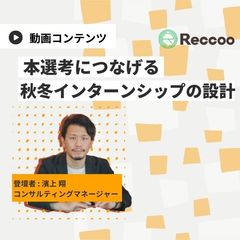「内定者研修」とは
「内定者研修」とは、新卒採用の内定者を対象として入社前に実施する研修だ。企業概要や社会人として必要なマナー、基本的なスキルを学んだり、ビジネスパーソンとしての意識を醸成したりする場として位置付けられている。内定者の不安や悩みの解消にも大きな効果が期待できる。【内定辞退でお悩みの方、内定者研修をご検討の方へ】内定者フォロー(新卒採用)に関するお役立ち資料やセミナー情報はこちら >>
●「内定者研修」の時期と頻度
一般的に「内定者研修」は、正式内定の10月から翌年4月の入社までの6カ月間で実施される。近年は就職活動のスケジュールが前倒していることもあって、単発ではなく、時期を分けて複数回実施する企業が増えている。中には、10月1日の内定式よりも前に行うケースもあったりする。いずれであっても、それぞれの時期に見合った目的や研修内容を組み立てる必要がある。【HRプロ】でできること、詳しい活用方法はこちら >>
「内定者研修」の目的
「内定者研修」を行う目的は、以下の通り3点挙げられる。●内定者の疑問や不安の解消
内定者は、内定通知が出た後でもさまざまな疑問や不安を抱えている。当然ながら、それらを解消することができれば、内定者は安心して入社できる。例えば、どんな仲間と一緒に働くのかがわかるようなプログラムを工夫すれば親近感が高まるし、仕事への意欲も向上するはずだ。●内定辞退の防止
近年は、内定辞退や入社後の早期離職に対するハードルが下がっている。中には、転職を前提に就活している学生もいたりする。企業としては、採用に多大な労力とコストを要しているだけに、内定辞退や早期離職のリスクを避けなければならない。だからこそ、内定者を積極的にフォローする必要がある。その手段として「内定者研修」が有効となる。●内定者のマインドセットやスキルアップ
採用競争がますます激化しているだけに、優秀な人材を確保するのが困難になってきている。なので、採用した人材に早い段階から活躍してもらえるよう育てていくことが重要だ。その意味でも、「内定者研修」が果たす役割は大きい。内定者の就業意欲を高めると共に、入社までに社会人として求められるマインドやビジネススキルなどを身に付けてもらえれば、本人も自信を持てるし、即戦力としての活躍も期待できる。近年の新卒内定者に見られる傾向
近年の新卒内定者には、さまざまな傾向が見られる。主な傾向を紹介しよう。●自発的な挑戦より安定を求める傾向がある
近年の新卒内定者は、真面目で指示には従いやすい傾向があるが、一方で自発的に挑戦する意欲はやや控えめと言える。安定志向が強く、リスクを避けたがるため、創意工夫や積極的な提案などの自発性を発揮する点が課題になることがある。企業としては、挑戦を促す環境づくりを図ったり、メンター制度を実施したりすると効果的だろう。●失敗や注目を避ける傾向がある
近年の新卒内定者は失敗を恐れるあまり、無難な行動を選ぶ傾向が強いと言われている。周囲からの評価や注目を過度に気にし、リスクを伴うチャレンジを控えるケースが多いと言う。そのため、成長の機会を逃しやすく、また問題解決力の習得に時間がかかることがある。企業には、失敗を許容し、学びを促す風土づくりが求められる。●コミュニケーションスタイルの変化
オンライン面接やリモートでのコミュニケーションへの対応力が高く、デジタル上でのやり取りに慣れているのは新卒内定者の特徴だ。一方で、リアルな場面での交渉や雑談、臨機応変な場面での応答が苦手な面が見られる場合もある。●ITリテラシーが高い
年の新卒内定者は、デジタルツールやITスキルを抵抗なく使いこなす。基本ツールだけでなく、オンライン学習プラットフォームを活用し、新しい技術を学ぶ意欲も高い傾向だ。企業のDX推進における即戦力として期待できる。●報酬よりも成長環境を重視する
給与水準以上に「成長できる環境」や「自己実現が可能な職場」を重視しがちなのも、近年の新卒内定者に見られる傾向の一つだ。自身のスキルアップやキャリア形成ができるかどうかを軸に企業を選ぶため、成長支援体制や研修制度の充実、キャリアパスの明示などが求められてきている。新卒内定者が感じやすい不安や課題
内定者が抱く不安や課題を解消するには、まずはその実態を把握しておかないといけない。●職場で上手く馴染めるかどうかの不安
選考を通じて会社の雰囲気は、何となく理解しているとは言っても、「職場に馴染むことができるのか」「人間関係が上手くいくだろうか」という不安は誰もが持つはずだ。入社する側の努力も欠かせないが、受け入れ側からも積極的に働きかけるようにしたい。●入社先選びが正しかったのかという迷い
転職者が多くなって来たとはいえ、まだまだ多くの人にとって会社選びは、人生において大きな決断の一つと言える。「この会社に入社する」と決めたとしても、その判断が正しかったのかと迷ってしまうものだ。●仕事内容や企業理解が浅いための不安
就職活動中に企業研究はある程度してきたとは言え、インターネットなどを通じて知り得るレベルとなると、浅くならざるを得ない。「本当に安心できる企業なのか」「どんな仕事をするのか」「仕事についていける能力があるだろうか」などという気持ちがどうしても芽生えてくる。●配属先やキャリア形成の見通しが立たないことへの不安
「入社後、どんな部署に配属されるのかわからない」「希望しない部署かもしれない」「自分が将来どうなりたいのかも思い描けない」など、配属先やキャリア形成に関する不安や悩みも良く聞かれる。●社会人として通用するかどうかの自信のなさ
「採用されたものの自分が活躍できるかどうか自信がない」という不安を抱く内定者も多い。背景にあるのは、“自己効力感”の不足だ。特に、学生時代に成功体験があまりない場合には猶更だ。自信をなかなか持てなかったりする。●生活環境が変化することへの不安
社会人になるにあたって、多くの人々は生活環境が大きく変化するはずだ。「慣れ親しんだ場所を離れて寂しくならないだろうか」「仕事に追われ、プライベートを確保できなくなるのではないか」などと不安を抱いてしまう。「内定者研修」で達成したい目標・ゴール
ここでは、「内定者研修」を通じて達成したい目標やゴールを考察したい。●学生から社会人への意識転換を促す
内定者期間は、社会人になるための準備期間と位置づけられている。それだけに、「内定者研修」では、内定者に学生と社会人としての意識の違いや働くことに対するマインドを醸成したい。自立して働く大切さを早くから認識しておけば、入社後の成長もスムーズとなるはずだ。ひいては、自身が目指す理想のビジネスパーソン像を描きやすくなるし、入社する企業や組織への帰属意識も高められる。●基本的な社会人スキルを習得する
「内定者研修」を行う狙いとしては、社会人としての基本スキルの習得もある。内定者に社会人として順調なスタートを切ってもらうためにも、入社前に社会人としてのマナーや文書作成力、基本的なPCスキルをぜひ身に付けてもらいたい。現場としても、基礎力を持った社員であれば受け入れやすい。入社後にどこまでのスキルを備えておけば良いかを考え、そこから逆算して研修内容を検討していこう。●チームワークや人間関係を構築する
仕事を進めていく上で、何よりも重要となるのはチームワークだ。その大切さを認識してもらうためにも、「内定者研修」は有益な機会となる。先輩や同期とのコミュニケーションを通じて、仲間とのつながりを意識するとともに、チームワークを醸成するためのコツを体感的に得ることができるからだ。内定者の不安解消にもつながってくる。●入社までの期間に主体的な学びを習慣づける
「内定者研修」を通じて会社の事業内容を理解することで、内定者は入社前にどのような知識やスキルを身に付ければ良いのかをイメージしやすい。入社までの期間を活用して自己学習しておけば、早くから業務にも慣れることができるだろう。また、主体的に学ぶ姿勢が身に付いていたら、その後の成長が大いに見込める。「内定者研修」の内容
ここでは、「内定者研修」を行う際の内容について触れておきたい。●会社や事業の理解
内定者は、就職活動中に企業研究を行っているため、会社や事業に関して一定レベルの理解はあるはずだ。だが、それらはインターネットや企業から配布された資料などを通じて得た情報が大半だ。よりリアルな情報、生の情報に触れることができれば、入社への期待感が高まるであろうし、自分が活躍する姿も思い描きやすくなる。そのためにも、「内定者研修」では、企業のビジョンや価値観、業務内容をより丁寧に伝えるようにしたい。・経営層からの事業説明、経営方針プレゼンテーション
・工場・店舗・オフィスの現場見学ツアー
・各部署の業務紹介と質疑応答セッション
・企業理念・価値観に関するグループディスカッション
・競合他社との比較分析ワークショップ
・会社の歴史や創業精神を学ぶドキュメンタリー視聴
●同期入社や先輩社員との関係性構築
内定者同士はもちろん、先輩社員との関係性を築ける内容をぜひ検討したい。同期とのつながりができると安心感が持てるし、「疑問や悩みを抱いているのは自分だけではない」とわかれば、心理的な負担が軽減できる。また、先輩社員の話を聞いたり、個別に質問できる機会があれば、ロールモデルをイメージしやくなる。自ずと、内定者のモチベーションも高まってくることであろう。・アイスブレイクゲームや自己紹介タイム
・チームビルディングアクティビティ(脱出ゲーム、料理実習など)
・先輩社員との座談会、メンター面談
・入社1〜3年目社員によるキャリア体験談発表
・内定者同士のプレゼンテーション大会
・懇親会、食事会の開催
●社会人としての心構えやビジネスマナー
社会人になるためには、心構えやビジネスマナーは欠かせない。できれば、内定の段階でそれらを醸成しておきたいものだ。しっかりと習得できていれば、周囲からの信頼を得られやすくなる。・名刺交換、挨拶、お辞儀の実践練習
・電話応対・来客対応のロールプレイング
・敬語、丁寧語の正しい使い方講座
・服装、身だしなみチェックとアドバイス
・時間管理、スケジュール管理の基本
・社内外でのコミュニケーションマナー研修
●基本スキルの習得
どの仕事であっても、社会人であれば必ず求められる基本的なスキルがある。具体的には、ビジネス文書の作成スキルやコミュニケーションスキル、プレゼンテーションスキル、ExcelやWord、PowerPointなどを使いこなすためのPCスキルなどだ。それらを習得するための研修プログラムもぜひ取り入れたい。・Excel基礎〜応用(関数、ピボットテーブル、グラフ作成)
・Word文書作成(議事録、提案書、報告書の書き方)
・PowerPointプレゼンテーション資料作成
・メール作成、文書作成の基本ルール
・タッチタイピング練習、PCショートカット活用法
・Googleワークスペース・Teams等の協働ツール操作
●論理的思考・課題解決演習
論理的思考も社会人にとっては不可欠なスキルと言える。ビジネスのあらゆる場面で、自分の意見や考えを論理的に整理し、相手に分かりやすく説明することが求められるからだ。ただ、入社前の内定者に理論を説くだけでは興味を持ってもらえないだろう。グループ演習を通じて、身近なテーマを考察しあうという仕掛けを工夫し、楽しく学べるようにしたい。・ロジックツリー、MECEの実践演習
・ケーススタディ分析(企業の課題解決シミュレーション)
・フレームワーク活用法(3C分析、SWOT分析など)
・ディベート大会、グループディスカッション
・問題解決ゲーム、謎解きチャレンジ
・仮説思考・検証プロセスの体験学習
●コミュニケーション力の強化
仕事が有能な人は、短い時間であっても相手に物事を的確に伝えることができる。内定者期間中にコミュニケーション力や文書作成力、プレゼンテーション力を強化しておくことで、入社後の評価が得やすくなる。・1分間スピーチ、エレベーターピッチ練習
・模擬プレゼンテーション大会(相互フィードバック付き)
・傾聴スキル、質問スキルのロールプレイング
・会議での発言、ファシリテーション体験
・ストーリーテリング、説得技法の学習
・異なるタイプの相手への伝え方実習
●情報収集力と経済動向への理解
ビジネスパースンにとって情報収集力も重要だ。インプットの量・質はアウトプットの量・質に密につながってくるからだ。そのためにも、「内定者研修」を通じて情報収集力をいかに身に付けるかを学んでおきたい。特に、国内および海外の経済動向や社会トレンドに関する情報は抑えておきたい。「内定者研修」が、経済新聞を読む習慣付けるきっかけにもなるだろう。・日経新聞、経済紙の読み方講座
・業界動向レポート作成、発表
・ニュース解説、時事問題ディスカッション
・情報収集ツール活用法
・市場調査、競合分析の基本手法
・経済指標の見方、読み方セミナー
効果的な「内定者研修」を実施するポイント
効果的な「内定者研修」を行うために、押さえておきたいポイントを4点紹介しよう。●それぞれの内定者の特性やスキルを把握する
まずは、アンケートや課題提出などにより、内定者の特性やスキルを把握することだ。選考や面接を通じて知る情報だけでは十分に把握できていなかったり、内定者の特性が徐々に変わっていたりする。どのようなキャリアを志向しているのか、何に対して苦手意識を持っているのか、強みや弱みがどこにあるのかなど、内定者の現状での傾向やスキルを正確に把握することで、それらをフォローするためのより有益なテーマを設計することができ、配属先の決定にも役立つ。●現場で必要なスキルや行動指標を把握する
「内定者研修」の内容を設計する際には、現場の声を反映させるようにしたい。内定者を受け入れ、育成するのは現場の先輩であるからだ。現場でどのようなスキルや行動指標が求められるのかを確認し、研修内容とズレがないように気をつけたい。●具体的な育成イメージをもとに「内定者研修」を計画する
「内定者研修を通じて、どのような人材を育成したいのか」に基づき、研修のゴールが決まる。「内定者には、入社までにこういったマインドやスキルを身に付けてもらいたい」というイメージを明確に描き、そこから逆算して、どのタイミングでどのような研修を実施すると効果が高まるかを考えるとよい。●提出物や面談で効果を確認する
「内定者研修」に限らず、人事施策は必ずその効果を確認する必要がある。方法はさまざまだ。研修参加者に課題やレポートを課し提出してもらう、振り返りの面談を行う、フォローアップの研修を実施するなどが考えられる。ただ、注意しなければいけないのは、参加者に負荷をかけ過ぎないようにすることだ。また、次回以降の改善につなげていかないと意味がない。●内定者研修のスケジュールを設計する
内定者研修のスケジュールは、内定式後の10月から入社前までの期間を有効に活用できるように組んでいきたい。例えば、初期には企業理解や内定者同士の関係構築を目的とした研修を中心に実施し、徐々にビジネスマナーや実務スキルを身につける内容へと段階的に進めていく。また、研修期間中の頻度や実施形式は、内定者の学業への負担や生活リズムを考慮し、無理のないスケジューリングが求められる。「内定者研修」の実施についての注意事項
最後に、「内定者研修」を実施する際に注意すべきポイントを2点取り挙げたい。●研修の法的リスクや違法とならないための注意点
「内定者研修」への参加は任意にしなければいけない。もし、会社側が参加を命令・義務付け、しかも給料の支払いがない場合には違法とされる可能性がある。なぜなら、その行為自体が労働時間と見做されてしまうからだ。●研修に対する報酬や交通費の取り扱い
基本的には、「内定者研修」は任意参加なので労働時間とはならない。そのため、給料や残業代の支払いは不要となる。しかし、「どうしても内定者全員を参加させたい」「業務を経験させたい」などといった趣旨で行うと、労働時間と判断されてしまうので給料や交通費などの支払いが必要となる。【HRプロ】でできること、詳しい活用方法はこちら >>
まとめ
「内定者研修」を企画・立案する際のポイントを整理しておこう。まずは、内定者の考え方や特性を理解することからスタートしたい。「それらは例年変わり映えがしないのでは」と決め込んでおくのは禁物だ。特に、採用担当者と研修担当者が異なる場合には、必ずすり合わせることをお勧めしたい。また、「内定者研修」を行う目的・意義も毎年改めて検討する必要がある。すべては、そこから逆算して詰めていかなければならない。もう1点は、人事部門だけで研修内容を考察するのではなく、現場部門へのヒアリングも重視するようにしたい。「どのようなスキルが求められるのか」「育成に役立ったエピソードがないか」などを聞き出し、教育内容に加味していくことで「内定者研修」のアップデートにつなげていける。
【関連記事】内定辞退で損害賠償請求は認められる? 現実的には「内定承諾書」、「内定者フォロー」、「最終確認の徹底」で損害を最小限に
- 1