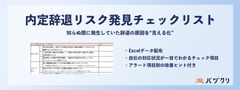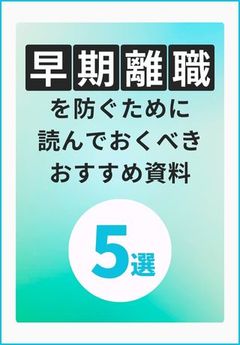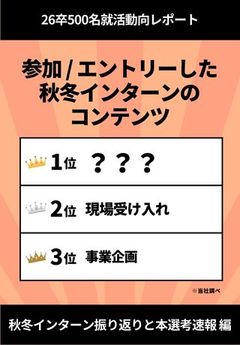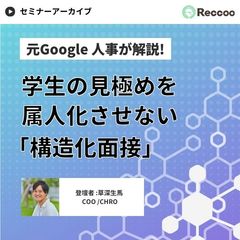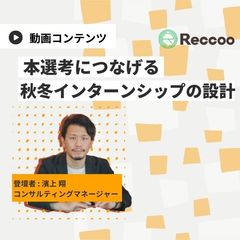労務行政研究所は、『労政時報』第4103号(25. 8. 8/ 8.22)にて、6月23日時点までの回答に基づき、「2025年度決定初任給の最終結果」を発表しました。調査対象は、上場企業3764社とそれに匹敵する非上場企業1396社の合計5160社で、有効回答は603社(上場223社、非上場380社)です。
全学歴で初任給を引き上げたのは、前年度より1.6ポイント高い82.9%で、逆に全学歴ともに据え置いたのは14.9%にとどまりました。大学卒の平均初任給は24万4602円で、前年度より1万3115円高くなっています。なお、1万544円上昇した2024年度よりも、さらに上げ幅は大きくなっています。過去10年の大卒平均初任給の推移を見ると、2024年度以降、初任給引き上げの機運が一気に高まってきたことが分かります。
2025年度の大学卒初任給額の分布状況を見ると、2万円刻みでは「24~26万円未満」が29.5%で最も多く、次いで「22~24万円未満」(27.4%)、「26~28万円未満」(17.2%)が続き、これらを合計すると74.1%と全体の約4分の3を占めます。「18.0万円未満」がいまだに0.2%存在する一方で、「30万円以上」が4.9%となるなど分散化の傾向が強くなっています。かつては数万円以内にとどまっていた初任給格差は、今や最大20万円前後にまで拡大しています。初任給の低い企業の人材獲得は、今後ますます厳しくなることでしょう。

2025年新卒採用より楽になった企業はゼロ
さて、今回は、HR総研が人事採用担当者を対象に実施した「2026年&2027年新卒採用活動動向調査」(2025年6月3~14日)の結果を紹介します。ぜひ参考にしてください。まず、ここまでの2026年新卒採用(以下、26卒採用)活動を振り返って、2025年新卒採用(以下、25卒採用)と比較しての所感を従業員規模別に見ていきましょう。「かなり楽になった」「やや楽になった」と回答した企業は、どの規模でも皆無でした。この時点で各企業とも苦労した様子がうかがえます[図表1]。
![[図表1]企業規模別 2026年新卒採用活動の所感](https://img.hrpro.co.jp/images/tokushu/hr_tokushu_photo_4450_1_B9I5X3.png)
次に、最終的な目標指標ともいえる「採用計画に対する内定者充足率」についても、2025年6月時点の状況を企業規模別に比較してみると、内定充足率が「100%以上」は大企業の3%に対して、中堅企業11%、中小企業23%と、企業規模が小さいほど割合が高くなっています[図表2]。
![]企業規模別 2026年4月入社の採用計画に対する6月時点での内定者充足率](https://img.hrpro.co.jp/images/tokushu/hr_tokushu_photo_4450_2_W1JX06.png)
今回は、幾つかの調査結果について、企業規模別だけでなく、この内定者充足率別でも比較していきます。