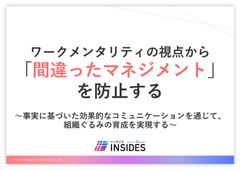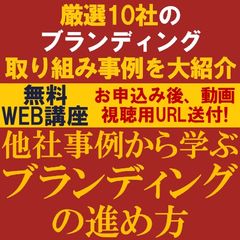採用内定は「雇用契約の成立」とみなされるか?
企業が求職者に対して内定通知を出すと、一般的には双方の間に労働契約が成立したものとみなされることが多いです。求職者は応募・面接等を経て入社の意思を示していますし、企業側も採用の意思を内定通知という形で意思表示しているため、双方の合意が成立していれば、労働契約が成立した、と解釈することができます。ただし、労働者側から見た場合、内定通知を受け取ったからといって、入社する義務があるかというと、必ずしもそうと言い切ることができません。それは、労働者には職業選択の自由(日本国憲法第22条)が保障されており、労働者が退職する権利と同様に、内定を辞退する権利も認められているからです。
では、企業側は内定辞退者に対して損害賠償請求をすることはできないのでしょうか。
企業側の損害賠償請求が認められるケースはあるか
結論から申し上げると、原則としては企業側から内定辞退者に対しての損害賠償請求が認められることはほとんどない、と見られます。ですが、内定の辞退の仕方があまりにも不誠実で企業に損害が実際に生じた場合は、「例外的に」請求できる可能性があります。たとえば、企業が社宅の借上げの手配や研修準備などで実費を負担していたような場合です。このようなケースでは、民法第1条第2項の「権利の行使及び義務の履行は信義に従い誠実に行わなければならない」という信義則に違反したとして、損害賠償請求が認められる可能性があります。
もっとも、企業側が請求を行うには、
●実際に損害が発生していること
●内定辞退との因果関係があること
●損害額を客観的に立証できること
といった要件をすべて満たす必要があり、ハードルは高いです。
また、損害賠償請求を提起しても、裁判所が企業側の主張を認めるとは限りません。むしろ、訴訟による費用・労力・社会的信用の損失などを考えると、訴訟を選択することは難しいです。
内定辞退の被害を最小限にとどめる「内定承諾書」、「内定者フォロー」、「最終確認の徹底」
司法の制度としては内定辞退者に対して訴訟を提起することは可能です。ですが、訴訟にかける費用や時間の面で企業側がかかることも事実です。裁判所が必ずしも企業に対して好意的に対応してくれるとも限りません。このようなことから、企業が取るべき対応は、内定辞退をいかに防ぐか、という視点も必要になります。
たとえば、次のような対処が考えられます。
(1)内定承諾書を求める
内定通知と同時に「内定承諾書」の提出を求めましょう。承諾書には以下のような条項を明記します。●辞退する場合は○日前までに申し出ること
●正当な理由なき辞退の場合は実費請求の可能性がある旨
●辞退時にはその理由を誠実に説明すること
上記のような記載をすることで、内定者の責任意識を高めることが期待されます。
(2)入社までのフォローアップ
内定者との定期的な連絡を通じて内定者の不安を取り除き、信頼関係を構築することも重要です。入社までの間に職場の雰囲気や仕事の内容を共有することで、内定者の気持ちの変化を防ぐ効果が期待できます。(3)最終確認の徹底
社宅や備品の手配、研修準備などの費用が発生する段階に差し掛かった時を見計らって、入社の最終意思を確認することも重要です。万が一、この段階で辞退があっても、損害を最小限にとどめることが可能です。*
いかがでしょうか。内定辞退者が出た場合、その者に対して発生した損害を負わせたいというお気持ちも出てくるかもしれませんが、内定の辞退を未然に防ぐ対策を出来るだけ講じておくことの方が現実的で効果が見込めるのではないでしょうか。
人材確保が一層難しくなる中で、採用プロセスそのものの見直しや、内定者との信頼関係構築が、企業の安定的な成長にとってポイントになります。
- 1