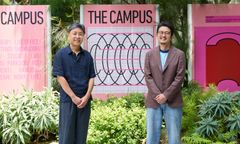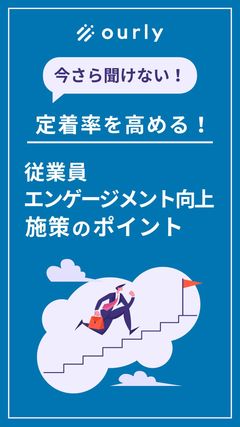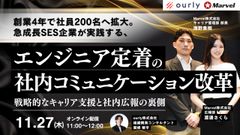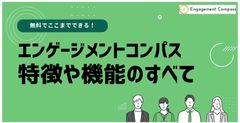雇用契約終了の類型~辞職・解雇・合意退職の違い
期間の定めのない雇用契約であれば、「民法」627条1項により退職の申出から2週間を経過すれば社員は退職することができます。会社の承諾も不要です。また、就業規則で1ヵ月前までの申出を義務付けたとしても無効です。しかし、これは、社員の一方的な意思表示による雇用契約の解消の場合の話です。以下、社員の一方的な意思表示による雇用契約の解消を「辞職」と呼ぶことにします。なお、会社の側からの一方的な意思表示による雇用契約の解消として「解雇」があります。対比して頂くとイメージしやすいと思います。
雇用契約の終了として、労使どちらかの一方的な意思表示による類型しかないわけではありません。労使の合意による雇用契約の終了として「合意退職」があります。会社からの働きかけに社員が応じる場合が退職勧奨になりますが、社員からの退職の申出に対して会社が承諾する類型も存在します。実際、この類型の退職は多いでしょう。
具体的な就業規則の条文として、厚生労働省のモデル就業規則の退職に関する条文(第52条1項1号)をご覧ください。「(社員が)退職を願い出て会社が承認したとき」は合意退職を指しています。
第52条 前条に定めるもののほか、労働者が次のいずれかに該当するときは、退職とする。
(1)退職を願い出て会社が承認したとき、又は退職願を提出して__日を経過したとき
(出典:厚生労働省モデル就業規則)
このように、退職には「一方的な意思表示による雇用契約の解消」と「合意による雇用契約の終了」があり、法律上はそれぞれ別の仕組みとして理解する必要があります。
「辞職」と「合意退職」の混同などが労使トラブルを招く
社員の一方的な意思表示による雇用契約の解消(辞職)か、労使双方の合意による退職(合意退職)かを混同していると労使のトラブルを招きます。曖昧にしていても同様です。社員が退職の意思表示をするに際して、会社の承諾を得る必要はありません。退職の申出から2週間経過で退職できます。しかし、逆に、社員の合意退職の申込に対してなら、会社は承諾をするに際して、「1ヵ月前までの申出」を求めることも可能です。つまり、就業規則に「(退職希望日の)1ヵ月前までに退職を申し出ること」と規定することは可能ですし、また、合意退職の手続としてなら非常に意味のある規定です。
しかし、このような構造を正しく理解せず、又は、曖昧にしたまま、社員が退職の意思を明確に伝えている状況下で、会社が「1ヵ月前までの申出が必要」、「会社の承諾が必要」と主張することは誤解を生み労使トラブルを招きます。
「辞職」と「合意退職」の違いを踏まえた現実的な対応策
社員が退職するに際して、1カ月以上前に申し出てもらえれば、関係者へのご挨拶・説明も含め、十分な引継ぎ等を行うことが可能ですので、突然の退職による混乱を避けることができます。しかし、それを可能にするためには、前提として、退職希望日の1ヵ月以上前までに申し出やすい環境にすることが必要です。退職を申し出た社員が気まずい雰囲気で過ごすことになる職場では、早目の申出を求めること自体が無理な話です。そこで、「退職希望日の1ヵ月以上前までに申し出た場合には、会社は原則として、退職を承諾する」とし、無理に引き止めないことが必要です。
そのうえで、早めに申し出てもらう以上、社員の側に具体的なメリットがあることも重要です。以下のような制度や取組みが考えられます。
●再就職活動のための特別休暇を付与する
退職を希望する社員が、円滑に転職活動を行えるよう、在職期間中に特別な休暇を設けて求職活動を認める制度です。●退職金について、優遇措置を設ける
早めの退職の申出により円滑な引継ぎを可能にしてくれたことへの感謝の気持ちを金銭面で示すことも1つの方法です。これらは一般的に、『早期退職者優遇制度』として行われることが多い制度です。退職勧奨の場合にも行われます。しかし、突然の退職は、職場が混乱し会社に残っている社員も困ります。これらの取組みを広げることで、退職をめぐるトラブルを未然に防ぐことは会社にとっても利益になります。
多くの社員は一定期間で退職するという事実があります。これらの制度は、その現実を受け入れたうえで、円満な退職を促すものです。社員が辞めない魅力的な職場にすることは大切なことです。また、会社が退職を推奨しているという誤ったメッセージが伝わらないようにする配慮も必要です。しかし、それと同時に、労使の合意による退職へ導く仕組みづくりも同時に必要なことです。
- 1