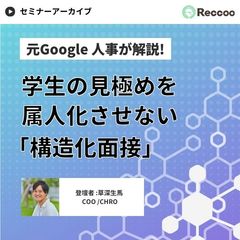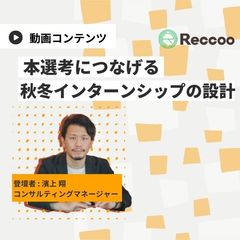「採用代行(RPO)」とは
「採用代行(RPO)」とは、「採用アウトソーシング」や「採用代行サービス」とも呼ばれており、自社における採用業務の一部、あるいは全てを外部の専門事業者に委託することを言う。自社の採用担当者の負担軽減や業務の効率化を図る上では、非常に有効なサービスとなる。「RPO」は「Recruitment Process Outsourcing」の略称だ。【合わせてチェック】「採用代行(RPO)」のサービスやお役立ち資料はコチラ >>
●BPO・人材派遣・人材紹介との違い
「採用代行(RPO)」と混同しやすい言葉に、BPOや人材派遣・人材紹介などがある。基本的に、「採用代行(RPO)」は企業の採用業務に特化しているのに対して、BPO(Buiness Process Outsourcing)は企業の業務プロセス全般が委託の対象となる。また、「採用代行(RPO)」はメンバーへの業務指示を委託先企業が行うのに対し、人材派遣では契約に即した内容であれば、受け入れ側が派遣された人材に対して業務指示を直接行える。さらに、「採用代行(RPO)」と人材紹介では、サービス内容が全く異なる。人材紹介は、企業の人材要件に合致する人材を登録者の中から選定し、面接を設定するところまでが業務の範囲となる。●導入が進んでいる背景
「採用代行(RPO)」の導入が進んでいる背景としては、いくつかの要因が挙げられる。一つ目は採用の難易度が高まっていることだ。より優れた人材を採用するためにも、採用を外部のプロに託すという企業が増えている。二つ目は攻めの採用活動へのシフトだ。もはや、求人を掲載して応募を待つだけでは人材は確保できない、ダイレクトリクルーティングを活用する攻めの採用も必要となっている。だが、社内のリソースだけではそれに対応できる専門性が足りないと言わざるを得ない。三つ目が採用担当者を雇用するリスクの増大だ。市場の急激な変化により、人員計画が揺れ動くことがある。そうした状況では、外部リソースを活用した方がリスクを抑えられると考えられている。●「採用代行(RPO)」は違法ではない?
「採用代行(RPO)」は、許可を取得していれば違法ではない。ただし、職業安定法が定める委託募集(労働者の募集を第三者に委託すること)に該当する業務では、委託元となる企業も代行サービスを請け負う会社も、厚生労働大臣または都道府県労働局長の許可が必要となる。仮にこの許可を取らずに「委託募集」に該当する業務を委託した場合、違法行為となり、懲役や罰金などの法的な罰則の対象となる。一方で、業務内容によっては許可が不要なケースもあるため、委託の範囲と法的要件は事前に確認することが重要だ。
【HRプロ】でできること、詳しい活用方法はこちら >>
「採用代行(RPO)」のメリット
続いて、「採用代行(RPO)」を活用するメリットを取り挙げていく。●採用工数の削減
「採用代行(RPO)」を導入すれば、採用活動に関する一部の業務を外部に委託できる。その分、工数の削減につなげられる。●採用担当者の負担軽減
採用業務は多岐に渡るため、採用担当者の負担は相当なものがある。しかも、新卒採用の担当者になると業務が特定の時期に集中せざるを得ない。その点、「採用代行(RPO)」を活用すれば、スカウト運用や候補者との日程調整などのノンコア業務を委託することが可能となる。浮いた時間を面談や内定者フォローなどのコア業務に集中できる。●採用成功率の向上
「採用代行(RPO)」を活用することで、外部の専門知識やノウハウを取り入れられる。また、代行会社がこれまでに培ってきた実績を活かした支援も期待できる。場合によっては、自社ではアイデアが浮かばなかった画期的な施策や方法を実施できるので、採用成功率が自ずと高まる。●ノウハウの活用と改善提案
採用代行事業者は、採用に関する豊富な経験やノウハウを有している。それらを活かして、自社の状況に応じて効果的かつ効率的な採用手法を提案してくれるはずだ。母集団形成のための媒体選定、人材エージェントの開拓などについても、アイデアを提示してもらうことができる。●スピーディーな採用体制の構築
採用担当者の人数やスキルが不足していると、業務の遂行が遅れがちとなり、有能な人材を逃すリスクが高まる。その点、採用代行事業者は、スピーディーかつ丁寧な対応、正確なデータ管理などを強みとしているだけに、より精度の高い採用体制を構築・運用できる。●採用コストの削減
「採用代行(RPO)」を使うことで採用コストを削減できるケースは多い。採用知識を持った事業者に任せることで採用プロセスの効率化が進み、採用担当者の人件費や残業代などが抑えられるからだ。また、複数の求人媒体に一括で広告出稿できるため、求人広告費を抑えられることもある。ただし、「採用代行(RPO)」自体の費用は決して安くはないため、自社の採用規模や課題に応じて、一部業務のみ委託するなど費用対効果を見極めて利用することが求められる。●採用パフォーマンスの可視化
「採用代行(RPO)」では、採用に関する指標をデータとして計測・分析するため、自社の採用活動にかけたコストに対する成果を把握しやすくなる。社内だけで採用を進めるよりもパフォーマンスが可視化しやすいため、人事部門としても次の施策を立てやすくなり、より効率的な採用活動へとつなげられる。「採用代行(RPO)」のデメリット
「採用代行(RPO)」はメリットばかりではない。デメリットもあることを考慮しておかなければならない。●コスト増加の可能性
「採用代行(RPO)」を導入することで、採用コストが逆に高くなるケースもあり得る。「採用代行(RPO)」の料金は委託する業務の内容やボリュームによって変動する上に、利用するサービスによっても費用が異なるからだ。事前に見積もりチェックを丁寧に行っておきたい。●社内ノウハウが蓄積しづらい
「採用代行(RPO)」を利用すると、採用担当者が外部に委託した業務に関与する機会は大幅に減少する。そのために、社内に採用関連のノウハウを蓄積しづらくなってしまう。また、採用担当者のスキルアップも期待できない。特に、注意すべきはコア業務を依頼するケースだ。それでは、いつまで経っても自社の採用力向上にはつながらない。●自社文化に合わない場合がある
「採用代行(RPO)」を行う企業の特長は千差万別だ。サービス内容や得意領域もさまざまといえる。それだけに、選び方を間違えてしまうと自社の採用課題の解決につながらない、自社文化にフィットしない人材だけを採用してしまうというケースが起こり得る。自社に最適な「採用代行(RPO)」を選ぶことを心がけよう。●コミュニケーションミスのリスク
「採用代行(RPO)」では社内に常駐するケースは少ない。なので、業務報告や相談事項などのやりとりは、電話やメールで行うのが一般的だ。それゆえ、コミュニケーションがしっかりと取れていないと、コミュニケーションミスどころか、人材要件の共有が十分できず、人材のミスマッチが発生する可能性がある。●契約内容による柔軟性の制限
一旦契約した内容を簡単に変更できないサービスも中にはある。その場合、採用市場の変化に合わせて柔軟な対応をしようとしても難しい場合が多い。あらかじめカスタマイズが可能なサービスを選ぶと良いだろう。「採用代行(RPO)」で依頼できる業務
次に、どのような業務を「採用代行(RPO)」に依頼できるのかを見ていこう。●採用計画の立案
コンサルティングを強みとする採用代行事業者であれば、採用計画や手法についての戦略部分の立案にも応じてくれる。●求人広告の作成・掲載
求人広告の作成、求人媒体の選定・発注・出稿などの業務を委託することもできる。まとめて委託できれば、工数だけでなく、コスト削減も図りやすい。●母集団形成・応募者管理
「採用代行(RPO)」では、自社にマッチした採用チャネルの策定、実行から振り返りまでを行ってくれるので、効率よく母集団を形成できる。また、求人媒体や人材紹介サービスなどを通して応募してきた求職者の管理・やりとりや、応募者への選考の合否結果通知業務なども頼める。●書類選考・スクリーニング
応募者が多い企業では、書類選考に対応するだけでもかなり大変になる。その点、選考基準が確定しているのであれば、「採用代行(RPO)」に伝え応募者のスクリーニングを実施してもらうと負担が少ない。●選考日程調整・面接代行
各選考に合わせて、電話やメールで求職者との日程調整業務を行ってもらえる。また、日程の確定後には、当日の詳細に関する事前確認のメール送付や電話確認をしてくれる。さらに、求職者が遠隔地に住んでいたり、面接官の時間が確保できなかったりする場合には面接業務の代行もしてもらえる。●内定・入社フォロー
内定後や入社に向けたフォローアップ業務も委託できる。もっと言えば、入社後に会社になじめるようサポートも依頼できる。具体的には、内定者への入社に関する連絡業務や書類の取得、各内定者へのフォローアップ面談、定期的なアンケートの実施、早期離職を防ぐための施策提案などが挙げられる。●レポート・振り返り業務
一連の採用活動において設定したさまざまなKPIを可視化し、レポートとして報告してもらえるので、進捗状況や課題の分析がスムーズに行える。また、全体を振り返った上での改善や追加施策の提案なども行ってくれるので、社内に採用のノウハウを蓄積していける。「採用代行(RPO)」会社の種類
「採用代行(RPO)」の会社・サービスにはさまざまなタイプがあり、自社の採用ニーズや規模に応じた選択が採用成功の鍵となる。主な5つのタイプに分類して紹介しよう。●総合人材サービス系
総合人材サービス会社は、多種多様な人材サービスを提供し、採用代行もその一環として手掛けている。豊富な人材データベースと長年蓄積されたノウハウを活用できる点が特徴と言える。そのため、大手企業も多く利用し、幅広い業界や職種に対応可能だ。リクルートやマイナビなどが代表的で、新卒から中途まで幅広い採用領域に対応し、母集団形成や求人媒体の運用、選考プロセスの支援、内定者フォローまで幅広い業務をサポートしてくれる。料金はやや高めだが、採用戦略の立案やコンサルティングも受けられ、効率的な採用活動ができる。●RPO特化型専門会社
「採用代行(RPO)」に特化した企業で、採用プロセス全般を任せられる。中規模から大規模の企業に適し、機械的な業務の自動化や進捗管理、選考代行などを効率化しつつ、採用戦略の策定から採用ブランディングまで総合的なコンサルティングをしてくれるサービスが多く、支援の幅は広い。委託範囲をカスタマイズでき、柔軟に契約形態も変更できる。●業界特化型(IT・介護・製造など)
特定の業界に特化した「採用代行(RPO)」サービスは、業界特有の採用課題やニーズ、トレンドに精通しているため、質の高い母集団形成やマッチングができる。業界内のコネクションを持っており、ニッチな人材にもリーチできるため、競争が激しい領域でも効率的に採用活動を行える。●スタートアップ・ベンチャー向け特化型
ベンチャー企業やスタートアップ向けの「採用代行(RPO)」は、限られた予算と時間の中で、コストやスピード感を考慮して採用を進めてくれるのが特徴だ。新規採用や少人数体制でもフレキシブルに対応し、人材ブランディングやカルチャーフィットも重視してくれる会社が多い。●グローバル採用対応型
グローバル採用対応型の「採用代行(RPO)」は、外国人材の採用ニーズが高まる中、注目度を増している。採用プロセスの支援だけでなく、ビザ申請支援や入社後フォローまで一貫したサポートを提供してくれるサービスが多く、海外大学との連携による新卒採用や高度専門人材のヘッドハンティング、現地法人の立ち上げに伴う採用支援など、グローバル展開を進める企業に打ってつけだ。多言語でのコミュニケーション、各国の労働法規制への理解、文化的背景などの課題にも専門家がしっかり対応し、煩雑な外国人採用をスムーズに進めてくれる。「採用代行(RPO)」の料金相場
「採用代行(RPO)」の料金はどのくらいなのであろうか。相場を説明したい。まず、料金の算出パターンとしては主に3つある。
・月額一律料金の固定制
毎月一定額を支払い、採用支援業務を委託する方式。業務内容が明確で一定の場合に向いており、相場は10万円から100万円程度と、業務範囲によって大きく異なる。
・従量課金制(作業量・件数に応じた料金)
実際の業務件数や作業量に応じて費用が発生する形態。業務内容に応じた費用の相場としては、新卒・中途の媒体管理:5万円~70万円/月、選考日程調整:5万円以上/月、DM・スカウト配信業務:3万円以上/月、面接業務代行:30万円以上が目安となる。
・成果報酬制
採用成功時にのみ費用が発生する方式。採用者の年収の20〜35%程度が相場となっている。初期コストを抑えたい企業に適しているが、総コストが高くなりやすい点に注意が必要。
事業者ごとに強みや得意分野も異なるため、複数社から見積もりを取って、費用とサービス内容を比較検討することが重要だ。短期のスポット契約から年間契約まで柔軟に対応している企業も多く、自社の採用計画や目的に応じて選びたい。
「採用代行(RPO)」導入のポイント・注意点
「採用代行(RPO)」にはメリットもデメリットもあるだけに、導入に際して注意すべきポイントがいくつか挙げられる。●自社課題の明確化
まずは、自社の経営戦略や事業計画を踏まえて、どんな採用課題があるかを抽出した上で「採用代行(RPO)」を導入したい。もし、これを怠ると“あれもこれも”と任せてしまい、コストが膨らんでしまう。また、採用課題に合わせて採用代行事業者選びも変わってくる。言い換えれば、最適な事業者を選択するためにも自社の課題を明確化する必要がある。●業務範囲と契約内容のすり合わせ
自社内で実施できる業務、プロに任せたい業務は会社によって違うはずだ。また、得意とする業務も委託先で異なってくる。そのため、委託する場合には、事前に依頼する業務範囲と責任を明確にし、契約内容に齟齬がないかをしっかりと確認するようにしたい。特に、個人情報の取り扱いや情報連携に関してはしっかりと詰めておきたい。●進捗共有・情報連携の体制構築
採用業務をアウトソーシングしたら、結果が報告されるまで何も関知しないというのは良くない。かなりの確率でトラブルが生じてしまう。一定のタイミングで進捗を確認したり、状況把握や情報共有を行ったりする必要がある。その場合、どういった手段を用いるかも事前に検討しておきたい。●支援実績・担当者の質の確認
採用代行事業者を決めるにあたっては、過去の実績を確認するようにしよう。実績が少ないと机上の空論となり、採用活動が失敗に終わる可能性があるからだ。併せて、担当者の仕事ぶりもしっかりと評価しておきたい。会社としての実績があっても、担当者の質が悪ければ何の意味もない。●自社ルールとの整合性チェック
採用代行事業者を選ぶ際には、自社ルールとの整合性にも配慮したい。チェック項目としては、進捗報告や状況の共有方法、契約書の締結方法、各業務の対応方法など多数ある。認識にずれがあると、トラブルにつながるケースも考えられる。まとめ
「採用代行(RPO)」にはメリットとデメリットがそれぞれあり、それを踏まえて、自社で導入するかどうかを検討してもらいたい。リソース不足によって採用活動が進まない企業にとっては、「採用代行(RPO)」が課題解決の手段となるはずだ。「募集ポジションが多様で、しかも母集団形成の仕方や選考方法に違いがある」、「採用枠を広げたいが、人事担当者に余力がない」、「社内的な事情で早期に人材を確保する必要がある」などの悩みを抱える企業は前向きに検討してみても良いだろう。ただし、ベンダーにすべて任せるのではなく、自社の採用課題を明確にした上で、委託範囲を精査しながら中長期的な目線でベンダーと協力して採用を進める姿勢が成功の鍵となることを忘れてはいけない。【HRプロ】でできること、詳しい活用方法はこちら >>
- 1