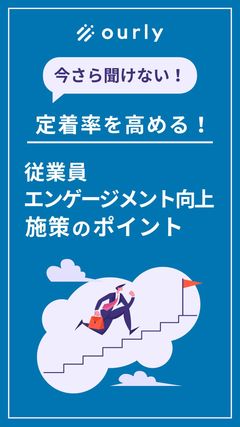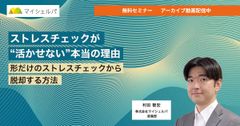「ワークエンゲージメント」と「従業員エンゲージメント」の違いは
厚生労働省「働きがいのある職場づくりのための支援ハンドブック(以下、厚労省資料)」で、「ワークエンゲージメント」と「従業員エンゲージメント」は次のように紹介されています。※厚生労働省「働きがいのある職場づくりのための支援ハンドブック」より
●ワークエンゲージメント
ワークエンゲージメントとは、仕事にやりがい(誇り)を感じ、熱心に取り組み、仕事から活力を得ている状態を指しており、従業員個人と、取り組んでいる仕事との関係に着目した概念です。ワークエンゲージメントは、活力、熱意、没頭の3つの要素で構成されています。
●従業員エンゲージメント
企業など組織への貢献意欲を指しており、従業員個人と、所属する組織との関係に着目した概念です。組織への貢献意欲とは、従業員が組織の発展や目標達成に貢献したいと考え、組織の目指す方向へ自発的に活動しようとする気持ちのことです。
ワークエンゲージメントは、「個人」と「仕事」との関係に着目しています。例えば、他人から言われるまでもなく、積極的に自己啓発に取り組み、仕事に生かそうとする姿勢などが、ワークエンゲージメントのような状態といえます。
そのワークエンゲージメントを構成するのが、次の3つの要素です。
●活力(例:仕事をすることでエネルギーを得られるような感覚)
●熱意(例:仕事に対して強い意欲を持って向き合えるような感覚)
●没頭(例:時間を忘れるくらいに仕事へ集中できるような感覚)
そして、従業員エンゲージメントは、「個人」と「組織」との関係に着目しています。ワークエンゲージメントにより仕事へのモチベーションが高まったとしても、その仕事内容が組織の方向性と違っていれば、組織の利益につながりません。組織としての方向性などを明確にし、従業員の組織への貢献意欲を高め、従業員と組織の方向性を一致させることも大切になります。
過度に仕事に取り組むことは「ワーカホリズム」
厚労省資料では、ワークエンゲージメントと混同する概念として「ワーカホリズム」を挙げています。仕事に対して高い水準であることはワークエンゲージメントと共通していますが、「ワーカホリズム」は強迫観念など本人の意思とは無関係に過度に仕事に取り組む姿勢を指しています。例えば、次のような状態です
●過度な心配(例:常に仕事をしていないと、仕事で失敗してしまいそうな恐怖感)
●過度な仕事量(例:常に仕事の予定で埋まっていないと落ち着かない)
●過度な他者への指導(例:自らの仕事に対する姿勢と比較し、他者の仕事に対する姿勢が物足りない)
厚労省資料では「ワーカホリズム」が続くと、疲れ果て、やる気が起きず、心身に支障をきたすような「燃え尽き症候群(バーンアウト)」になる可能性を指摘しています。だからこそ「ワークエンゲージメント」の大切さについて触れているのです。
「ワークエンゲージメント」を知ること、伝えることからスタート!
しかし、誰もがすぐに「ワークエンゲージメント」になれるわけでもありません。日々の忙しさに追われてしまうと、そのような気持ちに行きつくことも困難となります。また「ワーカホリズム」は避ける状態ではありますが、その人が持っている個性の裏返しでもあります。慎重に仕事をする人、たくさんの仕事をこなすことができる人、職場に適度な緊張感をもたらしてくれる人など。それが過度になりすぎることは避けるべきですが、いろいろな人たちがいて、組織が持続できることも事実です。
まずは「ワークエンゲージメント」を知ることから始めてみましょう。「ワークエンゲージメント」と「ワーカホリズム」、「燃え尽き症候群(バーンアウト)」との関係性を知るだけでもメンタルヘルス対策につなげることができます。
あとは「ワークエンゲージメント」を広げていきましょう。ただ従業員が忙しさに追われると「そんなことを言われても……」と実感できないことも考えられます。積極的に自己啓発をしている従業員からワークエンゲージメントを発信してもらったり、メンタルへルス研修の講師にワークエンゲージメントの内容を伝えてもらったりするなど、自組織内の現状を把握し、効果的な伝え方を見つけていきましょう。
- 1