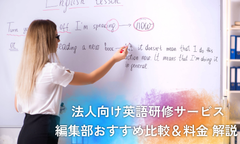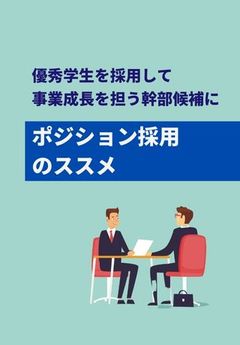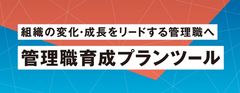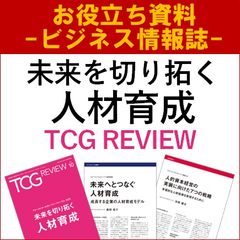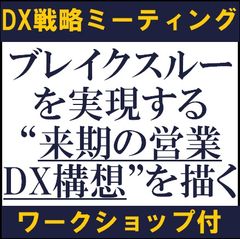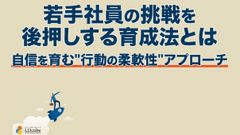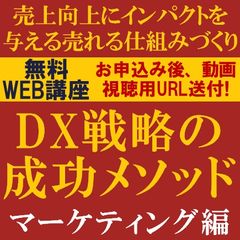「ナッジ」とは何か?
「ナッジ」の事例でおそらく最も有名なのは、アムステルダム・スキポール空港の男子トイレの小便器に描かれたハエの絵でしょう。それまで小便器の周辺の汚れで床の清掃費が高くついていたことに業を煮やしていた職員が、ふと思いついて小便器にハエの絵を描いたところ、なんと清掃費は8割も減少したそうです。そう、利用者がこの小便器のハエの絵をめがけて用を足すようになったことで、便器の周りの汚れが激減したのです。ちなみにこれは1999年のことで、その後、この小便器のハエは世界各国に波及しています。読者の皆さんも見たことがあるかもしれませんね。「ナッジ」とは、「軽く肘でつつく」という意味の英語です。セイラー教授はナッジについて、「選択を禁じることも、経済的なインセンティブを大きく変えることもなく、人々の行動を予測可能な形で変える選択アーキテクチャーのあらゆる要素を意味する」と定義しています。要は力ずくではなく、そっと優しく、それとなく良い方向へ行動を促す策を指していると、私なりには理解しています。
では、そのようなナッジを私たちはどのようにすれば導入することができるのでしょうか。
ナッジの設計方法として、「BASIC」(Behavior:人々の行動をみる→Analysis:行動経済学的に分析する→Strategy:ナッジの戦略を考える→Intervention:ナッジによる介入をする→Change:変化を計測する)というものがあります。また、実際に選択したナッジが適切なものかどうかをチェックするためのチェックリストとして、「EAST」(Eeasy:簡単か、Attractive:魅力的なものになっているか、Social:社会規範を利用しているか、Timely:意思決定をするベストタイミングか/フィードバックは早いか)という理論が提唱されています。ご興味あり詳しくお知りになりたい方は行動経済学タイトルのビジネス書などを当たってみて頂ければと思います。
「ナッジ」に使える私たちの意思決定のクセ、身近に溢れている「ナッジ」
行動経済学が明らかにした私たちの意思決定のクセは、大別すると4つあると言われています。(1)確実性と損失回避を求める「プロスペクト理論」
(2)先延ばし行動など時間割引率の特性である「現在バイアス」
(3)他人の効用や行動に影響を受ける「社会的選好」
(4)合理的推論とは異なる直感的意思決定である「ヒューリスティックス」
そもそも私たちの日常は、ナッジで溢れています。私たちは毎日、なにがしかのナッジに行動を促されていると言っても間違いないでしょう。
例えば、私たちがコンビニやスーパーで、棚のどこを最もよく見て、どの位置の商品を手にする確率が高いかということは、心理学的・行動学的に明らかになっています。立っていて目の高さにあるもの、また同じ高さであれば左から右に視線を移しますので、その順番に商品が目に飛び込んできて購買意欲をくすぐられます。これを踏まえて、例えば健康志向のお店が、顧客の健康を考えて目の高さに健康志向の商品や生鮮食品を置くような行為が「ナッジ」に当たります。
一方で、お店が自分の私利私欲のために行動経済学的知見で行動を促すことは「スラッジ」(ヘドロや汚物を意味する英語)と呼ばれます。例えば、同じお店が顧客の常習性を狙って習慣性・依存性の強い商品を同じ場所に展開し購買促進するとすれば、それはスラッジでしょう。また、ネット販売などで購入時にデフォルトで継続購入フラグが立っており、オプトアウトがしにくくなっている(本人からの申し出やアクションがあって初めて解除される形式)ケースなどもスラッジですね。
そう理解すると、これは果たしてナッジなのかスラッジなのか、なかなか難しいマーケティング施策が私たちの生活環境には溢れかえっていることに気づきます。
うな重などの定食価格が松竹梅で設定されている場合もそうですね。上1500円・並1000円の2つのメニューのときは多くが並を選択しますが、これに特上2000円が加わった途端、私たちの多くは上を選択します。そのほかにも、購入時に「効果を感じられなければ全額返金保証」とうたうインセンティブ提供や、「今月に限り、半額!」などの期間限定アナウンスなどは、私たちに純粋なメリットを得る機会を促してくれているケースももちろん多くあれば、提供者のマーケティングの罠におめおめとやられてしまうケースも少なくないように思います。
私たちがナッジ/スラッジ、行動経済学を知っておく最大の価値は、こうした私たち自身の意思決定のクセがあると認識した上で、その意思決定のクセを狙った情報を見たときに「非合理な意思決定」を回避することにこそあるのです。
職場で活かす「ナッジ」
さて、当連載としては、このナッジを経営幹部の皆さんがどう職場で使うのかということが重要ですね。まずひとつ、興味深い話として、年功的給与制度は行動経済学的には妥当性があるというお話からいたします。私たちは、現在の給与水準を参照点として、それより上がれば「利得」、下がれば「損失」と感じます。例えばある3年間、あなたの年俸が評価によって700万から800万になり、次年度は業績低迷で600万になったとしましょう。一方、別の3年間、600万から700万、800万へと昇給が続いたとします。絶対的に見れば、この3年間の平均年俸はいずれも700万、総年収は2100万です。収入的には同じなのですが、あなたは、後半の3年間は非常にハッピーな気持ちで過ごしますが、前半のうちの2年目・3年目は、評価は致し方ないと理解しながら、やるせない気持ちと大きく減俸されたという印象を持って過ごすことになるでしょう。
そもそも給与が下方硬直性を持つのはこうしたバイアスから説明できますし、行動経済学的に言えば、給与システムは年功的側面~経年で上がっていく体系を基本として、「頑張って、毎年少しづつ給与が上がっていく」というナッジを使った方が、社員のやる気は下支え継続するのです。
実際のところ、今どき年功的給与体系が適している企業は極少ですから、理論は分かってもなかなかそれを活かすことは難しいでしょう。成果主義・実力評価は合理的には正しいので、その筋をしっかり通しつつ、社員モチベーションを考慮すると、仮に大きく減給せざるを得ないときにも必ず「この次に挽回できるチャンスとその方法・ロジック」をしっかりセットで渡してあげることが大切です。そうすれば、次の半年・1年の頑張りを促すことができるでしょう。
部下に計画を立てさせてもなかなか実行、達成できないことに悩む上司は常に多くいらっしゃいます。これは行動経済学的には、「現在バイアス」で説明されます。
現在バイアスは、将来のことについては我慢強い意思決定ができる(「1年後なら100万円、1年と1週間後なら101万円を受け取ることができる」という2択の際は多くが後者を選ぶ)のに、現在のことについては安易な意思決定をしてしまう(「1週間後なら100万円、1年後なら101万円を受け取ることができる」という2択の際は多くが前者を選ぶ)、計画はできても(半年後に5キロ痩せる!)、実行段階では現在の楽や楽しみを優先(お菓子やケーキ、ラーメンなどを食べてしまう)し、計画を先延ばししてしまうという特性を表します。
Q(クォーター)、半期、通期の売上目標を達成するにあたって、「達成したくない」と思っている社員はいないでしょう。しかし、目の前の日々ではそのための充分な業務活動ができない。気がつけばまた半期末や期末が近づいてきて、少なくない目標残を抱え、残された営業日数での打ち手も尽き、鬱々と期末を迎える日々を過ごす…。
行動経済学的にもこの回避策は至って王道で、中長期目標を達成するために可能性をたぶんに含む短期目標~毎日の行動計画を決め、この日々の行動計画を習慣ルール化することが、結局のところ最も上手くいくであろう最善策なのです。マネジメントとしては、先々の大きな目標だけをロックインさせていてもダメで、部下たちの毎日の行動をしっかりチェック・管理することが、中長期目標達成に至る道なのです。
できる部下は、自分でこの毎日の行動計画の策定と実行、習慣化ができます。普通以下の部下については、結局はある程度以上、行動を具体的に細かく管理できる上司が業績を上げざるをえないということが、残念ながら行動経済学で実証されてしまっているのです。
さて、ここまでのお話から、「ナッジは危険なマインドコントロールではないか」と思う方もいらっしゃるかと思います。実際に、先の通りスラッジも存在しますしね。行動経済学が提唱するナッジは、あくまでも「良い行動を、当事者に主体的に促すもの」です。ナッジ的思考行動特性を持つ人が、これからのできる経営幹部、社長になる人だと私は思います。
- 1