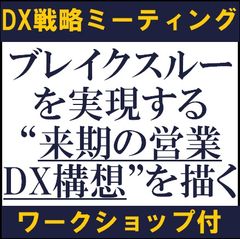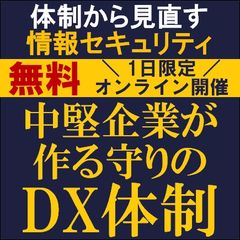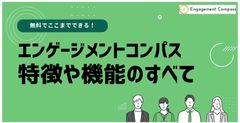とはいえ、部下の動きが悪ければ強制や管理を強めてしまうというのは、上司の立場にある人たちが共通して陥る罠です。これで上手くいくようになるということは、残念ながらあまりありません。“北風より太陽”、“押してもダメなら引いてみな”は、今に始まったコミュニケーション術ではなく、いにしえからの知恵でもあります。そして興味深いのは、いま注目かつ流行りの行動経済学がこれを実証していること。今回は、逆説的に部下を動かす“使える行動経済学理論”を見てみましょう。
「イケア効果」で業務への愛着とコミットを持たせる
「ちゃんと毎日、営業日報の入力やってくれよ」いくら口を酸っぱくして言っても、「はい」と言いながら一向に行動してくれない部下は、おそらくあなたのもとにもいることでしょう。上司からして、部下の商談状況の詳細や進捗はなるべくリアルタイムに知っておきたいところですが、その情報をなかなか用意したフォーマットに落としてくれない。こうした状況では、「あいつは怠慢だ」、「仕事力に劣る」、「いい加減なやつだ」などと思ってしまいがちです。
「ダメなメンバーだ」と評価を確定させる前に、一つ試みてみて頂きたい方法があります。それは、その日報入力の習慣行動ができないメンバーに、「いま使っている営業日報をより分かりやすく、入力しやすいものにバージョンアップしたいんだが、更新版の日報フォーマットを作ってみてくれないかな」と、自ら営業日報を作らせることです。
人は他人に言われたことをやったり、与えられたものを使わされるよりも、自分が考えたこと、自分で作成したものに愛着・やりがいを感じます。デューク大学で教鞭をとる、心理学・行動経済学のダン・アリエリー教授は、出来上がった家具より自分で苦労して組み立てた家具に愛着が湧き、値段以上の価値を感じてしまう現象に「イケア効果」と名付けました。上から言われたことになかなか従ってくれない部下には、「イケア効果」を狙って自分で仕事を組み立てさせることで巻き込みを狙ってみましょう。
「ツァイガルニク効果」で“もっと仕事をさせてください!”と思わせる
働き方改革で、「残業規制」もより重要となっています。皆さんの職場でも、上司のあなたに課される部下の残業管理司令は厳格なものになっているのではないでしょうか。大手企業にお勤めの上司の皆さんの場合、部下の残業時間の多さがあなた自身のマイナス考課に反映されるような人事評価制度になっているケースもあると思います。「仕事量は増え続けていて、業務時間は減らせって、会社も無茶ばかり言うよなあ」。そうぼやいている方も多いでしょう。ここはひとつ、これを逆手に取るメンバーマネジメント法を手にしておきませんか?あなたのチームで、一定以上仕事に乗っている部下に効果的な心理学アプローチがあります。それは、まさにいま乗っている部下に対して、上司のあなたから先に「もうそこまででやめて、今日は帰れ」と、あえて仕事を中断させる方法です。「今いいところなので、もうひと踏ん張りやってから帰ります」と部下は言ってくるかもしれませんが、「ダメダメ。今月の残業時間、月初でなくなってしまうのは課としてまずいんだ。さあ、終わり終わり!」とまで言えば、部下はデスクを片付けオフィスを出るでしょう。
これは、自分がやりたいことを中断されると、より意欲が高まる「ツァイガルニク効果」を狙ったものです。心理学者ツァイガルニクの行った実験によれば、作業タスクを途中で中断させることで、作業を中断させられたチームは継続したチームに比べて2倍、その作業について後々鮮明に記憶していたそうです。さらにこれを発展させたいくつかの実験では、同様の作業中断で、興味関心が高まることが分かったとのことなのです。
私たちは日常、このツァイガルニク効果に“ヤラれて”います。それは、「続きはCMのあとで」、「詳しくはWEBで」といったうたい文句。「おいおい、続き見せてくれよ!」とムッとしながらも、続きが気になってCM後も見続けたり、スマホでサイト検索に行ったりしてしまいますよね。
ノッている仕事を強制終了させられたことで、部下はその仕事への注視度合いとコミットメントを高めます。帰宅後、翌日朝まで「続きはこうやってやろう」、「関係する情報、ネットや本で調べておこう」という志向行動が発生し、翌日の出社後、猛然と昨日の続きに取りかかってくれることでしょう。
「サンクコスト効果」、「保有効果」で刺激を与え、最後までこだわらせる
人は、ある程度まで進めたことを途中で捨てることに心理的な抵抗を持ちます。私は漫画をよく読むのですが、時折、途中で話がつまらなくなってしまっているにも関わらず、「でも25巻まで読んでるしなぁ」と続刊が発売されては買い続け、義務のように読んでいるときがあります。仕事においても、プロジェクトワークなどが長期化してくると、悪意なくだれてきたり、飽きてきたりするものです。そんな折に、上司の隠し玉として使える心理テクニック(ちょっと意地悪い策略ではありますが)をご紹介します。
そのテクニックとは、部下のプロジェクトワークがある程度以上進んだところで、上司のあなたが「このまま予定通りのプランで進めていくのはどうかなと思うんだ。これはやめて別のやり方をするのはどうだろう?」と、やり方の変更を提案するというもの。実はそのまま完成させてOKな状況なのですが、部下には逆のことを敢えて言い、業務を止める“妨害”に入ってみせます。すると部下は内心、「せっかくここまでやって、終わりも見えてきているのに!」と思うでしょう。もしかしたら惰性になっていた業務に、メラメラと火がつきます。
これは、せっかく途中まで作ったものは捨てたくないという「サンクコスト効果」の表れです。部下にその気持ちが生まれているのを読み取ったら、のらりくらりと会話しながら、「そうか、分かった。キミがそこまで言うなら、このまま続けて完成させてくれ。その代わり、最高のものに仕上げてくれよ」と、ポンと肩を叩いて颯爽と部下のデスクから去りましょう。
次に、さらに性格悪いアプローチもご紹介します。同じく、部下が仕事の最終仕上げにかかって、いよいよ来週に事業本部の会議でプレゼンを行うというタイミングで、「ここまでお疲れさま! 最終プレゼンは先輩のAに任せるか?」と提案するというものです。最後の最後で手柄を別のメンバーに渡すよう、取り上げてしまう(ふりをする)のです。「それはないですよ!」とはっきり言う部下もいるでしょうが、言えない部下もいるでしょう。どちらであっても、ここまで頑張ってきた部下であれば、内心のスイッチがカチッと入ったはずです。「ここまでやってきたのだから、自分がプレゼンしたい!」と思うでしょう。
これは、「現状維持バイアス」や「保有効果」のスイッチが入った状態です。「このまま自分で…」という意識をグッと強め、自分で最後までやり遂げたい気持ちを高めることで、来週のプレゼンに気持ちを入れてもらいましょう。上司のあなたの目的は、部下に最高の状態でプロジェクトを完遂してもらうことなのですから、そのためであれば部下への多少の心理学的意地悪も許されることと思います。
- 1