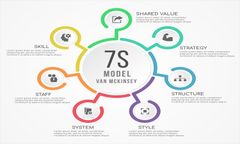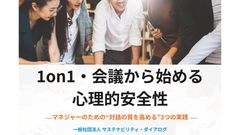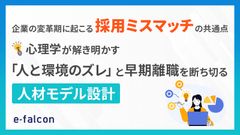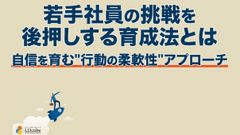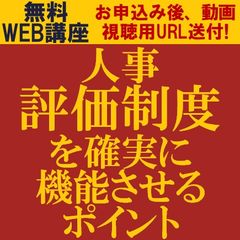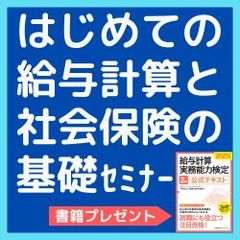──大変な試行錯誤を繰り返して、完成に至ったのですね。その組織図鑑の内容とは具体的にどのようなものでしょうか。
嶋谷 人を軸にした「社員編」と、組織を軸にしてまとめた「仕事編」に分かれています。
「社員編」は、39ページにわたり、国内外で多様なキャリアを積んだ16名の中堅社員が、それぞれどんな職種を経てきたのか、その時々で学んだことを時系列で図解しています。仕事の成果ではなく、どういう「技術」や「知識」をそれぞれの職種で身につけたか意識して「学んだこと」を記載して頂きました。
また、各部署で身につけたスキルの変遷もまとめています。例えば私の場合、マーケティングのスキルとして身につけていたのが、最初は「POPや販促ツールなどの制作」と「導入イベント」でした。これが、「商品担当業務」をすべてできるようになり、最終的には海外に行って「現地のメンバーにマーケティングやセールスの手法をレクチャー(ローカライズ)」する業務も担当した、というような具合です。さらに、前の部署で学んだことが、次の部署でどう役立ったのか、スキルの繋がりも分かるようにしています。もう一つ、アンケート等で「どんな点に苦労したのかを知りたい」というニーズが挙がっていたので、この点にも触れています。これらの情報から、例えば「海外志向ならどんな経験を積めばいいのか」、といったことが把握できるようになっています。
──非常に分かりやすいですね。見事にキャリアプランが見える化されています。
嶋谷 ありがとうございます。まさにそこが狙いです。参考にする情報がない中で、いざキャリアプランを考えてくださいと言われると、、現実ではあり得ないような、キャリアプランを立ててしまう場合があります。その点、この「社員編」があることで、どのようなステップを踏めばよいのかを実例をもとにイメージでき、現実的なキャリアプランを描きやすくなります。
黒木 社員には名前や顔写真も含めて情報を公開することを了承いただいた上で、協力してもらっています。なので、何か知りたいことがあれば、誰々さんに相談をしに行くといったことができるのも特徴です。実際に若手から人事部に「職種図鑑に載っている社員に話を聞きたい」とリクエストが来るようになりました。
──イメージ通りに使われているのですね。もう一つの「仕事編」についても教えてください。
嶋谷 「仕事編」は、各組織の繋がりを一つの図にまとめた「組織連携図」で全体を俯瞰し、次に各職種の業務内容を具体的に把握してもらう構成にしています。当社には、さまざまな部署や仕事があるので、まずはその全体像を掴むことで、どう連携して業務を行っているかを把握できるようにするためです。
業務内容(職種紹介)のパートは代表的な57職種について、身につく実務能力や積むことができる経験、そして得たことが将来どのようなキャリアに活かせるかといったことを、写真とともにまとめたものです。そのボリュームは全部で145ページになります。
黒木 こちらは現場のマネジメント層や、実際に活躍している若手に書いてもらっています。そのため、社員が他のメンバーから「職種図鑑見たよ」といった声をかけられ、働くモチベーションにも繋がるという副次的なメリットもありました。
嶋谷 さらに、巻末で「身につく実務能力一覧」を掲載しています。ここで紹介する実務能力は、「コミュニケーション能力」のような多くの部署で身につく汎用的な能力ではなく、本当にその部署で身につく、固有の実務能力をまとめています。
黒木 これにより、ゴールから逆算の発想でキャリアプランを描けるようになっています。例えば、「将来海外でこのような仕事で活躍したい」と考えたときに、ある特定のスキルが必要だと分かったとします。そのスキルを身につけるためには、この部署でこの実務能力を身につければ実現できる、といった目指すべきキャリアを自らプランニングすることができます。
「社員編」と「仕事編」を組み合わせることで、こういう部署に行きたい、という漠然的な考え方の「点」から、具体的なキャリアプランを想定した「線」を描けるようになるのです。
――「職種図鑑」を正式にリリースしてから、社員よりどのような反響が上がってきましたか。
嶋谷 「仕事編」では、100名以上の社員から、自らの経験をもとにコメントを記載してもらった「どのように今後のキャリアに経験がいきるか」というパートがキャリアの具体的な指針になった、と好評でした。誰しも自分が今やっている業務は今後のキャリアに役立つのか、と疑問を持つことがあるかと思います。例えば、弊社の若手社員は入社時から2年間営業現場を経験しますが、もしマーケティング部を希望している場合、毎日店舗回りをしていると自ら描いたキャリアプランから外れた気がしてくるものです。しかし「職種図鑑」を開くと、「営業活動が将来マーケティングや商談などに、このような経緯で役に立った」という先輩の実体験を知ることになります。そのため、言われたことをやるだけの後ろ向きの姿勢から、キャリア形成のための貴重な経験と思い直し、モチベーションがアップし、現在の仕事に熱心に取り組めるようになったという声が多くありました。
また「社員編」で好評だったのは、活躍する先輩社員が自ら作成したキャリア変遷を、テキスト&図解付きで見れることですね。過去にどのような職種を経験し、現在に至っているのかを時系列で体系立てたものがこれまではありませんでした。若手社員にとってロールモデルとなる先輩達の歴史が一覧で確認できるようになったので、自分のキャリアプランを組み立てる上で非常に参考になる、との声が多く挙がっています。
黒木 「職種図鑑」を活用することで、今までの上司と部下のコミュニケーションだけでは、ある意味、表面的な情報にとどまっていたキャリアの会話が、今では「君はここが不足しているから、この部署に行けばこのようなスキルが学べる」というように、具体的なアドバイスに変化したことも大きいと思います。
――「職種図鑑」の誕生により、より若手社員に伝えたい、知ってもらいたいと思うことはありますか。
嶋谷 「職種図鑑」作成にあたり、現在活躍している社員にたくさんインタビューをしたのですが、意外にも入社時に描いていたキャリアプランを実現していない人が多いことがわかりました。最初に思い描いていたキャリアと、実際に職場で活躍することは、全く別のことなんだという発見がありました。もちろん、そこには本人の力量や意思が大きく関わってくるのですが。会社という組織に属する以上、自分の希望する部署にすぐ配属されるわけでもありません。何かに迷った時には、そういうキャリア経験を積んだ先輩社員の事例を参考にすると良い、と新入社員にメッセージを発信しています。
黒木 「このキャリアプランには、このスキルだけが必要」といった単線型のキャリア観では、そこから逸するとネガティブになることが多いものです。「職種図鑑」を通して多様なキャリアの選択肢があることを知れば、たとえ理想のキャリアから外れたとしても、別の道、別のやり方で、やりがいや満足感を見出すこともできるでしょう。「職種図鑑」の誕生によって、若手社員をはじめ、多くの社員がキャリアに関してより鮮明な会話ができるようになったと思います。
――社員自身がキャリアアップを果たした事例は出ているのでしょうか。
嶋谷 昨年(2018年)にリリースしたにも関わらず、支社から本社に戻ってくる営業3年目の社員達にとって、すでにバイブル的な存在となっています。「職種図鑑」の情報を元にその後目指すキャリアを考え、希望先の部署を決定した社員事例はすでにでています。
黒木 約200名の社員に自らロールモデルになってもらい、「職種図鑑」を制作しました。彼らのキャリアを参考に、他の社員が中長期の視点で自身のキャリアプランを具体的に描けるようになり、若手社員のキャリアアップへのモチベーションは確実に高まりました。
嶋谷 またキャリア研修や人事・上長面談で、「職種図鑑」をベースに具体的な相談が行われるようになりました。人事部としても、キャリア情報を体系化したことによって、人材のローテーションを考える際にどのような能力がどのような分野で生きるのか、といった生産性の高いスキル配分がより具体的にわかってきましたので、人材育成プランを考える上でも非常に役立っています。
黒木 やはり人事担当者にとっても、どのような社員がどのような職場に向いているのか、最適配置を考えることは大切ですから、そういった意味でも「職種図鑑」は役立っています。
――この取り組みは他のソニーグループでも展開されているのでしょうか。
黒木 ソニーグループ全体でキャリア開発も含め、会社・社員の双方向で情報を民主化する動きがあり、「職種図鑑」を横展開できないかという声が他の人事部から挙がっています。
嶋谷 グループ内からも反響がありまして、我々も資料提供をしたり、実際に説明に行ったりしています。同様に部門の「職種図鑑」を作りたい、社内求人に「仕事編」のフォーマットを使用したいといった相談を受けました。また中堅・シニア版の「職種図鑑(社員編)」を作って、シニア向けのキャリアセミナーで内容を紹介し、参加者全員が自らのキャリアを棚卸しすることで、今後のキャリアを再構築する機会を作っていこうという動きも出ています。
黒木 また、今後さらに情報を豊かにすることができれば、ソニーの共通システムに「職種図鑑」のコンセプトを展開することができると考えています。
嶋谷 「職種図鑑」自体のブラッシュアップとさらなる活用も進めています。この情報をベースに人材ローテーションの最適化や、既存の「仕事編」の「身につく実務能力」の欄をさらに具体的にかみ砕いて、実務能力取得の支援策を実施していこうと考えており、現在準備を進めているところです。
黒木 今はまだ情報をオープンさせたばかりの状態なので、その情報を今後人事部のデータベースとリンクさせ、キャリアモデルや人材育成などに繋げて、こうした活動を、人材開発のための大きなプラットフォームに育てていければと思っています。データベースとしての性能を高め、常に更新し続けることによって、社員のコミュニケーションプラットフォームとして、たとえばオンライン上で社員同士が自由にキャリアの意見交換ができるようにするなど、もっと進化させたいと考えています。自らのキャリア実現のために努力しようにも、方向性を間違えるとすべてが遠回りになってしまう時がある。これは、本人はもちろん、企業にとっても大きな損失だと言えよう。しかし、「職種図鑑」のようなキャリアの道標があれば、最適なルートで自分が望むキャリア形成に注力できる。これは、若手のみならず、全社員の成長へのモチベーションにつながり、仕事や組織へのエンゲージメント向上にも直結するはずだ。組織に合わせた調整が必要なものの、「職種図鑑」の作成自体に難しい知識もテクニックも要らない。業種、職種を問わず、あらゆる企業で取り組みやすい点も素晴らしい。ぜひ、あなたの会社でも「職種図鑑」の制作を検討してみてはいかがだろうか。
ソニーマーケティング株式会社