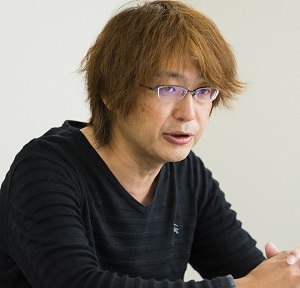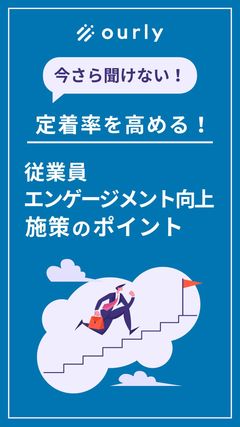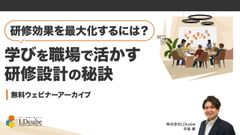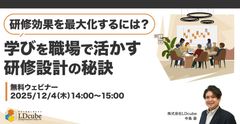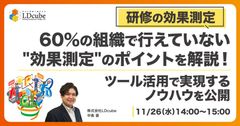――求職者はどの段階で「SUDAchi」を知り、研修を受けるのでしょうか。また、カリキュラムの内容や実施期間、研修中の賃金などについても教えてください。
太刀掛 SUDAchi」の取り組みについては全面的にアピールしているわけではありません。一般的な求人サイトや求人誌から応募してきた方を面接し、その中でいますぐ就業は難しいであろうという方がいれば「SUDAchi」のプログラムをお勧めするという形をとっています。当社HPの中に「SUDAchi」の記載がありますが、まだほとんどの求職者が知らないのではないでしょうか。
田中崇氏(以下、田中) カリキュラムは、求職者の不足しているスキルに合わせて、一人ずつ内容を設定しています。スタート前の求職者間のレベル格差が大きいので、ベーシックスキル、マインドセット、プロフェッショナル職業訓練などに分類し、テストやアンケートの結果に基づいて学習計画を立て、それぞれの個人に向けてカスタマイズします。
太刀掛 研修期間はカリキュラムによって異なるのですが、概ね80時間です。今のところ研修の想定期間を超えた人はいませんが、今後そういう方が出た場合でも、追加の研修時間を設定するつもりです。また研修中の賃金は、ほとんどの場合通常業務と変わりません。案件にもよりますが、変わるとしても差額は時給にして数十円程度です。
――現在に至るまで何名が「SUDAchi」で研修を受け、実際に就業しているのでしょうか。
田中 スタート時の2017年からの約2年半でおよそ260名が受講し、そのうち100名ほどが卒業、実際の現場で活躍しています。受講した方々の年齢は、下は18歳から上は70代までと幅広いですが、30~40代が中心です。
太刀掛 今期(2019年)の目標は1,000名の受け入れです。求職者は前述のように、一定賃金を得ながら汎用性の高いスキルを醸成することができます。また離職を防ぎ、長く勤続してもらうことで、企業側としては教育コストを回収できるというメリットがあります。
――「SUDAchi」は御社の全国の拠点で展開されているのでしょうか。また、内容は各拠点で同じなのでしょうか。
太刀掛 池袋でスタートした後、名古屋、松江、仙台、横浜、札幌、福岡、関西、岡山の各拠点にも「SUDAchi」を開設しました。内容は基本的には同じですが、地域や業務の特性によって多少の違いがあります。例えば、クライアント先で勤務するケースでは、求職者に早く慣れてもらうために、お客様先で一日過ごすなどといったカリキュラムを加えています。
――外国籍労働者の採用にも力を入れているそうですが、「SUDAchi」では言葉や習慣などの多様な問題に対してどう対応していますか。
太刀掛 当社で働く方はある程度日本語が話せる方ばかりなので、言葉の問題よりもビザの更新や日本の法律、労働時間などの法令遵守に気をつけています。
田中 情報やコンプライアンスの捉え方、働き方の概念が外国人と日本人では異なります。そのため、ロッカーの開け方や勤務時間の考え方、機密保持の問題まで、マンツーマンでしっかりと教育しています。その点では、日本人の研修生よりも多くの時間を割いていると言えるでしょう。
太刀掛 我々日本人からすると当たり前のことでも、文化背景が異なると色々なことが当たり前ではなくなります。その事実を事前に説明するのと、後で説明するのでは相手の反応も大きく変わるので、可能な限り丁寧に時間をかけて説明し、納得してもらうよう努めています。
例えば100人を超える大規模のコールセンターでは、全員の出勤希望をシフトに反映するため、2~3週間前には希望シフトを出してもらわなければなりません。ですが、「なぜ事前に希望シフトを出さないといけないのか」という理由を事前に外国籍の求職者に説明しないと、「自分の希望する時間に勤務できるからこの仕事を選んだのに、どうしてそんな前にシフトを出さなければならないんだ?」というように認識に語弊が生じます。
田中 日本人の場合は話し合いで解決できることが、外国人の場合は「聞いていないので応じられない」という認識のミスマッチに陥ることがあります。そのため、勤務時間やシフト変更の事前申請などにおける考え方など、細かいレクチャーも「SUDAchi」のカリキュラムに設けています。
太刀掛 人材が集まりにくい業種は、事前に求職者に説明すべきことを伝えきれていないのではないかと思います。例えば介護業界では、なぜその業務が発生し、対応しなければならないのかと事前に伝えるべきところを、なんの説明もなく即戦力として人材を送り込んでいるのではないでしょうか。その結果、介護を受ける方と介護者との間にトラブルが生じたという話を聞きます。そのため、コールセンターで働く上でどのようなスキルや心構えが必要なのかということも、カリキュラムに組み込むようにしています。
――「SUDAchi」の卒業生が現場に配属された後、どのようなフォローをしているのでしょうか。
太刀掛 基本的に通常入社の方と同様、適性に合った現場に就業してもらいますが、何か悩みや疑問があった場合に相談しやすいよう、トレーナーによるカウンセリングを継続しています。職場のトレーナーが親身にケアしてくれることによって心理的安定が保たれ、また時間の経過とともに会社への帰属意識が醸成されることで、就業定着率が高まるのもポイントです。将来的には、卒業生にも「SUDAchi」のトレーナー役を担ってもらいたいとも考えています。
田中 「SUDAchi」トレーナーはメンターとも呼ばれており、卒業生が独り立ちした時の心強い支えになります。実際に現場に出たらイメージと違っていた、というミスマッチの問題が浮上しても、上司には直接悩みを打ち明けにくいものです。そんな時は「SUDAchi」トレーナーに相談することで解決に繋げることができます。「SUDAchi」トレーナーが働く人と現場のハブになることで、次第にトラブルもなくなるのです。実際に現場で悩み苦しんだ経験を経た「SUDAchi」卒業生であるトレーナーのほうが、求職者のメンターとして活躍していることが多いですね。
またトレーニング後のフォローの一環として、現場の責任者や上司が感謝の言葉や苦労をねぎらうビデオレターを、「SUDAchi」を卒業して3ヶ月経った方々へに送っています。そういう、人と人との繋がりに興味のある卒業生が「SUDAchi」の運営スタッフとして業務に携わることもあります。また、現在業務外のカウンセリングは資格を有したプロのスタッフが行っているのですが、自身が同じような悩みを経験している、していないではフォローの仕方にも大きな違いがあるため、今後は悩みや苦しみを克服した方に、ケアスタッフとして就業してもらうことも検討しています。
――「SUDAchi」の卒業生がトレーナーや運営スタッフになる道もあるということですね。
田中 現場のトレーナー経験者や元保育士さんなどがトレーナーとして中心的な役割を担っており、現在社内で適正のある方を募っています。いわゆるホスピタリティがあり、受け止める力の高い方ですね。
太刀掛 コールセンターでマネージャーやスーパーバイザーなど、オペレーターから昇格している方に共通していることは、飲み込みが早いということです。全員というわけではありませんが、そういった方は、たいていの人が仕事で躓くポイントがわからないことが多い。だから、ポイントを誤認して教わる側との意識にズレが生じやすいのです。だからこそ、前職で悩んだ経験のある方や、育児経験者など、ケアする側の経験が豊富な方を中心にトレーナーを選ぶようにしています。
――「SUDAchi」トレーナーの育成も必要だと思います。どのような方針で指導されているのでしょうか。
太刀掛 「SUDAchi」を受講した方々に仕事が楽しい、もっと長く働きたいと思ってもらうために、トレーナーはどのようなマインドを持ち、求職者に対して何をするべきなのかをいまも模索しながら育成しています。何を、どうすればいいのか自ら気づき、実践していく方法を取っています。“コミュニケーターファースト”を軸に人材をアサインし、育成しているので、ようやく一人前として任せられるようになるには一年くらいかかりますね。
田中 「SUDAchi」のトレーナーは求職者に技術を教えるだけでなく、メンターとして精神的な助言や指導を行う必要もあります。そのためトレーナーの育成では、いかに人の気持ちを理解し、寄り添うことができるかなど、人間力を養うことに重点を置いています。マインドセットの手法やコツから学ぶことになるので、一般的なコールセンターのトレーナーとは役割が違ってくるかもしれません。
――「SUDAchi」導入後、どのような成果がありましたか。
太刀掛 地域によって異なるのですが、これまではせっかく入社しても一年後には半分程度になっているという状況がありました。しかし、「SUDAchi」の導入・活用によって個々人が長く勤務するようになり、目標であった7~8割の定着率を達成しました。そのため、離職した分求人広告を出し、また採用するといった一連の流れが緩やかになると言うのでしょうか、極論で言うと止まりました。
――企業・卒業生(就業者)双方にとって、「SUDAchi」を活用することによって得る利点は何でしょうか。
太刀掛 コールセンターに就業する際、弊社が独自に集める場合と派遣会社様を通す場合があるのですが、派遣会社様から紹介された方にも「SUDAchi」を利用していただいています。そのおかげで「派遣支援するならベルシステム24」と言ってくださる派遣会社様もいらっしゃいます。
また、100名規模のコールセンターを例に効果試算も調べました。就業者の定着率が1年で50%、常に100名を維持するために研修を年9回行うとした場合に比べ、100名中80%が退職せずに働き続ければ、研修回数は年3回まで短縮できることがわかりました。つまり、求人広告を出す頻度を減らせるのです。そして、研修にかける人的、時間的な労力が削減されることによって生産性が上がり、退職補充コストもカットできるという良い連鎖が生まれます。
我々の調査では、同様の100名規模のコールセンターで求人広告費が約20~30%カットできるという見通しも出ています。また、同じ方が継続勤務することでスキルが上がりますので、品質も向上し、企業側および就労者本人の満足度も上がるといった効果が期待できます。
田中 企業側の管理者にとっては、研修に費やす工数が減ることで、お客様のニーズを汲み取ったよりクリエイティブなマーケティング施策などを考える時間が持てるようになるのではないでしょうか。企画を練る時間ができるので、そこから新しいビジネスが生まれます。「SUDAchi」導入によって、求職者にとっては就職の選択肢が広がり、企業側にとっては今まで採用を見送っていた人材の中に潜在ニーズを見つけるだけでなく、利益創出を生み出すこともできます。
――「SUDAchi」に取り組むにあたって課題や気づきはありましたか。また、開設にあたり社内的な障害はありましたか。
太刀掛 採用基準に未達な方が多くいる中、まだ「SUDAchi」の存在をアピールしきれていないのでは、と思います。どのような情報発信をしたら、自身にとっても企業にとっても良い人材になりうる求職者から応募がくるのか、まだ模索中なので、そのための訴求方法を思案しているところです。
また、人が介在しているので不適切な表現だとは思いますが、ビジネスの基本はコストを抑えて成果を出すこと。「SUDAchi」という取り組みは、最初そのコストを上げてしまうのではないかという反対意見がありました。しかし、今の経営者の方針「小さく産んで大きく育てる」に基づき、まずはやってみようと。今までビジネスは収益を増やして利益を提供すれば良かったのですが、そうでないところで貢献しなければならないよね、という話になりました。その結果、色々な面で社会貢献に繋がり、今では積極的に活用していく流れになっています。
――今後の展望をお聞かせください。
太刀掛 人材不足は全業界共通の課題です。「SUDAchi」は我々のスキームとして活用するだけでなく、人が集まりにくい他業界にも有効活用していただけると考えています。そのためまずは介護業界にアプローチし、仕事のやりがいをうまくイメージ化することによって就労への期待や満足度を形にし、将来的には人材を誘致する一助になればと思っています。
当社の札幌オフィスでは、社内のバックオフィス業務の集約や、障がい者雇用を促進する動きも出ています。人と人との繋がりを大切にする「SUDAchi」の概念を浸透させることによって、障がい者雇用も促進していきたいですね。また、就業先に困っているシングルマザーの方々など、さまざまな人材に可能性を見いだして、今後も積極的に採用していきたいと思っています。日本のサービススキルは世界最高と言われており、日本人が接客に求める水準も当然高い。本来であれば、高いスキルを持った人材を採用し、育成にかかるコストを抑えようとしがちだ。しかし、それでは採用に対する視野が狭まって人材不足が起こりやすい。そこで、これまで学ぶ機会がなかったことによりチャンスを得られなかった人たち(=他社では採用に至らないレベルの人材)に目を向ける“逆転の発想”で人員を獲得。自前の教育機関「SUDAchi」で、業務上必要な技術的スキルはもちろん、人間力も養いつつ一人前に育て上げるスキームは、今後の人材不足解消に繋がる画期的な取り組みではないだろうか。今回の取材を通して、個々の能力や事情に寄り添い、多様性を持って大切に育てている姿勢にも共感を抱いた。「SUDAchi」の存在は、コールセンターのみならず、様々な業界に通用するものであり、企業・求職者双方に多くの享受を与えるものだと思う。
株式会社ベルシステム24