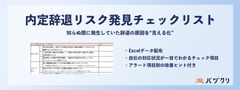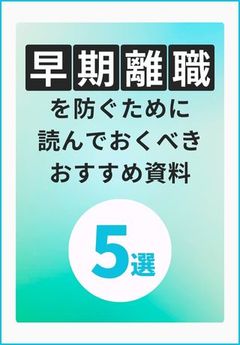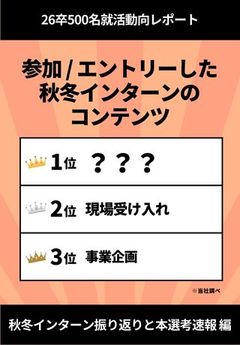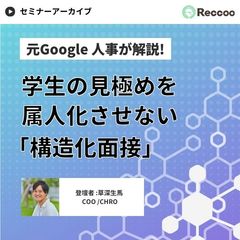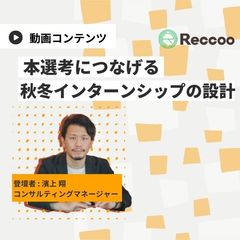選考採用の具体的な方法:【学力試験・作文】の場合
選考採用における「学力試験・作文」について、厚労省資料では次のとおり留意点を示しています。※厚生労働省「公正な採用選考をめざして(令和7年度版)」より
●学力試験・作文を行う場合、応募者が、求人職種の職務遂行上必要な適性・能力(知識)をもっているかどうかを判断するための方法として適当かどうか検討しましょう。
●作文を書かせる場合は「私の家族」「私の生いたち」等本人の家庭環境にかかるものや、思想・信条を推測させるものをテーマとしないようにしましょう。
ポイント:応募者の「誤解を避け」、「過度な負担とならない」配慮を
まず、学力試験でも、作文でも実際の職務内容と何かしら結びついた内容にすることが大切です。学力試験であれば、その職務に必要な適性・能力を確認につながる設問にするといったことです。そのように考えると、仮に「人を大切にする職員かどうかを確認したい」というのであれば、作文で『私の家族』をテーマにすることも結び付いた内容とも捉えられます。しかし、留意すべきは『私の家族』、『私の生いたち』等をテーマとすることは、家庭環境などにより採用を判断したと誤解されるおそれがあります。採用する側に、家庭環境により採用を判断する意思がまったく無かったとしても、応募者や第三者から見れば、就職差別と受け止められるおそれがあるということです。
また、『私の家族』、『私の生いたち』等をテーマとした作文が、応募者にとって過度な負担と感じることも考えられます。過去を振り返ること自体は大切なことともいえますが、一方で応募者にとって振り返ることが過度な負担になる(例:過去の嫌な出来事を思い出すきっかけとなってしまう)ことも十分に考えられ、作文がそのような場面になってしまうことは望ましくありません。
応募者の人生そのものを尊重する意識を常に心掛けていきましょう。
選考採用の具体的な方法:【適性検査等】の場合
選考採用における「適性検査等」について、厚労省資料では次のとおり留意点を示しています。※厚生労働省「公正な採用選考をめざして(令和7年度版)」より
●「職業適性検査」「職業興味検査」「性格検査」などを用いる場合は、目的に応じて適切な種類の検査を選んだうえで専門的な知識と経験をもった人が用いるようにしましょう。
●適性検査等の結果を絶対視したり、うのみにしないようにしましょう。
●適性検査等によって適性・能力に関係のない事項を把握したり、その結果のみで採否を決定しないようにしましょう。
ポイント:「適性検査」の結果だけではなく、活用して『人(応募者)』をより知ること
公正な選考採用のポイントは、職務遂行上必要な適性を確認することも一つであり、したがって「適性検査」は有効な方法の一つといえます。しかし「適性検査」の結果に依存しすぎることは、望ましくありません。大切なことは「適性検査」の目的を明確にすること。そして、「適性検査」をどのような段階・場面などで活用していくかということです。
採用が決定されるべき要素は「適性検査」ではなく『人(応募者)』そのものです。その『人(応募者)』をより知るために、「適性検査」を活用するといったことです。また「適性検査」の結果に依存しすぎると、『人(応募者)』を知る意識が希薄となり、その人に対して特定の印象付けをしてしまうことにもなりかねません。
応募書類、学力試験・作文、面接などの方法とも組み合わせ「適性検査」をどのように活用するかを整理することが大切です。適性検査の結果に向き合うのではなく、会社として『人(応募者)』としっかりと向き合うことこそが、人権を尊重した選考採用につながります。
- 1