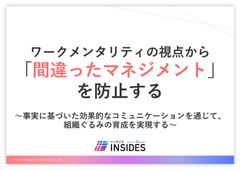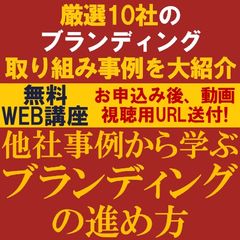この職場では、この状況が職場でのチームワークに影を落とし、単なる個人の働き方の問題に留まらず、周囲のモチベーション低下や不公平感、ひいてはチームの生産性にも影響を及ぼしている様子。感情も絡むこの状況をどう捉え、企業はどう対応すればよいでしょうか。

毎週の有給休暇の取得が「悪用」と見られる背景にあるもの
周囲の社員が「悪用」と見なす背景には、いくつかの感情や事実が絡み合っていると思われます。(1)不公平感と業務負担の集中
フルタイム契約でありながら、実質的に週4日勤務のような状態が続くと、その分の業務は他の社員に割り振られます。特に繁忙期や突発的な業務発生時に、休んでいる本人の業務をカバーする社員は「なぜ自分たちだけがしわ寄せを受けるのか」という強い不公平感や不満を抱くのは自然なことです。(2)責任感の欠如への疑念
契約上の責任を果たしていない、チームへの貢献意識が低いと映る可能性もあります。特に「ほぼ毎週」という頻度は、計画的というよりは業務やチームへの配慮が不足していると受け取られがちです。(3)コミュニケーション不足
有給休暇を頻繁に取得する背景が周囲に共有されていない場合、憶測や誤解が生まれやすくなります。「個人的な都合ばかり優先している」とネガティブに解釈されることも少なくありません。確かに有給休暇は労働者の権利で、「自由にいつでも取得できる」ものではありますが、日頃からのコミュニケーション不足から、たとえ法的には問題のない有給休暇取得であったとしても、チーム内の軋轢は避けられません。
労働者の「負担」で有給休暇を取得している可能性も考慮
一方で、当該パート従業員が、週5日勤務に何らかの負担を感じている可能性も考えられます。(1)体調や精神的な問題
表には見えない体調不良や精神的ストレス、家族の介護や育児といった個人的な事情が背景にあるかもしれません。週5日勤務では対応しきれず、有給休暇を頻繁に取得せざるを得ないのかもしれません。(2)業務内容や人間関係への不適応
仕事内容が合わない、あるいは職場の人間関係やハラスメントに悩み、出社すること自体に精神的な負担を感じている可能性も考えられます。(3)有給休暇に対する極端な考え
有給休暇の適切な利用方法について本人が十分に理解していない、あるいは「使えるものは最大限使うべき」と極端に解釈している可能性もあります。企業の「時季変更権」の限界
(1)有給休暇取得の原則
「労働基準法」第39条により、有給休暇は労働者の権利として保障されています。労働者は希望する時季に有給休暇を取得できます。(2)時季変更権の限界
企業は「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り、労働者の希望日を変更できる「時季変更権」を有しています(労基法第39条5項)。しかし、単に人員不足や業務の繁忙を理由とする抽象的な理由では不十分で、「代替要員の確保が不可能であり、業務運営が著しく妨げられること」を企業側が具体的に立証できる必要がある等、厳格な要件があります。
安易な時季変更権の行使は、違法な行使と判断されるリスクが高く、損害賠償請求や労働基準監督署からの是正勧告、企業イメージの低下といった重大なリスクを招きかねません。
法的リスクを避けるための具体的な対応策
(1)事実確認と丁寧な対話
管理職や人事担当者が個別面談を実施し、「有給休暇取得頻度が高い背景に何かあるのか」を冷静に確認します。できるだけ傾聴するようにしましょう。そのうえで、企業としての期待(例えば、「週5日フルパートとしての役割を担ってほしい」)を誠実に伝えることが重要です。労働契約は、労働者の労務提供に対して使用者が報酬を支払う双務契約です。場合によっては、契約上の労務提供ができていない状況を本人に理解してもらう必要もあるでしょう。
(2)契約内容の見直し提案(所定労働日数の変更など)
もし本人が何らかの理由で週5日勤務を負担に感じている場合は、週4日勤務への契約変更を提案することも一つの解決策です。あるいは、業務内容を見直して週4日勤務で行っていただける内容で契約変更を提案することも一案です。ただし、これは一般的には労働者にとって賃金減少等の「不利益変更」となるため、本人の自由意思による合意が不可欠です(「労働契約法」第8条)。そのため、社会保険・雇用保険の加入資格や労働条件の変化についても具体的に説明し、十分に理解を得た上で、話を進めるようにしましょう。
この提案は、当該パート従業員が周囲とも軋轢なく無理なく長く働ける環境を整えるための「選択肢」であることを伝える姿勢が何よりも重要です。
(3)公平性の確保と他社員へのケア
公平性の確保という点では、計画的有給休暇を導入して、他の社員も有給休暇を取りやすい環境をつくります。一方で、相手の事情や仕事に対する考え方、価値観などを知ることで「お互いさま」、「助け合い」の意識は醸成してきます。対話の場を設け、チームのメンバーのことを知る機会を多くすることも大切です。- 1