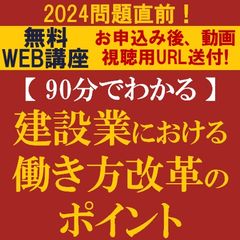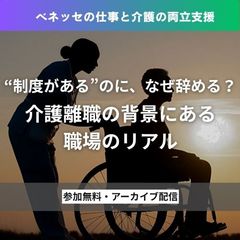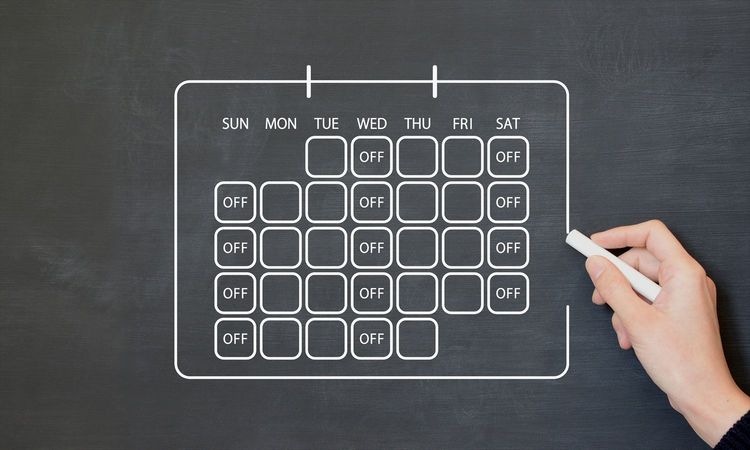
「労働時間」と「賃金の観点」からの週休3日制の“3類型”
現在、「週休3日制」が話題になっています。特に、2025年4月から国家公務員に週休3日制が導入され、注目を集めています。確かに、休日が週3日になれば、魅力的な働き方になります。会社にとっても採用などでアドバンテージになることは確かでしょう。しかし、週休3日制は一括りにされがちですが、以下の観点から分類されます。●総労働時間を減らした場合、その分の賃金を減額するか否か
(1)労働時間短縮・賃金維持型
週の休日を1日増やしその分の労働時間を減らしますが、賃金は減らさないパターンです。しかし、この制度の導入は、多くの企業にとって現実的ではないでしょう。労働時間を減らしても、その分の生産性が上がることは通常はないからです。また、賃金が同じまま総労働時間を減らすと、時給単価が上がります。当然、時間外労働をした場合、週休2日制のときより割増賃金額も上がります。割増賃金の計算に関しては「労働基準法」上の問題です。「労働基準法」を下回る計算方法は、社員の同意があってもできません。
(2)労働時間短縮・賃金減額型
このパターンは、減った労働時間の分だけ賃金が減らされるというものです。現在働いている社員に対して行う場合は、労働条件の不利益変更の問題が生じますので、社員の同意が必要です。そこで、希望者のみに導入するという方法がとられます。しかし、様々な事情を抱えた方がいらっしゃいますので、このパターンで働きたいという社員は多く見られます。また、会社にとっても、育児・介護等による離職の防止や採用の点でメリットがあります。
(3)総労働時間維持型
このパターンは、今までの総労働時間を維持したまま、休日を週3日に増やすというものです。この場合、1日の所定労働時間は増えますが、それでも週3日の休日があった方が良いと考える社員は多いでしょう。仕事以外に大切な活動がある方にとっては魅力的な働き方になります。ただし、このパターンは「労働基準法」上の観点から検討しなければならない点があります。以上、週休3日制について3パターンを見てまいりましたが、国家公務員に導入され注目を集める週休3日制は、(3)のパターンになります。(1)(2)の労働時間を減らすパターンは、限定正社員(多様な正社員)制度につながる話になります。限定正社員とは、地域・職務・労働時間のいずれかが正社員と比べて限定されている社員のことをいいます。
そこで、この記事では、従来の総労働時間を維持したまま、休日を週2日から3日に増やすという(3)のパターンについて、法的に注意すべき問題点を解説します。
「総労働時間維持型」の週休3日制導入に必要な法的対応
総労働時間を維持したまま週休3日制を導入するにあたって、一般的に多いであろう「1日8時間・週休2日・週所定労働時間40時間」の企業が、週休3日に移行するケースを想定して考えてみましょう。なお、話を簡潔にするため、ここでは国民の祝日などは考慮しないことにします。そもそも、総労働時間を維持するためには、週に1日増えた休日分の労働時間(8時間)を、他の勤務日に働いてもらう必要があります。週4日勤務なので、1日平均10時間となります。
しかし、「労働基準法」では1日8時間・週40時間が法定労働時間とされていますので、1日8時間を超える時間は時間外労働となります。当然、2時間分の割増賃金が発生することになります。
この問題を解決するためには、変形労働時間制の導入が一般的です。以下では、変形労働時間制のうち、「フレックスタイム制」と「1ヵ月単位の変形労働時間制」をご紹介します。
●フレックスタイム制
フレックスタイム制とは、清算期間(1ヵ月以内の一定の期間)で労働時間を考える制度です。例えば、清算期間を4週間とし総労働時間を160時間と決めた場合、4週間で160時間を超えない限り、1日や1週間単位での時間外労働は発生しない制度です。したがって、フレックスタイム制を導入すれば、法定労働時間の問題はクリアできます。しかし、フレックスタイム制は、社員が始業・終業時刻を決めることができるのが前提の制度です。この条件を満たせる職場はそれほど多くないのが実情です。実際、フレックスタイム制の導入がなかなか進まない理由でもあります。
既にフレックスタイム制を導入している企業が週休3日制という選択肢を追加するのが現実的でしょう。また、フレックスタイム制の導入を検討している企業にとっても、制度設計を進める中で、週休3日制を選択肢の1つとして検討する価値はあると思われます。
●1ヵ月単位の変形労働時間制
この制度は、1ヵ月(以内の一定の期間)を平均して週40時間以内であれば、特定された日や週について法定労働時間を超えて働かせることができる制度です。特定された日や週については法定労働時間を超えても時間外労働となりませんが、この制度にも様々な条件があります。大切な条件の1つとして、事前に勤務日ごとの始業・終業時刻を特定しなければならない点が挙げられます。しかし、「1日8時間・週5日勤務(週40時間)」という働き方を「1日10時間・週4日勤務(週40時間)」に変える週休3日制の導入なら勤務日ごとの始業・終業時刻を特定しなければならない条件は容易にクリアできます。週休3日制との相性は良く導入しやすいと考えられます。
新制度導入時に押さえておくべき注意点
週休3日制に限ったことではありませんが、新しい働き方を導入する際には、現実的に運用できる制度の導入が求められます。しかし、それと同時に、法的な問題点の検討が不可欠です。週休3日制のような労働時間にかかわる問題は割増賃金の問題につながります。法的検討が不十分な導入は未払い残業代が発生することになりかねません。- 1