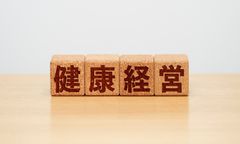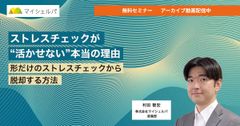五月病=ハネムーン期の終わり
日本でこの病名が人々に浸透したのは1960年代から70年代にかけてです。当初は大学生に対して使われていた言葉ですが、最近では社会人に対しても使われています。この「五月病」の本質は現在の言葉で言うと、環境が変わったことによる「適応障害」や「抑うつ状態」に近いと考えらます。僕は産業医として、新入社員研修を毎年実施しているのですが、その際には必ずこの五月病について触れます。ただし五月病という言葉は使いません。僕が使うのは、「ハネムーン期とその終わり」という言葉です。
現代の就職は、情報を集めたり、インターンに行ったりと、結構大変な作業を経ている方も多いです。そうなると、多くの方々が希望に満ちて就職することになります。さぁこれからやるぞ、という気持ちに溢れています。この時期をハネムーン期と呼びます。
ただ、実際に入職して働いてみると、外から見ていた頃やインターンをしていた頃とのギャップに戸惑う人も多いです。それもそのはず、企業はいい学生を集めたいので説明会では会社のキラキラした部分を押し出しますし、担当する面接官もそれなりの人材を用意します。
ところが実際入社してみると、上司が嫌な人だったり、対外的にはペコペコしないといけなかったり、最初のうちは泥臭い仕事をしなければいけなかったり、海外に向けて大きな仕事をしたいと思って入社したのに「てにをは」を直される細かな書類づくりに追われたりの毎日だったりします。
そうすると、入社した時点の夢とは違っているので、全員とは言いませんがほとんどの人が軽い落胆や幻滅を覚え、一時的に落ち込む時期が来ます。これがいわゆる「五月病」だと僕は考えています。
大切なのはあらかじめ「五月病」について知っておくこと
その対処はどうすればいいのでしょうか。誰にでもそういうことが起きうるということ、そしてその状態からは割と早めに復活するということを、あらかじめ知っているということが重要です。というのも五月病の状態に陥ったときに、そのことを知っていれば気が楽だからです。
一般的に人は先が見えないストレス状態には弱いのですが、先がわかっていればそれなりに頑張れるものです。例えば、期末で無茶苦茶仕事が忙しい場合を考えてみましょう。期が終わるとこの仕事は楽になると知っているから、多くの人は頑張りが効くのです。先が見えずに大変な仕事を延々と続けられる人は極めて少数です。
そこで僕は新人研修でいつもこんな風にお話しします。
「今は高揚感に満ちたハネムーン期だけど、これから実際働いてみると思っていたのと違っていて落ち込む時期が来ます。落ち込み方は人それぞれです。ただ、半年から一年すればまた気分が戻ってきて平常通りに働ける日々が始まります。そこからが社会人としての真の始まりです。
あなた方の多くは今後40年以上働く人生を送ります。もちろんこの会社に残って、出世し、最終的に経営陣になる人もいるでしょう。あるいは途中で転職する人、独立する人、早期にお金をためてリタイア(今流行のFIREですね)、あるいはセミリタイアする人もいるでしょう。
いずれの道に進むにしても、就職した直後にこういう落ち込む時期が来ることは普通です。」
相談できる場所を教えておくことも大切~必要に応じて産業保健職も使いましょう
とはいえ、先は必ず明るい道が開けているということを教えるだけでは十分とは言えません。さらに、悩んだ時に相談できる所をあらかじめ提示しておくことも有効でしょう。僕自身は産業保健職として「いつでも相談に来てね」と新入社員研修時に言ってはいますが、実際にはあまり相談に来ません。おそらくは、自分のロールモデルとなる先輩に相談をしているのでしょう。
そう考えると新入社員の管理職になった方々こそ、この経過は新入社員にとって自然であることを理解することが大切になってきます。もしよくわからないと思ったら、ご自身が新入社員だったときの上司や先輩に話を聞くのもいいかもしれません。おそらく何か参考になる話を聞かせてくれると思います。
最後に、こういった手をいろいろ使ったにもかかわらず、部下が「五月病」にかかって休みがちになった、あるいは休職してしまったときの対処法です。もし産業医や産業保健師がいるなら一日でも早く連絡しましょう。「まっとうな」産業医や産業保健師であればいち早く面談を組むなり何らかの手を打つはずです(逆に言うと、連絡したのに対応しない、あるいはできない産業保健職は、思い切って別の産業保健職に変更することも考慮に入れたほうがいいかもしれません)。
産業保健職は本人の話を聞いたうえで人事労務と相談して、あるいは三者面談、場合によっては親御さんを入れた四者面談をしたあと、落としどころをいくつか提案してきます。そこから先は就業規則や会社の考え方に則って人事労務として対応してきましょう。
- 1