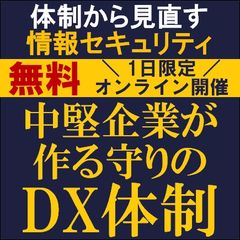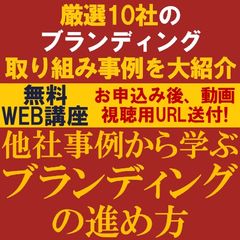「演技性パーソナリティ障害」の特徴
そもそも、「演技性パーソナリティ障害(Histrionic Personality Disorder:HPD)」とは、過度な感情表現と注目を浴びたい欲求を特徴とするパーソナリティ障害である。周りからの注目や承認を得るために、演技のように大げさな言動をとったり、感情を必要以上に誇張して表現したりすることがある。その特徴を整理すると、下記のようになる。1)過度な感情表現
感情豊かに、喜び、悲しみ、怒りなどを表現。しかし、その感情は浅く、すぐに変化することがある。2)注目を浴びたい欲求
常に周りから注目を浴びていたいと願い、そのために劇的な行動や言動をとることがある。3)性誘惑的な行動
異性を惹きつけるために、不適切なほど性的に誘惑的な言動や服装をすることがある。4)自己中心的な言動
自分の欲求や感情が最優先で、他者の気持ちや立場に配慮することを苦手とする。5)影響を受けやすい傾向
他者からの影響を受けやすく、流行や周りの意見に流されやすい傾向がある。6)人間関係の不安定さ
表面的な人間関係を築くことは得意であるが、深く安定した関係を維持することを苦手とする。演技性パーソナリティ障害の原因
以上のような特徴を持っているから、演技性パーソナリティ障害のことを知らない一般人は騙されることが多い。精神疾患の一種であり、それが無意識的に表現される。原因は解明されていないが、以下の要因が複雑に絡み合って発症すると考えられているようだ。1)遺伝的要因
パーソナリティ障害は遺伝する可能性がある精神疾患であり、演技性パーソナリティ障害も例外ではない。2)環境的要因
幼少期の養育環境や経験が影響している可能性があると考えられている。例えば、愛情不足や過保護、虐待などが要因となるとも言われている。3)心理的要因
自己肯定感の低さや、他者からの承認を強く求める心理などが関係していると考えられている。いずれにしても、精神疾患であることに変わりはないから、早期に専門医師の診断を受け、治療を行うことが大切である。ちなみに、アメリカのDSM-5(精神障害の診断・統計マニュアル第5版)における演技性パーソナリティ障害の診断基準は下記のとおりとなっている。
1.自分が注目の的になっていない状況では楽しくない。
2.他者との交流は、しばしば不適切なほど性的に誘惑的な、または挑発的な行動によって特徴づけられる。
3.浅薄ですばやく変化する感情表出を示す。
4.自分への関心を引くために身体的外見を一貫して用いる。
5.過度に印象的だが内容がない話し方をする。
6.自己演劇化、芝居がかった態度、誇張した情緒表現を示す。
7.被暗示的(すなわち、他人または環境の影響を受けやすい)。
8.対人関係を実際以上に親密なものと思っている。
DSM-5(精神障害の診断・統計マニュアル第5版)から引用
早期に発見・治療する必要があるのは、この疾患は他の精神疾患と併発する可能性が高いからでもある。次のような精神疾患が併発することがあると言われている。
1)他のパーソナリティ障害
自己愛性パーソナリティ障害、境界性パーソナリティ障害など、他のパーソナリティ障害と併発2)気分障害
うつ病、双極性障害など、気分障害を併発3)不安障害
パニック障害、社交不安障害など、不安障害を併発4)身体症状症
身体的な症状を訴えるものの、医学的な原因が見つからない身体症状症を併発このように、精神疾患が拡張していく可能性が高く、周りの人たちも巻き込まれて非常に困惑してしまう場面が多くなる。従い、早期に専門医の受診を促すことがまずもって肝要である。
「演技性パーソナリティ障害」の人への対応のポイント
演技性パーソナリティ障害の人は、人間関係や業務内容などの職場環境によってストレスを感じやすく、周囲の人と衝突してしまうことも多くなりがちである。一方で、適切な治療を受けることで症状が改善され、社会生活での困りごとを徐々に減らしていくことも可能であると考えられている。職場に演技性パーソナリティ障害の人がいる場合には、例えば次のような対応を思考錯誤しながら行うようにしたい。●障害にあった業務を切り出す
障害の特性に合わせ、「納期のない、マイペースに行える業務」、「自分自身が興味がある得意な業務」などを考慮し、業務の切り出し、配置が必要●パーソナリティ障害に適した配慮を行う
パーソナリティに配慮した業務の割り当てや、障害に理解のある人を近くに配置するなど、本人の不安感を少しでも減らす配慮が必要●チームでコミュニケーションをとる
1対1のコミュニケーションは誤解が生じることが多いので、メッセージを伝えるときなどは1対1にならないよう、チームでコミュニケーションをとる●根拠をもとに冷静に話し合う
重要な事柄を本人に伝えるときは、実際のデータや記録等の客観的な指標や数値を用意し、冷静に話し合うようにする●適度な距離を保って接する
本人との関わり方について一定のルールや枠組み等を作っておき、それを保って接するようにする- 1