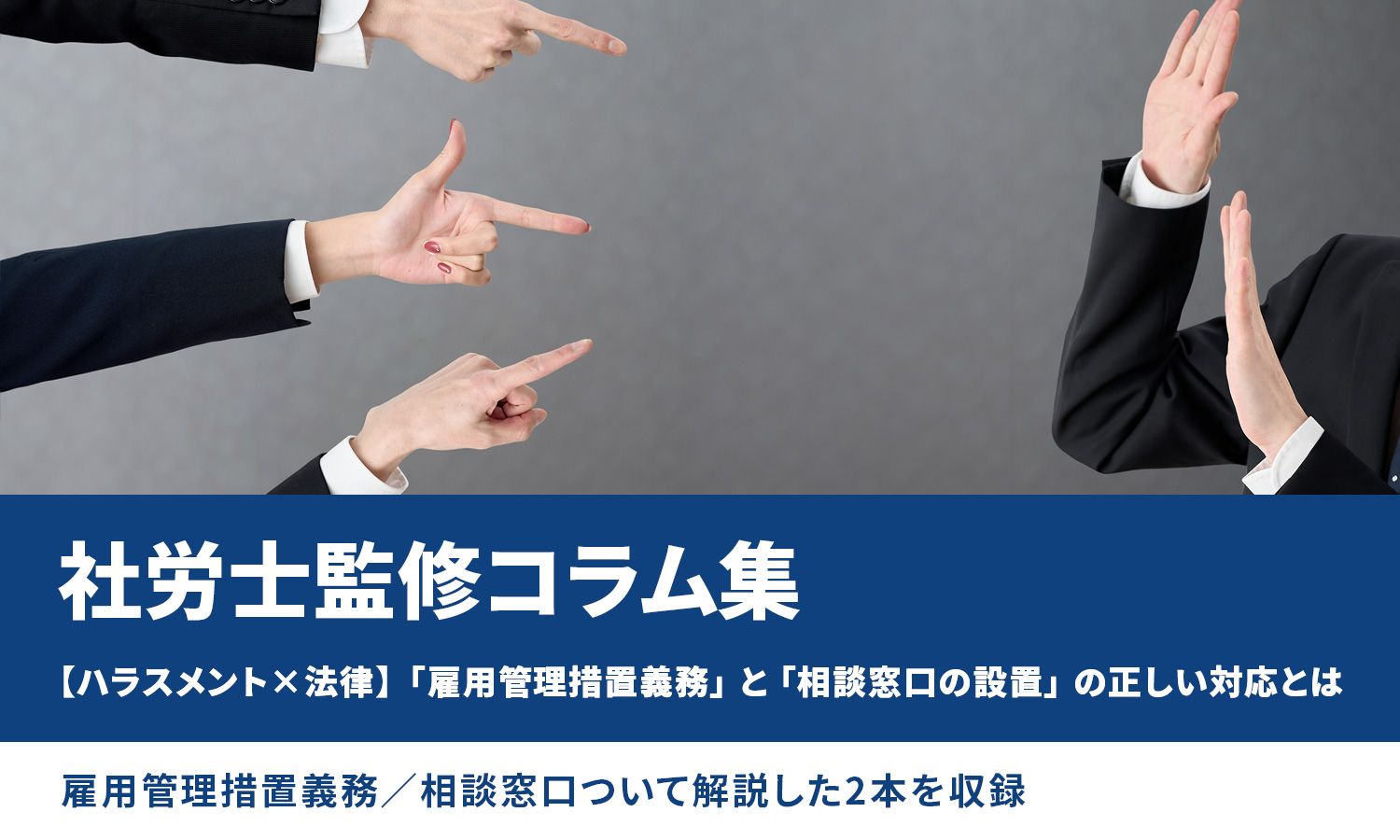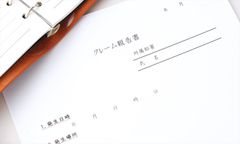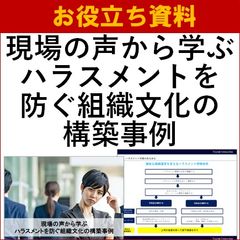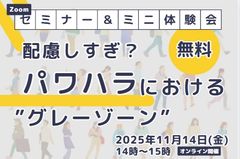■「セクハラ」に関する資料ダウンロード、セミナー、サービス、ニュースなどの最新コンテンツはこちら
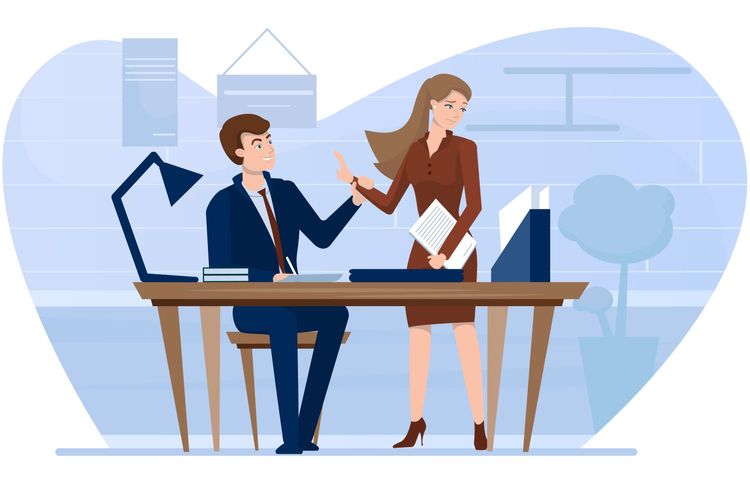
「セクハラ(セクシャルハラスメント)」とは
「セクハラ(セクシャルハラスメント)」とは、性的な言動によって相手に不利益を与えたり、職場環境を悪化させたりすることを言う。男女雇用機会均等法11条1項において「職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること」と定義されている。「セクハラ」は加害者の悪意の有無を問わず、相手が不快に感じれば成立する可能性があり、また相手の性的指向(どの性別を恋愛・性愛対象とするか)や性自認(性別に関する自己認識)に拘わらず、異性間だけでなく同性間でも起こり得る。
こうした「セクハラ」を防止するため、2020年6月から改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)によって、事業主には職場でのパワハラ防止対策が義務付けられ、また同時に男女雇用機会均等法の改正によってセクハラ防止対策も強化された。
「ハラスメント」とは? 一覧表と事前対策や起きた時の対処法を解説
●「セクハラ」の定義
上述のとおり、「セクハラ」は、男女雇用機会均等法11条1項において「職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること」と定義されている。つまり、「セクハラ」の定義は3つの要素から成り立っていると言える。「職場で行われたものであるか」、「労働者の意に反するものであるか」、「性的な言動であるか」という点だ。「職場」で行われたものであるか
セクハラにおける「職場」とは、単に会社のオフィス内に限定されるものではなく、「労働者が業務を行う場所」全般を指す。例えば、出張先、業務で使用する車中、取引先の事務所なども含まれる。また、勤務時間外の宴会や懇親会などであっても、職務との関連性がある場合や参加が実質的に強制されているような状況では、「職場」と見なされることがある。「労働者」の意に反するものであるか
ここでいう「労働者」には、正社員だけでなく、アルバイト従業員、パートタイム従業員、契約社員、派遣労働者など事業主が雇用するすべての従業員が該当する。そして、「労働者の意に反する」とは、被害者が明確に拒否の意思表示をしていなくても、不快感や嫌悪感を抱いていれば「意に反する」と判断される可能性がある。重要なのは、行為者の意図ではなく、被害者がどう感じたかという点だ。発言や行動の受け取り方は人によって異なるため、一般的な社会通念や状況も考慮したうえで判断される。
「性的な言動」であるか
「性的な言動」とは、性的な冗談や質問、容姿に関する発言、不必要な身体への接触、性的な画像の見せつけ、性的な噂の流布といった、“言葉”や“視覚”、“行動”によるものを指す。さらに、性的な興味や欲望から行う言動だけでなく、「男だから」、「女だから」という固定観念で役割を決めつける言動やLGBT+などの性的少数者に対する偏見からくる言動も含まれる。●厚生労働省が示す「セクハラ」の判断基準
「セクハラ」が発生する状況はさまざまであり、個別の状況を考慮する必要がある。そのため厚生労働省では、「労働者の意に反する性的な言動」と「就業環境を害される」の判断にあたっては、労働者の主観を重視しつつも、事業主の防止措置義務の対象となることを考えると一定の客観性が必要だとし、その判断基準を示している。それに準拠して事案ごとに判断していく必要がある。・一般的には、意に反する身体的接触によって強い精神的苦痛を被る場合には、一回でも就業環境を害することとなり得る。
・継続性または繰り返しが要件となるものであっても、回数のみを判断材料とはせず、少ない回数でも「明確に抗議しているにもかかわらず放置された状態」、または「心身に重大な影響を受けていることが明らかな場合」には、就業環境が害されていると判断し得る。
・被害を受けた労働者が女性である場合には「平均的な女性労働者の感じ方」を基準都市、被害を受けた労働者が男性である場合には「平均的な男性労働者の感じ方」を基準とすることが適当である。
【参考】
厚生労働省:職場におけるハラスメント対策マニュアル(PDF)
●「セクハラ」が社会問題として重要視される背景
「セクハラ」が社会問題として重要視されるようになった背景には、職場における男女平等の推進と人権意識の高まりがある。とりわけ1980年代後半から女性の社会進出が進む中で、職場における男女間の力関係の不均衡が問題視され、かつては「職場でのコミュニケーションの一部」や「冗談」として見過ごされていた言動が、実は個人の尊厳を傷つけ、働く権利を侵害するものだという認識が広まっていった。1997年には男女雇用機会均等法が改正され、事業主に対して女性労働者への「セクハラ」防止のための配慮義務が初めて規定されると、その後2007年の改正では、「セクハラ」防止措置が事業主に義務づけられ、対象も男女の労働者に拡大された。これによって「セクハラ」が単なる個人間の問題ではなく、企業が組織として取り組むべき課題であるという認識が定着するようになった。
さらに、2020年6月の法改正では防止対策が強化され、より一層「セクハラ」を行ってはならないという関心や理解を深める責務が明確化されるとともに、「性的な言動」の対象範囲が取引先や顧客などにも拡大された。
近年ではグローバル化の進展により、国際的な人権基準や企業倫理の観点からも、「セクハラ」防止は企業の社会的責任として重視されるようになっている。多様な人材が尊重され、能力を発揮できる職場環境の整備は、企業の持続的成長のためにも不可欠な要素として認識されているのである。
●「セクハラ」による企業リスク
社内で「セクハラ」が発生したとあれば、従業員のモチベーションや生産性が急激に低下し、離職率が高まる傾向がある。優秀な人材の流出は避けられず、組織力は弱体化してしまう。そうした内部崩壊だけではない。「セクハラ」の事案が公になれば、企業の社会的信頼は大きく損なわれ、顧客離れや株価の下落などによって経営危機にも発展しかねない。被害者が損害賠償請求や労働審判などの法的措置を取ることもあり、そうなれば、高額な賠償金の支払いや裁判費用など直接的な経済的損失も発生する。
セクハラ防止措置を怠った場合には、企業名の公表や行政指導といった法的制裁を受ける可能性もある。「セクハラ」は被害者個人に心理的・身体的な悪影響を及ぼすだけでなく、企業の評判、財務、法的リスクなど多方面に悪影響を及ぼす重大な問題と言える。
「セクハラ」の種類と具体例
「セクハラ」は主に以下の4つのタイプに分類できる。厚生労働省が示す分類では「対価型セクハラ」と「環境型セクハラ」の2種類だが、そこに「制裁型セクハラ」と「妄想型セクハラ」を加えたものが一般的だ。それぞれの特徴と具体例を見ていこう。●対価型セクハラ
「対価型セクハラ」とは、性的な要求を受け入れるかどうかによって、昇進や評価、仕事の配分などに影響を与える行為を指す。性的な言動を拒否された時には報復として業務上の不利益を与えるケースもある。地位や立場を利用しているケースが多く、被害者側は拒否することによる報復を恐れ、被害を訴えにくいという問題がある悪質なものだ。具体例としては以下のような行為が該当する。・契約更新を条件に食事や旅行に誘い、断られたら契約を打ち切る。
・業務評価を高くする見返りに、プライベートな写真を送るよう要求する。
・残業手当を多く支給する代わりに、二人きりでの飲み会に参加するよう強要する。
・社内プロジェクトのリーダーに抜擢する条件として、性的な関係を強要する。
●環境型セクハラ
「環境型セクハラ」とは、性的な言動によって職場環境を不快にし、労働者の能力の発揮を阻害する行為だ。直接的な利益や不利益の条件を提示していなくても、性的な言動で職場の雰囲気を悪化させ、業務に支障をきたすケースが該当する。このタイプ、「冗談のつもり」、「親しみの表現」として行われることもあり、加害者自身が問題意識を持っていないケースも少なくない。例えば、以下のような行為が挙がる。・女性社員の体型について「痩せた? 太った?」と繰り返し公然と言及し、周囲に聞こえるようにコメントする。
・休憩時間に不快に思う社員がいるにも拘わらず、性的な冗談や体験談を大声で話し続ける。
・業務用パソコンの壁紙に水着姿のアイドルの画像を設定し、周囲から見えるようにしている。
・部下の肩や腰に頻繁に触れ、「スキンシップだから問題ない」と主張して続ける。
●制裁型セクハラ
「制裁型セクハラ」とは、性差別的な価値観に基づいて異性に対して圧力をかけたり、相手の性別によって態度を変えたりする行為だ。直接身体に触れるわけではないが、態度として表れることが多い。具体例としては以下のケースがある。・女性部下の発言を無視し、同じ内容でも男性が発言すると真剣に聞く。
・「女性は家庭を優先すべき」と言い、育児中の女性社員の昇進を意図的に妨げる。
・男性社員には専門的な業務を任せ、女性社員には一律にお茶出しや掃除などの雑務だけを担当させる。
・「男のくせに力仕事ができないのか」と罵倒し、特定の男性社員に過剰な肉体労働を強いる。
●妄想型セクハラ
「妄想型セクハラ」とは、相手に好意を持たれていると勝手に思い込み、一方的に性的な言動を繰り返す行為だ。相手の気持ちを確認せず、自分の思い込みだけで行動するため、被害者に強い不快感や恐怖を抱かせてしまう。加害者は自分の行動が「好意の表現」であると考えているため「セクハラ」であると認識していないことが多く、指摘されても理解できないケースもある。・相手が笑顔で挨拶してくれたことを「脈あり」と勘違いし、毎日SNSで私生活の写真や近況を送り続ける。
・業務上の会話をしただけなのに「親密な関係になった」と思い込み、休日のデートにしつこく誘い続ける。
・「あの人は僕のことが好きに違いない」と勝手に決めつけ、相手の服装を「今日は可愛くないね」などと日々評価する。
・仕事の質問に丁寧に答えてくれたことを恋愛感情と誤解し、深夜に「今何してる?」と頻繁に連絡する。
「セクハラ」に該当しうる発言一覧
「セクハラ」には、具体的にどんな発言や行動が該当するのかを理解しておく必要がある。以下に、「セクハラ」となり得る発言の具体例を紹介したい。●性的な内容に関する質問
性的な内容の質問は、プライバシーの侵害に当たる可能性が大きい。軽はずみに聞いてしまうことは絶対にないようにしたい。・初体験はいつだった?
・まだ童貞じゃないのか?
・子供はまだできないの?
・スリーサイズを教えて?
●性別や年齢に関する偏見
性別や年齢に関する偏見に基づいた発言、行動も「セクハラ」として受け止められやすい。多様な価値観を受け入れる姿勢が求められている。・これだから女はダメだ
・最近の若い奴は責任感に欠けている
・男ならこれぐらいの酒は飲めるだろ
・40歳を過ぎたら、この職場には必要ない
●容姿に関する発言
容姿に関する過度な発言、差別的な発言も問題となる。冗談のレベルでも許されず、また褒めた発言が「セクハラ」と捉えられるケースもある。・最近太ってきているよね
・ガリガリすぎ。しっかり食べているの?
・ダイエットしたんだね
・垢抜けたね
●わいせつな発言
「宴会では無礼講だ」などと上司が発しても、わいせつな発言が許されることはない。・今日は、短めのスカートで出勤なんだね
・このところ、かなりイライラしているみたいだけど生理中なの?
・君もこういうプロポーションを目指さないとモテないぞ
・今日はどんな下着なの?
●「ちゃん」、「くん」付け
男女平等、ジェンダーフリーの意識が高まりつつある現代社会では、「ちゃん」や「くん」付けは職場環境や相手との関係性によっては不適切と受け取られる可能性がある表現なので注意を要する。ビジネスシーンでは、「さん」付けを勧めたい。・〇〇ちゃん、〇〇くん
・そこの新人くん
「セクハラ」に対する責務
「セクハラ」の防止と対応には、事業主、労働者、そして加害者それぞれにどのような責務と罰則があるのか。それぞれの立場における責任について解説する。●事業主の責務
事業主には、職場における「セクハラ」を防止するための積極的な措置を講じる法的義務がある。男女雇用機会均等法第11条では、職場での性的な言動によって労働者が不利益を受けたり、就業環境が害されたりすることがないよう防止措置を講じなければならない旨が明確に規定されている。事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
具体的には、以下のような措置が求められる。
(1)事業主の方針の明確化および周知・啓発
(2)相談窓口の設置と適切な対応体制の整備
(3)セクハラ発生時の事実関係の迅速かつ正確な確認と適切な対処
(4)相談者や行為者のプライバシー保護と不利益取扱いの禁止
以上の措置義務に違反した事業主に対しては、厚生労働大臣から報告の徴収、助言、指導、勧告が行われ、勧告に従わない場合は企業名が公表されるという罰則がある。また、「セクハラ」が発生した場合は、使用者責任(民法715条)や安全配慮義務違反(債務不履行責任)に基づく損害賠償責任を負う可能性があり、さらに被害者が受けた精神的・身体的苦痛に対する慰謝料や、休業による逸失利益などの賠償も求められるケースがある。
●労働者の責務
「セクハラ」の防止・対策は事業主だけの責任ではなく、職場で働くすべての労働者にも責務がある。男女雇用機会均等法11条の2第4項は「労働者は、性的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない」と定めている。従業員はまず何よりも自分自身が加害者にならないよう、言動に注意を払うことが基本となる。また職場でセクハラを目撃した場合は、見て見ぬふりをせず、被害者に寄り添い、必要に応じて相談窓口への報告を促すなど、「セクハラ」を許さない職場風土づくりに貢献することが求められる。
●加害者の責務
「セクハラ」の加害者は、他人の人格や尊厳を傷つけてしまった自らの行為に対する責任を認識し、二度と同様の行為を繰り返さないという道義的な責務だけでなく、刑事・民事上の法的責任を負う。刑事上の責任としては、行為の内容によって、不同意わいせつ罪(刑法176条)や不同意性交等罪(刑法177条)、名誉毀損罪(刑法230条)、侮辱罪(刑法231条)などが成立する可能性がある。
被害者の同意なく身体に触れるなどの行為が該当。
6月以上10年以下の懲役が科される。
・不同意性交等罪(刑法177条)
被害者の同意なく性的な行為を強いるなどの行為が該当。
5年以上の有期懲役が科される。
・名誉毀損罪(刑法230条)
被害者の社会的評価を低下させるような性的な情報を流布する行為が該当。
3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金が科される。
・侮辱罪(刑法231条)
相手の性的な特徴を揶揄したり、性的な蔑称で呼んだりするなど、人の名誉を傷つける行為が該当。
3年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金、または拘留もしくは科料が科される。
民事上の責任としては、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償責任がある。加害者に被害者に対して、精神的苦痛に対する慰謝料や、医療費などの積極損害、休業による逸失利益などの消極損害を賠償しなければならない。
企業における「セクハラ」防止策
企業が「セクハラ」を防止するためには、以下の4つの対策が有効と言える。それぞれの具体的な実施方法を説明していく。●セクハラ防止方針策定および周知・啓発
企業はまず、セクハラの内容と「セクハラがあってはならない」という明確な方針を策定し、全従業員に周知・啓発する必要がある。具体的には、就業規則やその他の服務規律においえて、職場におけるセクハラ禁止の方針を明記し、セクハラの定義や具体例、発生原因などを説明し、加害者には厳正に対処する旨と処分内容を規定する。さらに、周知・啓発の方法としては、社内報やパンフレット、社内ホームページ等の広報・啓発資料への掲載に加え、経営トップからのメッセージを繰り返し発信することが重要だ。定期的に社内アンケートを実施し、社内の実態把握に努めることも有効な啓発活動と言える。こうした周知・啓発活動によって、従業員に「セクハラ」に対する共通認識を持ってもらい、職場全体の意識改革を図っていく。
●セクハラ防止研修の実施
セクハラ防止研修は、従業員のセクハラに対する理解を深め、防止意識を高めるために非常に有効だ。研修内容は主に、セクハラの定義と種類の理解、セクハラに該当する言動・行為の把握、正しいコミュニケーションスキルなどが良い。ポイントは、業種、企業文化、従業員構成に合わせて実施することだ。特に管理職向けには、部下からの相談への対応方法やセクハラを未然に防ぐための職場環境づくりについて、より実践的な研修を行うことが重要となる。
●セクハラ相談窓口の設置
セクハラ相談窓口の設置は、セクハラを早期に発見し、対処するためにも不可欠である。相談窓口の設置にあたっては、相談担当者を複数の男女で構成し、相談者が相談しやすい体制を整えることが理想的だ。また、内部相談窓口(人事部や法務部が中心)だけでなく、外部相談窓口(専門業者や法律事務所、社会保険労務士事務所などへの委託)を併用することがなお望ましい。「相談しても不利益を受けない」という安心感を与えるために、利用方法をあらかじめ全従業員に周知しておくようにしたい。
●セクハラ発生時の対応手順整備
万が一セクハラが発生した場合に備え、あらかじめ対応手順を明確に定めておくことが重要だ。具体的には、相談受付から事実確認、処分決定、フォローアップまでの一連のプロセスと担当部署を明確にしたマニュアルを作成しておく。さらに、このマニュアルには、被害者と加害者の隔離措置、被害者のプライバシー保護と二次被害防止策、加害者への適正な処分基準も盛り込み、相談者や協力者を不利益な取扱いをしない旨も記しておきたい。
「セクハラ」発生時に必要な対策
実際に職場で「セクハラ」が発生してしまった場合、企業はどう対応すべきか。(1)事実関係の確認、(2)被害者へのフォロー、(3)加害者への処分、(4)再発防止策の検討・実施というプロセスが基本となる。4つのプロセスをそれぞれ解説していこう。(1)事実関係の確認
「セクハラ」の相談を受けた場合、まず優先すべきは正確な事実確認だ。被害者からの聞き取りを丁寧に行い、「いつ、どこで、誰が、どのような言動をしたのか」を具体的に記録する。この際、被害者の心理的負担に配慮し、安心して話せる環境を整えることが重要だ。次に、加害者とされる人物や関係者からも事情を聴取する。この段階では、予断を持たず中立的な立場で調査を進めることが大切となる。また、メールやメッセージ、目撃者の証言など、客観的な証拠も可能な限り収集していく。
なお調査の過程では、当事者のプライバシーを厳守し、噂や憶測が広がらないよう細心の注意を払う必要がある。
(2)被害者へのフォロー
セクハラ被害者への対応で最も重要なのは、プライバシーを守ったうえで被害者の気持ちに寄り添い、安全と安心を確保することだ。被害者の話に真摯に耳を傾け、希望があれば、加害者との接触を避けるための配置転換や業務調整を速やかに行う。また、必要に応じて休暇取得の推奨を勧めたり、外部の専門家によるカウンセリングを受診させたりするなど、メンタルケアをしていく。(3)加害者への処分
一方で加害者に対しては、事案の程度に応じた適切な処分を行う必要がある。就業規則に基づいて、懲戒処分や降格、配置転換、解雇などの措置を決定する。また、単に罰則を与えるだけでなく、どの言動が「セクハラ」に該当し、なぜ問題なのかを具体的に説明することで、加害者の意識改革を促すことができ、再発防止につながる。ハラスメント防止研修の受講や外部専門家によるカウンセリングなどによる指導も行うと良いだろう。(4)再発防止策の検討・実施
同様の事案が繰り返されないよう、再発防止策の検討・実施は必ず行わなければならない。ポイントは発生原因の分析だ。特定の部署での発生が多い場合は、その部署の風土や管理体制に問題がある可能性がある。そうした組織的な問題点を洗い出すことで再発の恐れを低減できる。具体的な再発防止策としては、全社でのハラスメント防止研修、管理職への特別研修、相談窓口の機能強化、定期的な職場環境調査の実施などが挙がる。それに加え、就業規則や社内規定の見直しも進めたい。
「セクハラ」の裁判事例
次に、実際の判例から、どのような行為が「セクハラ」にあたるのか見ていきたい。●被害者による行為を煽る言動があっても「セクハラ」と認定された判例
広島地裁平成19年3月13日判決は、生命保険会社の忘年会で男性上司3名が女性社員7名に対して行った抱きつく、肩を抱き寄せる、押し倒して顔を舐めるなどの行為を「セクハラ」と認定した事案だ。女性社員らが嬌声を上げて騒いだり、中には男性上司を押し倒して乗りかかったりするなどの行動があったにもかかわらず、裁判所は男性社員らの行為が女性社員らの身体的自由、性的自由および人格権を侵害する不法行為に当たると判断した。ただし、女性社員らの態度がセクハラ行為を煽る結果になったとして、過失相殺の法理を類推適用し、慰謝料額の2割を減額している。さらに忘年会は業務の一環であるとして、企業の使用者責任も認められた。
●被害者の拒否がなくても「セクハラ」となった判例
最高裁平成27年2月26日判決は、大阪市の水族館に勤める40代の男性社員2名が20~30代の女性派遣社員らに対して性的な発言を繰り返したことに対する出勤停止と降格処分が有効であるかが争われた事案だ。最高裁は、男性社員らがセクハラ防止研修を受け、管理職として部下を指導すべき立場にあったこと、企業側がセクハラ行為を具体的に認識できない状況で被害申告まで警告や注意を行う機会がなかったことを理由に、事前の注意警告なしに行われた懲戒処分の社会的合理性・相当性を認め、有効と判断した。この判決は、被害者の明示的な拒否がなくとも「セクハラ」が成立することを示している。
あかるい職場応援団:海遊館事件
●フリーランスに対しても「セクハラ」の安全配慮義務が認められた判例
東京地裁令和4年5月25日判決は、エステティックサロンを経営する会社の代表者が、業務委託契約を結んだフリーランスの女性ライターに対して行った性的言動等が「セクハラ」に当たるとされた事案だ。代表者は女性に対し、「何人くらいと付き合った?」、「バストを見せて欲しい」などの性的発言や体を触るなどの行為を行い、また「さぼったでしょ」、「こんな記事じゃ報酬を支払えない」などと責め立てる発言を繰り返した。裁判所は、約7カ月にわたるセクハラ行為と、報酬支払いを正当な理由なく拒むパワハラ行為を認定し、その態様は「極めて悪質」と判断。さらに、被害者が「実質的に会社の指揮監督の下で労務を提供する立場にあった」として、直接の雇用関係がないフリーランスに対しても会社は安全配慮義務を負うとし、140万円の慰謝料支払いを命じた。この判決は、業務委託契約によるフリーランスへの安全配慮義務を肯定した先例的な裁判例であると言える。
あかるい職場応援団:アムールほか事件
まとめ
「セクハラ」は、被害者を傷つけるだけでなく、職場環境の悪化や企業の信頼損失など、あらゆる方面に悪影響を及ぼすため、その防止には細心の注意を払わなくてはならない。「セクハラ」のない職場づくりは、事業主だけでなく労働者一人ひとりの意識と行動にかかっている。互いを尊重し、多様性を認め合う職場風土の醸成こそが、最も効果的なセクハラ防止策とも言える。そのために人事担当者は、明確な企業方針の策定と周知徹底を行い、全社員に対して定期的な研修を実施していきたい。●厚生労働省:職場のセクシュアルハラスメント対策はあなたの義務です!!(PDF)
【HRプロ関連記事】
●「ハラスメント」の意味や種類とは? 事前の対策や起きた時の対処法も解説
●「マタハラ(マタニティハラスメント)」とは? 定義や具体例、防止措置を解説
●「パタハラ」の意味とは? 気になる該当事例や対策方法なども解説
●「モラハラ(モラルハラスメント)」の意味や特徴とは? 職場で起こる実際の具体例も解説
●「カスハラ(カスタマーハラスメント)」とは? 意味や事例と併せて対応策も解説
●「スメハラ(スメルハラスメント)」とは? 意味や職場への影響と対策を解説
●「アルハラ(アルコールハラスメント)」とは? 意味や事例と併せて職場での対策を解説
「セクハラ」に関する資料ダウンロード、セミナー、サービス、ニュースなどの最新コンテンツはこちら
よくある質問
●女性から男性への「セクハラ」の例は?
女性から男性への「セクハラ」としては、外見や体格に関する不適切な発言や「男なんだから」と力仕事を強要する行為、私生活や結婚に関する執拗な質問、身体に不必要に接触する行為などがある。●性的な嫌がらせとは?
「性的な嫌がらせ」とは、相手の意思に反して行われる性的な言動で、相手に不快感や屈辱感を与える行為だ。不必要な身体接触、性的な冗談や質問、性的な噂の流布、露骨な性的表現を含む画像の見せつけなどがあたる。- 1