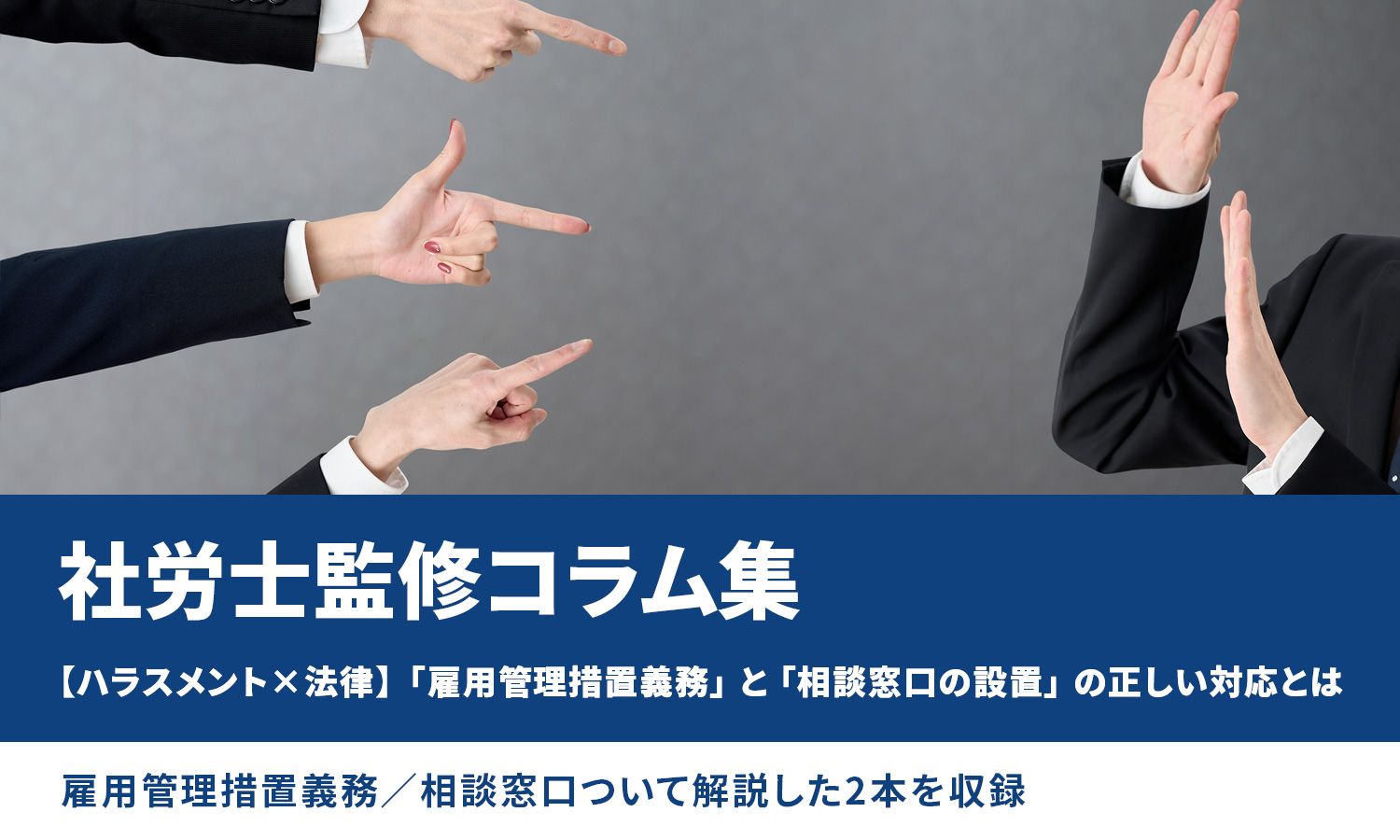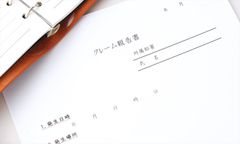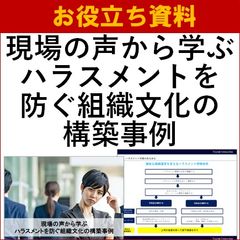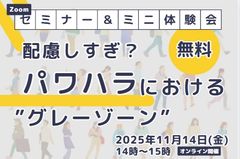■「ハラスメント」に関する資料ダウンロード、セミナー、サービス、ニュースなどの最新コンテンツはこちら

「アルハラ(アルコールハラスメント)」とは
「アルハラ」とはアルコールハラスメントの略称で、飲み会など飲酒に伴う場で見られる嫌がらせや迷惑行為・人権侵害を指す。被害者は身体的・精神的な健康を損なうだけでなく、職場における人間関係を悪化させる原因となり得るので、注意する必要がある。「ハラスメント」とは? 一覧表と事前対策や起きた時の対処法を解説
「アルハラ」の6つの定義と行為例
特定非営利活動法人ASKでは、「アルハラ」に該当する行為例を6つ提示している。それぞれを見ていこう。(1)飲酒の強要
上下関係や所属組織の伝統、しきたり、儀礼などを理由として相手に心理的なプレッシャーをかけ、飲酒を強要することは「アルハラ」の典型的な行為と言える。「俺の継いだ酒が飲めないのか」などと強い言葉が伴う場合はもちろんだが、飲まないといけないような雰囲気を醸し出すこと自体も「アルハラ」として認められる。(2)イッキ飲ませ
飲み会を盛り上げるために、大量のお酒を一息で飲み干させたり、早飲み競争・罰ゲームなどを強いたりすることも「アルハラ」に当たる。急性アルコール中毒のリスクがあり、大変危険な行為と言える。(3)酔いつぶし
相手を意図的に酔わせる行為も「アルハラ」に該当する。これも、場合によっては急性アルコール中毒をもたらすかもしれない、極めて危険な行為となるので注意を要する。例えば、事前に酔いつぶすための準備をした上で飲み会を開く、複数名で取り囲み何度も飲ませる、度数の高いアルコールしか飲ませないなどは、酔いつぶしと判断される。(4)飲めない人への配慮を欠くこと
アルコールを飲めない人に対して配慮がない行為も「アルハラ」とされる。例えば、本人の意向を無視して飲酒を勧める、飲めないことを理由に職場で嫌がらせをする、会席の場にソフトドリンクを一切用意しないなどの行為が挙げられる。(5)酔ったうえでの迷惑行為
酔った状態で行う迷惑行為も「アルハラ」に当たる。具体的には、セクハラ行為をする、暴言を吐く、暴力を振るう、しつこく絡む、延々と説教をするなどの行為が挙げられる。(6)20歳未満の人に飲酒を勧めること
法律で、20歳未満の人の飲酒は禁止されている。20歳未満の人に飲酒を勧めることは当然「アルハラ」であり、あってはならない。むしろ20歳未満の人の飲酒を制止しなければならない。「アルハラ」が発生する背景
「アルハラ」が発生する背景としては、主に以下の3点が指摘できる。●お酒をコミュニケーションの潤滑油と捉えている
古くからお酒を飲み交わすことは、人間関係を円滑にする良き手段とされてきた。それだけに、相手と一緒にお酒を飲むことを避ける、酌を受けないなどといった行動は敵意を示していると捉えられてしまう。●「アルハラ」の加害者である認識がない
「アルハラ」の加害者は、お酒を飲むことで人間関係が良くなる、コミュニケーションが深まると思い込んでいる。そのため、お酒を勧めること自体に問題があるとは全く思っていない。相手が嫌がっていても何も感じていない場合もある。●年功序列や風習を重んじている
近年はだいぶ変わってはきているものの、組織によっては上下関係を尊重する思想がまだまだ根強い。そうなると、上司からの命令や指示は絶対だという雰囲気が醸し出されてしまい、抵抗できないケースがある。「アルハラ」をしやすい人・受けやすい人の特徴・思考
「アルハラ」をしやすい人や受けやすいには独特の特徴や思考がある。それぞれ紹介しよう。●「アルハラ」をしやすい人の特徴・思考
「アルハラ」をしやすい人の特徴や思考として、具体的には以下が挙げられる。・旧来からのしきたりや伝統、文化を重んじる
・お酒の席では無礼講だと思っている
・お酒を飲むことでストレスを発散しようとしている
●「アルハラ」を受けやすい人の特徴・思考
「アルハラ」を受けやすい人にも共通した特徴や思考が見られる。例えば、以下の通りだ。・断ってしまうと相手に失礼だと思ってしまう
・上司の言うことは絶対だと考えている
・いじられやすい
「アルハラ」が企業と従業員に与える影響
「アルハラ」が社内で発生すると、企業および従業員に多大な影響を与えてしまう。●企業への影響
「アルハラ」が多発するような職場では従業員、特に若手世代のモチベーションが低下し、離職率の増加につながってしまう。また、もしも「アルハラ」が原因で従業員の心身が不調になった場合、しばらくの間仕事に復帰できないという事態も予想される。労災だと認定されると、会社も損害賠償責任を負うことになるかもしれない。さらには、そうした事実がマスコミ等で報道されてしまうと、企業としての社会的なイメージも大幅にダウンせざるを得なくなるので注意しなければならない。●従業員への影響
一方、「アルハラ」を受けた従業員にも多大な影響がもたらされる。まずは、肝臓や胃腸などの健康面に何らかの問題を引き起こしかねない。また、飲酒を強制されたというストレスは、うつ病や不安障害につながる可能性もある。「アルハラ」の実態
「アルハラ」の実態がどうなっているのか。ゼネラルリサーチ株式会社が実施した「アルコールハラスメントに関する意識調査」の結果を検証してみたい。●「アルハラ」を受けたことがある人としたことがある人の割合
「アルハラ」を経験したことがある人は18.1%だが、お酒を強要されたことがある人の21.6%を足すと、4割近くの人が「アルハラ」を受けたことがあると回答している。一方、「アルハラ」をしたと自覚している人は10.8%と、30%近くもの開きが見られる。この結果から、「アルハラ」は無自覚のまま行為に及んでいることがわかる。●「アルハラ」に至ってしまう理由の割合
アルハラに至る背景としては「酔った勢いでのこと」が68.6%で最も多い。以下、「場を盛り上げるための一気飲み」(47.7%)、「お酒を飲んで気が大きくなったから」(25.7%)と続いている。場の雰囲気や流れに飲まれ、勢いのままハラスメントに発展していることがうかがえる。●「アルハラ」を断れない人の割合と理由
「アルハラ」を受けた際に断れない人の割合は、5割を超えている。その理由としては「上司や先輩からの強要は断れない」(60.7%)、「空気が読めないなど自分の立場を気にして」(49.7%)、「周囲も飲むため断れない」(29.2%)などの回答があった。場の空気を読むことの弊害が現れていると言って良いかもしれない。「アルハラ」の加害者と企業が負う法的責任
社内で「アルハラ」が起きた場合、加害者と企業は責任を負う可能性がある。●「アルハラ」加害者の責任
「アルハラ」をした加害者は、被害者に対して不法行為に基づく損害賠償責任を負う(民法709条)。慰謝料の他、治療や入院にかかる費用が請求されるケースが多く、特に被害者に重篤な健康障害が生じた場合および、被害者が死亡した場合には、数千万円から数億円の損害賠償が認められることもあり得る。故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
また、以下のような刑事上の罪に問われる可能性も想定される。
・強要罪(刑法223条1項、3年以下の懲役)
・傷害罪(刑法204条、15年以下の懲役または50万円以下の罰金)
・傷害致死罪(刑法205条、3年以上の有期懲役)
・保護責任者遺棄等罪(刑法218条、3カ月以上5年以下の懲役)
・現場助勢罪(刑法206条、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料)
●「アルハラ」が発生した企業の責任
従業員間で「アルハラ」が発生した場合、企業は安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任を負う可能性がある(労働契約法5条)。また、業務の一環として「アルハラ」が行われたと認定されてしまうと、使用者責任に基づく損害賠償責任も負うことになる(民法715条1項)。使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
「アルハラ」の事例
実際にあった「アルハラ」に関する事例を紹介していく。●ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル事件
ザ・ウィンザーホテルズインターナショナル事件(東京高裁平成25年2月27日判決)は、ホテル会社の上司が部下に対して行った「アルハラ」が問題となった事案だ。「お酒は飲めない」と言う部下に対して「少しくらい大丈夫だろう」、「私の酒が飲めないというのか」などと執拗に飲酒を強要し、部下が体調不良で嘔吐した後も「吐けばまた飲める」と飲み続けさせた。こうしたアルハラを含む一連のパワハラ行為により、従業員は精神疾患を発症し、休職。その後、休職期間が満了し、会社から自然退職扱いとされた。これを受けて従業員は、治療費の支出、休業による損害、多大な精神的苦痛を受けたとして、会社と上司に対して不法行為に基づく損害賠償を請求。また、精神疾患が業務上の疾病であるとして、休職命令および自然退職扱いは無効であると主張し、自然退職後の賃金の支払いなども求めて提訴に至った。東京高裁は、飲酒の強要を含む一連のパワハラを不法行為と認め、150万円の賠償責任を認定し、会社と上司に150万円の損害賠償を命じた。
●神戸学院大学飲酒学生死亡事件
神戸学院大学飲酒学生死亡事件は2008年3月に、神戸学院大学ユースホステル部の合宿で起きた「アルハラ」に関する事件だ。3年生8人が2年生13人に対し、「部の伝統行事」として4リットルの焼酎の回し飲みを強要。残り約500mlを飲み干した20歳の男子学生が急性アルコール中毒で意識を失ったが、適切な処置がされないまま翌朝まで放置され、吐瀉物による窒息で死亡した。遺族は大学と学生20人を相手取り約1億円の損害賠償を求め提訴。2011年、神戸地裁で和解が成立し、大学側が飲酒強要を認めて和解に応じた初めての例となった。「アルハラ」防止のために企業がとるべき対策
社内で「アルハラ」が起きないようにするため、企業は以下の対策を講じることが求められる。●飲酒や飲み会に関するルールの明確化
「アルハラ」を禁止する旨の方針や飲み会でのルールを明確化し、従業員に対して周知・徹底することが重要だ。手法としては、社内報・パンフレット・ホームページなどを通じて発信するのが得策と思われる。具体的には、一気飲みやコールを禁止する、ソフトドリンクを準備する、飲み会への参加を強制しないなどが挙げられる。●「アルハラ」に関する研修実施など危険性の周知
「アルハラ」は被害者の生命を奪いかねない。「アルハラ」に関する研修を実施し、飲み会でのルールや「アルハラ」がもたらすリスクなどを周知、教育することも有効だ。●ハラスメント相談窓口の設置
「アルハラ」の実態を把握し、早期にかつ適切に対処するためにも、ハラスメント相談窓口を設置するようにしたい。窓口の担当者は人事部門と連携しながら対応マニュアルを準備したり、研修などに参加したりして対応スキルを向上するようにしたい。●宴会や飲み会を強制しない
宴会や飲み会のほとんどは、勤務時間外に開催される。そうした場に参加を強制すること自体が「アルハラ」だ。ましてや、断られたことを理由に、「付き合いの悪い奴だ」とレッテルを貼るのも良くない。●宴会に酒を交えない
「アルハラ」を行う社員がいる企業というイメージがあると、採用や職場環境、業績、社会的イメージなど、さまざま面で影響が出てしまう。ノンアルコールの食事会を実施するという思い切った施策も検討する価値があるだろう。「アルハラ」の対処法
「アルハラ」を避けるためには、どうしたら良いのか。知っておきたい「アルハラ」の対処法を3つ紹介しておく。●飲み会や宴会に出席しない
「アルハラ」を回避する最も確実な方法は、そもそも飲み会に参加しないことだ。無理に参加して体調を崩すよりも、自分の健康を優先するほうがよっぽど重要である。事前に断りの旨を丁寧に伝えておき、上司や先輩からの誘いでも、毅然とした態度で断ることがポイントとなる。●飲酒を勧められてもキッパリと断る
飲み会に参加する場合でも、飲酒を強要されたらキッパリと断る姿勢が大事だ。「ありがとうございます。しかし、お酒が飲めない体質なので、代わりにソフトドリンクでお付き合いします」と笑顔で伝えるなど、断る際は感謝の気持ちを示しつつ、伝えると嫌味がない。一度でも妥協すると「少しなら飲める」と思われてしまうため、一貫した態度を保つようにすると良い。●飲んでいるフリをする
場合によっては断ることが難しいこともあるだろう。そんな時は「飲んでいるフリ」をするのが良い。グラスに口をつけるだけで実際には飲まない、ソーダ割りなど薄めたものを少量だけ飲む、席を離れる際にグラスの中身を捨てるなどの方法がある。信頼できる同僚に事情を話し、自分の飲み物を引き受けてもらう協力関係を築くのも一手だ。「アルハラ」を受けた時の対応
最後に、職場で「アルハラ」を受けてしまった場合、どう対応すべきか、解説していく。●上司や人事部、社内相談窓口に相談する
「アルハラ」を受けた場合、まずは信頼できる上司や人事部に相談するようにしたい。また企業によっては、ハラスメント対策の窓口が設置されている。プライバシーを保護しつつ、加害者への対応や異動などの措置を検討してくれるだろう。●外部の相談窓口に相談する
社内では解決できない場合、外部の相談窓口を利用する手もある。例えば、各都道府県の総合労働相談センターでは、ハラスメント全般の相談を受け付けている。●転職を検討する
「アルハラ」が常態化し、改善の見込みがない職場環境だとしたら、自分の健康と安全を最優先に考え、転職を検討することも一つの選択肢だ。ハラスメントの脅威から離れることで、安心して働くことができる。まとめ
「アルハラ」が絶対に許されないのは間違いない。だからといって、すべての会食を禁止するという極端な行動だ。従業員の中には、お酒が好きな人もいるし、お酒が飲めなくても場の雰囲気が好きな人もいる。もちろん、全くお酒が飲めない人も少なくない。人によって捉え方が異なってくるので、型通りの飲み会への参加を無理やりに押し付けないようにする必要がある。また、参加者、特にお酒を好む人にも節度が求められる。ついつい度を過ぎてしまう人がいるものだ。そうした場合に、たしなめられる上司や先輩・同僚がいるかどうかも気になる。その意味では、人事担当者やマネジメント層がまずは模範となる言動を示していかないといけない。●厚生労働省:職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)
【HRプロ関連記事】
●「ハラスメント」の意味や種類とは? 事前の対策や起きた時の対処法も解説
●「セクハラ(セクシャルハラスメント)」とは? 定義や具体例から防止策・判例まで徹底解説
●「マタハラ(マタニティハラスメント)」とは? 定義や具体例、防止措置を解説
●「パタハラ」の意味とは? 気になる該当事例や対策方法なども解説
●「モラハラ(モラルハラスメント)」の意味や特徴とは? 職場で起こる実際の具体例も解説
●「カスハラ(カスタマーハラスメント)」とは? 意味や事例と併せて対応策も解説
●「スメハラ(スメルハラスメント)」とは? 意味や職場への影響と対策を解説
- 1