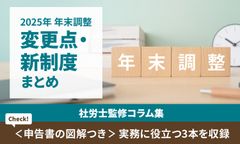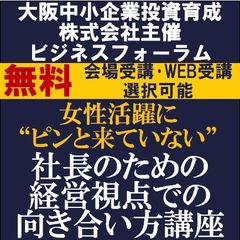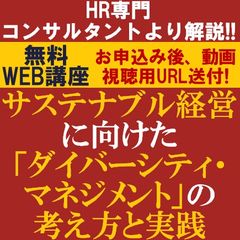――以前から社内では、男女の賃金格差は課題として認識されていたのでしょうか。
バーク氏:その通りです。メルカリでは2020年から男女の賃金格差について議論をしていました。2021年には、スイス・ジュネーブに本拠地を置くEDGE Certified Foundationにより制定されたジェンダー平等のためのグローバル認証「EDGE Assess」取得のために、社内データのモニタリングを始め、2022年12月に認定を取得しました。「EDGE Assess」では、男女の賃金格差を単に平均だけで見るのではなく、ジェンダーのみの要因でどのくらい差があるのかも、監査項目に入っています。認定取得の取り組みの最中に法令改正があったことが、プロジェクト推進の追い風となりました。
――この取り組みによって、どのような成果が生まれましたか。
バーク氏:分析結果を受けた報酬調整によって、7%の差は2.5%にまで縮小しました。さらには、2023年9月に発行したインパクトレポートで、男女の賃金差について開示しました。また、なぜ男女の格差が生じるのか、原因の分析を進めたところ、最も大きな要因が「入社時のオファー年収の差」であることが分かったのです。メルカリでは中途入社が多いのですが、中途入社の場合、選考過程で前職の年収を聞いて、それを基準として入社時の賃金を決めていました。しかし、社会構造的に女性の方が、年収が低い傾向にあります。つまり、前職の年収の時点で発生していた男女の説明できない賃金の差を、引き継いでしまっていたということです。これは、採用時のオファープロセスに原因があったということで、現在では前職の年収を考慮しないようにルールを見直し、徹底して運用しています。
――「説明できない差」を明らかにするために、どのような分析を行ったのでしょうか。
諏訪氏:日本国内では、説明できない差を明らかにする計算手法はまだ確立されていません。今回は、「重回帰分析」という手法を取り入れました。こちらは、賃金に影響を与える変数を考え、それを一つの式で表して賃金を予測する統計的手法です。まず着手したのは、メルカリにおける年収を決める要素の洗い出しです。当社は職種ごとに給与レンジが異なりますし、能力に応じて決まる等級によっても異なります。そういった様々な要素を列挙し、モデルに入れて賃金を予測します。
さらに、その変数を男女で入れ替えたときの差を算出していきました。つまり、「もしこの女性社員が男性だったとしたら、賃金はいくらになるのか」がシミュレーションできるということです。例えば、「もしこの女性社員が男性だったとしたら、賃金1000万円のはずなのに、実際は930万円」といったことが分かります。そうして分析を進めた結果、7%の説明できない差があることが分かりました。
――7%から2.5%に差を縮めるにあたり、どのような対応をされたのかが気になります。
諏訪氏:その方の能力やこれまでの評価、そして総合的に評価してどの程度賃金を引き上げるべきか、個別で判断していきました。その報酬調整に向けたレコメンド値については、階層ベイズモデルという統計モデルを用いて提案を行い、そのデータも参考にしつつ一人ひとりの対応を行いました。
――データの扱いでは、どのようなところに注意されたのでしょうか。
諏訪氏:プライバシーに関わるデータの扱いには注意しました。例えば、子育てや介護の有無などご家庭の事情は、もしかしたら賃金に影響を与える変数なのかもしれません。しかし、社員のプライバシーを守ることも重要です。まだそのようなデータを当社では収集しておらず、関連データの取り扱いについては今後の検討とし、このタイミングでは使用しないという意思決定をしました。他にも、社員一人ひとりに改めて確認していかなければ収集できないデータはもちろん活用できません。そういった制約はあったものの、できる限りの精度での予測を実現することができました。
――前例がない取り組みゆえに、難しい部分も多そうです。
バーク氏:メルカリとして初めてというだけではなく、国内でも事例のない取り組みでしたので、とても苦労しました。グローバル事例の収集をすべくEDGE Certified Foundationにヒアリングをしていたのですが、日本企業と欧米企業は状況が異なります。法令も違えばカルチャーも違うため、欧米でベストプラクティスとされている方法が、そのまま日本企業には適用できないケースが多いんです。とはいえ、国内ではメルカリと同様の取り組みを進めている企業もほとんどないため、ゼロベースで分析方法を構築する必要がありました。どのようなデータを収集して活用すればいいのか、諏訪と連携をして判断をするのにかなりの時間を要しましたね。政府のリーフレットに載っていない情報については、厚生労働省に問い合わせをして、一つひとつ細かく確認をしていきました。また、初めての取り組みですから社内の関係各所との体制をつくることも苦労しました。
――データの収集や分析における苦労を、どう乗り越えていったのでしょうか。
諏訪氏:情報開示にあたり、最大限政府の方針に則して、当社が可能な範囲はどこなのか、落としどころを探りながら進めました。今回政府が開示を義務化しているのは、理論年収ではなく実際に支払った給与です。給与・賞与にはさまざまな項目があり、それぞれどのように扱うのか。集計期間の途中で入社・退職した社員はどう計算するのか、休職している場合はどうするのか、細かな定義は目的に沿って自社で決めていく必要があります。2023年9月に「インパクトレポート」で開示をすることは決まっていましたから、そのデッドラインから逆算して動いていきました。
――前例のない中、素晴らしい成果を出されていますが、プロジェクトの体制は、どのように作っていったのでしょうか。
バーク氏:賃金は、会社のすべてに関わることです。そのため、インクルージョン & ダイバーシティチームはもちろん、評価運用の担当者や労務がプロジェクトメンバーとして関わりました。社内の各部署に伝える際には、HRBPの協力も得ました。そして、最終合意については、経営の意思決定が必要です。関わる人が多いため調整には苦労しましたが、メルカリ全体として「説明できない差がある以上、解消しなければならない」という認識は一致していたため、社内の協力は得られやすい環境でした。
――社内にプロジェクトを周知する際、どのような点に気を付けたのでしょうか。
バーク氏:まず、社内のコミュニケーションをどうするか、経営層と議論しました。メルカリの組織文化には「Trust & Openness」があり、かなりオープンに話せる文化があります。そのため、9月のインパクトレポートで外部に開示する前に、社内全体に取り組みについてオープンにすることを決めました。そこで、7月の全社集会で、分析の結果と差異の要因、そして今後の目標について、経営陣から話してもらいました。
――それを受けて、社内からの反応はいかがでしたか。
バーク氏:賃金というセンシティブな話題のため心配はしましたが、社内の反応はポジティブでした。やはり男女の賃金差はメルカリ1社だけの問題ではなく、社会全体の課題として認識されているため、解決していくべきだと社員も理解してくれているのだと思います。
――前例のない取り組みゆえ、社外からも大きな反響がありそうです。
バーク氏:やはり、同じ悩みを持っている企業はかなり多いですから、反響は非常に大きいですね。メルカリとしても、社外に良いインパクトを与えていきたいと考えているので、とても嬉しいことです。ただ、1社で社会課題を解決できるわけではありませんから、他の企業と連携してナレッジをシェアしていきながら、日本企業におけるベストプラクティスを模索していきたいと考えています。
――実際に、ナレッジシェアの取り組みなども動き出しているのでしょうか。
諏訪氏:メルカリでは、大阪大学社会技術共創研究センター(ELSIセンター)という研究機関との共同研究を進めています。その中で、アカデミアの先生方と共に、今回の男女の賃金格差是正の取り組みについてディスカッションする場を設定いただきました。そのディスカッションの内容は、「ELSIセンター」のホームページ(※)で公開しており、ぜひ企業人事の方々にもご覧いただきたいです。
※
大阪大学社会技術共創研究センター「人事データ分析を利用した男女間賃金格差是正の取組み : 株式会社メルカリにおけるケーススタディ」
――最後に、プロジェクトの今後の展望や構想をお聞かせください。
バーク氏:7%から2.5%に男女賃金の格差を縮めましたが、現在はプラスマイナス1%のギャップに収めることを目標に、定期的にモニタリングを続けながら調整を続けています。もちろん今後も引き続き開示をしていく予定です。そして、こうした「説明できない差」は、男女間のみならず、様々な属性の間で発生していると考えられます。さらに、すべての人にフェアな環境をつくるための取り組みを進めていきたいですね。今回、諏訪の力もあり、データで様々なことが可視化できるというのが改めてわかりました。データにはとてつもないパワーがあることを実感できたので、今後もそのパワーを正しく活用して、色々なバリアを払拭する取り組みを進めていきたいと思っています。
諏訪氏:人は誰しもアンコンシャス・バイアスを持っています。バイアスが生じてしまうこと自体は仕方のないことですが、だからといって許容し続けるわけにはいきません。データの力でしっかりとそのバイアスを分析しながら可視化して、フェアな環境を実現していきたいですね。男女間の賃金格差について、単純に平均値を出すのではなく、「説明できない格差」にまで分析を深め、さらにはその差の是正にまで踏み込んだ、メルカリの先進的なプロジェクトについてお届けした。国内には前例がなく、海外の事例も当てはめられない。そんな中で悩みながらもベストな手法を模索していく姿は、メルカリのバリューのひとつである「Go Bold」を体現する取り組みといえよう。
バーク氏も話していたように、男女間の賃金格差は日本だけではなく世界的な社会課題であり、それは1社だけで解決できるわけではない。メルカリが進めているように、アカデミアとの連携や、同じ課題を抱える企業間でのナレッジシェアの場を設けることも大切なのではないだろうか。